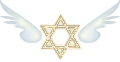
―逆さまの樹―
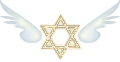
―逆さまの樹―
|
柔らかな寝台に腰を下ろしたまま、第七代目の巫女姫…エル・エリューシア、あるいは楽園に至る光、と呼ばれる少女は、
ぼんやりと髪を梳いていた。 この国の人々は、総じて髪の色が薄い。神に祝福された地に相応しく、光糸の髪は、女性たちの自慢でもあった。 特に、先代の巫女姫は、ことのほか美しい銀色の髪をしていて、その天使のような姿と共に、数知れぬ唄や伝説を残した。 神聖なる巫女姫が、俗の美しさで称えられることは、神殿にとってありがたくはないことだろうが。 自分に関しては、そんな心配もないだろう、と、エリューシアは思った。 闇のごとき漆黒の髪。 それは、まだ名前も貰えず、大勢の子供たちと一緒にいた頃から、他の子と彼女を隔てていた。 神殿では、捨て子や親が死んだ子供を集めて育てており、彼女もその一人だった。 国の慈善事業の一環ともなっていて、その行く末は殆どが巫女や神官として神に仕えることになる。 子供たちの中でも稀な彼女の姿は、生まれつき光の祝福を貰えなかったせいだと、噂されたものだ。 ……しかし、それは真実ではない。表向き神殿に集められたと言われる子供の多くは、出産が出来ない程幼い巫女の堕胎や、神官たちの”信仰のため”と称される魔道の実験によって神殿内で生まれたものであり。 その殆どが祝福など受けていないと……彼らが知ることは無い。 エリューシアは、ふと、髪を梳く手を止めて、帯の間から小さな赤い花を取り出した。 花びらには少し皺が寄ってしまったが、その色はまだ燃えるように美しい。 彼女の瞳は、僅かに寂しげだった。 *** 逆さまの樹。それがこの神殿の中心にあるもの。 それは、樹なのか、そもそも植物なのかさえ、疑わせる白い大きな柱。 柱の表面は複雑な凹凸があり、大きな窪みには人が何百人も入れるほどの広さがあった。 その周囲には幾重もの螺旋状の階段があり、その段を透き通った水が流れ落ちていく。水は留まることなく樹の中から流れ出でる。 周りの階段も通路も、全て水晶で出来ており、その表面は磨かれぬ原石のように粗く、鈍い耀きを見せている。 この道を毎日、エリューシアは登って行った。 雲の上に登るように。高く。 生きながら、神の国に近付いて行くように思われた。 やがて……。 現われるのは、小さな石の座。 ケセドの名が刻まれたその場所で、少女は跪く。 いつか、切り刻まれる体を置いて。 少女は祈る。ついぞ見たこともなく、これから歩くことも無いであろう、広大な王国の安寧を。 ただ、その存在を賭けて、少女は祈り続ける。 その窓に。 彼女が気付いたのは、偶然だった。 祈り場への道の途中。位柱の陰に、一つ。 小さな窓が。 その細さゆえに、両手を差し伸べても肩が通る幅も無いほどの、窓。 しかし、神殿に灯される銀色の灯りではない柔らかな日溜りがそこに出来ていた。 その時、珍しくも彼女の周囲には誰もなく。惹かれるように、エリューシアは窓の方に近付いていった。 日の光が眩しくて、滅多にそれに晒されることの無い瞳が、チリチリ痛んだ。 ふと、風に林檎の匂いがした。 ぽっかりと空いた小さな隙間から、まるで別の世界のように、青い中庭が見えた。 小さな子供が一人、明るい金色の髪に暖かな光を零しながら、花を編んでいた。 年は五、六歳だろうか。愛らしい薔薇色の頬に、ふっくらと陶磁器のような腕を伸ばして、一本、また一本と花を摘んでいく。 「………あ」 ふいに、彼女が顔を上げた。大きなターコイズの瞳が、エリューシアを見上げる。 青白く透けそうな肌が幼い少女の視線に触れて、エリューシアは身を翻した。 ……ふわり。 窓から身を引いたエリューシアの前に、小さな赤い花が落ちた。 温かそうな色に引かれて、エリューシアはその花を手にとった。そして、もう一度窓辺に近付く。 「こんにちは」 彼女は、にっこりと微笑んでいた。空色の瞳に、タンポポ色の巻き毛が揺れた。 スカートの裾を摘んでお辞儀をすれば、エリューシアも軽く会釈を返す。 「このお花を、巫女姫さまに上げたいの」 自分が編んでいた花輪を、惜しげも無く差し出して、少女が言う。 「…巫女姫を知っているのですか」 エリューシアが尋ねると、彼女は首を振った。 「お会いしたことはないの。巫女姫さまは、お花はお好きかしら?」 「そうですね…きっとお好きだと思います」 少女はにこっと笑い、伸ばした指と指に、花輪が渡る。 「おねえちゃま、綺麗な髪ね。赤いお花が映えるわ」 「……髪?」 エリューシアは目を伏せて、自分の髪に触れる。 「変わった色でしょう。好きではないんです。光の祝福を貰えなかったせい…かもしれません」 「あら、光と闇は対のものだわ」 少女はませた口調で言って、小首を傾げた。 「私は、とても綺麗だと思うわ。黒曜石の宝珠みたい。ねぇ、嫌いだなんてもったいないわ」 彼女の口調に、エリューシアは初めてふんわりと微笑み、懐の銀の短剣を抜いた。 黒髪の一房が切り取られ、少女の手の中に落ちた。 「……神の名の元に、これを寿ぐ。貴方に祝福があらんことを…」 *** エリューシアは、花を帯の間に隠すと、手にした櫛をそっと置いた。 彼女に許されているのはここまで。巫女姫の身支度は、全て他の巫女たちがする。 例え自分の体であっても、妄りに触ることは許されない。 沈黙と純潔の誓いを立てた巫女たちは、いつも通り足音一つ立てずに、彼女の体を清め、新しい衣を着せる。 エリューシアの着たものは、全て燃やされるのがしきたりだった。それは、彼女がすでに神のものであるから。 死んだ者は選ばれて神の国に入り、それを認められぬ者は、カオスの海に投げ捨てられるというのが神殿の教えで、 生きているうちから神のものとなることは大層な名誉とされたが、ようは死者と同じ扱いを受けるだけ。 幾夜となく、彼女の世話をする乙女達の中には、かつて同じ場所で生活していた子供もいる筈だと、エリューシアは思っていたけれど。 薄いベールを被り、一言も音を発することなく動き回る巫女は、皆、同じ顔に見える……。 この国には巫女は大まかに分けて二ついる。 ”沈黙の巫女”、そして”樂の巫女”。 何事もなければ、エリューシアは樂の巫女になる筈だった。 神殿の生活を支え、純潔を誓い、嫁入り前の貴族の令嬢を預かる”沈黙の巫女”とは異なり、 神楽、舞い、そして神の愛を身を持って与える”樂の巫女”たちは、半ば公の娼婦のようなもの。 しかし、異国の稀人や、高貴な血を受けて身ごもることは誇りであると言われている上、神殿を一歩も出られない沈黙の巫女に比べて、遥かに自由を与えられる。 勿論、暗い色の髪を持った大人しい少女が、舞いや枕事で名を得るとは思えないが、 楽器を扱う筋は良いと言われていたので、礼拝や祭りの奏者にはなれたかもしれない。 この国で、巫女の地位は奴隷に準じる。 俗世を捨てて神に仕えるためと言われるが、民を導く”神官”との扱いは、まさに貴族と奴隷ほどの隔たりがある。 その中で、神楽や神舞を奉納する名誉を得ることは、世に認められる数少ない手段でもあった。 神殿一番の奏者は、目に布を巻いて視力を奪われ、優れた舞手は薬によって声を奪われたが、皆の尊敬を集めていた。 けれど、エリューシアは神の声を聞いた。 それは、絶対的な威圧感と、聖なる輝きを持って、彼女の中に入ってきた。 齎されたのは、選ばれたという恍惚ではなかった。 むしろ、絶望に近い。まるで、決して抗えない運命のようなものを見て。 初めから、偶然ではなかったのかもしれない。 本当に彼女が捨て子であったか、それとも、魔道実験の果てであったかは解らないが。 神殿に居たのはそのように作られ、育てられた子ばかりだから。 ただ、神と通じるために。 人の全てが持つと言われる、その能力がほんの少し優れた器となるために。 ……彼女自身やその意思とは、なんの関わりもない所で。 後々、この頃のことを思い出した彼女は言った。 私は、決して優秀な巫女ではなかった、と。 巫女姫には、自分という物があってはいけない。全ては、神の受け皿なのだから、常に空っぽでなければいけないと教えられていた。 しかし、それは声を聞くだけで、力を通すだけで、何も理解は出来ていなかった。 だから、故郷の人々の本当の声にも、苦しみにも気付かなかった。 私は、私であることに手一杯で、何も癒せなかったのだ、と。 しかし、その時のエリューシアには解る筈もなく…。 エリューシアの髪の長さがおかしいことは、すぐに世話係の巫女たちから、神官の耳に入った。 彼らの急な来訪の知らせに、彼女は自室に置かれた丸い大きなイスに腰掛け、背筋をピンと伸ばした。やがて、数人の神官たちが入って来る。 「……髪をどうなさったのですか」 白服に、飾り帯の房が二つついた高神官…彼は、神殿を一つの家族と見る習慣から”白き兄”と呼ばれているが、 兄と言うには些か冷たい視線で、エリューシアを見下ろした。 「勝手なことをして貰っては困る。貴方の髪は、貴方が無事神に召し上げられた後、遺品として民に配られるものです。 貴方の体は、貴方のものではなく、神とこの国の民のものなのですよ」 「……申し訳ありません」 エリューシアは神官の薄い瞳を見返すことなく、小さく呟いた。 「今後、このようなことは一切なさらぬよう。それから、貴方にはこの罪を漱いで頂かなくては」 それは、端的に言えば罰を与えるということだった。エリューシアの巫女姫としての地位は、彼等よりずっと高い筈だが、 結局の所、神官たちに抗うことは出来ないので、エリューシアは僅かに体を硬くした。 若い正神官(こちらは房が一つの”弟”その前が、房なしの見習い神官になる)が捧げるようにして持ってきた青い布の上には、 銀細工が施された豪奢な枷が置かれていた。彼はエリューシアの方を気遣わしげにちらりと見たが、高神官の指示する通りに、 布を差し出した。 「暫くこれを付けて頂きます。何も不自由はありますまい」 神官は枷を取ると、エリューシアの重ね合わせた細い手首を繋ぐ形で嵌めた。鏤められた宝石が煌く。 「食事は、巫女たちに口まで運ばせましょう…。ああ、そう、この短剣ですね。賊が侵入した場合の自害用に、と渡して置きましたが、 余計な使い方をするようなら必要ありませんか。大丈夫、儀式も間もないことですし、尊い御身は全力でお守りする。 貴方がケセドに至るのも、そう遠くはありません。それでは」 神官たちは、入ってきたのと同じ足取りで、出て行った。巫女が見送る形で続き、部屋には枷を付けられた少女が一人、 残された。 今の若い神官は誰だったろう、とふと考えて、どうしても名前が思い出せないことに気付いた。 そういえば、昼間の幼子にも名前を聞かなかった。自分が、名前が必要ない暮らしをしているからだろうと思う。 ここに来るまで、少女は名もなき番号で呼ばれ、時に自由に番号を変えられてしまう、そんな子供の一人に過ぎなかった。 今は、七代目エル・エリューシアで、それも記号のように立場を現しているだけだ。 エリューシアは、不自由になった手で、帯の間を探る。名も知らぬ小さな花が一輪、そこにあった。 花輪は泣く泣く捨てた。どうせ、見付かれば取り上げられてしまうからだ。それどころか、あの幼子にまで咎が及ぶかもしれない。 生まれて初めて、貰った花だった。 *** 若い神官……彼にはエリューシアに思い出せない名前がちゃんとあるわけだが、彼はとても戸惑っていた。 彼は、幼い頃から信仰心が厚く、高い志を持って神殿に入ったのだった。 しかし、この春ようやく”赤き弟”の地位につくと、神殿の内部が考えていたような場所ではないことに気付いた。 特に、七代目の巫女姫は、無表情な、人形のように見える黒髪の子供で、彼が想像していたような…神聖で気高い存在からは遠かった。 しかも、周りの”兄”たちの態度も、それを扱うのに相応しいとは思えずにいた。 今日も、「姫の髪の長さが、一部変わっています」との報告を受けた”白き兄”が不機嫌に眉を顰めたかと思うと、 彼に宝物庫にある品を持ってついて来い、と命じたのだった。 「全く、せめて銀か、金の髪ならいいものを。量まで減らすようなまねをして……!」 少女の手に不似合いな枷を付けた後、”白き兄”は唇を歪めて呟いた。 「…髪の色が大事ですか?」 恐る恐る声を掛けると、兄はふん、と鼻で笑った。 「飾りにはいいだろうと言う話だ。あのインクのような髪では、とても映える遺品になるとは思えないだろう?」 なにしろ、貴族達が高い金を出して買っていく物だからな、と彼は言った。 「でも、それじゃああんまりです。まるで彼女は……」 正神官はそう言い掛けて、口篭もる。彼の脳裏に浮かんだのは生贄の鳥。殺された後は羽根を毟られ、肉の一欠まで売り飛ばされる。 「その金は、貧しき者に施され、捨て子たちを育て、神殿を支える資金となる。いわば、神に対する喜捨なのだ。 別に心が咎めることもあるまい?」 ”白き兄”は、少し優しい声で言った。若い神官の父は有力な商人で、その喜捨の額も素晴らしいものだった。 息子を速やかに正神官に押し上げる程の。 「そ…そうですよね…」 「その為には、姫の我侭は少し押さえて頂かなくてはな。それが神殿のため、強いては国のためなのだから」 「………」 にこりと微笑まれ、若い神官はおずおず頷いた。 少女への淡い同情心は、大義名分のために、消えた。 神は、生贄を必要としている。 それは、この国の変わらぬ信念なのだから。 やがて…。 エリューシアにとって、十二回目の新年が訪れる。 彼女最後の祭の日。 あっけないほどに…その時が。 |