
2004.05.03-05.04
長崎本線漫遊(鳥栖−長崎) 路線図を表示
あなたひとりーにー、(わわわわー、わわわわー)
かけーたーこいー、(わわわわー、わわわわー)
愛のことばに・・・。
やはり、クールファイブのバックコーラスも忘れてはいけない。
まあ、そんなことはどうでもいいが、この歌は本当だった。
昨日まではいい天気だったが、長崎に向かう段になってこの天気である。
そして、ここまで熊本−久留米間を鹿児島本線経由で来たなら82.7キロ。
これを綾小路さんは豊肥本線148.0キロと久大本線141.5キロとで走破したのであった。
おまけにその途中、日豊本線にまで乗車している。
何はともあれ、久留米駅までたどりついた綾小路さんの漫遊は続く。
さあ、今日はお待たせの長崎本線に乗車する。 |
 |
|
 |
|
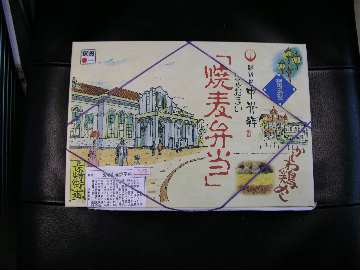 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
このダイアでは、小長井−多良間にある、肥前大浦駅の発車時刻が通常に比べて遅い。 おそらくは列車交換をするのだろう。 時刻表をよく見ると、この列車に遅れること31分後に長崎駅を発車する、特急『かもめ36号』が諫早−肥前鹿島間で追い抜く事になっている。 しかもおおよそ、肥前大浦駅辺りで追い抜くダイアとなっていた。 列車は小長井駅を発車すると、ひとつのカーブにさしかかった時に警笛を鳴らして減速しだした。 そしてそのまま停車してしまったのである。 土井崎信号場だろう。 ここで停車する可能性もあるなとは思っていたが、なんとラッキー。 ただし信号場と言っても、北海道にあるような大きな管理施設があったり、ホームや駅名標があるものとは違っていて、ただ列車交換用の線路が2本並んでいるだけである。 そこで待つこと10分弱、『かもめ36号』は綾小路さんが乗車している列車を追い越していった。 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
列車は19時40分過ぎに、諫早駅に到着した。 ホテルのチェックインを済ませると一息つき、夕食を求めて近辺をうろついた。 ホテルでもらった案内図によると、ラーメン屋が一軒目に付いたが、行ってみると営業していない。 先ほどチェックインする前に見かけた、和食レストランやホテルのレストランでは『長崎ちゃんぽん』というメニューがでかでかとでていた。 ここで綾小路さんは我にかえった。 そうだ、ここは長崎ではないか。 何も『とんこつラーメン』が名物ではない。 『長崎ちゃんぽん』であり、『皿うどん』であろう。 そこで、先の和食レストランに行って見たが閉店間際で、結局はホテルのレストランに戻った。 『長崎ちゃんぽん』には様々な具材がたくさん。 あさり、豚肉、こえび、キャベツ、かまぼこ、きぬさや、にんじん、ちくわ、きくらげ、そして綾小路さんの嫌いな『いか』も入っていた。 しかしこれはいける。 ホテルでこの味。 人気店ではどれだけ旨いことか。 長崎ちゃんぽん、恐るべし! |
 |
|
 トップ |
 鉄道 |