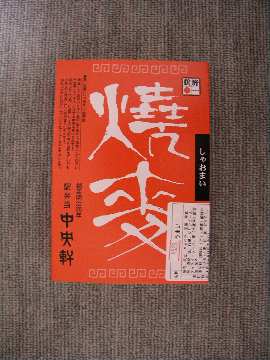綾小路さんは北海道の札幌在住である。
その北海道には鉄道に関して、『日本一』が数多く存在する。
まずもっとも有名なのは『日本一北にある駅』の稚内駅であろう。
その次が『日本一東にある駅』の東根室駅ということになるだろう。
綾小路さんは北海道在住ということもあり、そのどちらにもすでに到達していた。
それに対して、九州には『日本一南にある駅』と『日本一西にある駅』がある。
ところがそのどちらも2003年8月開業の沖縄・ゆいレールの駅であった。
うーん、沖縄には行った事がない綾小路さんもぜひ行って見たいが、モノレールにだけ乗るために沖縄には行けないか。
少なくともJR、第3セクターを制覇してからだな。
大きいところを置いておけば、九州本島には『JR最南端』と『JR最西端』の駅がある。
このうちJR最南端・西大山駅は通過しただけで、まだ下車には至っていない。
そして今日、JR最西端駅の佐世保線・佐世保駅を含んだ、JRで西の果ての漫遊を迎えることになった。
ちなみに北海道には他に、日本一長い『駅間距離』、『直線区間』、『レール』、『トンネル』と『日本一低いところにある駅』などがある。
もちろん、綾小路さんがそれらすべてを体験しているのは言うまでもない。
まずは諫早駅から大村線の乗車である。
綾小路さんは6時49分発の、大村線から佐世保線直通の列車に乗車した。
大村線は発車後の短い区間、長崎本線と並走する。
分岐点が来ると、大村線はそのまま直進して、長崎本線が大きく右方向に曲がっていった。(左)
大村線が先に敷設されたのを象徴する配線だろう。
そして8分で次の岩松駅に停車した。(右)
相対式ホームの脇にプレハブ調の待合室があった。
|