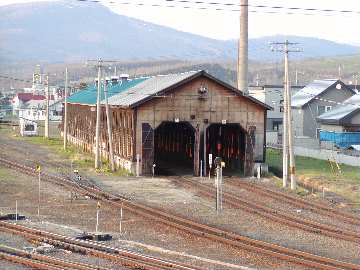気が付けば翌朝だった。
しまった、もう一度くらいは温泉に入っておきたかった。
しかし、幸い。
まだ6時過ぎだった。
7時の朝食までは時間があった。
今日は少し余裕のある行程を組んでいて正解だった。
さて、朝風呂を浴び、朝食を取って天塩川温泉を後にした。
天塩川に架かる橋を渡ると、先ほどまで滞在していた天塩川温泉が一望できた。
天塩川温泉はその名が示すように北海道第2の長流『天塩川』のほとりにある。
大正初期に発見され、当時は『常盤鉱泉』と呼ばれていたらしい。
飲用薬として世に広まり、高価な日本酒と取引されていた歴史もあるとか。