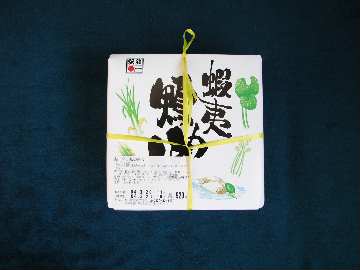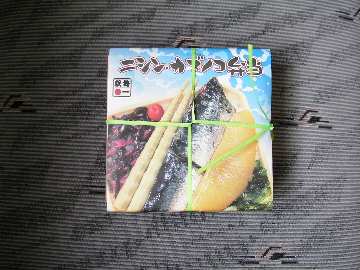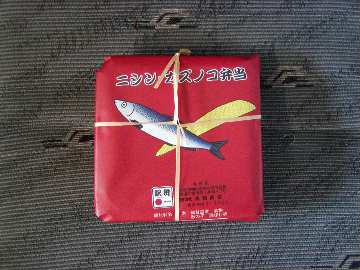日本最北の路線である宗谷本線。
もちろん綾小路さんもこれまでに何度か乗車していた。
しかしどうも灯台元暗しのようになっていた。
北方の稚内方面に位置する駅の写真はそこそこ充実しているが、南方で旭川方面に位置する駅の写真は、まだまだ寂しいものであった。
これは根室本線や函館本線、日高本線にも当てはまる事となっている。
どうもいつでも行けるという感覚からそういう傾向となっているのだろう。
その中で石北本線については先日、札幌から一番近い新旭川−上川間を漫遊して、ようやく足元がしっかりした感じとなった。
せっかく乗車するのだから終点まで行きたいのは山々である。
しかし今回の行程は2日間と限られていた。
そこでここはじっと我慢して、足元付近を見つめる事にした。
まだ特集していない旭川−名寄間と、音威子府までの列車で訪れていない駅を中心とした計画を立てたのである。
宿泊を伴うので今回はパーク&トレインを利用する事は考えなかった。
JRの駐車場とはいえ駅前、盗難やいたずらに会わないとも限らないからだった。
そこで久々の札幌駅出発となった。
地下鉄福住駅からの移動もあったので、札幌駅6時38分発の各駅停車に乗車した。
しかしこの列車は滝川行きであった。
8時18分に滝川駅に到着したが、次の旭川行きの各駅停車は12時01分発だったのである。
その上、綾小路さんご用達の白石駅6時13分発の列車に至っては、札幌駅を33分早く発車していた。
途中岩見沢駅で5分、滝川駅で10分、その他の列車交換時間を入れると僅か8分前に滝川駅を発車したばかりだった。
おいおい、かんべんしてくれよ。
それならあと8分ぐらい待っててくれよなあ。
まあそれも分かっていた話。
ここで綾小路さんが立てた計画は網走行きのオホーツク1号を利用することだった。
石北本線(新旭川−上川)の漫遊時に深川駅から旭川駅まで乗車した特急である。
この特急の滝川発が8時23分だったのである。
そしてオホーツク1号に乗車して8時38分に深川駅で下車した。
すると、なんと白石駅6時13分発の列車が待っているではないか。
そのまま旭川まで乗車すると2140円かかるが、滝川−深川間の特急利用は740円で済んだ。
そして各駅停車に乗車して、9時14分にようやく旭川駅に到着した。
しかし、ここから稚内駅まで、全線を通して乗車できる各駅停車はなかった。
名寄駅まで運行する快速列車の発車までもまだ2時間あったので、ここは区間列車で出来るだけ多くの駅に下車する事にした。
もとよりこの区間の漫遊であったのだから、長距離を走破する列車に乗車する必要もなかった。
4分間の乗換時間であわただしく9時18分発の永山行き列車に乗車した。
そして下車した駅は隣駅の旭川四条駅だった。
両隣の旭川駅と新旭川駅は地平駅であるが、旭川四条駅は高架駅である。
地図を見ると、この付近は碁盤の目の通りの中に鉄道が敷設されている。
宗谷本線の列車に加え、石北本線の列車も運行する区間である。
まして永山駅までは通勤圏で、区間列車の運行は多く、高架にしないと渋滞がひどかっただろう。
駅前の通りは狭く、撮影者泣かせの駅である。(左)
ホームは相対式で、ここでは列車交換風景が頻繁に見られるようだ。(右)
昭和32(1957)年2月に仮乗降場として開設、昭和48(1973)年9月に正式に駅として開業。
|