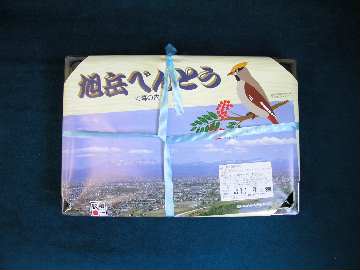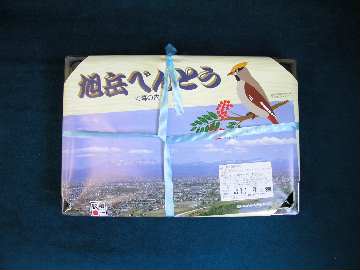2004年も早や3月となった。
これから4月上旬までは青春18きっぷの利用期間でもある。
今回も1セット購入して、これであちこち漫遊してみようと思う。
しかし、ボチボチ行動範囲が限られてきた。
毎回、同じような行程になってしまう。
そこでちょっと贅沢、ポイントポイントで特急を利用して、移動する列車および時間帯を変えて見ようと考えた。
こうすると現地での漫遊の効率化も図れて、一石二鳥になる。
青春18きっぷの利用規定にも書いてあるように、青春18きっぷでは特急に乗車する事は出来ない。
特急券だけ買ってもだめである。
特急に乗車するには特急券と乗車券を別に購入しなければならない。
これなんとかなりませんかねえ、JRさん!
まあ、そう言ってもしかたない。
それでも全て乗車券を買った上で特急券を利用するとかなり高くなる。
特に綾小路さんのように行ったり来たりする漫遊では倍増する。
やはり周遊タイプのきっぷが欠かせないのである。
そこで青春18きっぷと一般の乗車券&特急券を併用してみることにした。
今回は石北本線の新旭川−上川間を漫遊することにした。
白石駅でパーク&トレイン、6時14分発の函館本線で旭川方面に向かう・・・。
おいおい、いつもと変わらないではないか。
いや、ここからが違っていたのである。
このまま各駅停車に乗車すると、旭川駅には9時14分着となる。
しかしタッチの差、石北本線の各駅停車は9時11分に発車してしまうのである。
そして次の各駅停車は12時40分発であった。
それではお話にならない。
そこで特急を利用することにしたのである。
8時34分に深川駅で下車すると、5分の乗換時間で札幌発・網走行きのオホーツク1号に乗車できるのであった。
この列車に乗車すると旭川駅に9時ちょうどに到着できる。
そして11分間の乗換時間で石北本線の各駅停車に乗車できるのであった。
もちろん札幌からオホーツク1号に乗車してもいいが、それでは4000円もかかってしまう。
それが深川−旭川間の利用では1220円で済むのである。
綾小路さんは深川駅でオホーツク1号に乗換え、旭川駅で下車した。
そして余裕で9時11分発の石北本線の列車に乗車した。
石北本線の起点は宗谷本線の新旭川駅であるが、列車は全て旭川駅に発着となっている。
列車は2駅目の新旭川駅を発車すると宗谷本線から分岐、いよいよ石北本線の区間に入った。
今日はこの後、いきなり上川駅まで行って折返す予定である。
旭川駅では石北本線に乗換える際に駅弁を購入していた。
幕の内弁当にあたる旭岳べんとう¥890である。
実は”蝦夷鴨めし”という駅弁を雑誌かテレビで見ていて、購入しようと思っていた。
ところがホームの売り場では販売してなく、やむを得ずこれを購入した訳であった。
普段はあまり幕の内弁当は購入しないが、なかなかよかったね、これは。
鰊、鰊昆布巻、帆立、鳥の照焼、えびフリッターなどなど。
いろんなものが一度に味わえ、これぞ幕の内といった内容である。
”蝦夷鴨めし”はまたのお楽しみにしよう。
|