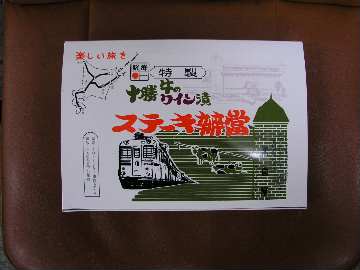決死の覚悟で厳冬期のふるさと銀河線漫遊に挑んだ綾小路さんであったが、あまり寒くはなく、少し拍子抜けとなった。
実は着ぶくれ、ステテコ、長靴・・・さすがに長靴は考えた末に断念したが・・・、準備万端で挑んでいたのだ。
2日目になったが、朝から小雨である。
しばれの町、陸別は何処にいったのだろう。
先週にはしばれフェスティバルが行われたはず。
今は1年で1番寒い時期のはずだが。
余談だが、綾小路さんは人が多そうな先週はわざわざ見送って今週にやってきたのである。
そのしばれフェスティバルの中に“人間耐寒テスト”というイベントがある。
これは寒さがピークに達する夜間から朝にかけて、寝袋一つで過ごしてもらうというものらしい。
途中で逃げ出さず、無事に朝を迎えた人には、日本一の寒さを克服した証として、認定証が発行されるとか。
まあ我慢比べみたいなものか。
綾小路さんはもちろん参加しようという気はこれっぽっちもない。
まあ寒くないのはいいが、雨はいやだなあ。
陸別駅は大きく姿を変えたようだが(左)、構内は昔のままのようである。(右)
給水塔や転車台こそ残ってないようだが、木造の跨線橋や車庫が健在なようだった。
|