ジャスミンの風




さて肝心のダイヤモンド探査作業の方ですが、Geological survey(地質調査)班とGeophysical prospecting(物理探査)班と2班に分かれて作業
を進めています。
を進めています。
Geological surveyは現場で露頭を観察したり、Trench(浅い溝)を掘って地質断面を調べたり、時には渓流で底さらいをして(Panning)含まれて
いる鉱物を判定したりする作業です。また現場で種々の鉱物を採集(Sampling)して持ち帰り化学分析もします。
いる鉱物を判定したりする作業です。また現場で種々の鉱物を採集(Sampling)して持ち帰り化学分析もします。
一方、我が担当のGeophysical prospectingは地球の種々の現象(地磁気・地電流・重力の差・地震動等)の異常を捕らえて鉱物のあり方や地
質の構造を判定しようとするものです。今回はダイヤモンドを含む可能性のあるKimberliteという鉱物を対象としており、含まれている鉄分が磁
気を示すということと、当地質調査所に古いけれども磁気探査機器(Magnetometre)を所有していたということで、磁気探査法を採用することに
しました。
質の構造を判定しようとするものです。今回はダイヤモンドを含む可能性のあるKimberliteという鉱物を対象としており、含まれている鉄分が磁
気を示すということと、当地質調査所に古いけれども磁気探査機器(Magnetometre)を所有していたということで、磁気探査法を採用することに
しました。
 |
現場事務所 |
現場は宿営地から東に1kmほどの小高い丘より成り、周辺には低い潅木やブッシュが生い茂り、途中の緩やかな斜面には綿花畑・キャッサバ
畑・メイズ畑・バナナ畑が点在しています。地質図にはKimberliteの存在が明記されており、現場にもそれらしきものも見受けられます。また
1950年代から60年代にかけて、近くの河川でダイヤモンドのかけらが見つかっていて、その後も保護領だった英国のGeologistたちによって調
査もされたようであるが、これといった成果はあがっていないということです。
畑・メイズ畑・バナナ畑が点在しています。地質図にはKimberliteの存在が明記されており、現場にもそれらしきものも見受けられます。また
1950年代から60年代にかけて、近くの河川でダイヤモンドのかけらが見つかっていて、その後も保護領だった英国のGeologistたちによって調
査もされたようであるが、これといった成果はあがっていないということです。
朝食後、調整されたMagnetometreを持って3人で出発。現場で携帯GPSを使って位置と標高を確認した後、その位置で磁気を測定する、という
作業を位置を順々に変えて繰り返し行います。斜面や畑の中を移動して200点ほど測定するとかなり疲れます。午後1時か2時頃宿営地に帰
着、昼食となります。
作業を位置を順々に変えて繰り返し行います。斜面や畑の中を移動して200点ほど測定するとかなり疲れます。午後1時か2時頃宿営地に帰
着、昼食となります。
午後は暑いので洗濯をしたり、周辺をウロウロしたりして過ごします。テントの中は蒸し暑くなっていてとても昼寝どころではありません。
小学校のだだっ広い運動場では、ヤギの群れや鶏それにホロホロ鳥が集団で餌をついばみながら朝夕歩き回っています。JICAの関係者から
ホロホロ鳥は元気がついておいしいよ、と聞いていたので、一羽多少高かったけれども買い入れて調理してもらい食べてみました。チキンよりも
味が濃くて噛み応えがあり、量もかなりありました。満足すべき味でした。それ以来一緒に行った仲間は折につけ、「ホロホロチョー」、「ホロホロ
チョー」と後ろにアクセントのある変な訛りの日本語で話しかけてくるようになりました。
ホロホロ鳥は元気がついておいしいよ、と聞いていたので、一羽多少高かったけれども買い入れて調理してもらい食べてみました。チキンよりも
味が濃くて噛み応えがあり、量もかなりありました。満足すべき味でした。それ以来一緒に行った仲間は折につけ、「ホロホロチョー」、「ホロホロ
チョー」と後ろにアクセントのある変な訛りの日本語で話しかけてくるようになりました。
 |
村の中にある水汲み場(井戸)には興味があって何度か行ってみたのですが、主に女性たちが大小色とりどりのポリバケツを並べて手押し式で
水を汲み上げています。試しにやってみたのですが、かがんだり立ったりするので数回で腰がだるくなり、腕も身が入ったような感じになり結構
重労働であることが分かりました。初心者には続けられません。
水を汲み上げています。試しにやってみたのですが、かがんだり立ったりするので数回で腰がだるくなり、腕も身が入ったような感じになり結構
重労働であることが分かりました。初心者には続けられません。
振り返ってみると、当地の女性は何をするにも前かがみになって作業をし、決してしゃちこばるということをしません。また汲み上げた水で満杯
になったバケツ(上端部から2,3cmぐらいの余裕を残すのみ)を器用に頭の上に載せて一滴もこぼさず坂道を昇り降りして運んでいきます。裸足
の人が多いのですが(その方が安定が良いのでしょう)、見ていると下半身はともかく頭は全く動いていません。小さい女の子も、母親から教え
られたのでしょう、同様に運んでいきます。これを一日に何回も繰り返すのですから、生活のためとはいえ頭の下がる思いです。
になったバケツ(上端部から2,3cmぐらいの余裕を残すのみ)を器用に頭の上に載せて一滴もこぼさず坂道を昇り降りして運んでいきます。裸足
の人が多いのですが(その方が安定が良いのでしょう)、見ていると下半身はともかく頭は全く動いていません。小さい女の子も、母親から教え
られたのでしょう、同様に運んでいきます。これを一日に何回も繰り返すのですから、生活のためとはいえ頭の下がる思いです。
蛇口をひねれば何の苦もなく水が出てくる便利な水道水を使い慣れた我々ですが、この水は一滴も無駄遣いするわけにはいかない、というこ
とを強く再認識させられました。
とを強く再認識させられました。
そばにはコンクリートで作られた洗濯用の台がいくつかあって、井戸端会議をしながらまた小さい子供たちを遊ばせながらたたきつけるように
して衣類を洗っています。近くの谷川でも、家族ぐるみで洗濯をしているのをよく見かけます。
して衣類を洗っています。近くの谷川でも、家族ぐるみで洗濯をしているのをよく見かけます。
これらの光景は、山中の集落だけでなくZombaのような都会でも中心部を除いて日常的に見られます。
また現場には、木の枝と同じ格好をして横に伸びた蛇とか、触ると後から腫れてくるというBaffalo beansという枝豆によく似た植物も繁茂して
いるので、気をつけて歩かないと危険です。
いるので、気をつけて歩かないと危険です。
 |
近くの井戸 |
ひととおり現場作業の目処がついたところで、今回の作業のスケジュールが調査所の人員と他の現場作業との関連で大幅に変更になり、9月21
日に一旦Zombaに帰ってきました。残作業は12月に入ってからということになりました。
日に一旦Zombaに帰ってきました。残作業は12月に入ってからということになりました。
帰って来る前の日に、記念に現場の仲間たち8人と写真を撮り、寄せ書きを作りました。
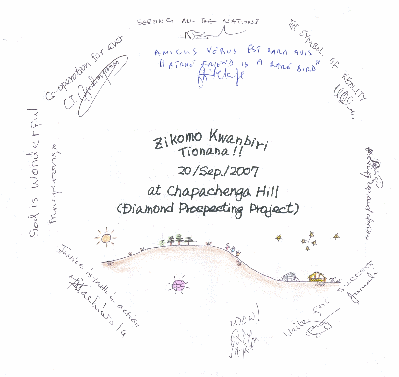 |
 |
Magnetometreの調整のため途中で首都Lilongweに行ったのですが、うまくいかなかったり、一時帰ったZombaでは政府から燃料代が出ないか
らと言って動けなかったり、やっと燃料代が出るようになったと思ったら今度は車の故障とかで長らく待たされたりという事態もあって、イライラす
ることが多く、当方の当初の目論見よりかなり遅れている現状です。
らと言って動けなかったり、やっと燃料代が出るようになったと思ったら今度は車の故障とかで長らく待たされたりという事態もあって、イライラす
ることが多く、当方の当初の目論見よりかなり遅れている現状です。
現地の人たちに近い生活を数週間体験してきたのですが、Zombaへ帰って来てやはりホッとしています。食事の内容が全然違います。きれい
な水も豊富に使えます。
な水も豊富に使えます。
現場周辺では何故かジャカランダを見掛けなかったのですが、ここZombaでは至る所で今を盛りと咲き誇っています。調査所の職員やホテル
の人たちからはよく「マラウイはどうだった?」という質問を受けるので「暑くてしんどかった」と答えています。
の人たちからはよく「マラウイはどうだった?」という質問を受けるので「暑くてしんどかった」と答えています。
現場データの解析にはGeophysical prospectingの測定結果だけではなく、Geological surveyの調査結果それにGeochemical anarysisの分
析結果を総合して判断する必要があります。まだまだ取り掛かったばかりで、しばらくは現場データの整理と探査内容の検討、今後の日程調整
をすることになります。
析結果を総合して判断する必要があります。まだまだ取り掛かったばかりで、しばらくは現場データの整理と探査内容の検討、今後の日程調整
をすることになります。
10月半ばには、任国外旅行で今回は南アのケープタウン周辺に行く予定(10日間)にしています。
Tionana(=See you)!!
2007年 9月30日 Zombaにて
*Kimberliteは古い大陸にしか存在しなくて、日本のような新しい地盤変動の激しい島国には無いという風に解釈していたのですが、つい最近
日本でダイヤモンドが発掘された、ということを耳にしました。単なるうわさかも知れないのですが、これに関する何らかの情報をご存知でした
ら教えて下さい。
日本でダイヤモンドが発掘された、ということを耳にしました。単なるうわさかも知れないのですが、これに関する何らかの情報をご存知でした
ら教えて下さい。
 |




http://www5f.biglobe.ne.jp/~jasumin/