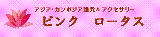ジャスミンの風


 №9 -1-へ
№9 -1-へ 
アンコール遺跡修復と土木工学
この5月から6月にかけて、赴任している学校の土木工学科で表題をテーマにしたVCD授業第3弾を実施した。対象は、Certificate3クラス、Diploma2クラス、
Engineer1クラスの計6クラス。教材は今まで収集してきた各種関連資料をとりまとめて作成したものである。実は当地に赴任することが決まってから、「カンボ
ジアと言えばアンコール遺跡」 ということで、それに関わることができたら……と考えていたので、1年余り振りに実現したことになる。
Engineer1クラスの計6クラス。教材は今まで収集してきた各種関連資料をとりまとめて作成したものである。実は当地に赴任することが決まってから、「カンボ
ジアと言えばアンコール遺跡」 ということで、それに関わることができたら……と考えていたので、1年余り振りに実現したことになる。
市販の書物*1以外に、昨年シエムリアップを訪れた際にUNESCOが支援するJSA(日本国政府アンコール遺跡救済チーム)の現地事務所を訪ね、遺跡建設およ
び修復と土木との関わり、例えば使用材料であるラテライト(紅土岩)や砂岩の産出元と岩質・現場への運搬方法・積み上げ方法、さらに基礎地盤の土性他
についての資料の有無を確かめた。その結果、修復工事に関する数本のビデオテープや「バイヨン北経蔵修復工事報告書」=修復前後の図面付き=・「アンコール
遺跡調査報告書」(いずれの報告書もJICA事務所の図書室にもあり)があることが分かり、ビデオテープとJSAの修復工事に関する説明用掲示板(日本語・ク
メール語・英語で記述)4枚を借用できることになった。
び修復と土木との関わり、例えば使用材料であるラテライト(紅土岩)や砂岩の産出元と岩質・現場への運搬方法・積み上げ方法、さらに基礎地盤の土性他
についての資料の有無を確かめた。その結果、修復工事に関する数本のビデオテープや「バイヨン北経蔵修復工事報告書」=修復前後の図面付き=・「アンコール
遺跡調査報告書」(いずれの報告書もJICA事務所の図書室にもあり)があることが分かり、ビデオテープとJSAの修復工事に関する説明用掲示板(日本語・ク
メール語・英語で記述)4枚を借用できることになった。
*1 「アンコール遺跡の地質学」,「アンコール遺跡の建築学」,「アンコール・ワットへの道」,……。
これらの資料に、公共事業運輸省(MPWT)内の地図センターで入手したカンボジアの地質図、それにアンコール遺跡やタイのアユタヤ遺跡を訪ねた時に撮影した写
真を加えて、教材を作成した。今回は前2回と異なり、新しく導入したLaptopパソコンとLCDプロジェクターを併用することによって広い教室で授業することが出
来、格段に操作し易くまた見易くなった(当初は執務室すぐ隣の試験室にDesktopパソコンをその都度運び込んで、そのモニター画面のみで供していたので数
段の進歩である)。
真を加えて、教材を作成した。今回は前2回と異なり、新しく導入したLaptopパソコンとLCDプロジェクターを併用することによって広い教室で授業することが出
来、格段に操作し易くまた見易くなった(当初は執務室すぐ隣の試験室にDesktopパソコンをその都度運び込んで、そのモニター画面のみで供していたので数
段の進歩である)。
教材の内容は次のようである。
①位置(アンコール・ワット,アンコール・トム,バンテアイ・スレイ,プノン・クーレン等アンコール遺跡の建設場所および周
辺の地形の特徴)
②歴史(802年;プノン・クーレンでのアンコール王朝誕生~944年;全国統一~1431年頃; タイのアユタヤ王
朝軍により陥落/当時の日本は794年;平安遷都により貴族文化が繁栄~1192年;鎌倉幕府設立により武家社会に移行/1860年;フランスの博物学者
アンリ・ムオーによりアンコール遺跡再発見/1992年;UNESCOの世界遺産に登録、同時に緊急な救済を必要とする危機遺産にも指定,1995年~;カンボジア側のアン
コール地域遺跡整備機構=APSARA=のもとで、フランス・日本・イタリア・中国・ドイツ・アメリカ・インドネシア等各国の援助により修復作業が継続中)
アンリ・ムオーによりアンコール遺跡再発見/1992年;UNESCOの世界遺産に登録、同時に緊急な救済を必要とする危機遺産にも指定,1995年~;カンボジア側のアン
コール地域遺跡整備機構=APSARA=のもとで、フランス・日本・イタリア・中国・ドイツ・アメリカ・インドネシア等各国の援助により修復作業が継続中)
③地質と地盤(アンコール地域の地質特性,各遺跡での地盤調査結果と土性)
④アンコール・ワットの建設(基準軸の設定方法,西参道での使用材料=ラテライトと砂岩=および基本構
造,石積み擁壁の安定性,修復方針 他)
⑤バイヨン北経蔵の修復(修復前後の図面,使用材料と基礎地盤の特性)
⑥写真(アンコール・ワット西参道での修復状況,ラテライトと砂岩,砂岩材の切出し地とされるプノン・クーレン
での砂岩露頭,タイのアユタヤ遺跡=レンガ材を使用= 他)
生徒たちにこれらの内容をPower Pointソフトを使って一通り説明し、特にアンコール・ワット西参道の石積み擁壁を取り上げて、その安定性について演習問題
を課してみた。擁壁断面で、石材や内部の土や水の単位体積重量・擁壁の高さや幅・土圧係数・摩擦係数等の数値を与えて擁壁に対する作用力と抵抗
力(摩擦力)を計算し、石積み擁壁が壊れないで耐えられるかどうか? という問題である。結果は、これらの作用力を全て加味して算定すると、作用力が抵
抗力に勝りすべりが生じ不安定の状態となる。一方、内部の土の中に水が溜まらなくて水圧がかからなければ、石積みは壊れないで安定であるというこ
とになる。豪雨に対する水はけの良否が如何に重要かということを示している。説明中、熱心にノートを取っていた女生徒のひとりから「ティーチャー、摩擦係数
の英語のつづりはどう書くのですか?」という質問や、「摩擦係数はどのようにして決めるのですか?」という男生徒のうれしい反応もあった。あとから、上記
教材の入ったCDを貸して欲しいとか、「バイヨン北経蔵修復工事報告書」をコピーさせて欲しいとかいう要望もあった。
を課してみた。擁壁断面で、石材や内部の土や水の単位体積重量・擁壁の高さや幅・土圧係数・摩擦係数等の数値を与えて擁壁に対する作用力と抵抗
力(摩擦力)を計算し、石積み擁壁が壊れないで耐えられるかどうか? という問題である。結果は、これらの作用力を全て加味して算定すると、作用力が抵
抗力に勝りすべりが生じ不安定の状態となる。一方、内部の土の中に水が溜まらなくて水圧がかからなければ、石積みは壊れないで安定であるというこ
とになる。豪雨に対する水はけの良否が如何に重要かということを示している。説明中、熱心にノートを取っていた女生徒のひとりから「ティーチャー、摩擦係数
の英語のつづりはどう書くのですか?」という質問や、「摩擦係数はどのようにして決めるのですか?」という男生徒のうれしい反応もあった。あとから、上記
教材の入ったCDを貸して欲しいとか、「バイヨン北経蔵修復工事報告書」をコピーさせて欲しいとかいう要望もあった。
この演習問題のすぐあとに、NHK・プロジェクトX「アンコール・ワットに誓う師弟の絆」のVCDを上映した。鬼の石工と呼ばれる60才を越した日本人の石工職人が、
遺跡修復のために何年にも亘って、アンコール・ワットの石積み手法(モルタル無しの空積み)を現地の若者たちに厳しく伝授していく物語である。生活費を稼ぐた
めに一旦やめて行った有望な若者が、悔いて再び弟子入りを志願して、石積み修復のたくましい親方となって他の若者たちを率いていくことになる。所々
に彼のクメール語会話が出てくるので、それまで眠そうにしていた生徒たちもこの時ばかりはシーンとして聞き入っていた。このVCDの中に上記の水はけの工
夫が出てくる。元々表面の敷石砂岩は緻密に、また目地(すき間)を通すことなく積まれていて雨水の浸入を防いでいたこと、石積み内部の締固め土(水を
通し難い版築土と呼ばれる)の間には何層にも亘りラテライトの石屑と粘土を混合した薄い土層が挟まれていて、浸入した水の動きを出来るだけ弱めて内
部の土を伴わないでゆっくりと自然排水で外部に出していたこと等、それなりの対策が施されていたのである。古えの人々の苦心と見事な工夫の跡が見
てとれる。学年によってはまだ土質力学や基礎工学を学んでいないクラスもあるので、生徒たちは口頭では分かった、とうなずいていたがどう認識してくれ
ただろうか? さらに、JSAから借用した「バイヨン北経蔵修復工事」の模様を撮影したビデオおよび「クメールの匠たち」というかつてのクメール人たちが成し遂げ
た種々の工夫を汲み取って、現代の技術者たちがいかに修復していったか、というビデオをそれぞれVCD化した映像を披露した。ひとクラス当り2時間半余
りの授業だった。説明に供したのは土木工学的な工夫のほんの一部に過ぎなかったが、借用したビデオでVCD化したもののまだ披露していないものも有
るので、機会があればまた供したい。最後に再び、構築物安定に対して「排水対策」が大きな役割を占めるということを強調して、今回の授業のしめくくりと
した。前2回のVCD授業も含めて、少しでも生徒たちの印象に残り、土木に対する興味を深めてもらえれば……と願うばかりである。
遺跡修復のために何年にも亘って、アンコール・ワットの石積み手法(モルタル無しの空積み)を現地の若者たちに厳しく伝授していく物語である。生活費を稼ぐた
めに一旦やめて行った有望な若者が、悔いて再び弟子入りを志願して、石積み修復のたくましい親方となって他の若者たちを率いていくことになる。所々
に彼のクメール語会話が出てくるので、それまで眠そうにしていた生徒たちもこの時ばかりはシーンとして聞き入っていた。このVCDの中に上記の水はけの工
夫が出てくる。元々表面の敷石砂岩は緻密に、また目地(すき間)を通すことなく積まれていて雨水の浸入を防いでいたこと、石積み内部の締固め土(水を
通し難い版築土と呼ばれる)の間には何層にも亘りラテライトの石屑と粘土を混合した薄い土層が挟まれていて、浸入した水の動きを出来るだけ弱めて内
部の土を伴わないでゆっくりと自然排水で外部に出していたこと等、それなりの対策が施されていたのである。古えの人々の苦心と見事な工夫の跡が見
てとれる。学年によってはまだ土質力学や基礎工学を学んでいないクラスもあるので、生徒たちは口頭では分かった、とうなずいていたがどう認識してくれ
ただろうか? さらに、JSAから借用した「バイヨン北経蔵修復工事」の模様を撮影したビデオおよび「クメールの匠たち」というかつてのクメール人たちが成し遂げ
た種々の工夫を汲み取って、現代の技術者たちがいかに修復していったか、というビデオをそれぞれVCD化した映像を披露した。ひとクラス当り2時間半余
りの授業だった。説明に供したのは土木工学的な工夫のほんの一部に過ぎなかったが、借用したビデオでVCD化したもののまだ披露していないものも有
るので、機会があればまた供したい。最後に再び、構築物安定に対して「排水対策」が大きな役割を占めるということを強調して、今回の授業のしめくくりと
した。前2回のVCD授業も含めて、少しでも生徒たちの印象に残り、土木に対する興味を深めてもらえれば……と願うばかりである。
以上趣味と実益を兼ね、沢山の人たちの助けと厚意により、時間と手間をかけて準備した教材をひと通り授業に供することが出来、ホッとしているところで
ある(VCDを上映し始めてすぐに停電に見舞われて延期せざるを得なくなったり、手違いで教室がダブルブッキングされていて右往左往する、というハプニングも
あったが)。
ある(VCDを上映し始めてすぐに停電に見舞われて延期せざるを得なくなったり、手違いで教室がダブルブッキングされていて右往左往する、というハプニングも
あったが)。
19/Jul./'04
プノンペンの自宅にて


 №9 -1-へ
№9 -1-へ