9.
「――気に入ったか?」
常と変わらぬ涼しげな声にふと気がつけば、口の端だけでうっすらと笑む、眼前のシオンと視線が合った。闇を祓う真珠色の光を放ち、しろがねの月は皓々と中天に在る。
言葉など返せる訳がない。
濡れた睫毛でゆっくりと瞬きをして、ムウは決まり悪そうに微笑する。できるだけさり気なく見えるよう、指の先で素早く涙を拭った。さらけ出すつもりなど無かったのに。……どうしようもない。
「詞は大昔の有名な詩人の作だ」
そんなムウの様子には立ち入るでもなく、何事も無かったかのような口ぶりで、問わず語りにシオンが言った。包み込むような見透かすような、眼差しはどこまでも穏やかである。敵わない。
「おおよそ三百年ほど前だったか」
「……そんなに昔の?」
「まあ私からすれば生まれる数十年ばかり前のことだがな」
個人的にはそれほど昔という感じでもない。平然とうそぶいて、にやりと笑う。こちらも苦笑するしかない。
「なかなか愉快な詩人だぞ。時の権力者にして宗教界の長でもあったのだが、王宮の生活に絶望的に馴染めなかったらしい。毎日のように神殿から抜け出しては俗人の格好で街を徘徊し、好き放題に遊び暮らしては即興の詩をばらまいていたと、正史に書き残されている」
「それは……すごいですね」
「些か羨ましい」
尊大な横顔でさらりと口にする。露も変わらぬ表情からは、胸の内を窺い知ることはできない。……ほんの少しだけ、不意を突かれた。
「人民からは絶大な人気を誇ったそうだがな。残された詩はいずれも有名だから、古くから様々な歌人が競い合うように、自分なりの曲をつけて唄い継いできたというが」
眼前の卓子に楽器を置いて、可笑しげにシオンは言葉を繋ぐ。
「先程の旋律は私の若い頃に流行ったものだ」
今となっては誰ひとり覚えている者もおらぬだろうから、お前は知らなくとも恥じることなどないぞ。言いながらゆったりと此方を見やる。
「……痛み入ります」
どんな顔をすべきかも判らぬままに、ムウは深々と吐息を漏らす。十八世紀。そんな時代の流行歌など、もはや文化遺産も同然である。何やら凄まじいような心地もするが、元より歳月の流れとはそのようなものと悟り知るべきか。
「……そう言われれば歌の詞書きの方も、三百年も昔のものだからでしょうか。随分と不思議な内容ですね」
何を歌ったものなのか、今ひとつ意味が取りづらいというか。そう何気なく、ムウが呟くと。
「何だ、解っていなかったのか」
半ば呆れ、半ば面白がるような口調でシオンが応じた。……何か変な事でも言っただろうか。
「いえ、その、言葉そのものの意味は解るのですが。全体としての文脈が、ちょっと」
……記憶術か何かのことを言っているのでしょうか。恐る恐る、遠慮がちに切り出してみる。問いを受けたシオンは酷く読み取りがたい表情をして、暫し、まじまじとムウを見た。
「……お前は本当にこういう分野に関しては色気の欠片も無いな」
心の底から感心したような口ぶりで、しみじみとそんな事を言う。そこまで面白がらなくたって良いではないか。何だか自分が情けなくなってきた。
「あの、しかし、筆記よりも暗記の方が後まで残ると、そういう内容のように……」
「微妙に間違ってはいないところが逆に重症だ」
自信なさげに口ごもるムウを前に、シオンは容赦なく言い放つ。だがその蒼い眼の奥底は、意外なほどに柔らかい。
「……それではもう一度だけ、読み上げてやろうか?」
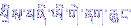
(黒々と文字に書かれたものたちは脆く)
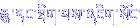
(水に濡れれば壊れて消えてしまう)

(けれども表に出して書かれることのない心のかたちは)
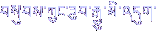
(どんな嵐にも消えることなく、いつまでも永遠に残るだろう)
低く穏やかなシオンの声をなぞるようにして、ムウもまた小声で繰り返す。そうして幾度か口ずさむうちに、突如はっとして、かつ理解した。重々しいほどの静寂が辺りを満たす。黙り込むムウを悠然と眺めながら、今ごろ気づいたのか、とシオンが揶揄った。かの六世は有名な恋愛詩人なのに。
「…………」
慮外の状況に耳まで紅くして、固まりきったままムウは途方に暮れる。何と言って返せば良いのだろう。顔から焔が燃え立つようだ。
――紙に書かれた愛の言葉はいつか消えてしまう。けれども言葉にすることもないお前への想いは、私のこの胸のなかで、永遠に――
「こ、恋歌とか、歌うんですね……」
そんな俗っぽい事物とは、無縁の人だと思っていたのに。動揺のあまり視線を合わせることさえできない。完全に挙動不審の体である。
「歌ったら、どうだと?」
「……いえ、あの……どうという訳ではないのですが……」
訊きたいことは山程あるのに、気の利いた科白ひとつ出てこない。最終的には消え入るような声でひとこと、絞り出すのが精一杯である。
「……意外です」
「成る程」
余人には判じがたい表情で、シオンはうっすらと眼を細くする。周囲の空気がいちどきに、濃密さを増したような気がした。
メタモルフォシス。
「その意外さはあながち間違いでもない」
ごく柔らかな口調でそう言うと、音も立てずに不意に立ち上がる。天の色を湛えた眼差しに、胸の奥まで刺し貫かれた。
「……珍しいものを見たと思っておきなさい」
高みから見下ろして艶然と微笑う。深い闇に黄金の滴るような。
瞬きひとつできずに魅入られたまま、ムウは為す術もなく眼前の人の、言葉の意味を受け止める。視線を外すことはもう叶わない。頬の緋色をいっそう深くして、消え入るようにこくりと頷いた。
月は遼々と、翳もなく。
鮮やかに照らされた卓子の上には古の六絃が訳知り顔で、夜の盛りに華やいでいる。