8.
星影も幽かな更夜の闇に、咲き誇るような満月が、石造りの室内を音もなく照らし出している。皓々と降り注ぐ光の下では、燭し火も殆んど必要ない。
――もうこんな刻限か、と明かり取りの質素な切窓越しに、ムウは傾き始めた月影を見上げた。
絵図や器具の類で取り散らかした、狭い工房の奥深く。しらじらと明るい卓子の上には修復作業もあらかた終えた、六絃の楽器が置いてある。艶やかな木肌には傷ひとつ無く、星を散らした花唐草は、見違えるほどの鮮やかさ。欠け落ちていた駒も糸巻も、それと気取らせぬ自然さで、見事に復元されている。涙型の胴の表には薄く伸べた鞣し皮が湖面のようにぴんと張りつめて、意匠を凝らした天神飾りも、輝くばかりに美しい。
月華に煌めくトルコ石。
修復の出来を評するならば、確かに見映えは問題ない。甚だ完璧な造形と言える。しかし音色の方は果たして、いかがなものか。外観ばかりが優美でも、音が駄目では意味がない。
考え込むように、長い棹に触れる。滑らかな指板の上には思いがけぬ厚情でオルフェのくれた、琥珀色に透きとおる絲が六条、取り敢えずの風情で張ってある。軽く爪先ではじいてみれば、相も変わらぬ物慣れなさで、ぱらぱらと不器用な音がした。響きそのものは悪くないのだが、やはり弾く方の技量が不味すぎるらしい。調律も至って適当な所為か、どこか微妙な違和感がある。
……琴座はあのように言ってはいたが。
再び黙りこんだ六絃をちらりと見やり、ムウは内心溜息をつく。せいぜい霊体に楽器が弾けることを祈るしかない。
諸々の思案に耽りつつ、卓上に散らかった瓦落多の山から削りたての木撥を手に取って、どうしたものか、しげしげと眺めていると。
「こんな時間まで熱心なことだな」
薄絹のような静寂を破って、いきなり真後ろから声がした。
心臓が止まるほどの不意打ちに、堪えきれずムウは息を呑む。背後を振り向く暇も無く、すみません、と答える余裕すら生まれぬうちに、馴染んだ気配が傍らに立った。
いつから見られていたのだろう。
返答も出来ずに固まっているムウの都合には頓着もせず、夜の帳を傲然と、シオンの低い声が落ちる。
「大きすぎるな」
「……えっ」
「材質も形状も悪くはないが、その寸法では小回りが利かぬ」
話の筋が皆目判らず、戸惑うムウの肩越しに、表情も無く見下ろしたままごく淡々と。その視線を辿って、漸く気づいた。木撥のことか。
「あ、えっ。はい」
その、すみません。予想外も極まる展開に、常ならず狼狽える一方で、じわじわと頬には血が上る。深緋染。こんな夜に限って、天満の月には翳ひとつ無い。
……逃げ場所くらい、残してくれても良いものを。
眦の熱を誤魔化すように、卓上の小刀を慌てて取って、手早く撥を削り出す。至って素朴な竹材の加工は元々大した手間でもないが、どうも思いのほか緊張をしているらしく、指先にはいつも以上の集中が要る。大好きな師の満足を得ようと切ない程に懸命だった、遠い幼な子の想い出が、幻燈のように胸をよぎった。
流れゆく。
ほんのりと紅を刷いたまま手を急がせるムウの動揺と焦りを余所に、シオンは悠然と寛ぎながら、手近な胡牀に緩く腰掛ける。そうしておもむろに右腕を伸ばし、傍らの楽器をついと取り上げた。長く強い指が気紛れのように、琥珀色の絃糸を幾度か揺らす。それから一見無造作に、しかし実際のところは空恐ろしくなるほど正確に、誂えたばかりの糸巻に触れ、ゆっくりと確かめながら巻きとって行く、その厳格な動きを視界の隅に見て取りながら、ムウは内心、気が気ではない。
ちゃんと直っているだろうか。
糸巻の構造に間違いはないか、音の高低に狂いはないか、響鳴の仕掛けはうまく機能するか。うわの空でひとつひとつ数え上げていると、不意にシオンが掌を出した。
「……?」
はっと気づいて慌てて削り直した撥を差し出す。否も応も無い。表情ひとつ変えることなく当然の様に受け取ったシオンは、滑らかな竹の切片を軽くかざして細かな木屑を一吹きすると、頓着のない手つきで楽器に当てた。
セ、テ、ホ。
深い音色が部屋中に拡がる。水底に射し込む光のように、この世の始まりの鼓動のように。
息が止まるほど鮮やかな。
声もなく呆然と見つめるムウの眼前で、シオンはひらりと手首を返し、迷いのない動きで再び糸巻を繰る。そうして微細な音のずれを修正すると、今度は左手で絃を押さえながら、確かめるようにもう一度鳴らした。
ラン、テ、クン、ペン、ホ、セ、イェ。
なだらかな所作でゆったりと、手遊ぶように、七音階。いつしか宵闇に星の浮かぶがごとく、音の波紋は徐々に増えてゆき、気がつけば優しげな旋律となって、夜の淵を流れ出している。
どこか遠く儚い懐かしさにも似た、古い節回しをひとくさり。
「――まあ、こんな所だろう」
手を止めて簡潔に評すると、シオンは楽器をさらりと撫でた。絶句したままのムウには一瞥もくれず、いとも悠然と言葉を続ける。室内の静まりきった沈黙も、気に留める様子は全く無い。
「音程は正確に合うようだし、響きも上質の部類に入る。欠損部位の補修も良好、ついでに外観にも些か手を入れたようだな。あらかた不具合も無いと思うが」
取り敢えず、趣味は悪くない。
そう言って唇の端で薄く笑み、ゆったりと弟子を流し見る。傲岸不遜。未だ呆然としつつも漸く我に返ったムウは、やっとの思いで声を絞り出した。
「……ひ、弾けたんですか」
「弾けないと言った覚えは一度も無いな」
お前が自分でやる気のようだったから、口出しを控えただけだ。
事も無げにそのような科白を吐いて、愉快そうにくつくつと笑う。実に鬼畜の所業である。二の句が継げぬとはまさにこの事だ。
反応も返答もできぬまま、ムウはただ唖然と師の横顔を観る。一体どういう嗜好なのだか、人が悪いにも程がある。初めからわざとであったのは、もはや疑うべくもないが――しかしながらこんな風に手を貸してくれるというそのこと自体、天地が引っくり返るほど珍しいのも事実であった。不摂生を叱責されるものとばかり思っていたから、余計に予想外である。
「まあ、それでも流石に仕上げくらいは手伝ってやらないと」
ぱちり。澄んだ音を立てて卓上に撥を置き、闇をも貫く強い双眸が、不意にまっすぐにムウを見る。
――射抜かれた。
「お前は相当幼いうちに俗世と切れてしまったから、楽器の事など何ひとつ判らぬだろう?」
胸の真芯に突き立てられた鋼の刃の向こう側、思いがけぬ近しさで緩やかに笑う、蒼い瞳の奥底が、想像もしない程にひどく優しくて。
静寂の真中で鼓動が跳ねる。フォルテシモ。
……全てお見通し、という訳か。
壱師の花の燃えたつような双頬の緋色を、誤魔化す術も持たぬまま、ムウは寄る辺なく視線を揺らす。確かに故国の文化に疎すぎることは、自分の中でも些かの引け目となってはいたが、そんな瑣末な感傷事など、表に出した覚えは微塵も無いのに。……それにそもそも俗世と切れていたという事情なら、シオンとて同じはずである。ごく若い頃から修行に明け暮れ、その後は教皇として終身聖域に居た人が、一体いつの間に、このような物を。
「一応、十八の歳まではそれなりに好き勝手やれたからな」
琥珀色の絃を気紛れに爪繰りながら、何気ない横顔でシオンが言った。
「お前よりは十一年ほど多く、時間が有った」
特に師についた訳でも無い、見様見真似の素人芸ゆえ、腕前の方は全く保証できぬがな。そう付け加えてにやりと笑うが、いっそふてぶてしい程の言い草である。独学でこれだけこなせるというのなら、常軌の逸し方としては余計に酷い。謙遜なのだか傲慢なのだか、……そのような話題のそらし方もまた彼のさりげない気遣いなのか。
揺れる感情をどうにか押し隠しつつ、ムウがそんな事を思う間にも、眼前のシオンは先刻調律したばかりの絃を手慰みのように鳴らしては、巻き直したり緩めたりを繰り返している。長い指先でゆったりと、いかにも無造作な風でいて、その実、扱いは非常に丁寧であった。
「……申し訳ありません。やはり音の調子が変ですか?」
修復師としての真顔に立ち返りながら、ムウは恐る恐る問いかける。
「いや。そもそも新品の絃は張力ですぐに伸びるからな。初めのうちは安定しないものだろう」
いともあっさりと否定して、おもむろにシオンは視線を上げる。
「むしろ、想像していた以上にうまく直せていると思うが?」
どうやらこの短期間に随分と根をつめて学んだらしい。どことなく愉しげなシオンの口ぶりに、ムウは眦の緋色をいっそう深くする。あながち羞恥心ばかりという訳でもない。どれだけ齢を重ねても、幼少時に繰り返されたこの癖だけは、抜け難いものであるらしかった。
彼に褒められれば素直に嬉しい。どんな些細な言葉でも。
淡く透きとおる月明かりの下、夜来香の蕾が綻ぶように、ほんのりと密やかな微笑が漏れる。甘く薫りたつその面影に、シオンが僅かに眼を細くした。
「……いいえシオン、お言葉は嬉しいのですが、少々身に余ります。実は助力がありました」
書物と絃の束を指し示し、ムウは正直に打ち明ける。今さら抗うだけ無駄というものだ、頬の色は褪せる気配すらない。いちしろく。
「お前が幼い時分には、この様な物を見せてやる余裕など無かったからな」
流し目でシオンはちらりと笑って、そうして再びゆるやかな所作で、卓上の撥を手に取った。
深い水底に星の火が灯る。一つ二つ三つ、絲の鳴る毎に。遠い国の旋律を奏でる温かな指先に、声もなく無心に見とれていると、響きあう六絃の音色に和して、不意に柔らかく空気が揺れた。
古い魔法を紐解くように、夜の波間を漂うように、穏やかな低音が唄を口ずさむ。詩篇のかけらでも囁くような、経典の一節でも諳んじるような、ごくさりげないその歌声は、意外なほどに流暢で、耳に心地良い。天の汀にそっと打ち寄せる、淡くやさしい星屑の波。
……歌っている。
予想すらしなかった展開に、ムウはただ呆然と息を奪われる。初めて聴くその旋律は、どこか無性に甘く懐かしく、切なげな響きを織り交ぜて、素人耳にもひどく魅入られた。紡がれる歌詞にも覚えはないが、どうやら古い形式の四行詩であるらしい。抽象的で、少し不思議な――
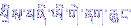
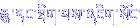

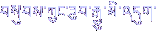
近くて遠かった、故郷の調べ。深い霧の向こうに埋もれたままの。
失くした過去の重さに寄り添うような、優しい音色に聴き入るうちに、不意に目の前に巨大な山脈がひらけた、ような気がした。
光の峰に風花が舞う。頭上には涯もない、永遠の蒼。幻のジャミールの空のもと、横顔のシオンが唄を口ずさむ。尾根道に降りそそぐ灼熱の陽射しを浴びて、低く伸びやかに古い詞を紡ぐ、面影の眩しさが胸を焼き切った。
風に流れる想いの破片。
神域を見晴るかす満月の下、温かな余韻を残して後奏が終わる。エピローグ。夜の静寂に溶け入るように、最後の一音がゆっくりと消える。……時を超えて。
冷めない頬の先を音もなく、涙がひとすじ伝って落ちた。