喜劇王ビギンズ
〜キーストンのチャップリン〜

「夕立」(1914年米)
チャールズ・チャップリンとフォード・スターリング
(「世界の映画作家19/チャールズ・チャップリン」より)
僕が映画好きになったきっかけがチャップリンだということは、以前「ほほ笑みと一粒の涙」で紹介した。だからチャップリンについては、正直いくら語っても語り足りないぐらいである。 そこで、もう一度チャップリンを取り上げようと思う。
チャールズ・チャップリン(1889〜1977)。言わずと知れた世界の“喜劇王”。以前指摘したように、彼は笑わすだけでなく、泣かせることもできたからこそ世界の喜劇王となり得た。チャップリンは生涯に82本の映画を製作しているが、俳優として出演するだけでなく、脚本を書き監督もする。そればかりか、トーキー以降は音楽を作曲し、「ライムライト」(1952年米)ではバレエの振り付けまで担当した。また、他のコメディアンたちがトーキー以降没落していく中、数年に1本というペースで作品を発表し続け、最後まで大物であり続けたように、時代の流れを読むことにも長けていた。
そんなチャップリンだが、もちろん最初から大物だったというわけではない。1914年「成功争い」(1914年米)でデビューした時のチャップリンは、助演という立場であった。その後も、しばらくは助演や悪役を務めている。チャップリンが監督に乗り出したのは、12作目の「恋の20分」(1914年米)が最初で、19作品には俳優として出演しているだけだ。
今回、大物になる前のチャップリンを追っていくことで、彼がいかにして“喜劇王”に上り詰めていったかを見ていきたいと思う。チャップリンは1914年2月 、マック・セネット(1880〜1960)率いるキーストンでそのキャリアをスタートさせた。彼は1915年にはエッサネイ社に引き抜かれることになるのだが、今回はキーストン社時代のチャップリンを取り上げたいと思う。
チャップリンが製作した映画は、従来81作品といわれていた。これは、チャップリンが「チャップリン自伝」の巻末につけたフィルモグラフィを元として、その後1971年にウノ・アスプランドが作品に通し番号をつけて整理したものに基づいている。その後2010年に、それまで知られていなかったチャップリン出演作である「泥棒を捕まえる人」(1914年米)が再発見され、82本目のチャップリン作品と認定された。
フィルモグラフィのうち、キーストン時代に製作された作品は全部で35本あるが、そのリストを整理するのが相当に困難であったことは想像に難くない。なにしろ映画創世記には、映画の製作・上映の記録がきちんと残っているわけではない。また、映画会社も利益をあげるために、同じ作品を題名を替えて何度も発売するということがざらにあった。中には別会社の名義にしてまで発売したようなこともあったという。実際、チャップリンの初期作品には複数の別タイトルを持つものが多い。日本においても同様で、再公開時にタイトルを替えて上映することも多く、やはり複数の邦題を持っている。
以下にキーストン時代のチャップリン作品の一覧を示す。英語題名については2012年時点での最新調査結果を基にしたDVD「チャップリン・ザ・ルーツ」解説の記述を採用することにし、邦題に関しては「世界の映画作家19/チャールズ・チャップリン」や「チャップリンのために」等を参照し、比較的よく知られているタイトルを複数あげることにした。
サイレント時代に製作された映画で現在までフィルムが現存しているものは1割に満たないという…。しかしながらチャップリンの場合は、82作中81本までが部分的なものも含めて現存している。2015年現在、フィルムがまったく存在していないのは、17番の「彼女の友人である追いはぎ」(1914年米)のみである。
| 公開 | 原題 | 主な邦題 | 監督 | |
| 1 | 1914.2.2. | Making a Living | 「成功争い」「成功争ひ」 | ヘンリー・レーヤマン |
| 2 | 1914.2.7. | Kid Aut Races at Venice, | 「ヴェニスの子供自動車競走」「ヴェニスにおける子供自動車競走」 | ヘンリー・レーヤマン |
| 3 | 1914.2.9. | Mael's Strange Predicament | 「メーベルのおかしな災難」「メーベルの奇妙な苦境」「メーベルの窮境」「犬の為め」 | メーベル・ノーマンド |
| 4 | 1914.2.19. | A Thief Catcher | 「泥棒を捕まえる人」 | フォード・スターリング |
| 5 | 1914.2.28. | Between Showers | 「夕立」 | ヘンリー・レーヤマン |
| 6 | 1914.3.2. | A Film Johnnie | 「チャップリンの活動狂」「新米活動屋」 | ジョージ・ニコルズ |
| 7 | 1914.3.9. | Tango Tangles | 「タンゴのもつれ」「タンゴがもつれる」 | マック・セネット |
| 8 | 1914.3.16. | His Favorite Pastime | 「アルコール先生お好みの気晴らし」「彼の好みの気晴らし」 | ジョージ・ニコルズ |
| 9 | 1914.3.26. | Cruel, Cruel, Cruel | 「痛ましの恋」「恋のしごき」 | ジョージ・ニコルズ |
| 10 | 1914.4.4. | The Star Boarder | 「幻燈会」 | ジョージ・ニコルズ |
| 11 | 1914.4.18. | Mabel at the Wheel | 「メーベルの身替り運転」 | メーベル・ノーマンド マック・セネット |
| 12 | 1914.4.20. | Twenty Minutes of Love | 「恋の20分」「恋の20分間」「半日ホテル」 | ジョゼフ・マダン |
| 13 | 1914.4.27. | Caught in a Cabaret | 「チャップリンの総理大臣」 | メーベル・ノーマンド |
| 14 | 1914.5.4. | Caught in the Rain | 「雨に降られて」「にわか雨」「とんだ災難」 | チャールズ・チャップリン |
| 15 | 1914.5.7. | A Busy Day | 「多忙な一日」「忙しい一日」「つらあて」 | マック・セネット |
| 16 | 1914.6.1. | The Fatal Mallet | 「命取りの木槌」「チャップリンの衝突」 | マック・セネット |
| 17 | 1914.6.4. | Her Friend the Bandit | 「彼女の友人は詐欺師」「彼女の友人である追いはぎ」「チャップリンの悪友」 | マック・セネット |
| 18 | 1914.6.11. | The Knockout | 「ノックアウト」「デブの選手」 | マック・セネット |
| 19 | 1914.6.13. | Mabel's Busy Day | 「メーベルの多忙な一日」「メーベルの忙しい一日」 | マック・セネット |
| 20 | 1914.6.20. | Mabel's Married Life | 「メーベルの結婚生活」 | マック・セネット |
| 21 | 1914.7.9. | Laughing Gas | 「笑いのガス」「笑いガス」 | チャールズ・チャップリン |
| 22 | 1914.8.1. | The Property Man | 「チャップリンの道具方」「チャップリンの小道具係」「チャップリンの舞台裏」 | チャールズ・チャップリン |
| 23 | 1914.8.10. | The Face on the Barrom Floor | 「チャップリンの画工」 | チャールズ・チャップリン |
| 24 | 1914.8.13. | Recreation | 「リクリエーション」「レクリエーション」 | チャールズ・チャップリン |
| 25 | 1914.8.27. | The Masquerader | 「男か女か」「男?女?」 | チャールズ・チャップリン |
| 26 | 1914.8.31. | His New Profession | 「チャップリンの新しい仕事」「チャップリンの看護人」「チャップリンの独立」「チャップリンの独身」 | チャールズ・チャップリン |
| 27 | 1914.9.7. | The Rounders | 「両夫婦」「二組の夫婦」 | ロスコー・アーバックル チャールズ・チャップリン |
| 28 | 1914.9.24. | The New Janitor | 「新米用務員」「新米雑役夫」 | チャールズ・チャップリン |
| 29 | 1914.10.10. | Those Love Pangs | 「恋の痛手」「髭のあと」 | チャールズ・チャップリン |
| 30 | 1914.10.26. | Dough and Dynamite | 「チャップリンとパン屋」「チャップリンのパン屋」 | チャールズ・チャップリン |
| 31 | 1914.10.29. | Gentleman of Nerve | 「アルコール自動車競走の巻」 | チャールズ・チャップリン |
| 32 | 1914.11.7. | His Musical Career | 「アルコール先生ピアノの巻」 | チャールズ・チャップリン |
| 33 | 1914.11.9. | His Trysting Places | 「他人のコート」「逢いびきの場所」「他人の外套」 | チャールズ・チャップリン |
| 34 | 1914.12.5. | Getting Acquainted | 「夫婦交換騒動」「チャップリンとメーベル」 | チャールズ・チャップリン |
| 35 | 1914.12.7. | His Prehistoric Past | 「アルコール先生原始時代の巻」 | チャールズ・チャップリン |
| 36 | 1914.12.21. | Tillie's Punctured Romance | 「醜女の深情け」「チャップリンの百万長者」 | マック・セネット |
◆デビュー作「成功争い」
チャップリンが映画界に入ったのは1913年12月のことであった。1912年10月、チャップリンは、当時所属していた劇団カーノー座のアメリカ巡業の一員に加わる。その際のステージを見たキーストン社のマック・セネットによってスカウトされた。マック・セネットの自伝によると、チャップリンに目をつけたのは、キーストンの看板女優でセネットの恋人でもあったメーベル・ノーマンド(1892〜1930)であった。初期のキーストン映画のスターだったフレッド・メイス(1878〜1917)が1913年4月にキーストン社を退社しており、その後釜を期待されてのことだった。また、当時のトップスターだったフォード・スターリング (1883〜1939)がキーストンからの独立を画策していたこともあり、その後継者も期待されていたようである。

「成功争い」(1914年米)
ヴァージニア・カートリー、ヘンリー・レーヤマン、チャールズ・チャップリン
(「チャップリン再入門」23ページ)
チャップリンがデビューしたキーストン社は、マック・セネット指導の下でコメディ映画で1時代を築いた。セネットとキーストンについては、機会を改めて述べることにしたいので、ここでは簡単に触れておくに留める。セネットは1908年にバイオグラフ社に入り、俳優として映画デビュー。映画の父D・W・グリフィス(1875〜1948)の下で俳優・助監督として活躍した。その後、1910年には監督にも進出している。そして1912年8月にキーストン社を設立し独立した。
キーストン映画の特徴はというと、いわゆるドタバタ(スラプスティック)コメディ。ストーリーは大概の場合、男女の仲のもつれなどのいざこざからいがみ合いが始まり、最後は追っかけで終わるというもの…。この追っかけに大量の警官隊―いわゆるキーストン警官隊(キーストン・コップス)が絡む場合も多い。キーストン映画の特徴としては、素早い場面の切り替わりで、テンポ良く追っかけを展開させたこと。セネットは、グリフィスの下で映画のキャリアをスタートさせているだけに、コメディであっても革新的な編集技術を取り入れていた。また、キーストン映画は、コメディ映画ではおなじみの“パイ投げ”を初めて取り入れたことでも知られている。
セネットは映画作りをチャップリンにこう語っている。「われわれはシナリオというものを持たないんでね――あるアイディアがうかぶと、あとは自然と事件の推移を追って、最後は追っかけの場面になる、これがわれわれの喜劇の本質なんだ」(*1)。キーストン映画では、実際にその場で行われていたイベントを積極的に取り入れている。例えばチャップリン作品だと「ヴェニスにおける子供自動車競争」(1914年米)ではベビーカーレースを、「多忙の一日」(1914年米)では軍隊のパレードを、「メーベルの多忙な一日」(1914年米)では競馬レースを背景に取り入れている。
また、キーストンは、個性豊かなキャラクターの俳優たちを多く雇い入れていた。デブのロスコー・アーバックル(1887〜1933)に、巨漢のフォード・スターリングやマック・スウェ イン(1876〜1935)、チビのチェスター・コンクリン(1888〜1971)に、のっぽのチャーリー・チェイス(1893〜1940)、スリムなスリム・サマービル(1892〜1946)に、やぶにらみのベン・ターピン(1874〜1940)…。3大喜劇王の一人ハロルド・ロイド(1893〜1971)もキーストンでデビューしている。セネットは1917年までキーストンで数多くのコメディを生み出し、笑いの王国を築いていった 。
セネットやキーストンはその後の映画界に大きな影響を与えたが、今日その評価は不当なまでに低い。何しろ、キーストン喜劇を鑑賞しようと思っても難しい。日本でソフト化されているのはチャップリンが出演した1914年の作品に限られている。しかし、近年YOUTUBE等の動画投稿サイトには数多くのキーストン作品がUPされており、観ることが容易になった。僕もこのエッセイの参考にするために片っ端から見てみたが、今なお十分に笑える映画が多く、決して色褪せていない。セネットの再評価はこれからだろう。
*1 チャールズ・チャップリン「チャップリン自伝/若き日々」301ページ

「成功争い」(1914年米)
ヘンリー・レーヤマン(中央)とチャールズ・チャップリン(右)
(「チャップリン 上」より)
記念すべきチャップリンの映画デビュー作は1914年2月2日公開の「成功争い」(Making a Living)であった。契約が前年の12月であったにも関わらず、 約1ヶ月もの間チャップリンは映画に出演していない。おそらく、この間にチャップリンは映画作りのノウハウをいろいろ学んだのであろう。「成功争い」はキーストンの第2撮影部監督だったヘンリー・パテ・レーヤマン(1886〜1946)の監督・主演作である。レーヤマンはオーストリア出身であったが、自称フランス人で、フランスの映画会社パテの代理人であるとの触れ込みでグリフィスのいたバイオグラフ社に入ったという。グリフィスは彼の嘘を見破ったものの面白がって“パテ”のニックネームを与えた。
この「成功争い」がどのような作品だったかを見てみたい。映画の冒頭、チャップリン演じるペテン師はやって来た主人公の新聞記者(演:レーヤマン)と何やら話をしている。ここでのチャップリンはフロックコートにシルクハット、ステッキ、そして八の字のドジョウひげ…。これがチャップリン出演作と知らずに見たとしたら、おそらく誰もチャップリンであると気がつかないのではないだろうか。チャップリンはこの新聞記者と、一人の令嬢(演:ヴァージニア・カートリー)をめぐって争う。あげくのはてに、ペテン師は新聞記者が手に入れた自動車事故の特ダネ写真を奪ってしまう。最後は、2人が殴り合っているうちに路面電車の前面部分に乗り上げ、それでも殴り合っているうちに幕を閉じる…。
今見てもそれなりに面白い。同時期のキーストン映画と比べても比較的手が込んだ作品と思われることからも、セネットらのチャップリンに対する期待が高かったことがうかがえる。しかしながら、セネットはこの映画を「大失敗だった」(*2)と語っている。その一方で、当時の業界紙には「詐欺師を好演する俳優は…第1級のコメディアンだ」(*3)と評したものもあったから、評価は当時から割れていたようだ。
チャップリンはこのデビュー作の製作に当たって、早くも大物ぶりを発揮し、監督のレーヤマンと衝突しまくったという。映画の中にチャップリンは多くのアイディアを出したが、レーヤマンはそれをことごとくカットした。2人の確執はそれからしばらく続くことになる。 チャップリンは結局、レーヤマン監督のもとで「ヴェニスにおける子供自動車競走」、「夕立」(1914年米)に出演するが、2人のコンビ作はわずか3作で終わっている。
*2 マック・セネット「〈喜劇映画〉を発明した男」198ページ
*3 デイヴィッド・ロビンソン「チャップリン上」148ページ

「ヴェニスにおける子供自動車競走」(1914年米)
チャールズ・チャップリンとヘンリー・レーヤマン(その右)
(「wikipedia:Kid Auto Races at Venice」より)
「成功争い」でのチャップリンは、我々の知っている姿ではない。あの放浪紳士チャーリーのスタイルが誕生するのは、それからすぐ後のことである。
チャップリンが例のスタイルに初めて扮したのはどの作品なのか、2つの説がある。チャップリンのフィルモグラフィの中で、最初に放浪紳士スタイルが登場するのは2作目の「ヴェニスにおける子供自動車競争」である。ところがチャップリンの自伝では、3作目の「メーベルの窮境」(1914年米)で初めて放浪紳士の格好をしたとある。当時の映画は1本製作するのに1週間もあれば十分だったから、製作開始は「メーベルの窮境」が先だったが、「ヴェニスにおける子供自動車競争」の方が先に完成したという意味だったのかとも思われる。

「メーベルの窮境」(1914年米)
メーベル・ノーマンドとチャールズ・チャップリン
(「チャップリン自伝 上」309ページ)
スウェーデンの映画学者ボー・ベルイルントは、関係者の証言や当時の天気予報などを調査した結果、「ヴェニスにおける子供自動車競争」の方が先に撮られたと断定している(*4)。「ヴェニスにおける子供自動車競争」 が無視されたのは、実際のベビーカーレースを背景に即興で作ったような作品なので、習作と見做されたからであろう。
一方、大野裕之(1974〜)は、第4作目「夕立」とのチャーリーの扮装の変化に注目し、自伝の通り「メーベルの窮境」が先だったとする(*5)。彼によると、「ヴェニスにおける子供自動車競争」と「夕立」ではチャーリーの扮装に違いは見られないものの、「メーベルの窮境」では微妙な違いがあるのだそうだ。そのことを知ってから僕も何度か作品を観返したのだが、正直紛争の違いについてはよくわからなかった。
当時のキーストン社のカメラマンだったハンス・コーンカンプ(1891〜1992)の証言によると、「メーベルの窮境」製作の際にチャップリンが初めて例の扮装をしたとのことである。さらにその後に発見されたキーストン社関係資料では「メーベルの窮境」は1914年1月6日から撮影が始まり12日に完成したとある。「ヴェニスにおける子供自動車競走」は1月10日に撮影されており、やはりチャップリンの回想は正しかったのだ。
自伝によると、セネットから「おい、なんでもいいから、なにか喜劇の扮装をしてこい」(*6)と言われたチャップリンは、衣装部屋へ行く途中で放浪紳士のスタイルを思いついたという。そうして、セネットに対してこう説明した。
「つまり、この男というのは実に複雑な人間なんですね。浮浪者かと思えば紳士でもある。詩人、夢想家、そして淋しい孤独な男、それでいて、いつもロマンスと冒険ばかりもとめている。自分じゃ科学者、音楽家、公爵、ポロ選手てなふうに考えてもらいたいと願っている。そのくせやれることというのは、せいぜい煙草のすいがら拾い、子供のあめ玉をちょろまかす、それくらいのことしかないんです。もちろん事と次第によっては、ご婦人の尻を蹴とばすことだってやりかねない」。
実際に撮影現場でここまで詳細に説明したとは思えないのだが、このチャーリーはやがてはチャップリン自身を離れて、独立した人格として大きく羽ばたいていくことになる。
*4 大野裕之「チャップリン再入門」24ページ
*5 以下、大野裕之による「チャップリン・ザ・ルーツ」解説20ページ
*6 以下引用はチャールズ・チャップリン「チャップリン自伝/若き日々」308〜310ページ

フォード・スターリング
(「チャップリン自伝 上」304ページ)
チャップリンがその後釜として期待されたフォード・スターリングは、1914年2月にキーストンから独立する。チャップリンが映画に出るようになってからは1ヶ月しか一緒ではなかったが、その間に4本の作品で共演している。「夕立」 、「チャップリンの活動狂」(1914年米)、「タンゴがもつれる」(1914年米)そして「泥棒を捕まえる人」である。スターリングは、キーストン警官隊の署長というヒーロー(?)を演じることも多かったが、その一方では悪役としても活躍している。もっとも、悪人というよりは、小賢しい小悪人といった感じではあるのだが…。
それがよく表れているのが、チャップリンの第4作にあたる「夕立」。夕立に見舞われたスターリングだが、持っているのは破れ傘。そこで、チェスター・コンクリン扮する警官の雨傘を失敬する。その傘をめぐって、チャップリンといがみ合うというのがストーリー。
スターリングの演技は、今見るとかなりのオーバーリアクション。彼が主演したキーストン時代の映画を見ると、傷だらけの画面でも、登場すれば一目でわかるほど。おそらく、当時の観客は彼がスクリーンに現れるだけで大笑いしていたに違いない。チャップリンによると、当時のキーストン社の俳優たちは、大スターのロスコー・アーバックルも含め誰もがスターリングの真似をしていた(*7)らしい。それだけ人気が絶大だったのだろう。
スターリングは「チャップリンの活動狂」と「タンゴがもつれる」 でもチャップリンと共演しているが、これらの作品ではあご髭の無い素顔で登場している。とりわけ、「タンゴがもつれる」ではチャップリンとスターリングが、ロスコー・アーバックルも交えて一人の女性(演:セイディ・ランプ)をめぐって争うという設定で、デビュー後間もないにも関わらずチャップリンは大スターのスターリングと肩を並べるほどの扱いである。当時のチャップリン の人気が瞬く間に上がっていったことがうかがえる。
1914年2月にキーストンから独立したスターリングだったが、人気はそれほどあがらず、結局1915年にキーストンに復帰している。
*7 チャールズ・チャップリン「チャップリン自伝 上」301〜302ページ
◆泥棒を捕まえる人
チャップリンとスターリングは、「泥棒を捕まえる人」(1914年米)でも共演している。この作品は、永らく存在自体が忘れられており、2010年になって発見されるという数奇な運命をたどった。製作順としては、3作目「メーベルの窮境」と4作目「夕立」の間に位置 している。発見された経緯は次の通り…。
2010年映画史家のポール・ギルミは、ミシガンの骨董市で「キーストン」と書かれた古い16ミリフィルムを購入した。その中に含まれていた映画のうちの一つに映っていたキーストン警官隊の中にチャップリンと思しき役者を見出した。その後の調査によって、これこそが若き日のチャップリンであることが確認され、「泥棒を捕まえる人」は82本目のチャップリン映画と認定された。
この「泥棒を捕まえる人」は、チャップリンが1914年8月に兄シドニー(1885〜1965)に充てて書いたフィルモグラフィに早くも記されていない(*8)。そのため、それから90年以上に渡って忘れられてしまうことになる。それにしてもなぜチャップリンは「泥棒を捕まえる人」の存在を忘れてしまったのだろう。チャップリンの記憶が確かである点は、50年以上後に書かれた「チャップリン自伝」の記述を見ても明らかである。その点はチャップリン研究家のデビッド・ロビンソン(1930〜)も舌を巻くほどで、「チャップリンの記憶はたいていの場合、他の証拠によって事実であることが確認されるので、証拠がないままに事実のくい違いが生じたときは、チャップリンの言をまず信用するのが妥当と思われる(*9)」とまで語る。ましてや、出演してからわずか半年後のことで あるから、チャップリンが「泥棒を捕まえる人」を忘れてしまったとは考えにくい。僕はチャップリンが意図的に作品をカウントしなかったのではないかと考える。なぜならチャップリンはあるインタビューの中で、「キーストン・コップの一人として何回かちょい役で出たこともある(*10)」 と語っているそうなのだ。その事実を覚えていて、作品を忘れているとは考えにくい。これまでチャップリンがキーストン警官隊を演じたその証拠は見つかっていなかったが、「泥棒を捕まえる人」 の発見によって、その発言が事実であることはわかった。しかし、この彼の発言を信じる限り、作品は他にもあったように思われる。
チャップリンはそのデビュー作「成功争い」からしてすでに主役級の大きな役を演じていた。2作目の「ヴェニスにおける子供自動車競争」が最初の主演作である。その後も、助演的な立場での出演作はいくつかあるが、いずれも作品において重要な役割を演じている。例えば、ロスコー・アーバックル主演の「ノックアウト」(1914年米)。 この作品のチャップリンは、終盤のボクシングのシーンでレフェリーを演じている。30分程の作品だが、チャップリンの出演シーンはわずか2分で、ほんのちょい役にすぎない。しかし、このシーンだけに限ると、チャップリンはアーバックルを食っている。その面白さは、後年の「街の灯」(1931年米)のボクシングシーンをも彷彿させる。そのため、いかにもアーバックルとチャップリンの共演作のような扱いで公開されたそうだ。そういう理由もあって「ノックアウト」はチャップリン本人のフィルモグラフィにもきちんと載せられているのだろう。その一方、「泥棒を捕まえる人」の場合、随所にチャップリンらしい動きが見られ 、ラストシーンでは主演のフォードと一緒に倒れるなどオチを担当してはいるものの、ほとんど印象に残らないほどの役にすぎない。だからチャップリンは、この作品を自身の作品として認めなかったのではないだろうか。
実際チャップリンはフィルモグラフィにある82作以外にもいくつかの作品にゲスト出演している。例えば、「彼の更生」(1915年米)は、チャップリンがキーストンから移籍したエッサネイの作品であるが、エッサネイの共同出資者であったブロンコ・ビリーことギルバート・M・アンダーソン(1880〜1971)の主演作。チャップリンは脚本を担当する他に、浮浪者の役で端役出演している。また、キング・ヴィダー (1894〜1982)監督、マリオン・デイビス(1897〜1961)主演の「活動役者」(1928年米)を観たことがある。チャップリンはマリオン演じるスター女優に、サインを求めるチャップリンその人として素顔で出演している。他にも「ナット」(1921年米)や「ホリウッド」(1928年米)などにもゲスト出演しているが、僕は観ていない。これらの作品も、チャップリンの作品として取り扱われることはほとんどない。
*8 ロビンソン「チャップリン 上」163ページ
*9 同書 5〜6ページ
*10 同書 165ページ
◆ジョージ・ニコルズと「アルコール先生」
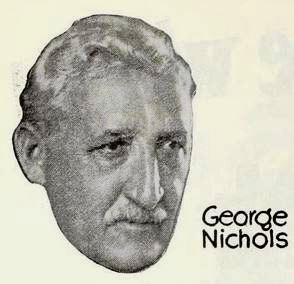
ジョージ・ニコルズ
(「wikipedia:George
Nichols(actor)」より)
チャップリンとヘンリー・レーヤマンとの間に確執が生まれたため、6作目の「チャップリンの活動狂」(1914年米)からはジョージ・ニコルズ(1864〜1927)が監督に当たることになった。ニコルズは、セネットと同じくD・W・グリフィス傘下の俳優としてキャリアをスタートさせ、1911年に監督に進出。セネットの独立にあたって志を同じくした。チャップリンはニコルズを当時「もう六十近い老人だった(*11)」と回想しているが、実際にはまだ50歳であった。とはいえ、ニコルズは製作責任者セネットより16歳年上で、キーストンの中でも老練な監督であった。おそらくセネットはニコルズならばチャップリンを御することができると判断したのではないだろうか。
しかし、相変わらずチャップリンはニコルズに対しても反発し続けた。ニコルズに対しチャップリンは、「あんたが要求するようなことは、一日三ドルのエキストラだってやれますよ。(*12)」と食ってかかった。
2人のコンビ作は「チャップリンの活動狂」、「アルコール先生彼の好みの娯楽」(1914年米)、「痛ましの恋」(1914年米)、「幻燈会」(1914年米)と4作作られた。2人のソリは合わなかったが、それまでスターリングやメーベルの共演者にすぎなかったチャップリンが本格的な主演デビューを飾ったのは彼のもとであった(即興で撮られた「ヴェニスにおける子供自動車競走」は除く)。チャップリンは「ちょうどうまく登場の瞬間とか退場の瞬間に、すばやくギャグを入れる(*13)」ことで、自分らしさを出していったと語っているが、実際 この時期の作品では随所にチャップリンらしさが現れてくる。それと同時にチャップリンの人気もこの頃から爆発的にあがっていった。チャップリンはこの頃、映画製作の方針をめぐってセネットと衝突し、セネットも一度はチャップリンを首にしようと決意する。それが、ニューヨークからの「チャップリン映画が大当りしているから、至急もっと彼の作品をよこせ(*14)」という電報で、態度を改め たという。また、「A Film Johnnie(新米活動屋)」に「チャップリンの活動狂」という邦題がつけられたように、日本でもこの頃にはチャップリンの存在がファンの間でも 認知されたようだ。
また、「アルコール先生彼の好みの娯楽」は、日本におけるチャップリンのあだ名である「アルコール先生」が初めて冠された作品である。「アルコール先生」の題名のつく作品は他にも「アルコール先生ピアノの巻」(1914年米)、「アルコール先生原始時代の巻」(1914年米)、「アルコール先生公園の巻」(1915年米)、「アルコール先生海岸の巻」(1915年米)がある。チャップリンは映画の中でしばしば秀逸な酔っ払いの演技を見せ、それが「アルコール先生」というあだ名につながった。そういえば、初めてチャーリーの扮装をした「メーベルの窮境」からして、チャーリーは酔っぱらっていた。いや、そもそもチャップリンが映画界にスカウトされたのも、舞台での彼の酔っ払い演技が認められたからなのである。ともかく、「アルコール先生彼の好みの娯楽」の頃に初めて日本ではチャップリン=アルコール先生という認識がなされたといえる。
そんな記念すべき「アルコール先生彼の好みの娯楽」では、チャーリーは酒場で女性を見初めて彼女の家までついていったため、旦那とトラブルになる。愛しの彼女と思って声をかけたら黒人メイドだったという、今なら考えられないような人種差別的なギャグが出てくるが、こうしたギャグは当時はごく普通に行われていたことで、チャップリンも疑問を持っていなかったのだろう。
この時期のチャップリンは、キャラクターについて色々と試行錯誤していたようである。例えばセネット自身が監督した「タンゴがもつれる」にはチャップリンは素顔で出演している。「痛ましの恋」ではデビュー作「成功争い」を思わせる八の字髭にフロックコートのスタイル。シルクハットにフロックコートという姿はニコルズの下から離れた後の「メーベルの身替り運転」(1914年米)でも見られるが、ここではあご髭を蓄えている。さらに、「多忙な一日」(1914年米)では女装演技も見せる。チャーリーのキャラクターが定着するには、もう少し時間がかかった。
この時期のチャップリンの作品には、後のチャップリンのルーツがあれこれと見られる点で興味深い。例えば、「痛ましの恋」のストーリーは、失恋したと勘違いして毒を飲んだ主人公(チャップリン)が、誤解とわかって大慌てするが、実は飲んだのが水だったとわかって一安心するというもの。後にこのエピソードは「チャップリンの殺人狂時代」(1947年米)で再現されている。
*11 チャップリン「チャップリン自伝 上」315ページ
*12 同書 317ページ
*13 同書 318ページ
*14 同書 324ページ
メーベル・ノーマンド
(「チャップリン 上」より)
レーヤマン、ニコルズといったベテラン監督の次にチャップリンが組んだのはメーベル・ノーマンドだった。メーベル・ノーマンドは当時のキーストンの看板女優であった。バイオグラフで映画デビューした後、マック・セネットと共にキーストンに移る。彼女のことをチャップリンは自伝でこう語っている。「まったくかわいい女だった。ちょっとはれぼったいような瞼をした大きな眼、両端が軽く曲線を描いたふくよかな唇、それはなんともいえぬユーモアと、複雑な気まぐれさを見せている。明るくて、親切で、気がよくて、みんな誰にも好かれていた(*15)」。さらに、一度などは「ほとんど恋の一歩手前まで行った(*16)」そうだ。キーストン時代のチャップリンの恋人はペギー・ピアース(1894〜1975)で、「アルコール先生彼の好みの娯楽」などで チャップリンと共演している。チャップリンが、その後多くの女性と浮名を流し、生涯に4度結婚したことを考えると、チャップリンがメーベルに好意を持っていたのはあり得る話であるが、メーベルのほうはどう思っていたのだろうか? ちなみにメーベルはこの当時セネットの恋人であった。1915年7月4日にセネットとメーベルは結婚式をあげる予定を立てるところまでいくのだが、結局破局してしまった。
そんな美人女優ではあったが、メーベルは当時の喜劇映画にありがちな彩りを添えるだけの立場には留まらなかった。自ら積極的にギャグやアクションをこなす。例えば、チャップリンと共演した「メーベルの身替り運転」(1914年米)では、チャップリンの運転するバイクの後部座席に座ったメーベルが振り落とされて水たまりに落ちるなんてシーンまであるぐらいだ。また、自ら監督を務めるほどの才媛であった。すでにチャップリンとは、彼のデビュー第3作「メーベルの窮境」で共演していた。
チャップリンとメーベルが再び組んだ作品は「メーベルの身替り運転」(1914年米)であった。チャップリンは、自分がメーベルの組に配属されたことを知って「憤然となった(*15)」。なぜなら、「メイベルが魅力的なことは認めるが、監督としての腕には疑問があったからだ」とのこと。その撮影第1日目に2人はさっそく衝突する。「メーベルの身替り運転」は、恋人の代わりにレースに出ることになった女性(メーベル・ノーマンド)が主人公で、チャップリンは悪役に扮する。チャップリンが水を撒いたために、車が横滑りするという場面があったが、チャップリンはそれに対して、「まずホースを踏んで水をとめ、筒先をのぞく拍子に、無意識に足が動いて、さっと水がかかるようにしてはどうだ」と提案した。リュミエール兄弟による喜劇映画の元祖ともいうべき「水をかけられた撒水夫」(1895年仏)を思い起こさせるギャグではあるが、その提案をメーベルは「そんな時間はないわよ! あんたはね、ただ言われたとおりにしてりゃいいの」といって拒絶した。チャップリンはそれに抵抗し、撮影をボイコットした。
結局、その日の撮影は中止となり、セネットは激怒。一度はチャップリンの首が決まるが、先にも述べた通り、彼の絶大な人気を知ったセネットによって首は取りやめとなる。セネットは結局、チャップリン自らに監督させるよう約束し、「とにかく、メイベルの作品を上げてくれたまえ。話はそれからだ」ということで、チャップリンもメーベルに謝ることになった。現存の「メーベルの身替り運転」には、チャップリンが水を撒くシーンはあるが、ホースを踏むギャグはないので、結局チャップリンの方が折れたようである。メーベルはそれ以降、チャップリンの意見を進んで聞くようになった。2人の共演は計12作を数え、「メーベルの結婚生活」(1914年米)では2人は共同監督をしている。
「チャップリンの総理大臣」(1914年米)もまた、メーベルの監督作で、チャップリンが出演している。ここでのチャーリーはスラム街のレストランのウェイター。そのチャーリーが、上流階級の娘メーベルを射止めるためにグリーンランドの総理大臣のフリをするという内容。チャーリーが上流階級の人間に成りすますというパターンは、後に「チャップリンの伯爵」(1916年米)や「チャップリンのスケート」(1916年米)などで繰り返された。後年の名作「街の灯」もそのパターンの一種だといえる。チャップリンのルーツがここにも見て取れる。
*15 チャップリン「チャップリン自伝 上」332〜333ページ
*16 同書 333ページ
*17 同書318ページ
以下の引用も同書318〜319ページ

「チャップリンの総理大臣」(1914年米)
メーベル・ノーマンドの監督作品
(「チャールズ・チャップリン」81ページ)
チャップリンとメーベルのコンビ作のうち、僕は「メーベルの結婚生活」(1914年米)を最高傑作だと思っている。メーベルの旦那のチャーリーは、公園で女たらしのウェリントン(演:マック・スウェイン)に絡まれてもやり返すことができない。メーベルはそんな夫を鍛え直そうと、スプリング付きのダミー人形を買ってくる。酔っぱらって帰宅したチャーリーは、その人形をウェリントンだと勘違い。一人悪戦苦闘する…。
チャップリンが人形を相手に見せる抜群のパントマイム芸が見どころとなっている。無生物を相手のパントマイムというと、後の「午前一時」(1916年米)が思い浮かぶが、これはその先駆的作品と見ることができる。

チャップリン初監督作(?)
「恋の二十分」(1914年米)
(「世界の映画作家19/チャールズ・チャップリン」81ページ)
セネットに約束された、チャップリンの監督デビューは、1914年4月のことである。実は、チャップリンの監督デビュー作がなんであったのかははっきりしていない。自伝によると、チャップリンの最初の監督作は、「とんだ災難」(1914年米)である。ところが1914年8月のフィルモグラフィでは、その1つ前に製作された「恋の二十分」 (1914年米)をはっきりと「自身の作品(My own)」と記している。大野裕之によると、キーストンの記録ではその「恋の二十分」の監督はジョゼフ・マダンだという(*16)。マダンはブロードウェイ俳優の出身で、1914年に短期間だけキーストンに所属していた。チャップリンは監督デビューするに当たり、不安がるセネットに対して、「どこでもお望みの銀行に千五百ドルあずけておきますからね、もしその作品が売れなかったら、そのお金を取ってもらって結構です(*17)」と見得を切った。そこで、スケジュールや予算の管理、カメラのセッティングなどの実務的な部分を担当する者としてマダンが起用されたのではないかと、大野は推測している。
チャップリンが自伝で「恋の二十分」を無視した理由についてロビンソンは、「『恋の二十分』に関しては五十年の歳月のうちに忘れてしまったとも考えられるし、習作とみなして省いたとも考えられる(*18)」と推測している。確かに、「恋の二十分」は公園で即興に撮ったかのようなたわいもないドタバタである。とある男(演:チェスター・コンクリン)が、恋人(演:イーヴァ・ネルソン)へのプレゼントにと、寝ている男(演:ジョゼフ・スウィッカード)のポケットから時計を失敬。それをチャーリーが横取りしたことから、追っかけが始まる…。しかしながら、ドタバタではありながらも、公園でいちゃついているカップル(演:エドガー・ケネディ、ミンタ・ダーフィ)に嫉妬したチャーリーが側の木に抱き着くという、どこか哀愁を誘うギャグが出ていたりと、後のチャップリン映画に通じるものが見られる。この作品の実質的監督がチャップリンだというのは、間違いないだろう。
一方、クレジット上においても正真正銘のチャップリン監督作の「とんだ災難」の場合はどうか。冒頭では、「恋の二十分」同様に公園でのドタバタが展開する。 チャーリーが公園で見かけた女性(演:アリス・ハウエル)にちょっかいを出すと、その旦那(演:マック・スウェイン)が激怒しぶちのめされる。その後、舞台はホテルに移り、酔っぱらったチャーリーが、先ほどの夫婦の部屋に間違えて入ったことから、浮気が疑われ…。おまけに夢遊病だった奥さんが、チャーリーの部屋に入ってきたものだから、ますます騒動が大きくなる。「恋の二十分」に比べれば、内容はだいぶ洗練されている。しかしながら、最後はキーストン 警官隊も交えてのドタバタで、まだまだこの頃のチャップリン作品は後年の作品とは大きく違った味わいである。
*16 以下、大野裕之による「チャップリン・ザ・ルーツ」解説33〜34ページ
*17 チャップリン「チャップリン 自伝」323ページ
*18 ロビンソン「チャップリン 上」162ページ

キーストン時代のマック・セネット
(「チャップリン 上」より)
1914年4月に監督デビューしたチャップリンであるが、その後再びマック・セネットの監督作に出演するようになる。チャップリンがセネット作品に出演したのは、キーストン期を通じて全9作に及ぶが、これはもちろん最多である。チャップリンも、「セネットが監督だと、まことに気が楽だった(*19)」と語る。セネットはどのような意見もよく受け入れてくれたらしい。
実は、ごく最近までセネットの監督作のいくつかが、チャップリンの監督作だと見なされていた。例えば、内田精一の「チャップリン全作品解説」によれば、セネット監督作のうち、「多忙な一日」がチャップリン単独監督作。「チャップリンの衝突」 (1914年米)がチャップリンとセネットの共同監督。「チャップリンの総理大臣」、「彼女の友人である追いはぎ」(1914年米)、「メーベル多忙の一日」(1914年米)、「メーベルの結婚生活」がチャップリンとメーベルの共同監督とされている。それが、 近年の調査によってこれらがセネットの監督作であることが判明 した(*20)。ところが、1914年8月のフィルモグラフィにおいてチャップリンは「メーベルの結婚生活」を「自身の作品」としてあげているのだ。メーベルもまた、1922年のインタビューにおいて「メーベルの結婚生活」を自身とチャップリンの共同監督作だと述べているそうである(*21)。このことからわかるのは、セネットは自身が監督する作品であっても、時には出演者たちに自由に撮らせたことがあったということではないか。そういう意味では、他の作品の場合も、チャップリンが実質的に監督した作品が含まれているのかもしれない。
「多忙な一日」(1914年米)はチャップリンが女装し、嫉妬深い妻を演じる異色作。「男か女か」(1914年米)、「チャップリンの女装」(1915年米)とチャップリンが女装演技を披露する作品は他にもあるが、この作品はチャップリンが‟女性”を演じた唯一の作品である(他の2作は男性が女装するという設定)。ここでの妻は、夫(演:マック・スウェイン)や警官に殴られたり突き飛ばされたり散々な目にあったあげく、最後は海に突き落とされる。以前「寂しい熱帯魚たち」で、アメリカ映画の女形というのはグロテスクさでもって滑稽さを表すために用いられることを指摘したが、この作品も例外ではない。もっとも、「男か女か」と「チャップリンの女装」では、チャップリンの女装ぶりは見事で、十分美しく仕上がってはいるのだが…。
「チャップリンの衝突」(1914年米)も印象的な作品だ。チャップリンは、セネット、マック・スウェインと3人でメーベルをめぐって争いを繰り広げる。「チャップリンの活動狂」 、「メーベルの身替り運転」、「ノックアウト」など、チャップリンとセネットが同じ映画に出演した例も他にあるが、2人が同じシーンで共演しているのは「チャップリンの衝突」が唯一だけに、大変貴重な作品だといえる。3人の恋のさや当ての末に、メーベルを手に入れたのはセネット。最終的に制作責任者がその面目を守った形になった。
セネットは1914年には、90分にも及ぶ大作「醜女の深情け」を製作し、チャップリンが出演しているが、この作品については後で詳しく取り上げたいと思う。
*19 チャップリン「チャップリン自伝 上」314ページ
*20 「チャップリン・ザ・ルーツ」大野裕之による解説15〜16ページ
*21 同書 33〜34ページ
チャップリンに関しては、近年新たな資料が数多く見つかり、これまで定説と言われた事の多くが覆っている。作品に関しても同様で、2012年に「泥棒を捕まえる人」が再発見されたことは先にも述べた通りだが、かつては存在しないと言われていたチャップリン作品の多くが、近年になって発見されている。例えば、内田精一「チャップリン全作品解説」において「残存プリント」不明とされた作品は計5作品あったが、それらの大半はその後発見された。現在、チャップリンが製作した映画全82作のうち、フィルムが確認されていないのは、「彼女の友人である追いはぎ」のみである。
「彼女の友人である追いはぎ」がどのような作品なのかは、文字情報でしか残っていない。「チャップリンが伯爵に化けて、メイベルの上流階級パーティに潜り込み、騒動に。最後は偽伯爵のチャップリンが警察に捕まる(*22)」というもの。内容は後の「チャップリンの伯爵」(1916年米)に似ているようだ。この作品の中でチャップリンは山賊でもある詐欺師に扮しているとされている。「…されている」と断ったのは、実はこの作品にチャップリンが出演していないという説があるからである。チャップリン自身が1914年に作成したフィルモグラフィに「彼女の友人である追いはぎ」は題名すらあげられていない。また、英国映画協会のブライオニー・ディクソン研究員の調査によると、当時のキーストン社の広告では、他のチャップリン出演作品の場合は広告にチャップリンの名前が載せてあるのに対し、「彼女の友人である追いはぎ」に限っては名前が出ていないという(*23)。その一方、「チャップリン自伝」のフィルモグラフィには「彼女の友人である追いはぎ」は載せられている。「泥棒を捕まえる人」(A Thief Catcher)がフィルモグラフィから抜け落ちているのは、「彼女の友人である追いはぎ」の別タイトルが「The Thief Catcher」とあるのと混同した可能性も考えられる。
しかし大野裕之は、1916年のアラスカの新聞広告にはきちんとチャップリンの名前が出ていることを根拠に、「彼女の友人である追いはぎ」は紛れもなくチャップリン出演作であると断定している(*24)。この映画を監督したマック・セネットも、この作品がチャップリンの出演作であると自伝の中で回想していることもあり、チャップリン出演作であることは間違いないと思われる。いずれにせよ、作品を観ることができない以上、これ以上の判断は困難である。
試しに動画サイトで「彼女の友人である追いはぎ(Her Friend the Bandit)」を検索してみた。するとそれらしい映像が見つかった(参照)。さっそく見てみた。一見してわかったことは、それが「彼女の友人である追いはぎ」ではないということだった。チャーリーは山賊で伯爵に化けるというのに、ここでは床屋に扮している。ストーリーも、床屋のチャーリーが引き起こす騒動がメインで、「彼女の友人である追いはぎ」のあらすじとはまったく違う。メーベル・ノーマンドも出演していないし、作中に登場する巨漢はエリック・キャンベル(1879〜1917)らしい。キャンベルがチャップリンの共演者だったのは1916年から1917年にかけて所属していたミーチュアル社時代のことなのだが、このような作品はチャップリンには存在していない。なんとも不思議である。
結論から言うと、この映画はチャップリン作品ではなく、その模倣者として知られるビリー・ウェスト(1982〜1975)主演作「 彼の一日の終わり(His Day Out)」(1918年)なのである。 エリック・キャンベルと思われる人物は、後に「ローレル&ハーディ」として成功するオリバー・ハーディ(1892〜1957)がキャンベル風にメイクをしたもの。このビリー・ウェストはチャップリンの模倣者としては最も成功を収めた人物で、寝るときには髪をカールし、左利きでバイオリンを練習するほどの徹底ぶり(*25)。おかげで今日でも彼の主演作がチャップリンの未発見作品として紹介されるようなことさえあるという。クローズアップになった時に、チャップリンより顔が四角いのが見分ける方法だそうで、確かに見ていてどことなく違和感があるとはいうものの、正直わかっていても区別をするのは困難だ。
*22 「チャップリン・ザ・ルーツ」大野裕之による解説38ページ
*23 大野裕之「チャップリン未公開NGフィルムの全貌」253ページ
*24 「チャップリン・ザ・ルーツ」大野裕之による解説38〜39ページ
*25 大野裕之「チャップリン未公開NGフィルムの全貌」201〜202ページ

「醜女の深情け」(1914年米)
マリー・ドレスラー、チャールズ・チャップリン、メーベル・ノーマンド
(「アメリカ映画200」9ページ)
1914年4月、マック・セネットは野心的な作品の製作に着手した。それが、上映時間90分にも及ぶ「醜女の深情け」(1914年米)である。
当時の映画というのは、たいていが10分、20分の短編であった。もっともヨーロッパでは、上映時間2時間の「クォ・バディス」(1912年伊)や4時間(ただし現存作品は1時間半)の「カビリア」(1913年伊)などの長編が作られていた。一方のアメリカではヨーロッパに遅れを取り、「まぐさ桶から十字架へ(From the Manger to the Cross)」(1912年米)や、「巌窟王」(1913年米)といった作品が5巻物の映画(約50〜100分)として製作され始めてはいたが、あくまで例外的なものだった。ましてや、コメディに至っては前代未聞 である。セネットの師ともいうべきD・W・グリフィスが2時間30分にも及ぶ大作「国民の創生」(1914年米)の製作に着手したことに刺激を受けたのかもしれない。
史上初の長編コメディということで、キーストンのオーナーも製作に慎重にならざるを得なかった。そこでセネットはネームバリューのある俳優として、ブロードウェイの大スター、マリー・ドレスラー(1868〜1934)の起用を提案した。セネットは故郷カナダにいた当時、このドレスラーの助言でショービジネスに入ったという縁があった。
助演に起用されたのがチャップリンとメーベル。メーベルは当然としても、チャップリンが選ばれたということは、彼がすでにキーストンを代表する大スターだったことの証明であろう。
原作は、ドレスラーの舞台での当たり役だった「ティリーの悪夢」。これをハンプトン・デル・ルース(1879〜1958)が脚本化。初の長編映画ということもあり、監督には製作部門の責任者であるセネット自身が当たった。撮影開始は1914年4月14日で、6月9日まで2ヶ月近くを費やしている。当時のコメディは1週間もあれば完成していたことを考えると破格の撮影期間である。この時期はチャップリンのキャリアでいうと、いったん自分で監督するのをやめ、セネット監督作に出演した頃であるが、セネットは長編を撮る一方で、短編を次々と監督していたのだから、おそるべきバイタリティである。
主演のマリー・ドレスラーは当時46歳。映画女優としては遅咲きであった。170センチと大柄であるにもかかわらず、純情な田舎娘ティリーに扮する。それがグロテスクなおかしみを醸し出すという、なんとも俗悪な喜劇だといえる 。
ストーリーは以下の通り。チャップリン演じる都会のイカサマ師が、ドレスラー演じるティリーの投げたレンガが頭に当たって昏倒する。彼女の家に担ぎ込まれたチャーリーは、ティリーの父が札びらを切って支払いをしているのを見て、彼女をカモにしようと決める。チャーリーに唆されたティリーは、有り金をハンドバッグに詰めて2人で家出する。メーベル演じるのはチャーリーの情婦。チャーリーとメーベルはティリーのハンドバッグを持って逃走。ティリーは無銭飲食として警察に捕まってしまう。
富豪の姪であることがわかったティリーは釈放される。そのティリーの叔父が遭難して、ティリーが遺産を相続することを知ったチャーリーは、慌ててティリーに求婚する。チャーリーとティリーの結婚パーティ。その家にメイドとして働いていたメーベルと再会したチャーリー。2人が抱き合っているの見たティリーは、嫉妬して拳銃を乱射。パーティは大混乱となり、キーストン 警官隊が駆け付ける…。
「醜女の深情け」(1914年
米)
左よりチャップリン、マリー・ドレスラー、メーベル・ノーマンド
(「世界の映画作家19/チャールズ・チャップリン」より)
長編ということもあり、ストーリーもしっかりと練られているし、シチュエーションの面白さを重視した部分もある。明らかに当時のキーストン喜劇とは違った味わいの作品だ。しかしその一方で、クライマックスにキーストン 警官隊による追っかけを取り入れるなど、十分にドタバタの面白さも組み込まれている。
「醜女の深情け」は大ヒットし、批評家の評判も良かった。もっともチャップリン自身は「マリイと一緒で仕事は楽しかったが、作品の出来はたいしたことなかった(*26)」と語るに留めている。マリー・ドレスラーはこう回想している。「撮影所のなかでまだ無名だったチャップリンに目が止まった。彼とメイベル・ノーマンドとをこの映画に引き入れることにした…世間の人たちも私の目に狂いがなかったことを認めてくれることと思う。というのも、チャーリー・チャップリンにとって事実それが初めて手にしたチャンスだったのだから(*27)」これは明らかな間違いで、すでに述べたようにチャップリンはこの当時にはキーストンの中でも有数の大スターであった。ドレスラーはブロードウェイでは大スターであったものの、国際的には無名であったから、海外市場も意識してチャップリンとメーベルを脇に配したというのが実情であっただろう。
マリー・ドレスラーは「醜女の深情け」での成功を受けて、その後も「ティリーのトマト奇襲(Tillie's Tomato Surprise)」(1915年米)と「チリーの覚醒」(1917年米)で当たり役のティリーを演じた。さらに「女掃除番」(1917年米)、「俄看護婦」(1918年米)にも出演したものの、成功を収めることはできず映画界をいったん引退している。1926年にはMGMの脚本家フランセス・マリオン(1887〜1973)の後押しで映画界に復帰。「惨劇の波止場」(1930年米)では62歳にてアカデミー主演女優賞を受賞した。残念ながら僕は「惨劇の波止場」を観る機会に恵まれていないが、同じ年にグレタ・ガルボ(1905〜90)主演作の「アンナ・クリスティ」(1930年米)で印象的な役を演じているのを観ることができた。
*26 チャップリン「チャップリン自伝 上」338ページ
*27 ロビンソン「チャップリン 上」169ページ

「チャップリンの画工」(1914年米)
(「チャールズ・チャップリン」81ページ)
1914年6月、「醜女の深情け」への出演を終えたチャップリンは、再び監督に復帰した。チャップリン自身も「よろこんでまた自作の監督に戻った(*28)」と語る。一度監督を経験した後、セネットのもとで再び俳優として映画のノウハウを学び、満を持しての復帰であった。実際、この時期のチャップリンの作品には、キーストン期でも充実した作品が多く。後のチャップリンにつながるものが数多く見られる。
監督復帰第1作となったのは「笑いのガス」(1914年米)。この作品でのチャップリンは、歯医者の助手を演じる。歯医者がいない隙に勝手に患者の治療を始めたチャーリーが引き起こす騒動が描かれる。歯医者の椅子や、治療器具が笑いの小道具として使われ、これ以前のチャップリン監督作である「恋の20分」や「とんだ災難」に比べてもストーリーやギャグはより洗練されている。
歯医者を舞台にしたコメディは、チャップリンのルーツであるミュージック・ホールでしばしば演じられたというが、次の「チャップリンの道具方」はそのミュージック・ホールが舞台そのものとなっている。チャーリーはミュージック・ホールの道具方に扮している。当時のミュージック・ホールの有様を知ることができる点でも興味深い。クライマックスは、チャーリーがホースで水を撒いて、舞台から客席からすべてを水浸しにするというもの。すでに「チャップリンの活動狂」で同様のギャグが見られたが、晩年の「ニューヨークの王様」(1957年英)で非米活動委員会に対する放水まで何度となく繰り返し用いられている。
このように監督に復帰したチャップリンだったが、以降チャップリンは遺作となる「伯爵夫人」(1967年英)まですべての作品で自作自演を貫くことになる。キーストンでのチャップリン監督作は、16作を数える(共同監督含む。「恋の20分」は除く)。後のチャップリンを思わせる作品が少しずつ見られるのがこの時期だと言える。
この時期には、ペーソス色の強い、後のチャップリン作品を思わせる映画がいくつも作られた。
例えば、「チャップリンの画工」(1914年米)。これは詩人ヒュー・アントワーヌ・ダルシー(1843〜1925)の詩を原作としている。飲んだくれの浮浪者となった元画家が、酒場で自身が転落していく様子を語るという、およそ喜劇とは思えないシチュエーションで幕を開ける。原作の詩がほぼそのままの形で字幕としてあらわれるが、チャーリーの恋人を奪った男を「ある色男」としながら 、演じるジェス・ダンディ(1871〜1923)はそれとはおよそかけはなれたハゲデブおやじであったり、元恋人とその男を「一年もたたぬうちに」見かけた時、とてもその期間ではありえないほどの数の子供を連れていたりと、映像はパロディとして描かれている。最後は、床にチョークで元恋人の似顔絵を描いた後に息絶えるチャーリーと、笑いよりも哀しさが強調された作品であった。
また、「新米雑役夫」(1914年米)も、低所得労働者の悲哀を描いたという点で、後年のチャップリンの名作を思い起こさせる。ここでのチャーリーは、とある銀行の用務員。チャップリンによると「単なるお笑いだけに終わらせず、いま一つ、別の面を加えたと思うようになったきっかけ(*27)」の作品だという。支配人によって首にされそうになったチャーリーは、自分に小さな子供が大勢いることを必死に訴える。この場面を眺めていた老女優ドロシー・ダヴェンポートが泣いていることを発見したチャップリンは、自身が笑わせるだけでなく泣かせることができることに気づいたのだという。ちなみに、泣いていたのがドロシー・ダヴェンポートだというのはチャップリンの勘違いだったようだ。というのも、ドロシー・ダヴェンポート(1895〜1977)はこの当時19歳。大野裕之は、その母親のアリス・ダヴェンポート(1864〜1936)のことであったろうと推測している(*28)。
この「新米雑役夫」は、その後よりペーソス感を強めた形で「チャップリンの掃除番」(1915年米)で再現されているが、「男か女か」(1914年米)も、後の「チャップリンの女装」(1915年米)の先駆的な作品。すでにチャップリンは「忙しい一日」で女装演技を見せていたが、この「男か女か」は、知らずに見たら僕らも騙されるほどの見事な女っぷりを見せている。
「チャップリンとパン屋」(1914年米)も、面白い作品だ。レストランのウェイターのチャーリーは、犬猿の仲のチェスター・コンクリンとはいがみ合ってばかり。パン職人たちのストライキによって2人は地下のパン焼き場で働くことになる…。パン生地や小麦粉、熱くなった竈が効果的にギャグを生み出す。最後は、パン職人たちの仕掛けたダイナマイトでレストランは大破。チャーリーはパン生地の中から顔を出す。キーストン時代のチャップリン監督作としては最長で、DVD収録版は28分ある。しかしオリジナルはもっと長 く、あまりに話が膨らみ長くなったために、レストラン以外の場面が「髭のあと」(1914年米)として切り離され別作品として公開された。また、1000ドルの製作費を大幅にオーバーする1800ドルを費やしたために、セネットを不安がらせたが、最終的に13万ドルの大ヒットとなった。
こうした傑作を生みだしている一方、この時期の作品の中にはいかにも即興で作られたかのような作品が散見される。例えば、「リクリエーション」(1914年米)。たわいもない公園での追っかけに終始した作品で、その前作に当たる「チャップリンの画工」とは比べ物にならないほどの出来栄え。しかも、よく見るとチャーリーの衣装には「チャップリンの画工」と同じ絵の具の染みがついている。いかに間に合わせであったがわかる。「他人の外套」(1914年米)、「夫婦交換騒動」(1914年米)も同様の印象を受ける。
どうもこの時期になるとチャップリンの人気がどうしようもないくらい高まり、劇場側からの要望に応える形で、チャップリンはじっくりと傑作を仕上げる合間に、間に合わせの作品を織り交ぜていたよだ。
*26 チャップリン「チャップリン自伝 上」338〜339ページ
*27 同書 331ページ
*28 「チャップリン・ザ・ルーツ」大野裕之による解説51ページ

「両夫婦」(1914年米)
チャールズ・チャップリンとフィリス・アレン
(「チャールズ・チャップリン」より)
「笑いのガス」で監督に復帰して以降の作品で、例外的な作品が1本だけ存在している。それが「両夫婦」(1914年米)。‟デブ君”として知られるロスコー・アーバックルがチャップリンと共演した作品だが、チャップリン単独監督作ではなく彼がアーバックルと唯一共同監督している。
デブ君とチャップリンの共演はそれ以前にもある。初期の「チャップリンの活動狂」、「タンゴがもつれる」では同じ映画に出演している。また、デブ君の主演作「ノックアウト」にチャップリンがゲスト出演したことも あった。しかし、2人が対等な立場で共演するのは「両夫婦」が唯一である。
チャーリーとデブ君は、お互い酔っぱらって帰ってきたから、それぞれの奥さんはおかんむり。やがて、奥さん同士が喧嘩を始めたので、2人で抜け出し飲みに行く。奥さんたちが追いかけてきたので、2人は逃げ出しボートに乗るが、眠りこけているうちにボートは池に沈んでいく…。
チャーリーとデブ君は息もぴったりで、のびのびと演じているかの印象を受ける。後にアーバックルは、「手早く作った1巻ものじゃなくて、長編でチャップリンの相手役をできなかったことをずっと悔やんでいる(*29)」と語っている。ずっと後にチャップリンはアーバックルの弟子であったバスター・キートン(1895〜1966)と「ライムライト」(1952年米)で共演し、名コンビぶりを見せている。それだけに、アーバックルとの共演ももっと見てみたかった。
*29 「チャップリン・ザ・ルーツ」大野裕之による解説51ページ

「夫婦交換騒動」(1914年米)
フィリス・アレン、マック・スウェイン
メーベル・ノーマンド、チャールズ・チャップリン
(「チャールズ・チャップリン」81ページ)
後年の名作でのチャーリーしか知らない人にとっては、キーストン時代のチャップリンを観ると戸惑うことであろう。なぜなら、ここには後年の優しいチャーリーの姿を見出すことができないからだ。正直言って、キーストン作品でのチャーリーは、 多くの場合ずる賢い小悪人なのである。
例えば、デビュー作「成功争い」でのチャップリンはペテン師であったが、同様のキャラクターは「メーベルの身替り運転」、「醜女の深情け」などで繰り返し演じられている。「メーベル多忙の一日」のチャーリーも、メーベルが売るホットドッグを盗んでしまうし、「恋の20分」では懐中時計を盗んで他人に売りつける。
チャーリーは時折残酷な顔を見せる。「チャップリンの道具方」では、老人が重い荷物の下敷きになってしまったにもかかわらず、その荷物の上に腰かけて煙草を吸う。「チャップリンの独立」でも、足を怪我して車椅子に乗った男を突き飛ばす。
そして、この頃のチャーリーは極めて好色なのである。そういった作品は「メーベルの窮境」、「アルコール先生お好みの気晴らし」、「とんだ災難」、「チャップリンの衝突」 、「髭のあと」などかなりの数に登る。「街の灯」で見せた善良で愛する人に対する献身的な姿とは打って変わり、ただ欲望のままに行動しているように見える。もちろん、現実のチャップリンは、生涯に4度結婚したばかりか数々の浮名を流しているのだから、ある意味これがチャップリンの本性なのかもしれないが…。
先にも述べたように、チャップリンがキーストンに入ったのは、フォード・スターリングの後継者を期待されてのことで、彼自身もスターリングの影響を受けていたようだ。キーストン時代のチャーリーのキャラクターというのは、それまでスターリングが演じてきた小悪人のキャラクターそのままなのである。チャップリンは自伝で、「わたのしの芸風というのは、フォードとはまるで正反対なのだ(*30)」といった具合にフォードの喜劇を批判しているが、意識してか意識せずか、チャップリン自身も最初のうちはスターリングの影響を強く受けていたのだろう。
しかし、「チャップリンの画工」や「新米雑役夫」などに見られるように、チャップリンは次第にペーソス色を強め、他のコメディアンにはない要素を生み出していくようになる。
*30 チャールズ・チャップリン「チャップリン自伝 上」301〜302ページ
僕がチャップリンを好きになったのは、後年の名作がきっかけである。チャップリンが自身のスタイルを完成させたのはチャーリーと野良犬の交流を描いた「犬の生活」(1918年米)であったが、以後「担え銃」(1918年米)、「キッド」(1921年米)、「黄金狂時代」(1925年米)、「街の灯」(1931年米)と次々と名作を生み出していく。これらの作品はいずれも、不朽の名作であることは間違いない。これらの作品でチャップリンに親しんだ身としては、キーストン時代の作品は戸惑いを感じるばかりであった。
しかし考えてみると、チャップリンが世界的に有名になったのは、まぎれもなくキーストン時代の作品がきっかけだったのだ。何度も繰り返し観ているうちに、次第にその面白さがわかるようになってきた。後のチャップリン作品は、時として説教臭くなる部分もあるし、何よりも泣かされるという喜劇としては致命的な欠点を持ち合わせている。それに引き換え、キーストン時代のチャップリンは、純粋に笑いを追求している。若き日のそんなチャップリンも、十分に魅力的である。 観直しているうちに、違った意味でチャップリンに魅かれていった自分に気づいた。
(2015年11月28日)
(参考資料)
「世界の映画作家19/チャールズ・チャップリン」1973年4月 キネマ旬報社
「世界の映画作家26/バスター・キートンと喜劇の黄金時代」1975年1月 キネマ旬報社
岩崎昶「チャーリー・チャップリン」1973年11月 講談社現代新書
チャールズ・チャップリン/中野好夫訳「チャップリン自伝/若き日々」1981年4月 新潮文庫
喜劇映画研究会編「サイレントコメディ全史」1992年9月 喜劇映画研究会
デビッド・ロビンソン/宮本高晴、高田恵子訳「チャップリン 上」1993年4月 文藝春秋
大野裕之編「チャップリンのために」2000年11月 とっても便利出版部
大野裕之「チャップリン再入門」2005年4月 生活人新書
大野裕之「チャップリン未公開NGフィルムの全貌」2007年3月 NHK出版
大野裕之「CHAPLIN THE ROOTS」解説 2012年
マック・セネット/石野たき子訳/新野敏也監訳「〈喜劇映画〉を発明した男/帝王マック・セネット、自らを語る」2014年3月 作品社
目次に戻る
サイレント黄金時代(10)「ほほえみと一粒の涙」へ戻る
サイレント黄金時代(11)「走れ無表情〜バスター・キートン〜」へ進む