

NO.1〜NO.15










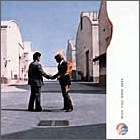

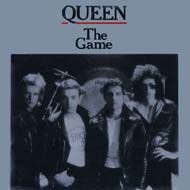
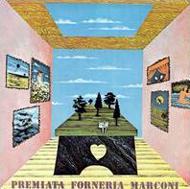

1969年 UK
記念すべき1回目は何ともインパクトのあるジャケットのコーマスのデビューアルバムを紹介しよう。このアルバムはイギリスのドーンレーベルから発売されたもので、当時このレーベルからはUK幻のファンタジックバンドのフループやUK正統派ロックのテンペスト、コラシアムといった、いわゆるB級路線のバンドを売り出しだ何とも素敵なレーベルなのである。その中でもこのコーマスは私が大学当時はまりにはまってしまったバンドなのである。正直言って、このバンドがいたからこそ、私はプログレッシプフォークデュオ“ゲロ”を結成したと言っても過言ではないくらいだ。全般的に狂気じみた曲が多く、アコースティックギター、バイオリン、フルート、パーカッション、異常に高音の男女ボーカルという構成になっている。日本でもテイチクレコードから発売され、一部のプログレファンからは絶大な支持を得ていた。しかし、このアルバムをプログレの範疇で語るのは勿体無い話である。これこそ究極のフォークバンドだと断言するべきである。泣く子も黙る狂気錯乱の曲群。まさに邦題の「魂の叫び」というべきものである。
1971年 UK
KING’S ROOMでも何回か紹介したことがあるが、ステイタスクオーはイギリスの国民的バンドである。日本で言うところのサザンオールスタースといったところか、まずイギリス人なら老若男女、知らない人はいないバンドである。その認知度はクイーンと変わらないであろう。彼らは67年結成以来、一貫したスタイルを崩さずやってきたすごーいバンドなのである。重厚なダブルギターでブルース、ブギーを奏で、どの曲を聴いても同じように聴こえるが、実はバラエティに富んでいる、まさに爽快ブギーバンドなのだ。時代性など関係ない、まるであのベンチャーズの如く、一貫した音楽スタイルを奏でる彼らの音楽を誰が否定できるものか。そんな中、あえてこの1枚を選んだのはパイレーベル最後のアルバムで、あのブギー節を確立したアルバムと言えるからである。それ以前のクオーは当時のムーブメントだったサイケデリックロックに趣きを置いていたバンドであったが、アルバム発表につれて独自のスタイルを確立していったのである。このアルバムはフォーク的な要素を組込みながら起伏感があり、アルバムの流れが非常に良い。クオーはどのアルバムを聴いても良いのだが、まずはこのアルバムということでここで紹介した。私が所有しているクオーのアルバムはすべてLPである。長い歴の中で多くのアルバムを残しているため、私もまだ半分くらいしか所有していないが、今後もクオーのレコードコレクターとして活動していきたい。
http://www.f3.dion.ne.jp/~doka129/Piledriver.html
1971年 日本
このアルバムは何年たっても色あせないし、ふと聴きたくなる名盤。ガロは日本のCSN&Yというキャッチコピーで売り出された。一役かったのが、あのかまやつひろしというのは有名な話である。当時世界的な活躍をしていたフラワートラベリングバンドのツアーに同行したのがプロになるきっかけで、全国的に有名になったのが、なんとシングルのB面曲であった「学生街の喫茶店」という誰もがご存知のヒット曲からである。私的には「学生街・・」や「ロマンス」などのメンバー外の人が作った曲よりも、デビューアルバムの「GARO]の曲が好きである。メンバーオリジナルソングがほぼ全編に聴けるのはこのアルバムくらいであって、「GARO2」からはカバー曲やプロの作詞家、作曲家が作った曲が大半になってしまい、本来ガロが持ち合わせている個性が発揮されなくなる。このアルバムのコーラスワークは天下一品である。「暗い部屋」なんか聴くと鳥肌がたってしまうほどである。その他にも「たんぽぽ」「地球はメリーゴーランド」などの名曲揃いで、私自身最も好きな曲はアルバムラストの「人は生れて」である。この曲を聴くとなぜか、トミーがなぜ自らこの世を去ったのかがわかるような気分になってしまう。
1971年 UK
「怪奇骨董音楽箱」というわけのわからない邦題を付けられた初期ジェネシスの名盤。至芸に近いフィルコリンズのドラムにスティーブハッケトのライトハンド奏法、文学的志向炸裂のピーターゲイブリルの詩、それを表現するボーカル、まあこのアルバムは正直言ってかなりマニアックな人でないと好きになれないであろう隠れROCK名盤と言ってもいい。とにかく1曲目の「ミュージカルボックス」とラストの「サルマシスの泉」が良い。まさに静と動が葛藤するような曲調は緊張感というものを感じさせる類少ない曲である。ジェネシスと言えば、どうしてフィルコリンズというイメージがあるが、私みたいにひねくれたおじさんはゲイブリル時代のジェネシスが好きなのでよ。「幻惑のブロードウェイ」ってアルバムなんか詩を理解しようと必死に格闘したこともあったが、結局良くわからなかったなんて思い出もある。この時代のジェネシスの良い所はなんていってもアルバムジャケットでしょう。ジャケットだけで買い!って感じである。このアルバムのジャケットをよく見ると、首の切られた人間の頭がボール代わりになっているところなんかちょっと想像を絶する所があってそれが詩の世界に反映されている。そんな所が素敵だといえるのがマニアックなジェネシスファンってとこかな!
1976年 日本
四人囃子の詳しい説明については下記のオフィシャルHPをご覧いただきたい。このアルバムは四人囃子のセカンドアルバムで1976年に発表されたものである。デビューアルバム「一触即発」で衝撃的なデビューを果たし、日本で最も高度なテクニックを持ったバンドとされていた。高度なテクニックを駆使すればプレグレと呼ばれるのかは定かではないが、このバンドは決してプログレバンドではなく、高度なテクニックを持った画期的なロックバンドという位置づけで語った方が適切であろう。デビューアルバムも素晴らしいが、私的にはこちらのセカンドが好きである。ビートルズのマイナーナンバー「フライング」のカバーをはじめ、どの曲も完成度は非常に高い。B面の大半を占めている大曲「泳ぐなネッシー」は私みたいな洋楽かぶれしていた人間にとっては心ときめく曲であった。ひとつの曲に様々なエッセンスが詰め込んであり、おなかいっぱいの消化不良になりかねないのだが、その辺は四人囃子のテクニックが見事にそれを克服している。ガツガツロックでない、大人のロックって感じがこのバンドの特徴のひとつである。
http://www.4nin.com/
1972年 UK
早くもNO.6にして私が超大好きなアルバムを紹介することにしよう。70年代ブリティッシュロックが誇る屈指名盤とされているこのアルバムは、まさにその名の通りの素晴らしいアルバムだと私も思う。このアルバムについては様々なところで様々な観点で語られているので、ここではそれとは別の私なりのコメントをずばり書くことにする。このアルバムの価値はすべて、ラスト曲「剣を捨てろ」だけにある。それ以外の曲はこのラストソングを迎えるための前座にすぎない。如何にしてこのラストソングを迎えるか、その方法論がこのアルバムの重要な部分であり、まるで人生の終焉を迎えるまで人間はどう生きるべきかを示唆しているかのようである。ちょっと大袈裟かもしれないが、それだけラストソング「剣を棄てろ」は価値ある曲だということだ。この曲におけるアンディパウエルとテッドターナーのツインギターソロは私が数多く聴いてきたギターソロの中で最高である。テクニック云々とかそういう問題ではない。このアルバムの最後の部分に鳴り響くからこそ最高なのである。ちなみにジャケットにも登場しているアーガスはギリシャ神話に登場する百の眼を持った巨人で世界を監視する役目を負っている。アーガスが見たものは、人間同士の愚かな争いの歴史である。「剣を棄てろ」とはアーガスの人類に対する最後の警告であると共に、人類が迎えるかもしれないある結末を暗示しているかのようである。ジャケットワーク、コンセプト、そしてラストソングの価値。この結びつきこそがこのアルバムが今も尚語り継がれている所以である。
1985年 UK
あまりにも有名なアルバム。この時代ちょうどレコードからCDへの転換期ということもあったためか定かではないが全世界で2500万枚という大セールスを記録。私の家にもなぜかLPとCDの両方あった。当初、MTVなどによる音楽巨大産業化を否定するために作られたとされているヒット曲「マネーフォーナッシング」が皮肉にもMTVで爆発的大人気となったのは有名な話。これが意図的であったとするならば彼らは世界最高の詐欺師に君臨していたであろう。それはともかくとして、ダイアーストレイツと言えば、ボーカル、ギターのマークノップラーというおじさんである。エレキでフィンガーピッキングという独自なスタイルで渋いギターと渋い歌を聴かせてくれる。78年「悲しきサルタン」でデビューし、もはや確立されていた独特なサウンドで数々の名曲をつくり上げてきた。ストーリーチックな曲が多く、ノスタルジックな気分にさせてくるものが多い。このアルバムはもちろん彼らの代表作であり、完成度も非常に高い。私的には戦友をテーマにしたタイトル曲がベスト曲で、今もこの文章を書きながらそのメロディーが浮かんできている。このアルバムを聴いていた当時の私の記憶までもが頭を過ぎっている。あれからもう20年近くも経ったのか。うーーん懐かしい。
1973年 UK
ひとりの素朴な少年。その少年の奏でるメロディが後に航空会社を設立するまでに発展すると誰が予想したものか。マイクオールドフィールドはヴァージンレーベル発足第1号のひとりとしてデビューを飾った。弱小のレーベルがこのアルバムの爆発的ヒットで巨大化し今の地位にあるという事実、まさに運命の1枚であった。マイクオールドの音楽は彼の内面にある世界を音で表現しているかのようである。すべての構成、すべて楽器、すべてが彼ひとりで行なわれて作られた作品である。音楽とは人間の想像力から生まれる。そしてその音楽は聴く者に新たなる想像力を芽生えさせる。そしてそれは映像という世界への結びけられる。その映像的な音楽こそがこの作品と言える。ROCKの世界にとどまらない、すべてのジャンルを超越した音楽。純粋に音楽と呼べるもの。それが「チューブラーベルズ」なのだ。ちなみにこの作品を知らなくても、この曲の一部はほとんどの人が知っている。翌年74年の映画「エクソシスト」に使われたかの有名なフレーズがそれである。この映画に使われたことがきっかけでアメリカ、そして世界へマイクオールドフィールドの名が知れ渡ったのである。
1999年 UK
60年代、70年代ロックの再生。そんな言葉を良く使われていたクーラシェイカー。しかしながらクーラシェイカーは再生であっても写真の焼増しとは違う。独特なグルーヴ感を持ち、インド的音楽要素などを取り入れた90年代にしか存在しない斬新的なバンド、いや60年代、70年代をある意味超えているバンドであると私は思う。再生なのか進化なのか、はっきり言ってこれはどうでもよいこと。そのバンドの音がよければそれでいいんじゃないの。私ははじめてこのバンドの曲をテレビで聴いた瞬間、すぐにCDを買いに行こう!と思ったくらい私の五感にビビッときたのである。このアルバムはクーラシェイカーの2作目にして最後の作品である。なんとプロデューサーはあのボブエズリン。この人のプロデュース作品は個性が強すぎて、どんなバンドの音でも似させてしまう傾向があるが、この作品は上手い具合にクーラシェイカーの個性を引き出したと言える。解散後、バンド中心人物だったクリスピアンミルズは3年の月日を得てTHE JEEVASを結成。クーラシェイカーにあった複雑的なものを一切取り払って、シンプルなロックバンドに生まれ変わった。
1978年 US
70年代前期アメリカ。この時代のロック界はイギリスがまさに主流であった。グラムロックの台頭からはじまり、プログレ全盛時代、ハードロックにしてもアイドルロックバンドにしても主流なのはすべてメイド・イン・UKであった。そんなイギリスの勢いに押し流された感のあるこの時代のアメリカのロックバンドといえばイーグルスがデビューし、リトルフィート、オールマンブラザーズ、ドュービーブラザーズなどといったカントリー系のバンドが主流だった。そしてここに紹介したスティックスは70年代前半に密かに生まれたバンドであり、当初ジャンル的にはB級ハードロック路線のバンドであったが、イギリスのハードロック、プログレ全盛の流れがアメリカにも波及し始め、ラッシュなどのハードかつプログレ的なバンドの人気が出始めると共にステックスも徐々に全米で注目されるバンドになってきた。6枚目の「クリスタルボール」からボーカリスト&ギターリストのトミーショーが加わり、デニスデヤングと共にダブルボーカルという形になり、トミーの卓越した作曲能力が開花すると共に完成度の高い作品を次々と送り出した。7枚目の「グランドイルージョン」ではついに全米で300万枚のセールスを記録し、ここに紹介した次作の「ピーシズオブエイト」そしてその後の「コナーストーン」「パラダイスシアター」までまさにスティックス黄金期と言える時代が続いた。ここにあげた「ピーシズオブエイト」はスティックスのアルバムの中で私が一番好きなので紹介したわけである。ジャケットも良い(ヒプノシス作)。
1975年 UK
ピンクフロイドの中で一番好きなアルバム。ピンクフロイドはどちらかと言えば肩がこりやすいアルバムが多い。それは私だけかもしれないが、おもわず力を入れてしまい、本来持ち合わせているフロイドサウンドの浮遊感を満喫できなくなってしまうのだ。しかしこのアルバムは特に力を入れて聴くようなアルバムではない。旧友のシドバレットをモチーフにしたコンセプトもどこか取ってつけたような感があり、それはそれとして捉え(それを語ったら文章がえらく長くなってしまう)、サウンド面を最大重視して聴けるフロイド唯一アルバと言ってもいい。このアルバムの最大の聴き所はオープニングの「狂ったダイヤモンド 1部」である。イントロの美しさなんか何とも言えないものがある。デビットギルモアのブルージーなギターもさることながら、リックライトの鍵盤系サウンドが非常に心地よいし、牧歌的な雰囲気を醸し出している。つづく「マシーンへようこそ」でもフォークソングにも関わらず多様なシンセサイザーを駆使しているし、アルバム全編にわたってリックライトが大きく功績を残している。そしてアルバム後半、AMラジオから流れてくるアルバムタイトル曲、このアイディアこそがピンクフロイドの真骨頂といえ、なぜこのアルバムが人々の心を打つのかという答えがそこにあるような気がする。薄暗い部屋でひとり、ロウソクなんかつけたりしちゃって聴くとたまらない。そして思う。あなたがここにいてほしいと・・・。
1975年 UK
ようやくキンクスです。キンクスは大大好き!といっているわりにはRCA時代(1971年〜1975年)のキンクスは嫌いという輩が多い。あのキンキーマニアとして有名で、キンクス裏ベストなる編集CDさえ出したコレクターズの加藤ひさし氏でさえ、この時代のキンクスは全くダメらしい。しかしながら、このRCA時代にこそ、ある意味、キンクスらしさがあると私は思うし、この時代があったからこそアリスタレーベル以後の全盛期があったのだと思う。RCA時代に残した6作品はすべてコンプセプトアルバムになっており、ホーンセクションメンバーまで加わり、レイデイビスのやりたい放題、他のメンバーも勝手にやれば!という感じであった。そのコマーシャル性の皆無にパイレーベルまでのファンは彼らの元を去り、バンド経営も窮地に追い込まれていたらしい。噂ではメンバーが他でバイトをしていたとまで言われている。ここに紹介したアルバムは邦題で「不良少年のメロディ」と名付けられた学園を舞台とした物語である。前作まで存在したホーンセクション部隊はなくなりストレートなロックンロールが展開されている。ユーモアを取り入れながら教育問題をさりげなく歌ったと思ったら、いきなり「ハードに生きろ」なんて歌っているレイデイビスはなんとも素敵な人である。誰にでも存在する学生時代、あの甘酸っぱい時代を蘇らしてくれる私にとって貴重なアルバムだと言える。このアルバム以降彼らは変貌し、ついにアメリカへ進出していくのだった。つづく。
1980年 UK
クイーン第2ステージ最初のアルバム。クイーンの70年代はアルバムに「我々は一切シンセサイザーを使っておりません!」と明記するほど音づくりにこだわりがあった。しかし80年代に突入し、クイーンは変貌を遂げた。というより前作の「JAZZ」でクイーンサウンドのひとつの行き詰まりがあったと私は思う。よって私はこの変貌を良い意味として今もなお解釈している。クイーンがシンセサイザー使って何が悪いの?それを否定する者はクイーンに対して異様な固定観念が植え付けられているだけである。バンドとは常に進化するものであっても良い。そしてこのアルバムは蓋を開けてみれば、全米チャートでけでなくブラックチャートさえ賑わすほどの大ヒットとなった。曲においても大作主義はなくなり、3、4分の軽快な小曲がずらりと並んでおり、アルバム半分の曲がシングルカットになったくらいである。今も尚クイーンがロック界においてトップの座に君臨するほどの功績があるのはこの変貌があってこそである。私はクイーンのアルバムすべてが好きであるし、特にこの「ザ・ゲーム」と次回作の「ホットスペース」はクイーンの新開拓として非常に高い評価をしている。クイーンがダンスミュージックやってもいいんじゃないの。いつまでも「ボヘミアンラプソディ」や「伝説のチャンピョン」がクイーンだ!なんて変なこだわりがある輩はもはや過去の固定観念に埋もれてしまった視野の狭いロックリスナーと言ってやる!
1972年 イタリア
私が所有するLPの中で一番にプレス状態の良いアルバム。まさにLPならではの奥の深いサウンドが楽しめる。ほんとイタリア盤は良い音が出るなあ。というわけでここに紹介したのは、知る人は本当によく知っている、イタリアンロックバンド、P.F.Mの2作目。今でも現役で根強い人気を得ているバンド。70年代初頭のブリティシュロック全盛期、そのムーブメントはヨーロッパ各地に飛火した。その中でもこのP.F.Mはクラッシクに根付いたテクニックを駆使し、シンフォニックロックの雄と呼ばれ?イギリスのキングクリムゾンやイエスといったプログレバンドと肩を並べる存在だった。そんな彼らを世界的なバンドに仕立てたのが、元キングクリムゾンの詩担当であったピートシンフィールドで、イタリア語を英語にすり替え、その叙情的な詩がメロディとマッチして美しいハーモニーを醸し出した。そのアルバムが邦題で「幻の世界」というタイトル。イタリアでの2作を再編集という形で発売されたそのアルバムは日本においてもイタリアンロックブームを広めるきっかけとなった。そのアルバムも良いのだが、私としてはそれ以前のイタリア語で歌われたこちらのアルバムが俄然良いと思う。とにかく柔らかい音。オープニング曲「人生は川の流れ」におけるクラッシクギターからフルート、そしてバイオリンに至るまで、まさにお見事、ほんとに心地良いのである。とにかく聴くならLPで!と太鼓判を押す私であった。
1973年 UK
私にとって、フーのベストアルバム。破壊的で荒々しいバンドというイメージが売り物だったフーが、様々な過程を経て辿り着いた頂点がまさにこのアルバムであるし、私にとっての「たかがROCK」を「されどROCK」に変えてしまったアルバムといえる。このアルバムは2枚組のコンセプトアルバムであり、前々作のロックオペラ「トミー」をさらに進化させた内容になっている。大まかな内容は人格が形成されていないゆえの苦悩、主人公ジミーというティーンエージャーの青春の葛藤記録であり、すべてのリスナーへ捧げる「青春とは何か」という命題がそこにある。このアルバムコンセプトは数年後「さらば青春の光」(邦題)というタイトルで映画化された。映画の舞台となったのはイギリス南方のブライトンという街。日本で言うところの湘南海岸みたいな所で、実際私もブライトンに行ったことがある。ビクトリア駅から電車で1時間の所にあり、ドーバー海峡が見渡せる素晴らしい街であった。私の頭の中にこのアルバムの曲が流れ出していた。果たしてジミーは死んでしまったのだろうか。モッズやロッカーズはまだ生息しているのか。愛の支配とは何か。本当の自分とは。そんなことを考えながらぼんやりブライトンの砂浜を歩いていた。音楽と風景、そしてエモーションとノスタルジア。とにかくこのアルバムは私にとって忘れらない英国の思い出の一部となっている。