第七十一話

淡(あわ)い月明りを頼(たよ)りにセイラが見たのは、とがった耳と美しい灰色の毛並み――狼(おおかみ)だった!
「なぜ、狼が都に……」
狼は元来(がんらい)用心深い性質で、人目につくことは滅多(めった)にない。
ましてや、天敵(てんてき)とも言える人の多い都に寄りつくなどありえなかった。
では、なぜ狼はあそこにいた――?
今夜、たまたま紛(まぎ)れ込んだだけなのか?
なぜ、餌(えさ)にもならない神剣を持ち去った?
その時、セイラは幽鬼(ゆうき)の言葉を思い出した。
あの幽鬼はなんと言った?
神剣を欲しがっているやつがいる――そう言わなかったか?
セイラが知る限り、神剣を欲しがっているのはただひとり。
もし、あの狼がそこへ向かっているのだとしたら――
そう思い当たった時、セイラの手の中で、空気がシュルシュルと音を立てて渦巻きはじめた。
大路(おおじ)を行く人はまばらになっていたが、広範囲の攻撃をしかければ、巻きぞえになる者が出ないとも限らない。
セイラは前を行く狼の足元一点に狙(ねら)いを定め、空気の球を投げ込んだ。
瞬間――
走っていた狼の身体(からだ)が、フワッと宙に浮きあがった。
圧縮(あっしゅく)された空気の渦(うず)が、狼の身体を漏斗状(ろうとじょう)に回転させながら上へ上へと押し上げていく。
「ウォォ――ン!!」
たまらずに、叫び声をあげた狼の口から神剣がこぼれ、上空に巻き上げられていった。
「しまった!」
セイラは人目もかまわず、神剣を追って空へ上った。
渦が消えても、狼は落下してこなかった。
かわりに、小さな紙切れがひらひらと宙を舞って落ちていくのが見えた。
それだけで、なにが起きたかを知るには十分だった。
最後に神剣を見た高さまで上昇して、セイラは足下に目を凝(こ)らした。
日中ならともかく、夜空に飛んでいった小さな石を見つけ出すのは不可能に等しい。
セイラは絶望的な気分で、小路(こうじ)や草むら、軒先(のきさき)を並べる家々を眺(なが)めた。
「なんてことだ……あれをなくしたら……」
理空(りくう)と神剣を返してもらう交換(こうかん)条件として、安倍晴明――ザフが要求したのは、柄岩(つかいわ)島の神剣。
それをなくしてしまったら、理空も神剣も取り戻すことはできない。
ならば、どうする――
しだいに険(けわ)しさを増していくセイラの表情は、この先に待つ厳しい戦いを予感させた。
「乙矢(おとや)、しっかりしろ!乙矢、目を覚ませ!」
小路に戻って、小さな身体を揺(ゆ)さぶりながら、セイラは声をかけ続けた。
「うーん……あれ?セイラさま、いる……」
眠そうに目をこすって、乙矢は寝ぼけ声を出した。
「気がついたか、乙矢!鳶丸(とびまる)はどうした?」
「鳶丸…?となりにいる。あれ……?」
きょろきょろとあたりを見まわして、乙矢はようやくそこが九条の邸内でないことに気づいた。
「さっきまで一緒に寝てたのに……ここ、どこ?」
「ここは六条だよ。そうか、では鳶丸も……とにかく、こんなところまで寝ぼけて歩いてきたらだめじゃないか」
セイラは、乙矢がここにいる理由を寝ぼけていたせいにした。
「みんな、どこ行くの?」
大路を行く人々を、不思議そうに見つめる乙矢。
そんな乙矢を、セイラはできるだけ怖がらせないようにした。
「南の方で、物の怪(もののけ)が出たから逃げてきたんだよ。物の怪は怖いだろ?乙矢もあの人たちと一緒にいきなさい、北の方が安全だから。鳶丸ともどこかで会えるかもしれない」
「セイラさまは、いかないの?」
「私は人を探してるんだ。危ない目にあうかもしれないから、乙矢は連れていけない」
「その人が、物の怪を出してるの?」
乙矢の直感力に、セイラは目を見張(みは)った。
「そうだよ。みんな困ってるから、やめさせないとね」
「だったらおいらも行く!おいらだって、鳶丸に負けないくらい強いよ!」
「乙矢が強いのはわかるけど……」
困惑(こんわく)したセイラが目を上げると、まっすぐにのびた朱雀大路(すざくおおじ)の北の空が、赤く染まっているのが見えた。
「火事――!?あの方角は……」
朱雀大路の北端(ほくたん)は、朱雀門につながっている。
そして、その先にあるのは――
「とにかく、ここにいては危ない。四条の本邸(ほんてい)か私の邸(やしき)にきなさい。内裏(だいり)には近づかないように……いいね!」
そう言い残して、セイラは夜空へ舞い上がった。
「うわあーっ!セイラさま、空飛んだ!すっげえーっ!」
後を追って駆け出そうとした乙矢の足が、なにかを踏(ふ)んだ。
「痛(い)たっ!なんだ、この石っころ!」
蹴(け)とばして、転がっていく石に、乙矢はなぜか目を止めた。
拾(ひろ)い上げて、まじまじとその石を見つめる。
暗闇に慣れた目に、石は淡い輝きを放って見えた。
「変な石。鳶丸に見せてやろ!」
その石を握(にぎ)りしめ、乙矢は喜々として走り出した。
家々の屋根を飛び越えて、内裏へ急ぐセイラの脳裏(のうり)を、さまざまな推測(すいそく)が駆(か)け巡(めぐ)っていた。
火事は失火(しっか)か、故意(こい)によるものか?
光や火に弱いはずの幽鬼が、放火したとは考えにくい。
失火だとすると、阿黒(あくろ)王とは直接関係がないのかもしれない。
それでもなぜか、セイラの胸騒ぎはおさまらなかった。
朱雀大路に阿黒王はいなかった。
では、どこにいる――?
五条大路にさしかかった。
方形(ほうけい)の結界(けっかい)に阻(はば)まれて、北へ進めなくなった幽鬼が群(むら)がっている。
怒りにまかせて、見えない結界に斧(おの)を振り下ろす幽鬼や、手当たりしだいに周囲の邸を打ち壊(こわ)そうとする幽鬼――
逃げ遅れた人々の、そこかしこから聞こえてくる悲鳴に、セイラの足は止まった。
「こんな時、神剣があれば……!」
だが今は、自分にできることをやるしかない。
できること――?
「私に、できること……うっ!」
突然、セイラは激しい頭痛に襲(おそ)われた。
頭を抱(かか)え、痛みに耐(た)えるセイラの脳裏に、浮かんでは消える幾多の映像。
それは、なくした記憶のかけらだった。
その映像のひとつに、セイラの意識が集中した。
「あった!結界があるなら、それを使って……」
セイラの波動(はどう)が一挙(いっきょ)に高まり、それが右手の人差し指一点に集中していく。
五条大路に面する結界の側面(そくめん)に、一筋(ひとすじ)の閃光が放たれると、一面に虹色の渦が現れては消え、次の瞬間――
日輪(にちりん)が都に出現したかのような光の洪水(こうずい)が、五条大路の幽鬼を襲った!
それは都の南半分を照らし出し、はるか羅城門(らじょうもん)まで浮かび上がらせている。
一瞬にして浄化(じょうか)された幽鬼から、解放された人々で埋(う)め尽(つ)くされる大路。
想像をうわまわるその威力(いりょく)に、セイラはとまどい呆然(ぼうぜん)とした。
「これが、私の力……?」
その時――
「セイラさま――!」
遠くの空から、緊迫(きんぱく)したオルフェウスの声が近づいてきた。
「今の光は?なにがあったのです!?」
「ああ……」
オルフェウスに尋(たず)ねられても、セイラは虚(うつ)ろな目をしたままだった。
「セイラさま……?」
「幽鬼を…浄化しようとしたら、あんなことに……」
「そうでしたか」
オルフェウスは、ほっと吐息(といき)をついて、
「力の大きさに驚いておられるのですね。ですが、本来のセイラさまなら……とにかく、幽鬼を一掃(いっそう)できたことはなによりでした」
「おまえは、驚かないのか?」
「光をあやつる能力(ちから)は、セイラさまの得意とするところ。セイラさまのことは、私が誰よりも知っています。それよりも……」
やさしい眼差(まなざ)しを曇(くも)らせて、オルフェウスは北の空を振り返った。
「阿黒王が内裏を襲撃(しゅうげき)しました。あの火事は、その騒乱(そうらん)によるものです」
「ばかな!結界をすり抜けたというのか!?」
「いえ……阿黒王と言えども、セイラさまの結界をすり抜けられるはずがありません。考えられるとすれば、私が朱雀大路を離れた間に、北に向かった可能性があります。六条の幽鬼は、我々の目を欺(あざむ)くためのおとりだったのでしょう」
「篁(たかむら)は……帝は、無事なのか!?」
「篁殿が帝の居室(きょしつ)に向かったのは、阿黒王が攻めてくる前でした。今のところ、阿黒王とその手勢(てぜい)は、配備(はいび)した守兵や門に阻(はば)まれ居室までたどり着けずにいるので、お二人はご無事かと……ただ、火の勢いが増せば、篁殿も帝も退路(たいろ)を断たれるかもしれません」
「迂闊(うかつ)だった!阿黒王がこれほど早く事を起こすとは……」
セイラは唇(くちびる)をかみしめ、意識が戻りはじめた眼下(がんか)の人々を眺(なが)めた。
幽鬼に憑依(ひょうい)され、さっきまで暴(あば)れていた者たちが不安げに周囲を見まわしている。
浄化(じょうか)されてしまえば、幽鬼だった者も元の人間に戻る。
だが内裏(だいり)を警護(けいご)する役人に、そんな理屈(りくつ)が通用するはずもない。
「急ごう!憑依さえ解(と)いてしまえば、争わずにすむ。阿黒王は私たちに殺し合いをさせたいらしいが、そうはさせない!」
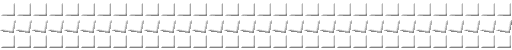
火の手は朱雀門(すざくもん)の近く、式部省(しきぶのしょう)の建物から上がった。
侵入(しんにゅう)してきた幽鬼(ゆうき)の集団に怯(おび)えた検非違使(けびいし)が、松明(たいまつ)を投げて遠ざけようとしたためだった。
火は風に乗って、となりの朝堂院(ちょうどういん)や豊楽殿(ぶらくでん)へと燃え広がり、内裏を囲(かこ)むようにのびていった。
セイラとオルフェウスが、炎に包(つつ)まれた朱雀門の中に下り立つと、そこには累々(るいるい)と屍(しかばね)が横たわっていた。
無数の矢が突き刺さった者、ザックリと背中を斬(き)られた者――
流れ出る血は、つい今しがたまで凄惨(せいさん)な戦いがあったことを物語っていた。
「クッ!阿黒王(あくろおう)、これがおまえの望みか!」
吐き捨てるようにつぶやくセイラの横で、オルフェウスは冷静に戦況(せんきょう)を分析(ぶんせき)していた。
「守兵(しゅへい)の死体もあります。この刀傷(かたなきず)は、幽鬼に殺されたというよりも守兵同士で争ったもの……殺された身体から離れた幽鬼が、守兵の身体に乗り移ったのでしょう」
耳を澄(す)ませば、遠く建礼門(けんれいもん=大内裏の中央にある内裏へ通じる門)の方から剣戟(けんげき)の音が聞こえてくる。
「時間がない!私は幽鬼を浄化(じょうか)する。おまえは火を消し止めてくれ!」
「わかりました」
オルフェウスが空へ上がると、セイラは体内の気を一気に押し上げた。
全身の細胞が賦活(ふかつ)し、内側から光が溢(あふ)れ出す。
その光が一本の指先に流れていくと、セイラはそれを結界の真上に向けて放った。
たちまち上空に虹色の渦(うず)が現れ、極光(きょっこう=オーロラ)のようにはためいて消えた瞬間――
影という影が消え失せるほどの、真っ白な光の世界が出現した!
その眩(まぶし)さに、争っていた者も身動きできず、膝(ひざ)を抱(かか)えてうずくまる。
直後に、幽鬼は消滅(しょうめつ)していた。
光が消えて目をあけると、幽鬼から解放された人々が死んだように横たわっている。
「終わ…ったのか……?」
検非違使のひとりがつぶやくと、どこからともなく歓声(かんせい)が上がった。
あの凄(すさ)まじい光がなんだったのか、誰にもわからなかった。
ただ、そのおかげで自分たちは救われた。
天恵(てんけい)とでも呼ぶよりない、不可思議(ふかしぎ)な力によって――
「見ろ!松原の火が消えていくぞ!」
「うわあ。なんかオレ、鳥肌(とりはだ)立ってきた!」
「わしらは、とんでもないものを目の当たりにしているのかもしれん。神仏のご加護(かご)というものを……都は守られている。ありがたいことだ」
その時、夜空を見上げていた検非違使が、ごしごしと目をこすった。
「どうした……?」
「見間違いかな。今、頭の君(とうのきみ=セイラのこと)が空を飛んでいたような……」
あたりが爆笑につつまれたその頃、セイラは清涼殿(せいりょうでん=帝のいるところ)へ急いでいた。
阿黒王の気配(けはい)が、どこにも感じられない。
さっきの光で浄化されていればいいが、そうでなければ、向かうところはただひとつ――
――どうか、間に合ってくれ!
祈るような思いで、セイラは清涼殿の中庭に下り立った。
最初に気づいたのは、血の匂(にお)いと肌を刺す妖気(ようき)。
物々しい二つの篝火(かがりび)の下には、警護(けいご)に当たっていた衛門府(えもんふ)の官人(つかさびと)たちの死体が無残(むざん)に転がっている。
「やはり、ここに……」
「セイラ!阿黒王はここだ!」
声のした方に目を向ければ、御座所(ござしょ)の孫廂(まごひさし)で、今まさに篁と阿黒王が太刀を構(かま)え対峙(たいじ)していた。
「篁!よかった……帝はご無事か!?」
「今の、ところは――っ!」
篁はあぶら汗を浮かべながら、阿黒王の太刀(たち)を受け止め、勢(いきお)いよくはね返した。
「奥の間に籠(こも)っておられる……みんなやられた!宿直(とのい)をしていた音羽(おとわの)中将も、肩を斬られてそこに……クッ!ぼくがやられたら後は頼むぞ、セイラ!」
「そんなことには、させないよ!」
セイラの放った閃光(せんこう)が、阿黒王の足元を襲(おそ)う。
たちまちできあがった巨大な氷塊(ひょうかい)の中に、しかし阿黒王の姿はなかった。
平然(へいぜん)として中庭に下り立った阿黒王の顔に、ぞっとするような笑みが浮かぶ。
「やはり汝(なれ)がきたか。氷攻めとは小癪(こしゃく)なまねを……吾(われ)を閉じ込めようとでも思ったか?」
「ああ。閉じ込めてしまえば、浄化するのは簡単だ。これでも忙しい身でね、手っ取り早くすませようと思ったんだ」
「手っ取り早く、か。フフッ、おもしろいことを言う。吾にそんな口をきくのは、汝がはじめてだ」
間合いを取りながら、円を描くようにじりじりと歩を進める二人の間に、緊迫(きんぱく)感が高まっていく。
「先の光も、汝の仕業(しわざ)か?恐ろしき力よ。幽鬼どもはひとたまりもなかったろう」
「幽鬼は全滅したよ。おまえはどうやってあの光から逃れたのか、教えてくれないか?」
「聞いてどうする?吾を、幽鬼どもと同じとは思わないことだ」
「阿黒王は地の下に隠れていたんだ!セイラ、おまえが落ちたあの時の……」
篁が言おうとしたことを、セイラが最後まで聞くことはなかった。
斬りかかってきた阿黒王から身をかわすため、注意をそらされてしまったからだ。
立て続けにくり出される刃(やいば)を、軽々とかわしていくセイラに、阿黒王の顔がゆがむ。
「汝(なれ)の剣はどうした?市で妖気を断ち切ったあの剣なら、吾を斬れるかもしれぬぞ」
「おまえを斬ればナギも死ぬ。それに、剣はなくした」
「なくした?……フッフッフ、ならばどうやって吾に勝つつもりだ?」
聞いていた篁は、ぎょっとして声を張り上げた。
「セイラ!神剣をなくしたって、本当か!?」
「ああ……」
セイラは苦渋(くじゅう)の色を浮かべて、
「晴明(せいめい)の式神(しきがみ)に神剣を奪われそうになった。取り戻そうとして吹き飛ばしたら、神剣もどこかへ行ってしまった。闇の中では、探しようもない」
「そんな……」
篁は唖然(あぜん)として言葉を失くした。
「晴明……?ふむ、いま一度聞こう。都の者ではない汝が、なぜ都を守ろうとする?」
「大切な友がいる。どこの誰とも知れない私を、あたたかく迎(むか)え入れてくれた人たちが……それで十分だろう?」
阿黒王は唇に酷薄(こくはく)な笑みを浮かべた。
「その都の者に、吾らは隠(おに=鬼)と呼ばれさげすまれてきた。貢(みつ)ぎ物を差し出さねば討伐(とうばつ)される。吾らにも意地はある……が、同胞(どうほう)は争いをよしとしなかった。幾年も……長い歳月にわたって、ふくれあがる貢ぎ物の要求に吾らは耐え忍んできた。家族や同胞を守るためだ!それも……すべては徒労(とろう)に終わった」
「……だまし討(う)ちにあったと聞いている」
「汝がどれだけ滅(めっ)しようとも、この都には死者の怨念(おんねん)があふれている。私欲のためとあらば、略奪(りゃくだつ)しあざむき人の命を奪う。この都はそうやって肥(こ)え太ってきた鬼畜(きちく)だ!そんな都に守るべき価値があるか?吾はこの時を待ち望んでいた。何百年たとうともこの恨み消えるものではない。腐(くさ)りきった都など、吾が呪い滅ぼしてくれる!」
阿黒王は太刀を地面に突き刺し、胸の前で両手を合わせ、何事かをつぶやきはじめた。
「ナギの……力を使っているのか?なにをする気だ?」
突然――
地面が大きく揺(ゆ)れて、地中を巨大なものが移動していく。
それは急速に近づいてきて、地表に姿を現した!
禍々(まがまが)しい気を放つ漆黒(しっこく)の長い胴体の先は地中にあって、その長さを測(はか)ることはできなかったが、鎌首(かまくび)は人の背丈(せたけ)ほどもあり、牙をむいてセイラを威嚇(いかく)していた。
「大蛇(おろち)――!!」
青白い燐光(りんこう)を放つ目と吹きかける息が、セイラの全身を麻痺(まひ)させていく。
「まずは、邪魔(じゃま)な汝から一飲みにしてやろう!」
洞穴(どうけつ)のような口が、獲物(えもの)を飲みこもうと襲いかかってきたその時――黒い風が、セイラを上空へ運び去った。
「オ、ル……」
「麻痺していますね、危ないところでした。お待ちください、今すぐ私が……」
オルフェウスはセイラの胸に手を当て、麻痺を解(と)いていった。
「助かったよ!あの大蛇は……」
「おそらくは、数知れぬ思念(しねん)の集合体のようなものかと……ナギの力を使って、阿黒王が呼び寄せたのでしょう」
思念の集合体――それは、他者を恨(うら)み妬(ねた)み呪い殺そうとする負の感情に満ち満ちていた。
あの邪悪な気をまともに浴(あ)びたら、人は正気ではいられないだろう。
「戻ろう、篁(たかむら)が危ない!」
急に姿を消したセイラを、捜(さが)しているよゆうはなかった。
次の獲物を求めて、大蛇の鎌首が篁に向けられる。
セイラに限って、大蛇に飲みこまれたとは思いたくなかったが、この場は自分の力で切り抜けるしかない!
渾身(こんしん)の力で振り下ろした太刀は、まるで歯が立たなかった。
強い念の力が、大蛇のうろこを黒鉄(くろがね=鉄)の強度にしていた。
「クッ!」
歯ぎしりする篁の頭上に、大蛇が覆(おお)いかぶさってくる。
青白い二つの燐光(りんこう)を見たとたん――篁は動けなくなった。
その横を、阿黒王が通り過ぎていく。
清涼殿の奥に消えていく阿黒王を横目で見ながら、篁は追いかけようと焦(あせ)った。
「まっ、て……」
だが顔前に、大蛇の顎(あぎと=あご)が迫(せま)っていた!
次回へ続く・・・・・・ 第七十二話へ
