第五十一話

篁(たかむら)はとっさに後を追った。
大通りに出たところで、篁は綺羅(きら)姫の牛車(ぎっしゃ)を見失ってしまった。
通りはたくさんの荷車や牛車が行きかい、戦(いくさ)の準備をする人々でごったがえしている。
「綺羅さん、どこへ……」
とにかく今は、綺羅さんをひとりにしてはおけない――と、篁は思った。
それでなくても慣れないこの難波(なにわ)の地で、迷子にでもなってしまったら……。
散々に捜しまわってなかばあきらめかけた時、目の前を行く牛飼(うしか)い童(わらわ)に、篁の目が止まった。
「鳶丸(とびまる)!綺羅さんはどうした?一緒じゃないのか!?」
だが、肩をつかんだ童の顔は、鳶丸とは似ても似つかなかった。
「すまない。人違(ひとちが)いをした……」
呆然(ぼうぜん)と立ちつくす篁の背後(はいご)から、その時突然なにかがぶつかってきた!
ぶつかってきたのは牛車で、驚いた御者(ぎょしゃ)が倒れた篁を助け起こそうと駆け寄る。
「まあ、なんてことでしょう!おけがはございませんでしたか?」
車の中から声がして、女が降りてきた。
「大丈夫、なんともありません。少し考え事をしていて……」
ほこりを払(はら)いながら立ち上がった篁を見て、女は目を見張った。
「まあ、あなたさまは――!」
「あなたは、さっきセイラを迎(むか)えにきた――」
「どうしたの、春日(かすが)?顔見知りのお方なの?」
車から聞こえてきたもうひとりの若い女の声に、篁ははっとした。
「はい、姫さま。セイラさまのお友だちでいらっしゃいますわ」
「まあ、セイラさまの……当家(とうけ)の者が、大変ご無礼をいたしました」
「いえ、ぼうっとしていたぼくも悪かったんです」
篁は苦笑(にがわら)いを浮かべて、牛車に近づいていった。
「佐保(さほ)姫…ですね。失礼ですが、あなたのような深窓(しんそう)の姫君が、どういった縁(えん)でセイラを見送りに……?」
「……それを、どうしてもお答えしなければなりませんの?」
「あっ、いえ。そんなことは……」
篁はカッと頬(ほほ)を赤らめた。
「すみません。無粋(ぶすい)なことを聞いてしまいました」
「それほど大したことではありませんのよ、ふふふ」
佐保姫はさほど機嫌(きげん)を損(そこ)ねたようすもなく、ほがらかな笑い声を立てた。
「車をぶつけたお詫(わ)びに、特別に話して差し上げますわ」
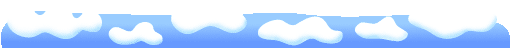
「姫さま、四天王寺(してんのうじ)からどんどん離れていきますよー!」
「離れていきますよー!」
「いつまで走ってればいいんですかー!」
「いいんですかー!」
御者台(ぎょしゃだい)の鳶丸(とびまる)が叫ぶたびに、となりにいる乙矢(おとや)がおもしろがって語尾(ごび)を繰り返す。
綺羅(きら)姫からの返事はない。
「真似(まね)すんな、乙矢!」
「真似すんな、鳶丸!」
いつまでもやめようとしない乙矢を、鳶丸はムッとしてにらんだ。
「おまえ、しつこいぞ!」
乙矢の耳を引っ張って懲(こ)らしめようとした時、
「……車を、止めて」
中から声がして、鳶丸はようやく車を止めた。
「ここ、どこ……?」
のぞき窓から外を見ると、そこはもう難波(なにわ)のはずれで、砂浜に押し上げられた舟が五艘(ごそう)と一面の海が広がっているだけだった。
「ずいぶん遠くまで来ちゃったのね……」
綺羅姫は、気が抜けたような顔でつぶやいた。
「真尋(まひろ)さまもいないし、いつまでもこんなところにいないで早く戻りましょう、姫さま。みんな心配してますよ」
「あたしは戻らないわよ」
綺羅姫は牛車から降りて、潮風(しおかぜ)に髪(かみ)をなびかせた。
「ちょうどいいわ、海が見たかったの。ここが気に入ったから、少し眺(なが)めていくわ」
そう言うと、ためらいもせず砂浜の方へ下りていった。
鳶丸と乙矢は、顔を見合わせて途方(とほう)に暮れた。
主(あるじ)を置き去りにできない以上、ここで綺羅姫が戻るのを待つしかない。
「姫さま、お見送りはどうするんですかー!」
「どうするんですかー!」
――見送りに行きたいわよ。でも……。
綺羅姫は、どんな顔でセイラと会えばいいのかわからなかった。
浜辺に立って、打ち寄せる波の音を聞いていても、佐保姫の牛車に笑いかけるセイラの顔が思い出されてくる。
うわさは本当だった――そう思うだけで、心が悲しみに塗(ぬ)り込められて息ができなくなりそうだった。
気まぐれな潮風(しおかぜ)が、しきりに綺羅姫の髪をなぶっていく。
泣き出したいはずなのに、不思議と涙は出てこなかった。
ただ胸を締(し)めつけられるような重苦しさだけを抱(かか)えて、綺羅姫はいつまでもそこを動けなかった。
沖合(おきあい)を、一艘(いっそう)の船が通りかかる。
――あの船も、海賊討伐(かいぞくとうばつ)に行くのかしら?
そう思って見ているうちに、船はみるみる近づいてきた。
――なっ…なに!?まさかこの浜に来るつもり……?
予感は的中した!
船から浅瀬(あさせ)に下りた十人ほどの男たちが、がやがやと話しながら浜に上がってくる。
もはや感傷(かんしょう)に浸(ひた)っている場合ではなかった。
見つかれば、男たちに太刀打(たちう)ちできる術(すべ)はない。
牛車まで戻るには遠すぎる。
綺羅姫は、とっさに隠れる場所を探した。
――さっきの小舟……あれにもぐりこめば……。
砂浜に並んでいる小舟には荷(に)が積まれてあって、大きな麻布(あさぬの)がかけられていた。
綺羅姫はその中の一艘に乗り込んで、荷と麻布の隙間(すきま)に身体(からだ)を滑(すべ)り込ませた。
麻布からは潮の香りと、生臭(なまぐさ)い魚の臭(にお)いがした。
しばらくすると――
「あったあった、これだ!郡司(ぐんじ=地方官)さまからわが殿へのはなむけだそうだ。こんなところに放っておかれたんじゃ、はなむけもなにもあったもんじゃないが……港まで運んでくれれば、面倒(めんどう)はなかったものを……」
「箱の中身はなんです、おかしら?」
「矢だとよ。船戦(ふないくさ)には欠(か)かせないし、いくらあっても困るもんじゃないからな。一艘に五箱づつ、全部で二十五箱か。ようしお前ら!二箱づつ担(かつ)いで船まで運ぶぞ!」
男たちの目的が、よりによってもぐりこんだ小舟の積み荷だとわかると、綺羅姫は恐怖した。
麻布が剥(は)ぎ取られ、ガタゴトと矢箱を運び出す音が次第(しだい)に近づいてくる。
すぐとなりの小舟から音がし出すと、綺羅姫は麻布の下で身体を強張(こわば)らせた。
――もうダメ!見つかる!
「おかしら!こっちの舟の荷はどうします?人手が足りませんぜ」
「ああ、それは舟ごと曳(ひ)いていく。おまえは舳先(へさき)に引き綱(づな)をつけてくれ」
「なるほど、そりゃ手っ取り早い」
――ええっ!えええ――っ!?
綺羅姫は、思わず漏(も)れ出しそうになる声を必死でこらえた。
海に出てしまえば、逃げ場はどこにもない。
狭(せま)い小舟の中で、男たちに見つからずにいることなど不可能だった。
――セイラ…篁…誰か、助けて――!!
小舟に揺(ゆ)られながら、薄汚れた麻布を握(にぎ)りしめて、綺羅姫は祈るよりなかった。
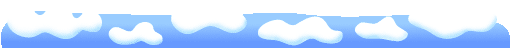
鳶丸と乙矢がうたた寝から覚(さ)めて、戻らない綺羅姫を捜しに浜辺に下りた時は、すでに海上から船影(せんえい)は消えていた。
周辺を捜しまわって主(あるじ)の姿を見つけられなかった鳶丸は、泣き出したい気持ちをこらえ、追い立てられるように四天王寺に戻った。
「姉さんが、いなくなった――!?」
すでに討伐軍の出港時間が迫(せま)っていた。
三人を見送ってひとり門前で綺羅姫が戻るのを待っていた真尋(まひろ)は、鳶丸の話を聞くと、反射的に港に向かいかけた。
「いや、ここはぼくがなんとかしなきゃ。鳶丸、浜辺まで案内しろ!」
真尋を連れて戻ってきた浜辺は、依然(いぜん)ひっそりとしていた。
「姉さん、どこへ行ったんだ……」
――綺羅さんなら、もうしばらくしたら戻ると思うよ。
四天王寺に戻ってきた篁は、そう言って真尋に目でなにかを伝えようとしていた。
それはおそらく――
「真尋さまー、小舟がひとつなくなってる!ここに来た時は五つあったのに……」
浜辺を駆(か)けあがり、息を切らして牛車に戻ってきた鳶丸の知らせに、真尋は愕然(がくぜん)とした。
「まさか、姉さんが――!」
目を皿のようにして隅々(すみずみ)まで見渡しても、穏(おだ)やかな海のどこにも小舟らしきものは見当たらなかった。
おそらく姉さんは、セイラが佐保(さほ)姫と会っているところを見たんだろう――と、真尋(まひろ)は思った。
それが、世をはかなむほどにショックだったんだろうか……。
女心はわからないけど、いつもの姉さんらしくない。こんな――!!
不吉な想像を振り払って、真尋は直(ただ)ちに行動を起こした。
とにかく今は、この広い海のどこかにいるはずの姉の命を救うことが大事だった。
それができるのは、セイラしかいない!
「鳶丸(とびまる)、全速力で港まで戻るぞ!船が出る前にセイラに会うんだ、急げ――!」
難波(なにわ)の港は、討伐(とうばつ)軍を見送る人々や見物客で溢(あふ)れかえっていた。
牛車(ぎっしゃ)の数も多く、民衆に混じって真尋が見知った顔の貴族も大勢やってきていた。
これも追捕使(ついぶし)がセイラと篁(たかむら)だからこそ――と言うべきだろうか。
都の貴族が追捕使の見送りにくるなど、ありえないことだった。
人混みをかき分け、やっとの思いでたどり着いた船着き場で、真尋はありったけの声でセイラの名を呼んだ。
だが声は群衆の喚声(かんせい)にかき消され、時遅く、船は次々と遠ざかっていく。
「セイラ、セイラ――!姉さんが大変なことになってるんだ、セイラ――!」
しだいに小さくなっていく船団(せんだん)に、その声が届くことはついになかった。
セイラ――!
「えっ……」
「どうした、セイラ?」
港を振り返ったセイラに、篁が声をかける。
「ああ、いや。今真尋に呼ばれたような気がして……」
「それなら、戻ってきた綺羅(きら)さんと二人で、港まで来てくれたんだろう」
「そうかも、しれない……」
セイラは顔を曇(くも)らせて、もう一度港を振り返った。
耳に残っているのは、真尋らしくない必死な叫び声だった。
「それより、本当に甲冑(かっちゅう)を着なくていいのか、セイラ?」
肩や胸に鎧(よろい)をつけた篁は、歩くたびにガシャガシャ音をさせている。
セイラは苦笑いして、
「そんなもの必要ないのに……追い風が盾(たて)になってくれるから、海賊(かいぞく)の矢は私たちのところまで届かないよ」
そう言うセイラは、涼(すず)しげな二藍(ふたあい)と青の色重ねの狩衣(かりぎぬ)を纏(まと)っているだけだった。
「そうはいかないよ。みんな甲冑を着てるのにぼくたちだけ着てないんじゃ、貴族は戦をなめてるって思われるだろ?」
言いながら、篁は額の汗を拭(ぬぐ)って日輪(にちりん)を見上げた。
「ふう、それにしても今日は暑いな。夏はこれだから嫌になる」
「重い甲冑(かっちゅう)を着てるからだよ。そろそろ風を呼ぼうか。ナギはどこだろ?」
「ナギならあそこだよ」
篁は振り向いて、船べりに並んでいる漕(こ)ぎ手の間を指さした。
そこに、うずくまって嘔吐(おうと)しているナギがいた。
「完全に船酔いだな。山育ちのナギには、足元が揺(ゆ)れるなんて経験なかったろうから」
自分も青い顔で話す篁を見て、セイラはため息をついた。
「それで?おまえは大丈夫なのか、篁?」
「ぼくは、気が張ってるから平気だよ。でもナギは……これから精神を集中させなくちゃならないんだろ?大丈夫なのか、あんなようすで……」
「大丈夫なわけがない!」
セイラはすぐにナギのところへ走っていって、人目もはばからず唇(くちびる)を合わせた。
まわりの漕(こ)ぎ手がぎょっとして二人を見つめる中、篁だけはその口づけの意味がわかっていた。
――セイラはああやって、自分の気をナギにわけてやってるんだ……。
そのナギは、やっと目が覚(さ)めたような顔でぽかんとしている。
「ナギ、そろそろ時間だよ。やれるかい?」
「セイラさま……」
「おまえを巻き込むつもりはなかったのに、こんなことになってしまってすまないと思ってる。でもここまできた以上、どうしてもおまえの力が必要なんだ」
「オレ、なんだってやります!それに、今はとても気分がいいんです。力がどんどん溢(あふ)れてきて、気の流れが遠くまで見通せる……これなら、精霊(せいれい)を呼び出すことだって……」
ナギは船の揺(ゆ)れをものともせず、それまでとは別人のような身のこなしで立ち上がった。
胸の前で手のひらを合わせ、精神を集中させはじめたナギの身体を光がおおっていく。
「風よ、海原をゆく風の精霊よ!わが求めに応じてその大いなる力を示せ――!!」
彼方(かなた)から風を集めて、突風が吹き寄せてくる。
突然の強風にあおられて水夫たちが身を縮(ちぢ)める中、渡辺薫(わたなべのかおる)がセイラに歩み寄った。
「セイラ殿――!この風はもしや、船に乗る前話していた――」
「そうだよ。私たちを三日で弓削(ゆげ)島まで運んでくれる風だ」
「おお!ならば恐れることはない。者ども、風はわれらの味方だ!帆柱(ほばしら)を立てろ――!」
号令一下、セイラたちの乗った先頭の船が帆柱に帆(ほ)を張ると、それを合図に三百艘(そう)の船が次々に帆を揚(あ)げはじめた。
「すっ、すごい!舳先(へさき)が水を切り裂(さ)いてる!さっきまでとはくらべ物にならない速さだ」
驚いているのは、篁だけではなかった。
同船している渡辺党の水夫や武者たちまでが、童(わらべ)のように興奮して奇声(きせい)を上げ、一様(いちよう)に上を見上げている。
見ると、風をはらみ目一杯に膨(ふく)らんだ帆を支えている帆桁(ほげた=帆を張るために帆柱の上に横に渡した用材)の上に、命綱(いのちづな)もつけず無防備なままのナギが両手を掲(かか)げて立っていた。
「ナギ、いつの間にあんなところに……ナギ?」
篁の視線の先にいたのは、ついさっきまで船酔(ふなよ)いしていたナギではなかった。
榛(はしばみ)色の目を爛々(らんらん)とさせ、鬼神のような《威(い)》を身にまとったなにかだった。
その異様(いよう)なナギの頭上に、黒雲が湧(わ)き急速に発達していく。
「まずいな、このままだと……」
セイラは眉(まゆ)をひそめ、次の瞬間――
船上にいたはずのセイラは、ナギと並んで帆桁(ほげた)の上にいた。
「ナギ、風の流れを上に向けたらダメだ!嵐になるぞ!船の進行方向に逃がしてやるんだ!もっと出力を弱めて、帆に風を集中させるだけでいい!」
『――承知(しょうち)』
ナギは、下ろした腕を船の前方に向けた。
空はいまだどんよりしていたが、身体に感じる風圧(ふうあつ)がやわらいでいく。
「そうだ。気を調整(ちょうせい)できればおまえに怖いものはない、風伯(ふうはく=風神)」
セイラはそっと笑って、
「本当は私がやろうと思っていた。篁がおまえの名を持ち出した時、おまえに頼もうと思いついたんだ。実際、ここまでやれるとは思っていなかったよ……おかげで楽ができた」
そう話しかけられても、ナギは依然(いぜん)なにかに憑(つ)かれたような状態で、無表情のまま前を見ている。
『主(あるじ)、船団の外に小舟が見える。中に人がいるようだ』
「小舟?このあたりの漁師の舟か?」
『舟はそうだが……漁師かどうかはわからない』
「さっきの突風で流されてしまったんだろう。この風の中を自力で戻るのは難(むずか)しいだろうな……私が行って手伝ってこよう」
セイラは瞬時に、帆桁(ほげた)のさらに上空へ飛んだ。
小舟の位置を確認するためだった。
「いた、あそこだ!」
鯨(くじら)に寄りそう小判鮫(こばんざめ)のように、小舟は船団の左側を並行して走っている。
漁師らしき人影は――
「―――!?」
色鮮(いろあざ)やかな紅色の小袿(こうちぎ)と長い黒髪。
漁師のものではありえないそれらが目に飛び込んでくると、セイラはすぐさま小舟に向かった。
身につけている上等な衣(ころも)からして、小舟の中にうつ伏せて倒れているのは、貴族の姫か高位の女房と思われた。
――気まぐれに、舟遊びでもしていたのか……?
「もし、もし……」
セイラは呼びかけて、軽く肩をゆすってみた。
だが、まるで反応がない。
仕方なく、抱き上げて身体をあおむかせようとした時、ぐったりした横顔を見てセイラの呼吸が止まった。
「綺羅(きら)姫――!?」
――見送りにきていたはずの綺羅姫が、なぜこんな舟に……。
だが、そんなことはどうでもいい。
今は綺羅姫の意識を取り戻すことが先決(せんけつ)だった。
頬(ほほ)を何度か叩(たた)いてみても、一向に目を覚ます気配(けはい)がない。
いつもは気丈(きじょう)な綺羅姫の身に、なにかあったのだろうか。
死んだように意識がない綺羅姫を見ていると、セイラはいたたまれない気持ちになった。
――頼むから目を覚ましてくれ!綺羅姫!
こみあげる愛(いと)しさがためらいを消し去り、引き寄せられるようにセイラは唇を重ねた。

次回へ続く・・・・・・ 第五十二話へ
