第三十話

綺羅(きら)姫はふうっと息を吐(は)きだして、チラッと御簾(みす)の方を盗み見た。
「あたしも、くわしいことはよく聞いてないの……。ただ讃良(さら)姫に、どうしても今日の右大臣邸の宴(うたげ)を、遠くからでもいいからのぞいてみたいって泣きつかれちゃって……。真尋(まひろ)に言っても、むかえが来るまでは動かない方がいいって反対されたらしいのよ。それで……」
綺羅姫は、今度は簀子縁(すのこえん)にひかえている安積(あさか)に目を移した。
「宴の準備で、手薄(てうす)になってる裏門の警護(けいご)の者を、桔梗(ききょう)が引きつけてる間に、二人で屋敷の中に忍び込んで植木(うえき)の陰に隠れてたの。その時ちょうど通りかかった、そこにいる安積を讃良姫が見つけて、声をかけたっていうわけなの……」
「まったく!」
篁(たかむら)は怒りを込めて、手にしていた扇(おおぎ)をパチンと鳴らした。
「綺羅さんまでまきぞえにして、どうしてこんな無茶をしたんだ、讃良!?今が一番大変な時だっていうのに……ぼくたちは、お前のわがままにつきあってるひまはないんだよ!」
「私……私……どうしても、藤見(ふじみ)の宴に……」
長い沈黙の後、今にも消え入りそうな声でそう言うと、讃良姫はわっと泣き崩(くず)れた。
重苦しい雰囲気につつまれた部屋の中に、讃良姫のしゃくりあげる声だけが聞こえていた。
「ねえ、篁……」
その重苦しさに耐(た)え切れなくなったように、綺羅姫が口を開いた。
「なにもそこまで問いつめることないんじゃない?今日の宴に、讃良姫のおしたいしている公達(きんだち)がいらしたのかもしれないし……いくら叔父(おじ)とはいえ、話せないことだってあるわよ」
「そんなはずが……!」
あるものか――と言いかけて、篁はふいに口をつぐんだ。
セイラが右大臣邸に来たばかりの頃、讃良姫が、今度の宴でセイラの奏楽(そうがく)を聞かせてもらう約束をしたと、うれしそうに話していたのを思い出したからだった。
――讃良、お前まだ……
篁が暗い目を向けたその時、きびきびしたセイラの声が、部屋の空気を一変(いっぺん)させた。
「綺羅姫の言うとおりだ。なにか事情があったにせよ、私たちの前では話せないこともあるだろう。ここは、篁にまかせるよ。まさかこのまま、讃良姫が戻ったことを正親町(おおぎまち)大納言殿に黙ったままでいるわけにもいかないだろうからね。問題は、讃良姫が失踪(しっそう)していた間、どこにいたのか聞かれた場合だけど……」
「ああ、そのことなら、ぼくから適当にごまかしておくよ。兄上にしても、とりあえず讃良が無事に戻ってきてくれただけで一安心だろうから、それほど深く問いつめたりはなさらないだろう。またへそを曲げられて、家出されても困るだろうし……」
セイラは、その言葉に大きくうなずいた。
「では、私はその間に、綺羅姫を裏門まで送りとどけるとしよう」
「ちょっと待ってよ、セイラ!」
思ってもみなかったことのなりゆきに、綺羅姫は猛然(もうぜん)と異議(いぎ)を唱(とな)えはじめた。
「せっかく苦労して会いに来てあげたっていうのに、そのあたしを、このまますぐに追い返そうっていうの!?それって、ずいぶんひどい仕打(しう)ちじゃない?」
「あっ。そう言えば、うっかり忘れるところだった」
セイラは、いきり立つ綺羅姫の声もまるで聞こえていないように、そらとぼけて言った。
「讃良姫を送りとどけてくれたお礼がまだだったね、綺羅姫」
ニコッと、泣く子をあやすような笑顔を向けられた綺羅姫は、顔を真っ赤に染めて立ち上がると、ついに怒りを爆発させた。
「あっそう。それが命の恩人に対する態度ってわけね、セイラ!あれからうちにも全然来てくれなかったし、二人とも、あたしのことなんてすっかり忘れてたんでしょ?大切な友だちだって言っておきながら、どうやらあたしだけ、いつの間にかのけ者にされてたようね。男ってこれだから信用できないのよ。嘘つきで、薄情(はくじょう)で、移り気で……セイラまでが、そんな奴(やつ)だったとは思わなかったわ!」
「あの、綺羅さん。ぼくとセイラはなにも遊んでたわけじゃ……」
おそるおそる弁解(べんかい)をこころみようとした篁は、しかし、たちどころに綺羅姫に一喝(いっかつ)されてしまった。
「言いわけは結構(けっこう)よ、篁!これで、あたしが世をはかなんで尼にでもなったら、薄情なあんたたちのせいよ。その時は、女行者(おんなぎょうじゃ)になって一生呪ってやるんだから!」
綺羅姫が、そう言い終わるか終わらないかの時だった。
突然プーッと吹きだしたセイラが、あたりをはばからぬ大声で笑い出した。
篁も綺羅姫も、御簾の中にいた讃良姫までが、唖然(あぜん)としてセイラを見守った。
まさか、綺羅姫におどされて気が変になったとも思えなかったが、それほどセイラの笑い声は、この場にそぐわない愉快で楽しげなものだった。
「セイラ……どうかしたの?」
すっかり毒気(どっけ)を抜かれた綺羅姫は、あべこべに心配になって声をかけた。
「なんでもないよ。ちょっとあることを、あっはっはっはっ……思い出したものだから。尼じゃなくて行者(ぎょうじゃ)とはね、はははは……いや、これは私が悪かったね、綺羅姫。はっはっはっ……」
セイラは、息をするのも苦しそうに、腹に手を当てて必死で笑いをおさめようとしていた。
ようやく息が整(ととの)って、セイラが話し始めた頃には、綺羅姫はもう癇癪(かんしゃく)を起こしたことなど、きれいに忘れたような顔をしていた。
「言い方がまずかったことはあやまるよ。でも篁もさっき言ってたように、讃良姫の入内(じゅだい)を阻止(そし)するためには、今が一番大切な時なんだ。綺羅姫のことを忘れてたわけじゃないよ。だけど、この件が片づくまで、あともう少し時間がほしいんだ。それがすんだら、二人で必ず綺羅姫を訪ねるって約束するよ。いかがでしょう、これでご納得いただけましたか?」
セイラはおどけたしぐさで、仰々(ぎょうぎょう)しく体をかがめた。
「――いいわ。そのかわり、今日の貸しは大きいわよ、セイラ」
綺羅姫はしっかりと釘(くぎ)を刺した後で、くったくのない笑顔を見せた。
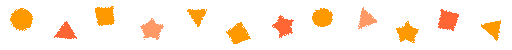
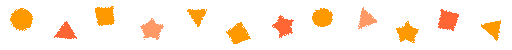
セイラと親しく話がしたいと思っていたのは、綺羅姫や讃良姫に限ったことではなかった。
権勢(けんせい)を誇る右大臣家の宴ともなると、招待客の数も並たいていのものではなかったが、そのほとんどがセイラ目当てだと言っても言い過ぎではなかっただろう。
管弦(かんげん)の宴の日以来、セイラの評判は高まる一方で、その人気は衰(おとろ)えることがなかったが、内裏(だいり)に参内(さんだい)するようになってからのセイラは、帝に独占されてしまったようなところがあり、それ以外の交際となると、宴の招待を受けてもなぜか容易(ようい)に足を運ぼうとしなかった。
そのセイラと親しく話ができる機会とあっては、宮中の名だたる公達(きんだち)がこぞって色めき立つのも無理はない。
なにしろ比類(ひるい)のない美貌(びぼう)に加えて、帝の寵愛(ちょうあい)を一身に集めているうわさの君ときては、誰しも特別な関心を寄せずにはいられなかったろう。
右大臣もその辺は心得(こころえ)たもので、宴がはじまるとすぐ、セイラに糸竹(しちく=和楽器)の調べを頼み込んできた。
セイラはこころよく引き受けて、藤見の宴は、ちょっとした管弦の宴の趣(おもむき)だった。
琵琶(びわ)と笛の演奏を終えて、ひとまず自分の務(つと)めを果たしたセイラは、視界の中に篁の姿を探した。
宴の場に見当たらなかったので、東の対屋(たいのや)に戻ったのだろうと思い向かおうとした時、後ろからセイラを呼び止める者がいた。
「おや、セイラ殿。せっかくの宴の席を抜け出して、どちらにまいられるのです?」
セイラが振り返ると、そこには権(ごんの)中将をはじめ、左馬頭(さまのかみ)、蔵人(くろうどの)少将など、なじみの顔ぶれが五、六人ズラリと勢ぞろいしていた。
「やあ、これはみなさまおそろいで……」
セイラは、うるさがたに見つかってしまったことを内心後悔して、笑みを引きつらせた。
「あいかわらずの見事な笛の音に、賛辞(さんじ)を申し上げようとまいってみれば、早々と退出のごようすとは、われらが君はちとつれなすぎるのではありませんか?」
蔵人少将は酒に酔ったのか、すでにほんのりと赤い顔をしていた。
「いやいや、それはならん。今宵(こよい)こそは、わしの盃を受けていただかねば。飲みくらべでは、セイラ殿には負けませんぞ。ワッハッハッハッ……」
と、これは左馬頭(さまのかみ)。
『酒豪(しゅごう)』という文字の前に、『激』と『超』と『絶』と『大』の字を冠(かん)したいほどの左馬頭と飲みくらべなどされたら、体がいくつあってもたりないと怖気(おぞけ)をふるったセイラは、神妙(しんみょう)な顔つきでもっともらしく切り出した。
「私としてもそうしたいのは山々ですが、残念なことに今は物忌み(ものいみ=方角や日が悪い期間、家にこもって身を慎むこと)中で、参内もひかえている次第(しだい)です。本来であれば、こういう晴れがましい席に出ることも遠慮すべきなのですが、右大臣殿に楽の音だけでもと請(こ)われたので――」
「おやっ、行き触れ(いきぶれ=出先で死体などに行き合って、けがれを身に受けたので外出をひかえること)ではなかったのですか?確か治部(じぶ)の大輔(たいふ)がそう……」
セイラの話の腰を折(お)って、左京大夫(さきょうのだいふ)が首をひねった。
今度は、それを聞いた左馬頭が口をはさんだ。
「わしは、方違え(かたたがえ=外出先の方角が悪い時、前夜に他の場所で一泊し、翌日そこから方角を変えて出かけること)先で、急な癪(しゃく=腹痛)を起こしたと聞きましたぞ?」
「そうそう、私もそう聞きましたよ。なんでもその方違え先には、目のさめるような美姫(びき)がいたとかで、さすがの月の君も、それには心を動かされたとか……」
話を聞いていたセイラは、唖然(あぜん)として頭をかかえてしまった。
篁は内裏(だいり)にどんな届出(とどけで)をしたのかと、つくづくとあやしまずにはいられなかった。
「さよう。おかげで本日の今上(きんじょう)のご機嫌は、あまりうるわしいとは申せませんでしたね」
そう言って、権中将はニヤニヤしながらセイラに近づくと、声を落とした。
「昨夜の騒ぎを、今上はことのほかお気にかけておられましてね……ここだけの話ですが、『右近衛(うこんえの)少将は、セイラに宮中の務(つと)めをなんと教えているのか――!』と、たいそう不快(ふかい)げにもらしておられましたよ」
「ははは……」
セイラのこめかみのあたりを、タラリと冷や汗が伝った。
賊(ぞく)をおびきだすために、承香殿(じょうきょうでん)の宴に身がわりを立てることは帝も承知していた。
だからこそ昨夜の物の怪騒ぎを聞いて、賊を捕らえたというセイラの報告を、帝は一日千秋の思いで待っていたことだろう。
「なんの、物忌(ものい)みでも方違(かたたが)えでもよいではござらぬか。天界からまいられたセイラ殿が、わが国の風習をさほど気にすることもあるまい。こんなところで立ち話をしていては酒も飲めん。ささっ、セイラ殿。そうと決まったら、向こうの席でわしらに少しおつきあいくださらんか?」
左馬頭(さまのかみ)にそう言われると、セイラもそれ以上断るすべがなかった。
「先ほど、三位中将(さんみのちゅうじょう)殿をちらりとお見かけしましたが、もうお二人の戯(ざ)れごとの種にされるのだけは、ご免(めん)こうむりますよ」
ため息まじりにセイラが念を押すと、権(ごんの)中将はニヤリとして答えた。
「戯(ざ)れごととおっしゃられては心外ですね。ですがお約束はできかねます。こればかりは相手のあることですから……」
その夜は、ささやかに吹き抜ける風が、少し肌寒く感じられた。
雨上がりの後の、湿気(しっけ)をふくんだひんやりとした夜気(やき)は、上空を赤々とこがす篝火(かがりび)によっても、完全に追い払われることはなかった。
だが、そんな肌寒さも感じさせないほど、宴の場は、いまや最高潮の盛り上がりを見せていた。
お目当ての君の登場に、人々は先を争ってセイラのもとに押し寄せた。
演奏の見事さをほめたたえる者から、酔った勢いで強引に盃をおしつけてくる者、はては家宝にしたいから髪の毛を二、三本わけてくれないかと言い出す者までいた。
さすがにそのお調子者は、左馬頭の一喝(いっかつ)で追い払われてしまったが、その後も、押しかける者は跡(あと)を絶たなかった。
その時――
「セイラさま。ただいま使いの者がまいりまして、これを至急(しきゅう)セイラさまにと……」
いつの間にかすぐ後ろにやってきていた安積(あさか)が、そう言って一通の文を差し出した。
「私に……?」
セイラは受け取ると席を立って、人気(ひとけ)のない庭はずれの篝火(かがりび)の前で文を開いた。
料紙(りょうし)からは、上質な練香(ねりこう)の香りがただよった。
『――この文をお読みになりましたら、今晩登花殿(とうかでん)までお越しくださいませ。セイラさまに、どうしてもお話ししておかなければならないことがございます。左大将さまが見張り役につけておいた女房には、ひまを取らせておきました。この機会を逃(のが)せば、当分お会いすることはできなくなるでしょう。紫宸殿(ししんでん)の北廂(きたひさし)にむかえの者をやります。なにとぞ、お越しをお待ち申し上げております』
「おむかえの牛車(ぎっしゃ)がまいっておりますが、いかがなさいますか?」
少し離れて待っていた安積が声をかけると、セイラは篝火に頬(ほほ)を染(そ)めて、
「もちろん、すぐ行くよ。着がえるまでの間、待ってもらってくれ」
「若君には、お伝えしておきますか?」
知らせを受けて、篁(たかむら)は車寄せ(=牛車に乗り降りするところ)に急いだ。
こんな時に、文に呼び出されて出かけるという、セイラの真意(しんい)がわからなかった。
――敵の策略(さくりゃく)に、わざわざ乗るようなものじゃないか!
そんな危険を冒(おか)す必要がどこにある?
明日になれば、賊(ぞく)を靫負庁(ゆげいのちょう)に引き渡して、すべては解決するというのに……。
「セイラ、待てよ――!」
渡(わた)り廊下で追いついた篁が、前を行くセイラの肩をつかんだ。
とたんに、上体がぐらりと揺(ゆ)れて、セイラはなんの手ごたえもなくその場に倒れ込んだ。
「大丈夫かい、セイラ!?どうかしたの?これぐらいで倒れるなんて……」
篁の腕にささえられながら、起き上ったセイラは、ばつが悪そうな照れ笑いをして、
「いや、ちょっとめまいがしただけさ。大丈夫なんともない」
「ならいいけど……」
この時、篁はなにかを言いかけようとした。
見過(みす)ごしにはできない、とても大事なこと……。
だが、それがなんだったのかを思い返すよゆうもなく、苛立(いらだ)ちが口をついて出ていた。
「むかえの牛車が来て、出かけるって聞いたよ」
「安積が言ったんだね。まったく有能(ゆうのう)な家令(かれい)だよ!あれほど口外(こうがい)しないように言ったのに……」
「ぼくは、安積が知らせてくれてよかったよ。誰に会うつもりなの?」
「それは言えない。でも、篁が心配するような方じゃないよ」
言いながら、車寄(くるまよ)せに向かおうとするセイラの前に、篁はなおも立ちふさがった。
「どうしても、出かけるつもり?」
「ああ。その方に会えるのは今晩だけなんだ。この機会(きかい)を逃(のが)したくない」
「今晩だけ、って……」
篁は、危機感のないセイラの反応にやきもきした。
「今晩出かけるのがどんなに危険か、わかってるの?たとえ誰に会うためでも、今晩だけは邸(やしき)にいた方がいい!だいたい今晩しか会えないなんて、見えすいてるよ。そうやって、いやでも出かけなくちゃならないように仕向(しむ)けてるとこが、罠(わな)だって言ってるようなものじゃないか!そのくらい、セイラにもわからないはずないだろ!?」
「これは、今回の件とは関係ないよ。その方は私に……とても大切なことを、伝えようとしてくれているんだ」
「大切なことってなんだよ!自分の命よりも大切なこと!?」
「篁!頼むから行かせてくれ!!」
セイラは、ついに怒鳴(どな)った。
「ここで言い争いをしているひまはない。亥の刻(いのこく=午後九時〜午後十一時)までには必ず帰ると約束する。だから……!」
決してひるがえさない、強い決意のこもった目を見ると、篁もそれ以上引きとめることはできなかった。
「本当に……本当に、信じていいんだね、左大臣や尹(いん)の宮とは関係ないって……」
「……ああ。帰ったら、今度こそ尼寺(あまでら)でのことを話すよ」
最後に、セイラはにこっと笑った。
その見なれた笑みが、なぜか篁の心に焼きついて離れなかった。
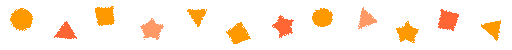
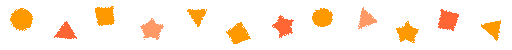
重い足取りで、東の対屋(たいのや)に戻った篁を、待っていた人影があった。
「セイラは、出かけたの?」
それは、とっくに帰ったはずの綺羅(きら)姫だった。
裏門から綺羅姫の乗った牛車を送りだそうとしていたセイラが、右大臣に呼ばれて行ってしまった後、綺羅姫は夕闇(ゆうやみ)にまぎれて邸にまい戻ってきていた。
東の対屋(たいのや)にもぐりこみ几帳(きちょう)の陰に隠れて、やってきた篁の前に飛び出すと、
「篁、今が一番大変な時って、どういうこと!?セイラはもうすんだことって言ってたけど、ほんとはそうじゃないんでしょ?あたしには、隠(かく)さずにおしえてよ!!」
招かれざる客の再来(さいらい)に、あんぐりと口を開けたままへなへなと座り込んでしまった篁から、綺羅姫はこれまでの経緯(いきさつ)をすべて聞き出していた。
安積が知らせを持ってきたのは、そんな時だった。
「ああ……」
篁は不機嫌この上ない顔で、どかりと腰を下ろした。
「セイラが尼寺(あまでら)へ行った理由も、まだ聞かされてないっていうのに……おかげでぼくは、また待ちぼうけだよ!」
「篁……あの、あたしが戻ってきたこと、怒ってる?」
「怒ってるかって!?そりゃあ――!」
言いかけて、篁はのどまで出かかった怒りを飲みこんだ。
今さら愚痴(ぐち)を言ったところで、どうなるものでもない。
責(せ)められるべきは、セイラをとめられなかった自分の方だ――
「あんなセイラははじめて見た。あんな必死な目をしたセイラは……たとえ綺羅さんが戻ってこなくても、ぼくにはセイラをとめられなかったよ」
「必死な目……?」
「うん。今回の件とは関係ないって、思いつめた顔して……。だからぼくも、それ以上行くなとは言えなかった」
聞いていた綺羅姫の顔が、みるみるこわばっていく。
「綺羅さん?……なにか心当たりでもあるの?」
「篁……もしかしたらセイラは、記憶の手がかりを見つけたのかもしれないわ」
「まさか!?」
「安積は、セイラが文をもらったって言ってたでしょ。きっとそうよ!だから、どんなに危険な夜かわかってても、行かずにいられなかったのよ!」
「そう言えば、その方はとても大切なことを伝えようとしてくれている、って言ってたっけ……」
「セイラは、誰に会いに行ったの!?」
篁は、力なく首を振って、
「聞いても言わなかった。ただ……正装(せいそう)に着がえてたから、もしかしたら内裏(だいり)に行ったのかも……」
「こんな時間に……?」
「こんな時間でも、お務(つと)めに励(はげ)んでいる者は大勢いるさ。ぼくなんか、しょっちゅう居残りさせられて……」
「こうしちゃいられない。篁、あたしたちもいくわよ!」
次回へ続く・・・・・・ 第三十一話へ
