第二十五話

「ただ今お見かけしたのは、正親町(おおぎまち)大納言殿ですね?」
「さあ、どなたでしたか。すれ違いざまにごあいさつをかわしただけでしたので……」
尹(いん)の宮は、あいかわらず優雅なしぐさで、扇(おおぎ)を口元にあてながらゆるゆると言った。
セイラはたまらずに吹き出した。
あまりの白々しさに、反論する気もなくしたようだ。
「いずれにしても、大納言(だいなごん)殿をお味方に引き入れたのは正解でした。このたびの入内(じゅだい)話に、帝が乗り気ではなかったとしても、むげには断りきれなくなるほどの世論(せろん)を作り上げるためには、格好(かっこう)の人選といえるでしょう。右大臣家の反対がなくなれば、三の姫の入内は決まったようなものですからね。ですがそのために、大納言殿の姫の入内というおまけまでついてきてしまったのは、左大臣殿にしてみれば痛しかゆしというところですか」
表情を変えない尹の宮の目に、かすかな動揺(どうよう)が走った。
「おや?図星(ずぼし)でしたか。ところがその正親町大納言殿も、肝心(かんじん)の姫に家出されたとあっては、さすがにうろたえざるをえなかったようですね。入内を嫌(きら)って家出したなどということが、宮中でうわさにのぼるようなことにでもなれば、せっかくの入内話もフイになりかねませんから。実のところ、昨夜は大納言殿の郎等(ろうどう)が右大臣邸まで乗り込んできて、大騒ぎでしたよ」
肩をそびやかしてみせたセイラを、尹の宮は冷ややかに見ていた。
「月の君はそれを、宮廷中に吹聴(ふいちょう)なさってまわるおつもりか?」
「まさか!」
セイラはニコッと相好(そうこう)をくずした。
「大納言殿の名を汚すようなことをするつもりはありませんよ。そんなことをしなくても、姫が行方(ゆくえ)をくらましたというだけで、あなた方の計画は頓挫(とんざ)してしまうことになるでしょうから」
「……あんがい、あなたの仕業(しわざ)かもしれませんね」
なに気なさそうに言った尹の宮の優雅(ゆうが)な声音(こわね)に、ぞっとするような寒々しいものが感じられた。
「私が――?とんでもない。右大臣家にはいろいろ世話になっている身ですからね。恩(おん)を仇(あだ)で返すようなことはしませんよ」
セイラは笑い飛ばしたが、尹の宮がその言葉を信用していないのは明らかだった。
「どこまでも目ざわりな方だ!」
ふいに、とりすました仮面を脱ぎ捨てるように言うと、尹の宮は憎悪に満ちた目で、セイラをにらみつけた。
「あの時、やはりひとおもいにあなたを始末(しまつ)しておくべきでしたよ」
セイラは、まるで楽しい冗談を聞いているように、笑いをかみ殺した。
「あなたには、私を殺すつもりなどありませんでしたよ、尹の宮殿。では……」
軽く一礼すると、それまでかわしていた恐ろしげな会話が嘘(うそ)のように、涼(すず)しげな顔をしてセイラは立ち去っていった。
後に残された尹の宮の胸に、セイラの最後の言葉が、鋭(するど)いとげのようにつき刺さっていた。
その頃、左大臣についてのうわさが、宮中のあちこちでささやかれるようになった。
うわさの内容は、例の物の怪(もののけ)騒ぎは、左大臣自身がしかけたのではないか――というものだった。
いかにもありそうなこの話に、うわさ好きの宮廷(きゅうてい)人は飛びついた。
――血のつながりのない東宮さまよりも、自分の孫(まご)を東宮にすえた方が、外戚(がいせき)として絶大な権力をふるえると考えたのだろう。
――その証拠に、物の怪騒ぎがあって間もなく、梨壺(なしつぼ)から桐壺(きりつぼ)に御所を移された東宮さまは、見違えたようにお元気になられて、近ごろでは食も進まれるそうだ。
――この分では、左大臣殿が入内話でもたついている間に、民部卿は思わぬ拾(ひろ)いものをすることになりそうではないか。
――なにしろ、物の怪はもう現れる必要がないだろうからね。
このうわさは、もちろんセイラが仕組(しく)んだものだったが、そのことを知らない左大臣は震(ふる)えあがった。
宮中のような閉鎖(へいさ)的な社会において、うわさほど怖いものはない。
たちの悪いうわさひとつで、宮廷人の政治生命が抹殺(まっさつ)されてしまうこともあるからだ。
身に覚(おぼ)えがなければなおさらに、すぐにでも潔白(けっぱく)を証明して見せねばならない。
入内話を進めている矢先(やさき)のこのうわさに、老獪(ろうかい)な左大臣もあせりが出たのか、慎重(しんちょう)さに欠(か)けていた。
うわさを打ち消そうと、左大臣はある思い切った行動に出た。
それが、自らの墓穴(ぼけつ)を掘ることになろうとは思いもよらずに――
その日、夜の帳(とばり)が都をおおいつくした頃、内裏(だいり)の東口にある建春門(けんしゅんもん)の下、篝火(かがりび)をたいて警護(けいご)する衛士(えじ)を遠くに見ながら、暗闇に立ちつくす影があった。
影は、人の力では飛び越えられそうもない、内裏を取りまく長壁をひと蹴(け)りで飛び越すと、淡(あわ)い月の光に長い髪をきらめかせて、地上の闇に消えていった。
「すると尹の宮殿は、昨年秋の除目(じもく)で帝に抜擢(ばってき)されるまでは、世にも忘れられた宮だったのですね?」
「ええ、そう申してもよろしいでしょうね。私も、司召(つかさめ)しの折(おり)にそのお名を耳にして首をかしげたくらいですから」
「帝の兄宮が、なぜそのような境遇(きょうぐう)に……?」
「さあ。その辺のことは私もよくは存じませんが、年寄りの話では、なんでも今から二十年近く前に、承元(じょうげん)の変と呼ばれる謀反(むほん)があったそうです」
「謀反……?」
「ええ。当時左大臣だった尹の宮殿のご祖父源(みなもとの)喬周(たかちか)卿が、ひそかに東宮御所に神璽(しんじ)・宝剣(ほうけん)を運び込んで、帝に退位(たいい)を迫(せま)ろうとしたのが露見(ろけん)して、ご一族は都から追われてしまったと聞いています。その後、喬周(たかちか)卿は太宰府(だざいふ)に遠流(おんる=流刑)となり、その地でお亡くなりになったそうです。ただ帝のご寵愛(ちょうあい)深かった潔(きよ)姫さまと、まだ幼かった東宮さま…今の尹の宮殿ですが、お二方だけは先の帝のお情けで、尼寺の庵主(あんじゅ)をなさっておられた喬周(たかちか)卿の姉上、慶尚院(けいしょういん)さまにあずけられたと聞きました」
「尹の宮殿に、そんな過去が……」
「ですから、宮とは申されても当時はかなり侘(わび)しいお暮らしぶりだったようで……。その後早くにご生母の潔姫さまを失くされ、慶尚院さまをご養母として尼寺でお育ちになったそうです。その頃のお名前が確か、素鵞(すが)の宮明理(あきまさ)さま…と申されましたかな。時おり訪ねてくる子等と、尼寺で遊んだりしたこともあると、笑って話しておられるのをもれ聞いたことがありますよ」
「尼寺(あまでら)……ですか」
セイラは、目の前を悠々(ゆうゆう)と泳いでいく緋鯉(ひごい)をながめながら、フーッとため息をついた。
宮中の中庭にある池のほとりで、セイラと権(ごんの)中将は、先ほどから長いこと声をひそめて立ち話をしていた。
左大将と左大臣をそそのかして、対立させようとする尹の宮の狙(ねら)いがどこにあるのか、生い立ちから手がかりがつかめないかと、宮中の事情通の権中将にその辺のことを聞いてみたのだが、はかばかしい答えは得られなかった。
尹の宮が東宮の位を追われ、一族が没落(ぼつらく)したのは、祖父が起こした謀反のせいに他ならない。
「尹の宮殿が昇殿(しょうでん)されて、初めてそのお顔を拝見した時は、さぞ驚かれた方もいらしたでしょうね。実は私もその一人ですが、今上の玉顔(ぎょくがん)を拝(はい)する光栄に浴(よく)したことがある者の中には、その面差(おもざ)しがあまりにも似ておられるので、これはまるで双子のご兄弟のようではないかと、ひそかに言い出す者までいる始末(しまつ)でしたよ」
「確かに……」
セイラは初めて帝と会った時、『尹の宮殿――』と呼んでしまったことを思い出して、口元をほころばせた。
「ご自分が今をあるのは、なにをおいても今上のおかげ、と申される尹の宮殿を、我々も見習いたいものだと思いますよ。今上もそんな尹の宮殿の心情を思いやられて、一番のご信頼をおいておられましたからね」
セイラはまた一つ、フーッとため息をついた。
聞いた限りの話では、尹の宮がこれ以上の栄達(えいたつ)を望んでいるような、野心のかけらはどこにも見当たらなかった。
――出世が目的ではないのか。
だとすると、あの冷たい殺気はどこからくるのか――?
単に、帝の寵愛(ちょうあい)を横取りしたセイラへの妬心(としん)からだけとも思えなかった。
それともまだなにか、他に見落としていることがあるというのか――?
池の水面(みなも)をのぞきこみながら黙りこんでしまったセイラを、権中将は意味ありげな目つきで見つめた。
「それにしても、セイラ殿が興味を示されたお方が尹の宮殿とは、私としては少々複雑な心境ですね。恋敵(ライバル)はてっきり――」
「はははっ。そんな艶(つや)めいた話ではありませんよ。私は、尹の宮殿にはひどく嫌われていますからね」
「嫌われている……尹の宮殿に?はて……」
権中将は納得しかねる顔で、何度も首をひねった。
が、やがてあきらめたように肩をすくめて、セイラの横顔をまぶしそうに見つめた。
「いずれにせよ、私がお話できることはこれぐらいです。お約束どおり、明夕(みょうゆう)の杜若(かきつばた)の宴(うたげ)にはお越しいただけますね、セイラ殿?」
「もちろん。お約束したからには、喜んでうかがわせていただきますよ」
それを聞くと、権中将はなんともうれしそうな顔をした。
「これでやっと、セイラ殿をわが邸にお迎えできるというわけです。それにしても、お歴々(れきれき)の方々をさしおいて、最初にわが邸にお越しいただけるとは、夢にも思いませんでしたよ」
ほがらかな権中将の笑い声は、しかしすぐに、真剣な表情で肩をつかんだセイラにさえぎられてしまった。
「今、なんとおっしゃったのです!?」
「ですから、やっとセイラ殿をお迎(むか)えできると――」
「その後は――!?」
権(ごんの)中将は、怪訝(けげん)な顔をした。
肩をわしづかみにして、語気(ごき)も荒くつめよるセイラは、いつもの落ち着きのある態度とは明らかに違っていた。
「他の方々をさしおいて、最初にわが邸にお越しいただけるとは夢にも思わなかったと……それがなにか?なにしろセイラ殿は、宮中に参内(さんだい)されるようになってからは、めったに外出もなさらないとうかがっていましたから……」
「そう。ずっと会いたいと思っていたから……と、あの時女御(にょうご)さまはそう言っておられた……しかし、それにしては……」
ようやくのことで権中将の肩を手放すと、うわ言のようにセイラはつぶやいた。
権中将は、心配そうにまだなにか言っていたが、もうセイラの耳には届いていなかった。
セイラの関心を、これほどまで強く引いたのは、
『――夢にも思いませんでしたよ』
という権中将の一言だった。
それは、登花殿(とうかでん)女御と対面した時に聞いた言葉でもあった。
『よもや、こうしてお目にかかれる日が来ようとは、あの頃は夢にも思えませんでしたもの』
という、まるでずっと以前からセイラを知っていたような口ぶり――
その時にも、セイラはひどく奇異(きい)な印象を受けたものだった。
だが女御に、セイラが昇殿(しょうでん)してからずっと会いたいと思っていたせいで、親しげなことを言ってしまったと言われ、それ以上の追求をあきらめたのだったが……。
「違う!!」
思わずセイラは、声に出して叫んでいた。
権中将は驚いてセイラを見つめた。
そのセイラは、なにかに取りつかれたような目をして、じっと虚空(こくう)をにらみすえている。
――登花殿女御は、私のことを知っていた!それも、私が吉野に現れるずっと以前からだ!でなくて、私が宮廷にあがったわずかひと月ほど前のことを『あの頃――』だなんて言うものか!
それは、セイラの中で確信に近いものだった。
ではなぜ、女御はセイラにそのことを告げようとしないのだろう?
なぜ、知っていることを隠そうとするのか?
そもそも女御は、どうやってセイラのことを知りえたのか?
セイラ自身が手に入る限りの情報をかき集めても、今だになんの手がかりも得られずにいるというのに……?
そう言えばあの時、女御はなにかを言おうとしていなかったか……?
さまざまな疑念が脳裏(のうり)をよぎって、その先の思考に意識が集中できなくなりかけた時、権中将がおそるおそる声をかけてきた。
「もし、セイラ殿。どうかなさいましたか?尹の宮殿のことで、まだなにか……?」
セイラは、パッと権中将を振り返った。
――そうだ。尹の宮!
物の怪騒ぎがあった夜、最初に尹の宮が言った謎の言葉を、その後の騒動にまぎれて、今の今までセイラは忘れ去っていた。
『本当に、あなたが現れるとは思いませんでしたよ』
その言葉が意味するものは、ひとつしかない。
尹の宮もまた、セイラが現れることを知っていた!
登花殿女御と尹の宮――まるで接点(せってん)のないこの二人が、以前からセイラを知っていたとはどういうことなのか?
それぞれが、まったく別の経路(けいろ)から情報を手にしたとも考えられるが、セイラの直感は強くそれを否定した。
――もし二人が、前々からの知り合いだったとしたら、珍しい銀色の髪をした人間がいることを話して聞かせたとしてもおかしくない!
それがセイラのたどりついた結論だった。
では、二人が知り合ったのはいつ?どこで……?
――尼寺(あまでら)だ!
尹の宮が、幼少(ようしょう)の頃あずけられたというその尼寺に行けば、失くした記憶の手がかりが得られるかもしれない。
「権中将殿!先ほどのお話にあった尼寺の場所をご存知ですか!?」
「いえ、私もそこまでは……」
「そうですか……」
セイラはキュッと唇をかみしめた。
すでに左大将の手がまわっている登花殿を、再び訪れるのはむずかしかった。
尹の宮から真実を聞き出すのは、さらにむずかしいだろう。
すぐ手の届くところに、探し求めていた答えがあるというのに、その扉は固く閉ざされていた。
やっと芽生(めば)えた希望の芽が、またたく間にしぼんでいこうとするのを、セイラはにぶい痛みとともに感じていた。
「ただ……尹の宮殿のお邸に、朝早く寺の尼が入っていくのを、時折見かけるという者がいます」
「寺の尼が?」
「ええ。おそらく昔なじみの尼ではないかと……」
「ありがとう、権中将殿!それだけ聞けば十分ですよ。このお礼は、いくら申してもたりないくらいです!」
セイラは権中将の手を握りしめ、乱暴とも思えるくらいに振りまわした。
この喜びように、権中将は面食(めんく)らって目を丸くしながらも、うっすらと頬(ほほ)を染めた。
「そうおっしゃられても、私にはなんのことかよくわかりませんが……セイラ殿のお役に立てたのなら、こんなにうれしいことはありません」
「そう言っていただけると、ご迷惑(めいわく)もかえりみずお引きとめしたかいがありました。私は寄るところがあるので、これで失礼します」
「あっ、セイラ殿!明夕(みょうゆう)のお約束を、くれぐれもお忘れなきよう!」
背を向けて歩き出したセイラに、権中将の声が追いかけてきたが、セイラの心はすでに尼寺に飛んでいた。
萌(も)えいでる若柳(わかやなぎ)の風情(ふぜい)をした登花殿女御。
その女御と尹の宮が古くからの知り合いだったとすると、女御に口止めをしたのは、おそらく尹の宮だろう。
この二人の関係が、今度の件となにか関(かか)わりがあるのだろうか。
それもこれも、尼寺に行けば、すべてわかるような気がしていた。
二人がセイラを知っていたことも、尹の宮の目的も……。
――尼寺に行きさえすれば……。
しぼみかけた希望の芽は、まだ摘(つ)み取られてはいない!
7.仕組まれた謀反
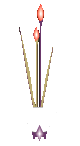
殿上口(てんじょうぐち=清涼殿にある殿上の間の入口)を目指していたセイラの足がふと止まったのは、聞きなれた誰かの声が、自分の名を呼んだような気がしたからだった。
顔を上げてあたりを見まわすと、正面にみえる殿上口の高欄(こうらん=欄干)に、身を乗り出さんばかりにして手を振っている三位(さんみの)中将の姿が目に入った。
ギクッと一瞬身をこわばらせたセイラが、そ知らぬ振りをして建物の陰(かげ)に隠れようとした時には、もう遅かった。
三位中将は履(は)き物をひっかけると、セイラをめがけて一目散(いちもくさん)に突進してきた。
「おお、わが背(せ)の君!こんなところにいたとは……いやあ、お探ししましたぞ!」
三位中将は、笑顔をひきつらせているセイラを有無(うむ)を言わさず抱きしめると、日の光を受けてキラキラと輝いている銀色の髪に、大胆に顔をうずめた。
そうしていると、外から見た限りでは、セイラの姿は三位中将の衣にすっぽりと隠れてしまい、ほとんど見えなくなってしまうほどだった。
セイラも長身の方だったが、三位中将は六尺(180㎝)を優(ゆう)に超えていて、頭半分ほどセイラより飛び抜けていた。
加えて、中背でどちらかというと細身の権中将と違い、隆々(りゅうりゅう)とした筋肉の持ち主でもあった。
がっしりとした三位中将の胸元にからめとられてしまったセイラは、力強い腕でぐいぐいと締(し)めつけられ、呼吸も満足にできないありさまだった。
「三位…中将……苦し…息が……」
「ん――?おお、そうかそうか!これはすまなかった。背の君」
声も切れ切れのセイラの訴(うった)えは、かろうじて三位中将の耳に届き、ようやくのことで荒々しい抱擁(ほうよう)から開放されたセイラは、むさぼるように二度、三度と息を吸い込んだ。
こんな目にあわされたのでは、セイラといえども、自然顔つきがけわしくなるのはしかたなかった。
「それで、私を探しておられたとは?」
とげとげしいセイラの声音(こわね)を、三位中将はまったく気にするようすもなく、
「そうそう、そのことそのこと。実は明日、わが邸でもよおす牡丹(ぼたん)の宴に、背の君にもぜひ来ていただきたいと思いましてな。こうして誘いにまいったしだいだが……どうであろう、今度こそ受けてくださらぬか?」
「あいにくですが三位中将殿、明日は――」
「明日、セイラ殿はわが邸の宴にまいられるのですよ。残念でしたな、三位中将殿!」
穏便(おんびん)に断(ことわ)りを申し入れようとしたセイラの横あいから、挑発(ちょうはつ)するように口をはさんだのは、後からやって来ていた権中将だった。
それを聞くと、三位中将はフフンと鼻を鳴らした。
「背の君、こういう輩(やから)とつきあうのは感心しませんな。今上のお気に入りとあらば誰にでも取り入ろうとする、権勢欲(けんせいよく)のかたまりのような連中ですぞ」
「これは聞きずてならないことを申される。三位中将殿こそ、年若い貴族や童(わらべ)をかこって、悪癖(あくへき)にふけるのはいかがなものかと思われるが……?」
二人の間に険悪(けんあく)な空気がただよい、はっしとにらみあった視線が、宙空(ちゅうくう)で見えない火花を散らした。
この最悪の取り合わせに、セイラは思わず頭を抱(かか)え込んだ。
次回へ続く・・・・・・ 第二十六話へ
