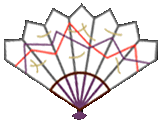第十話

――セイラが好き。セイラが好き。セイラが好き……。
走りながら、綺羅(きら)姫の鼓動はそう鳴っていた。
――どうしようもないくらい好き。どうしようもないくらい好き。どうしようもないくらい好き……。
いとしさが心の底からこみあげてきて、綺羅姫の目から、とめどなく涙があふれた。
その気持ちを、誰にも告げることはできなかった。親にも真尋(まひろ)にも、腹心の女房の桔梗(ききょう)にさえ、ましてや篁(たかむら)にも……。
そして誰よりもいちばん、セイラに知られてはならなかった。
もしセイラが綺羅姫の気持ちを知ったら、邸を出て行くと言いだすかもしれない。それだけは――
セイラが目の前から消えてしまうことだけは、どうしても耐えられなかった。
――セイラと結婚したい、なんて思ってたわけじゃないわ。側にいられるだけでよかったのよ。あの笑顔を見ていられるだけで……。
自分の気持ちを、目の前にいる相手に伝えられないことがどんなに苦しいことか、綺羅姫にはわかりすぎるほどわかっていた。
この切ない気持ちを、いつまで隠し続けていられるのかと思うと、あまり自信はなかった。
そのセイラに、とうとう自分の気持ちを知られてしまった――!
無意識のうちにセイラに触れていた自分を、綺羅姫は責める気になれなかった。
――だってしょうがないじゃない。あんな笑顔を見せられたら……。セイラが悪いのよ!みんなセイラのせいよ!セイラのバカ――!!
どこをどう走っているのかもわからなかった。
今はただ、このやり場のない想いをすべて吐きだしてしまいたかった。
息が切れ、頭の中が真っ白になるまでやみくもに走り続けて、ようやく足が止まった時は、綺羅姫は寺の裏側にあたる、鬱蒼(うっそう)とした林の中に迷いこんでいた。
あたりには人影もなく、昼だというのに、しげった葉かげにさえぎられた日の光は弱く、ひっそりと静まりかえっている。
いくら綺羅姫とはいえ、盗賊でも出そうなこんな気味の悪い場所を、一人でうろついたことなどあるはずもない。
急に恐ろしくなって、引き返そうかどうか迷っていると、はたして前方の樹の陰から、待ち伏せしていたように人相の悪い男が二人現れた。
「おい女!どこへいくつもりか知らないが、ここから先は通れないぜ」
「けっ、大事そうに花なんかかかえちゃってよ。兄貴、こりゃあ結構いいとこの娘だぜ。着てるもんも上等だ。こんな山の中をうろついてるから、てっきり里の娘かと思ったが……」
「ああ、オレたちにもようやくツキがまわってきたってことだ。貴族の娘なら、売りとばせば大した値になる」
とっさに、綺羅姫は今きた道を駆け戻ろうとした。
だが、気配に気づいた相方の若い男に、すばやくまわりこまれて逃げ道をふさがれてしまった。
綺羅姫はきっと男をにらみつけると、左手に花をかかえなおし、右手で懐剣を取りだした。
「あんたたちの言いなりになってるようなあたしじゃないわ!けがをするのはそっちよ!」
「ほう!気丈な女だな。この手の女は、なぶり甲斐があるってもんだぜ」
にやにやと薄笑いを浮かべながら、じりっじりっと男たちが前後からはさみ撃ちにしようとした時、聞きなれた声が、綺羅姫の耳に飛びこんできた。
「綺羅姫――!綺羅姫――!」
二人の男は、同時に声のしたほうを振り返った。
「セイラ!!あたしはここよ――!」
思わぬ邪魔者が入って気をとられている相方の男のすきをついて、するりと脇をすり抜けると、綺羅姫は死にもの狂いでその場を逃げだした。
綺羅姫の声にただならぬものを感じとったセイラは、文字通り飛ぶような速さで駆けてきた。
そこへ、笠をとばしながら、今にも転びそうな勢いで走ってきた綺羅姫を両手で抱き止めると、その後ろから追ってくる二人の男に気づいて、綺羅姫の無事を確かめた。
「大丈夫だったかい?」
「ええ、あたしは平気よ」
「そう。よかった!」
セイラは、ほーっと大きく肩で息をした。
「さあ、こんなところに長居は無用だ。はやく帰ろう」
二人のならず者のことなどまるで目にはいっていないかのように、綺羅姫をうながして、セイラは山道を戻りはじめた。
「えっ、ええ……」
綺羅姫は男たちのようすを気にして、ちらちらと後ろをのぞいた。
このままなにごともなく二人を帰してくれるとはとうてい思えなかった。
案の定、年かさの男が、癖のあるしわがれ声ですごみをきかせてきた。
「ちょっと待った!このままあっさりと帰すわけにはいかねえなあ。悪いが、その女はおいてってもらうぜ」
山道を戻りかけようとしていたセイラの足が、ピタリと止まった。
「聞いたかよ兄貴!やっぱりその女お姫さまだってよ。こりゃあ、なんとしても逃がす手はないぜ!」
「ああ。ついでに女みたいな顔をしたこの男もな。この手の美童好みの連中に売りつければ、女より高い金をはずむ好き者がいるからな。へっへっへ」
ゆっくりと、セイラが振り返った。
綺羅姫を後ろにかばいながら、口元に不敵な笑みを浮かべている。
「私を、どうするって?」
セイラの眼光が、矢のように二人を刺しつらぬいた。
その眼光に射すくめられて、一瞬、蛇ににらまれた蛙のように、男たちは動けなくなった。
「どうやら、脅す相手を間違えたようだね。私は今、無性に機嫌が悪いんだ。相手をしてやってもいいが、あばら骨の二、三本じゃすまないよ。手加減してやれる余裕はないからね。体中の骨をへし折られたくなかったら、このまま五体満足のうちに引きさがるがいい!」
「なっ、なんだとお!?おい、やさ男さんよ。細っこい体して、言いたいこと言ってくれるじゃねえか。こっちにはな、こういうものだってあるんだぜ!」
男は隠し持っていた短剣を、目の前に突き出した。
セイラは顔色も変えず、平然とそれをながめている。
「兄貴!こいつ、目の色が紫だぜっ!」
「ほーっ、毛色の変わったやさ男か。そう言えば、東の市に目のさめるような銀髪紫眼の美人が現れたって話を聞いたことがある。なるほど、見れば見るほどふるいつきたくなるようなべっぴんだ。ますます悪くねえ。おい!こいつぁ、女なんかよりずっと高く売れるぜ」
クッと、のどの奥でセイラが笑った。
もとより端整な顔立ちなだけに、相手をギッとにらみつけた顔には、ぞくぞくするような凄艶(せいえん)な美しさがあった。
「話のわからない連中だな。私は暴れたくてうずうずしてるんだ。だが、連れのいる前で血なまぐさい真似はしたくないと言っているのがわからないのか?綺羅姫に手出ししていなかったことを感謝するんだな。さもなければ、今頃はとっくにおまえたちの命はなかったところだ。こうして、私がおとなしくしているうちに、疾(と)く往(い)ね――!」
セイラの瞳が、一瞬にして深紅に燃えあがった。
その瞳の色に、二人は、この世ならぬものを見たようにゾーッと総毛だった。
圧倒的な恐怖がこみあげてきて、思わず後ずさろうとした時には、二人のならず者は、まるで目に見えない爆風かなにかを受けたように、猛烈な勢いで後ろにはじき飛ばされていた。
しばらくして叢(くさむら)から起きあがった二人は、お互いの顔を見やった。
自分たちの身になにが起こったのか、まるでわけがわからなかった。
とてつもない強い衝撃を受けたことは確かだったが、セイラは一歩も動いていなかったのだ。
「あ、兄貴、あいつは普通じゃねえ。バケモノだぜ!あいつの目が紅く光ったのを、おれぁ見たんだ!おれたちが吹っ飛ばされたんだって、よくわからねえが、なにか妖しげな術を使ったに違いねえ!」
「ああ。おまえの言うとおりだ。やばそうな奴にゃかかわらねえほうがいい。命あっての物種だ。おい、この場は逃げるぞ!」
そうと決まると、二人のならず者は先を争って山中に消えていった。
「もう大丈夫だよ、綺羅姫」
背中に張りついて狩衣を握りしめている綺羅姫を振り返ると、セイラはやさしく声をかけた。
「セイラ……」
綺羅姫の目から、じわーっと涙があふれ出した。
そこまでが、綺羅姫の限界だった。
緊張の糸が切れると、懐剣を投げ捨て、わあーっと声をあげてセイラの胸にしがみついた。
ぐったりとした水仙の花に、綺羅姫の大粒の涙が降りかかった。
「怖かったよぉー!セイラ、怖かったよぉー!」
「ごめん、綺羅姫。ごめん……」
セイラは綺羅姫の髪をなでながら、何度もそう繰り返した。
なにを謝るのか――
綺羅姫に怖い思いをさせてしまったことか、それとも、気持ちに応えられなかったことか?
おそらくはその両方だったのだろう。
しみいるようなその声を聞きながら、綺羅姫はいつまでも泣きじゃくっていた。
そのようすを、少し離れたところから見ている人影があった。
「うーむ。ますます気に入った!」
人影はひそかに感嘆の声をあげた。
「人のおよびもつかぬほど高々と宙を舞うかとおもえば、眼光一閃(いっせん)賊を退けるとは、わが天女殿はなかなかに楽しませてくれそうだ」
それは、セイラに小布(こぎれ)を渡してやった男だった。
さらに言えば、綺羅姫が『建――』と呼んだ男でもあった。
実際には、ならず者は爆風のようなものに弾き飛ばされてしまったのだが、遠目からではそこまでうかがい知ることは難しかっただろう。
が、たとえ間近で見ていたとしても、それを信じることができたかどうか。
セイラのすぐ後ろにいた綺羅姫でさえ、稀有(けう)な突風に見舞われたと思っているだけで、それがセイラから放たれたものであることに、まったく気づいていなかった。
「欲しい!あの天女を、ぜひとも私のそばに……」
うっとりとした目で熱っぽくそうつぶやくと、視線を泣きじゃくっている綺羅姫に移した。
「今は姫に預けておきますが、そういつまでもあなただけに一人占めはさせませんよ。天女は私がいただく。近いうちに、必ずね!」
謎めいた言葉を言い残して、男はしのびやかに遠ざかっていった。