<><> SUMIO'S HOME PAGE <><>
楽 書 帳 12
富士写ヶ岳に登る
(平成16年4月29日(緑の日)晴)

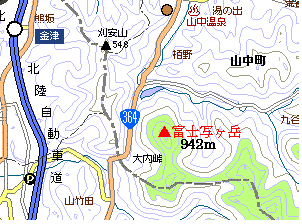 前日までの春の嵐のような空模様はどこかに飛んでしまい、素晴らしい天気となった1日、シャクナゲの群生で知られる北陸の富士写ヶ岳(942m)に行ってきた。北陸道、国道8号線とほぼ並行に走るR364の直ぐ脇、石川の名湯、山中温泉からも至近距離(右図)で比較的とっつき易い所にある。名前は山中町からの遠望が写真の通り富士山に似ていることから名付けられたのであろう、ホンシャクナゲの群落で知られている所らしい。
前日までの春の嵐のような空模様はどこかに飛んでしまい、素晴らしい天気となった1日、シャクナゲの群生で知られる北陸の富士写ヶ岳(942m)に行ってきた。北陸道、国道8号線とほぼ並行に走るR364の直ぐ脇、石川の名湯、山中温泉からも至近距離(右図)で比較的とっつき易い所にある。名前は山中町からの遠望が写真の通り富士山に似ていることから名付けられたのであろう、ホンシャクナゲの群落で知られている所らしい。ここを登ることになった理由は、例によって桂子の気まぐれである。山などによく行く行動派の俳優の某女が、花が多く登り易いいい山の一つであると、挙げていたのをたまたま週刊誌で読んだことによる。言い出したら実現するまで何時までも煩いので、早目に行くことにした。
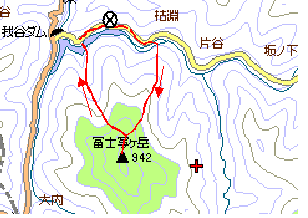 そして更に初めて聞いたこの山の名前ではあったが、金沢に育った自分達からすると、同県内でそれなりの土地感が全くないわけでもなかったこともある。
そして更に初めて聞いたこの山の名前ではあったが、金沢に育った自分達からすると、同県内でそれなりの土地感が全くないわけでもなかったこともある。登って見た結果は、某女の肩を持つわけではないが、成る程なかなか良い山だった。尾根道を登るのが多いこと、よくあるアップダウンを繰り返すコースではなく、殆ど登り一方で、辛いことは辛いが、小休を多くして呼吸を整えつついけば割合と楽に上がっていける。見晴しも良いが、直ぐ近くでいろいろな花が目を楽しませてくれる、などがその理由だ。快晴の天気も多いに味方をしてくれたが、そうでなくても、多分これらの好ましい感じは変わらないと思う。
朝8時過ぎに宿を出て登山口に向かった。登山ルートは3〜4通りあるようだが、はじめてのことでもあり最も一般的と思われる我谷ダムから入る予定にしていた。ダムの脇の道は、既に登山口に近いところから沢山の車で占領されていて、 結局半分以上も奥に入ったところでやっとスペースが見つかって駐車できた(拡大図×印)。偶々隣に同じように止めた夫婦連れが、準備を整えて奥の方向にむかって歩き出す様子なので、尋ねたところこの奥の枯淵から登り、我々が登ろうと考えていた道を下りてくるとのこと。簡単な説明を聞いて、相手の諒承もそこそこに即刻それに便乗させてもらうことにして、連れ立って出発した。この二人にはこの後も道中いろいろと話をしたり花の名前を教わったり、その上持参のよく冷えたトマトまで貰ったりしてしまった。非常に気さくな気の良い人達だった。



20分程歩くと案内板があり、工事中の九谷ダムを左手に見て山に入り、いよいよ登りが始った。南面のかなり急な斜面を斜めにジグザグ状に上がっていく。いきなりの急登だけに息が直ぐ上がる感じで、桂子も勿論もう顔を赤くしている。
ここまでで感じたのだが緑が実に綺麗ということだ。萌黄の新緑と針葉樹の濃い緑が重なったり、交じり合ったりで何とも云えない清々しい美しさで見飽きる事がなかった。先の二人連れには、お構いなくお先にどうぞと声を掛けてあったのだが、それでも初めのうちはところどころで待っていてくれて、これは春竜胆、一輪草、延齢草(写真上左から)等と咲いているところを教えてくれ、説明を加えるという親切さだった。しかし次第次第に間が空いていき、その内見えなくなってしまった。
相当年数の経った檜のよく手入れされた林が続いた後、こんどは沢伝いの道に変ってきた。といっても石や岩のそれではなくて歩き易い落ち葉の積もった小道である。前日までかなりの雨だったせいもあり、足許はよくない。もともと沢の横だから湿っているのだろう、三つ葉やシダ類など湿地特有の小さな草が沢山生えていた。

しばらくすると前方が明るくなって今度は尾根道になった。それと同時にそこかしこに待望のシャクナゲが目につきだした。しかし新葉は出ているものの肝心の花がいっこうにない。結局分かったのだが、今年は裏年というのか山全体にシャクナゲの花はさっぱりと言うことだった。凄かった去年に較べ、ほんの申し訳程度にパラパラ咲いているだけで、群生して花一杯とはお世辞にも云えい状況だった。他の色の濃い三つ葉つつじがかなりあったり、辛夷によく似た純白のたむしば(田虫葉)が残っていてそのほうが綺麗だった。

いささか落胆しつつ尾根をいくこと約1時間、かなり厳しい坂が続くが、まだ色つきも浅い、まだらな新葉の間から絶えず周囲の見晴しがきくので、気持よく、快適なトレッキングを楽しめた。特に登り始めて2時間位で来たところで、周りを270度くらい、展望が出来るところがあり素晴らしかった。遠方一番奥に依然として真っ白な白山、隣に別山、手前に僅かに雪をかぶった大日岳、その他の名前は分からないが、大小の山が二重三重に見えた。また手前の真下を見れば車を止めてあるダムと建設中の新らしいダムが見下ろせた。まことに見事な景観だった。
 この後も眺望がここよりよいところには出くわさなかった。
この後も眺望がここよりよいところには出くわさなかった。登り始めて2時間45分でやっと前山にたどり付いた。頂上から僅かに下ったところで、小ピークを形作っている。休憩しやすい広場状になっていて、眺めも割合利く。来る途中すれ違った人に、頂上は先客で一杯ですよと聞いていたので、早速そこにシートを広げ、昼食にすることにした。周りでは20〜25人が既に陣取って夫々休んでいた。朝方一緒だった夫婦連れも矢張りそこで昼食にしているのが見えた。この人達とは、また後からお互い写真を撮り合ったりしたが、ご主人だけが先に上がってこられたので、奥さんは途中でリタイヤされたのかと思いました、と云われ桂子は少々不満げの様子だった。

かれこれ1時間の休憩の後12時45分に頂上仁向う。4〜5分緩い坂を登ると頂上に出た。先ほどの前山と同じように広場になっていて、中央に頂上を示す三角点の標識と誰かが作った看板状の名板が立てられてあった。眺望は周囲に潅木が茂っている為、それほどはないものの、先程の白山などははっきりと望めた。それより驚かされたのは、先に上った面々がグループごとにシートを広げ、宴会のような昼食を取っている風景だった。コッフェルを真中にして缶ビール片手にワイワイガヤガヤとそのへんの居酒屋のような感じである。あまりいい気はせず、早々にそこを離れ、下山することにした。

来た道を少し戻ると我谷コースへの分岐がある。そこを通過したのは丁度13時だった。それからは急な下りが多く、ロープが張ってあるところがいくつもあった。ただその一方で午前の登りとは違って、一転して全く平らな道を行く場面も結構あった。そう言えば朝の登りはまったく登りだけで下る場面は全然なかった。だから大変ではあるものの、登った分は それだけ高度を稼ぐので、効率的である。急坂が多い割には疲れを覚えなかったのはその所為だろう。
途中ブナの林が結構あった。直経が30センチはあると思われるブナが瑞々しい新葉をつけて林立しているのは壮観であった。ここ白山山系はこのようなブナが多いのが特徴で、根に多量の水分を蓄え、チトンフッドを多く出すため安らぎの効果が大きいとも云われている由。ロープの助けで滑るのを防ぎながら下るところを何ヶ所か通り過ぎ
 どうやら二人とも、無事に麓の登山口まで下りきることが出来た。15時10分にダムを横切る赤い吊り橋を渡り、それから15分程歩いて、朝出発したところに目出度く辿り着けた次第。
どうやら二人とも、無事に麓の登山口まで下りきることが出来た。15時10分にダムを横切る赤い吊り橋を渡り、それから15分程歩いて、朝出発したところに目出度く辿り着けた次第。標高942mというと六甲山と殆ど同じで、登る前は内心かなり心配していたのだが、桂子もどうやらついてこれたので、芯からよかったと思った。しかし、感想を問うと ここは今日だけでいいかな、とぽつり呟くようにいったところを見ると、滑らないように相当苦戦したと感じている様子だった。
朝方偶然出会った人について行き、予定のルートを変えて歩いたが、振り返ってみるとこの逆の登り方でも悪くないと思った。いづれのルートを登りにしても、急な所が多いのは同じだが、後半の方がやや足場が緩く、降りるのに苦労した。登りのほうが未だ幾分ましかという感じだった。歩き出しの標高は約150mと資料にあったが、アップダウンもある芦屋川からの六甲山の方が矢張り少し厳しいのかもしれない。この後、戻る途中にあった健康村ゆーゆー館という公営の風呂で汗を流し、さっぱりしてから宝塚への帰途についた。

