
二人のウイリス先生
『思うこと 第224話』で、松村先生から送られてきたA4版5枚のコピーのお話をした。
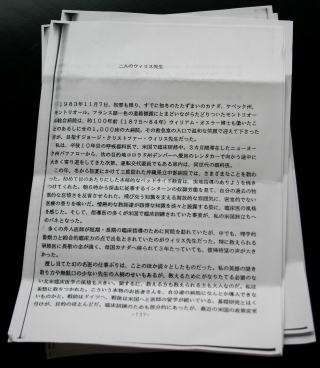
これは、先生が、約20年ほど前に、G.C. Willis先生招聘の感動の物語を綴られ、かつそれをウイリアム・ウイリス先生と結びつけて『二人のウイリス先生』のタイトルで書かれたエッセイである。先生は、二人のウイリス先生から、歴史は人が作るものであることを学ばれたと言う。確かに、そうだと思う。私は、松村理司先生という快男児もまた歴史を変えつつあると思う。すごいことだと思う。 先生から、その全文掲載のお許しがいただけたので以下に紹介する。
『二人のウイリス先生』 松村理司著 醫亊新報ジュニア版 1987年 第267号掲載
1983年11月7日、初雪も降り、すでに初冬のたたずまいのカナダ、ケベック州、モントリオール。 フランス語一色の道路標識にとまどいながらたどりついたモントリオール総合病院は、約100年前(1875〜84年)ウイリアム・オスラー博士も働いたことのあるしにせの1,000床の大病院。 その救急室の入り口で温和な笑顔で迎えてくださった方が、目指すジョージ・クリストファー・ウイリス先生だった。
私は、卒後10年目の呼吸器科医で、米国で臨床研修中。3ヶ月間滞在したニューヨーク州バファローから、次の目的地コロラド州デンバーへ愛用のレンタカーで向かう途中に大きく寄り道をしてきた次第。運転交代要員でもある家内は、同世代の眼科医。
この年、冬から初夏にかけて三度訪れた沖縄県立中部病院では、さまざまなことを教わった。初めて目のあたりにした本格的なベッドサイド教育は、実地指導のありようを焼きつけてくれた。朝6時から採血に従事するインターンの奴隷労働を見て、自分の過去の牧歌的な怠惰を反省させられた。飛び交う知識を支える開放的な雰囲気に、密室的でない医療の香りを嗅いだ。そして、指導医の多くが米国で臨床訓練されていた事実が、私の米国旅立ちへのバネとなった。多くの外人医師が同院を訪れていたが、中でも、理学的診察力と総合的臨床力の点で出色とされていたのがウイリス先生だった。特に教えられる研修医に畏敬の念が強く、母国カナダへ帰られて3年たっていても、復帰待望の声が大きかった。
捜し当てた幻の名医の仕事ぶりは、ことのほか淡々としたものだった。私の英語の聞き取り力や無駄口の少ない先生の人柄のせいもあるが、教えるためにがなりたてる必要のない北米臨床医学の風格も大きい。要するに教えるほうも教えられるほうも大人なのだ。私は妄想にとりつかれた。こういう本物のお医者さんを、自分達の病院になんとか導入できないものかと。戦前はドイツへ、戦後は米国へと医師の留学が続いている。基礎研究とはく付けが、目的のほとんどだ。臨床訓練のためも部分的にあったが、最近の米国の政策変更によりほぼ不可能となった。欧米人医師のごく短期間の輸入は、わが国の経済力のおかげでますます盛んになってきたが、講演に始終しすぎるため、臨床的諸問題のほりさげには至らない。不幸なことに、招かれる人々のほとんどが、わが国の医療の実態に知識も関心も持ち合わせていない。
ウイリス先生は、違う。上海で生まれ育った彼は、母国カナダのマギル大学医学部を選び、卒後初期研修を母国と英国で受けられたが、その後多くの年間をアジアで過ごされている。シンガポール3年、ボルネオのジャングル8年、沖縄5年、医師として、宣教師として、臨床の現場を熟知し、それと切り離せない文化も体得されている。
救急内科集中治療室の長として多忙な日常の休憩時、遠慮がちにふと漏らされた言葉を私は聞き漏らさなかった。「60歳の今でも、アジアで幾らかの影響を与えたい情熱はもちあわせています。」 「沖縄中部病院は、すでにトップクラスの病院ですから、先生の存在も相対的に低下せざるを得ません。その点、私共の病院こそ先生の影響力を十二分に発揮できると思われます。小さいですが、発展途上であり、専門家や年長者の嫌がらせもないからです。・・・・」と、すかさず私。
1986年1月6日、大阪国際空港。私は家内とともに、香港経由の先生夫妻を迎えた。4日間のモントリオール訪問後2年2ヶ月たって、ついに夢が実現した。この間にも先生は、エチオピアのアジス・アベバ大学で1年間内科指導をされていた。
200床あまりの地方自治体病院なのに成功した首尾は、当院長瀬戸山元一氏の魔法の手腕にある。ウイルス先生の知己でおられる日野原重明先生の適切な助言も、奏功した。私達も勉強して備えた。医学英語の発音の矯正やテープを用いた英語会話の練習は、稚気と滑稽さに彩られた。沖縄時代の作品『 Bedside Diagnosis in Internal Medicine 』の輪読は早朝から行ったが、歯ごたえがありすぎた。だが、みんな楽しかった。
「エチオピアにCTはないが、脾臓破裂はある。ボルネオに放射性同位元素はなかったが、甲状腺疾患はあった。・・・・私達が超音波を使っても誤診した膵臓破裂を、問診だけで言い当てた時に・・・・。正確な病歴獲得が、全ての基本となる。徹底した理学所見の把握が続く。ついで、病棟の片隅で簡便な検査を緊急に行い、迅速な診断を心がける。画像診断の洪水は、ずっと後方に控えさせる。
「地球上の他のすべての地域では、こんな場合に第三世代の抗生物質は使わない。ペニシリンがベストだ。効果が同じなら、安いほうがいい。日本が金持ちになったのも、最近ではないか。こんな無原則なぜいたくが、いつまで続くだろうか。」 先生は文字通り地球規模での医療費節減派といえる。
「私の先生の中には、部長や管理職としての仕事がいそがしすぎて、臨床的に自滅し果てた先生も多い。60歳を過ぎて、食道の前に気管があるのかその逆なのかさえわからなくなった教授もいる。そういう彼らも不思議と患者には受けがいいし、効率のよい教育について声高に、しかも上手に講演できることは皮肉なことだ。だが、幸いなことに、臨床現場で感心するのは、出来の悪いインターンに限られている。」 個々の症例を具体的に、水準高く見抜く臨床力がなくては、まともな医者とはいえないとする先生の日頃の信念と節制は、強烈だ。
--------------------------------------------------------------
手元に、ヒュー・コータッツイ氏著、中須賀哲朗氏訳の『ある英人医師の幕末維新』がある。戊辰の戦いで外科医として縦横無尽に活躍した英人ウイリアム・ウイリスが、東大医学部の前身(1869年)や鹿児島大学医学部の前身(1869〜77年)で、地道に患者を治療し、医学教育の確立や公衆衛生の普及に尽くした様が詳しい。外科、内科、耳鼻科、眼科、歯科等の講義だけでなく、ベッドサイドでの指導を重んじる英国式教育が採用されたと伝えられる。鹿児島時代に全国から集まった学生は500人を超える。その時代の弟子の一人高木兼寛は、実地臨床の育成の志が強く、5年に及ぶ英国留学から帰国後、1881年に東京慈恵医科大学の前身を創立した。
それ以前の外人医学教師には、シーボルトやポンペがあげられる。長崎でのポンペと松本良順を筆頭とする弟子達の交流は、1857年より5年間に及ぶが、司馬遼太郎氏の『胡蝶の夢』に楽しい。
ウイリアム・ウイリスもポンペも、異国での医学教育に賭ける情熱はすざまじく、その内容も多岐にわたっている。日本到着字ウイリス25歳、ポンペ28歳という若さや本国での医学教育の程度を考えると、驚異ですらある。
--------------------------------------------------------------
身分制度の廃止から120年、国民皆保険の施行から26年たち、わが国の医学、医療も飛躍的に発展した。基礎研究ではノーベル賞級の業績が散見されるし、画像診断機は眩しい輝きで迫ってくる。そして、暖かさの追求だけが残された課題とされる。
はたして足りないのはそれだけか、と私は不満である。臨床現場でのよき教師の伝統も欠けてはいないだろうか。立派な研究者ではあっても、優れた臨床家や良き教師とはいえない医師が多すぎないだろうか。少なくとも私の経験では、そう断言できる。私達の大先輩の中には、次のような光景を懐かしむ人達がいる。高度な検査がまだなかった時代には、医局講座制の頂点に君臨した彼らの恩師の一部は、患者心理を見抜いた上で、問診や理学的診察に深く根差した破格の臨床力を披露してくれたものだと。しかし、今の私達には夢か幻としか思えない。重々しすぎる教授改心も含めて、地位の低いものが高いものに対して質問を遠慮するといったいたわりと臆病ささえ、よくみかけられるありさまだからだ。明治期輸入したドイツ医学の日本式変容も、大きく影響しているようだ。ともかく、講義偏重で、偉ぶる学者の伝統が強すぎるのは、実りが少ないし、国際的にも滑稽だ。
こういう事情だから、わが国の臨床医学がアジアの横綱格かどうかも疑わしい。世界中で引っ張りだこのトヨタやニッサン、ソニーやニコンと異なり、わが国の医療が国際競争力を問われたことはない。市場開放とも無縁だ。しかし、今後は海外医療援助の分野で、その底力が問われるものと予想される。その際、私達の威容の本態が、経済繁栄下での最大限の自由裁量権=検査漬けにすぎないと化けの皮がはがれてはしゃくだ。
臨床現場における私達のささやかな試みは、始まったばかりである。地方都市の小さな病院なので、限界も多い。専門的掘り下げも不十分だし、興味ある症例にも事欠く。だが、ありふれた病気への暴露は、昼夜を問わず豊富だ。問診と理学的診察と簡便な検査を重視し、迅速な診断と治療の開始を心がける。若い医師たちは、肉体の酷使を要求され、ひとを配慮することを習慣づけさせられる。入・退院や検査の適応を厳しく吟味し、医療の費用や効率に対する感覚を身につけさせる。蚊をやっつけるのに大砲、像を打つのに吹き矢といったアンバランスを除き、我流に流れない医療を目指す。時には治療しない勇気もいることをわかりあう。これらはいずれもベッドサイドで執拗に点検、確認するので、主治医の思いつきの乱発や臭いものにフタの風潮は許されない。ガラス張りのチーム医療の下では、知識・技術だけでなくベッドサイドマナーの多くも、世代間の伝達事項となりうる。ハイカラにいえば、 Community Hospital General Internal Medicine となる。ちなみに、知識の情報源は原則として英語とし、教科書は少なく、雑誌を多くする。
教えられる対象者は、同世代のわが国の平均的青年よりも若干知能指数が高く、かといって医療者として必要な感性や思いやりに欠けるわけでない若年医師である。抜群の頭脳や超人的な優しさは、ないものねだりになる。毎年8,000人以上もの医学生が医者の卵になる。そのもともとの資質が開花してゆける環境の整備こそ重要だ。かっての秀才がまともな臨床家にすら成長できない現状の医学教育は、貧しすぎる。
主砲ウイリス先生との英語のやり取りは、適度に緊張した雰囲気を醸し出す。もとより教師は教育が仕事だから、必要以上に気むずかしい顔にはならない。小さな声でわざとむずかしそうに教えるのは、教師失格であるのも前提だ。彼と患者との日本語での語らい円滑さを増してきたのも、ほほえましい。すっかり舞鶴っ子の先生との最近の黙約が、ぼけてしまわれるまでこの地定住なのは、私達の望外の喜びだ。かってポンペやウイリアム・ウイリスの下で、精魂こめて学習に励んだ歴史上の大先輩の心意気が想像され、人知れぬ興奮を覚えることがある。日本のあちこちで、医学と医療にまつわる良き子弟の関係がもっともっと活発になり、さざなみのように広がってゆくべき時期に思えてならない。
