
“私の心臓が凍てつく感動”の文との出会い
私のこれまでの人生において、本やエッセイなどで個人の生き様を読んで、あるいは直接話を聴いて感動したことは多いが、“心臓が凍てつくような感動”を覚えたことはこれまでに一度しかなかった。それは、山村雄一先生が癌で亡くなられる直前に話された“遺言的な”お話を聴いた時のことであった(2006年4月6日記の思うこと『第83話』)。
 この度、私の人生で2回目となる“心臓が凍てつくような感動”を覚えた文に出会った。 著者の坂田隆造教授(左写真)と、この文の載っていた
Cardiovascular Med-Surg 誌の出版元のメディカルレビュー社とから私のHPへの掲載許可をいただけたので、ここにその全文を紹介する。ちなみに、坂田教授は2000年一月に彗星のように我が鹿児島大学医学部に教授として来られ、鹿児島大学に新風を吹き込み、またたくの間に全国に冠たる心臓外科教室を作り上げた方である。今回のことの発端は一昨日(3月7日)夜、鹿児島大学医学部教授会の私への送別会の席で、2人ともかなりの酒量の中での懇談から生まれた。私は、先生が幕末の志士、南 八郎の辞世の歌について語られた話に“普通に”感動し、そのことを伝えたのであった。実はかなり酔っていたのであまり詳しいことは憶えていないが『国の大事を余所にみる馬鹿』の言葉だけは記憶に残っていた。何故、南 八郎の話になったのかも思いだせない。というより、殆どあの時の会話は忘れてしまっていたのであったが、今朝、坂田教授が私の部屋に薄い別冊を持ってこられ、『これに、あの時の話も載ってますので、暇な時にでも読んでください』とのこと。私は、立ったまま即座に読み始め、一気に読み、そして、“心臓が凍てつくような感動”を覚えて、立ちすくんだのであった。しばらくして、落ち着いたところで、この文は私だけが感動するだけではもったいなさ過ぎる、私のHPで広く紹介させてもらおう、と思ったのであった。坂田先生のところに行き、そのことをお願いしたところ、承諾をいただき、出版社からの承諾まで先生がとってくださった。
この度、私の人生で2回目となる“心臓が凍てつくような感動”を覚えた文に出会った。 著者の坂田隆造教授(左写真)と、この文の載っていた
Cardiovascular Med-Surg 誌の出版元のメディカルレビュー社とから私のHPへの掲載許可をいただけたので、ここにその全文を紹介する。ちなみに、坂田教授は2000年一月に彗星のように我が鹿児島大学医学部に教授として来られ、鹿児島大学に新風を吹き込み、またたくの間に全国に冠たる心臓外科教室を作り上げた方である。今回のことの発端は一昨日(3月7日)夜、鹿児島大学医学部教授会の私への送別会の席で、2人ともかなりの酒量の中での懇談から生まれた。私は、先生が幕末の志士、南 八郎の辞世の歌について語られた話に“普通に”感動し、そのことを伝えたのであった。実はかなり酔っていたのであまり詳しいことは憶えていないが『国の大事を余所にみる馬鹿』の言葉だけは記憶に残っていた。何故、南 八郎の話になったのかも思いだせない。というより、殆どあの時の会話は忘れてしまっていたのであったが、今朝、坂田教授が私の部屋に薄い別冊を持ってこられ、『これに、あの時の話も載ってますので、暇な時にでも読んでください』とのこと。私は、立ったまま即座に読み始め、一気に読み、そして、“心臓が凍てつくような感動”を覚えて、立ちすくんだのであった。しばらくして、落ち着いたところで、この文は私だけが感動するだけではもったいなさ過ぎる、私のHPで広く紹介させてもらおう、と思ったのであった。坂田先生のところに行き、そのことをお願いしたところ、承諾をいただき、出版社からの承諾まで先生がとってくださった。前置きはここまでにして、あとは、その、文の1ページ目の写真に引き続き刷り上り3ページの文の全文を以下に記す。出版元はメディカルトリビューン社で、掲載ページは Cardiovascular Med-Surg Vol.8 No.3 76(292) 2006.8 である。
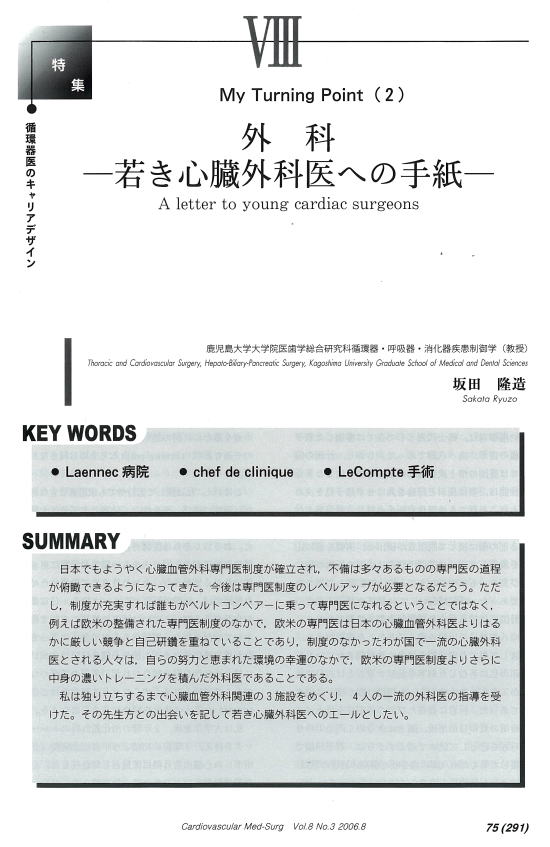
若き心臓外科医への手紙
私の田舎は兵庫県・但馬生野の近くで、そこに南八郎神社がある。神社と言っても小さな祠があるだけで普段は誰も住んでいない。村はずれの草深い山裾を切り削ぐように高さ5〜6mほどの石垣が連なり、その上の広場に祠はひっそりとあった。石垣を背もたれにするかのようにこれまた高さ6〜7m程の巨岩が一つ横たわり、巨岩の上はひと数人が立てるほどの広さがあった。楠に天空を遮られたそこは、眼下はるかに円山川のせせらぎを見下ろし、夏の日の午後を蝉の声のシャワーを浴びながら為す術もなく過ごすのに最適の隠れ場であった。
1863年、幕末の勤皇家、平野国臣が公卿の沢宣嘉を総師とし但馬の郷士や豪農と共に、倒幕の武装蜂起を企てた。大和の天誅組に呼応した倒幕運動で農兵二千とともに生野代官所を占拠した、世に謂う「生野の変」である。蜂起軍の軍事的指導者は、郷士代表として企てに参加した若干18歳の青年、南八郎であった。しかし、計画の段階では憂国の情と武装蜂起の意義を熱く論じた多くの仲間は、事に及んで行動を共にせず様子見を決め込んだ。それでも生野代官所を占拠し、意気盛んな蜂起軍であったが、大阪より幕軍が大挙押し寄せるとの報に接して脱落者が続出し、劣勢を背に山中を潰走した南八郎以下数名は山裾の巨岩の陰に忍び到り、もはやこれまでと岩上で切腹して果てたのであった。武装蜂起はここに鎮圧され、主謀者の平野国臣は捕らえられ翌年京都で処刑された。
南八郎神社の巨岩の傍らに苔むした石柱があり、切腹して果てた南八郎の辞世の歌が刻まれていた。少年の私に苔むした刻字を読解することは容易ではなかったが、教えてもらった辞世の歌が確かに刻まれてあった。巨岩に登る度にこの石柱を見上げ、蝉時雨の夏の日の午後、陽光にきらめく円山川のせせらぎを茫として眺めて過ごすうちに、若干18歳で割腹して果てた南八郎の血を吐く裂帛の辞世は石柱よりもなお深く私の心に刻まれたようであった。
―議論より実を行え田舎武士、国の大事を余所にみる馬鹿。―
私は大学卒業直前に心臓外科の道に進むことを決断した。理由の一つは一人前になるのに時間がかかるということであった。一人前になるのに時間がかかるということは、さし当たって当分の間目標があるということであり、目標がある限り、閑居して不善を為すことはあるまいと考えたからである。第二に、しかし一人前になれば自らの手術によって人は劇的に病を克服できるからである。この行為は少なくとも善く生きるということに反することではあるまい。以来、私は手術ができる一人前の心臓外科医になることを唯一の目標に生きてきた。この目標以外のことはどうでもよい小事であった。この道を進むのに何の迷いも疑念もなく、それは無碍の一道であり、turning point なるものは何もなかった。
とは言え、私は決して苦行僧でも求道者でもなかった。適度に遊び酒を飲み、仕事の大部分は大抵楽しく、時々辛い日々があった平凡な日常であった。恐らくそれは、医師として人間として非常に優れた指導者や、同じ志しを持つ陽気な仲間に恵まれていたからであろう。とりわけ直接御指導いただいた恩師には、心臓外科医の在るべき姿を、日常業務の会話や後ろ姿、あるいは酒席の雑談の中で指し示していただいた。恩師達との出会いによって私が思い描いている一人前の心臓外科医の姿が如何に甘かったかを思い知らされた。多くの恩師の中でここでは取りあえずフランス留学中に御指導いただいた二人の先生を紹介することにしよう。
私は大学卒業後、2年間の消化器外科のトレーニングを終え、3年目の初頭より小倉記念病院(北九州市)の心臓血管外科に医員として赴任した。心臓血管外科の医師として第一歩を踏み出したわけである。病院の中では、この時から私は既に心臓外科医であり、患者・家族も心臓外科医の私に接した。ある科に身を置くとその時から何々科医となってしまう状況は今もさして変わっていない。日本に心臓に触れたこともない心臓外科医が多く存在する所以である。私はこのような日本の状況の中で、何の疑いもなく自己意識を形成し、32歳の時にフランスへ行った。マルセイユで指導を受けたのはJ.P.Bex先生であるが、パリのLaennec 病院でchef de cliniqueを務めた後にマルセイユの病院の心臓外科部長として赴任していた人物であった。親しくなってからのある酒席で将来の夢はと聞かれて、心臓外科医と自覚している私は手術のできる心臓外科医になることが夢でそれ以外にない、と答えた。Bex先生は初めキョトンとして意味を解さず、何度か質問を重ねた。それは日本の心臓外科医がどのようなトレーニングを経て誕生するのかについての質問であり、この間の質疑応答の末に、私にもようやく彼がなぜ私の質問を理解できなかったかを理解した。簡潔にいえば、フランスと日本のトレーニングシステムの差、あるいは有無の差であり、日本では心臓外科に属した時から全員が心臓外科医であるのに対して、フランスでは最低8年のトレーニングを経て、その中から手術ができる者だけが心臓外科医となるのである。Bex先生はようやく彼我の違いを理解して大きく頷き、しかし、と言葉を続けた。「Ryuzo、本来心臓の手術ができる外科医を心臓外科医というんだよ。だから心臓外科医はだれもが手術ができるのだ。一流の心臓外科医と言われるにはその上に、この分野なら或いはこの手術ならお前だ、と言われるものを築かなければならない。You have to show your flag!」
即ち私はこの時点で未だ心臓外科医でなかったのである。心臓外科医を目指してのトレーニング中の何者かであったのである。まず私は心臓外科医になるべく、努力をしなければならない。心臓外科医になることは手術ができるということと同義なのである。手術のできる医者になるのが私の当初の目標であったが、しかしそれは当たり前のことなのであった。当たり前のことを人生の目標とする訳にはいくまい。私は自分の不明と狭量を恥じた。
次いで私はパリに移り、Y. LeCompte先生に御指導いただいた。大血管転位症に対するLeCompte手術の考案者である。彼はデカルト的明晰の人であった。彼の風貌と言動に胡敬臭い肥満と装飾はなかった。心身共にあいまいな無駄を削ぎ落とした様であった。そうして彼は世俗の些事で他人と争うことを嫌って身を引くような人物あった。ご婦人を愛し、子供達に優しかった。
LeCompte先生は私に、LeCompte手術の100余例を論文に書くように薦められた。しかも筆頭者として纏めるようにとのことであった。私は驚いた。LeCompte手術の第1・2報のあとの、最初の原著論文となるはずで、いわば彼のライフワークであった。それを日本から来た心臓外科医前の私に自分の名で論文発表をしろと言うのである。彼は極くさりげなく言い渡し、にっこり笑って肩をたたいて「さあ、日本に帰る前に仕上げよう」と付け加えたのみであった。私は100余例のカルテを文字通り解読すべく、辞書を片手に、手術の暇を見つけてはLaennec病院の地下のカルテ室に籠もった。当時のカルテはまだ手書きの書類や所見書が多く、それらが各種検査データとごっちゃにとじられてあり、論文の為に必要かどうかを選別するのにすべてのページを読解しなければならなかった。最初は日曜日の終日かけてやっと一冊といった難事業であった。しかしこのおかげで、始めて5〜6冊目のカルテの中に、LeCompte先生が患児を紹介してくれた小児科医に当てた返書を見つけた。乱筆の返書を辞書を引き引き読み進めるうちに私は背筋が寒くなるような戦慄を覚えた。それは手術後に亡くなった患児に関する返書で、その中で彼はまず結果について詫び、手術時の所見、施行手術、経過、そして剖検による検証を詳述した後で、今回の結果は自分の手技の未熟さによるものであり、手術法そのものに問題があるとは考えられない、と結論づけていた。そして最後に、一際大きな力強い筆致で、「とにかく今は続けることが必要だ」―Il fault continuer―と記して筆を置いていた。
このLeCompte手術を始める前、彼は小児病院の病理室に保管してある大血管転位症の剖検心をいくつも検証し、この手術が可能かどうかをとことん試みている。その結果を踏まえての臨床導入であり、最初の数例は目論み通りの素晴らしい結果であった。それにしても、自ら考案した術式で患児一人が死亡したのである。それでもなお、自らの方法に問題はないと確信し、今は続けねばならぬと記した修羅の心像風景に私は立ちすくんだ。このまま心臓外科医の道を進むべきか否か、進むとしたらよほど腹をくくらねばならぬ、途中で投げ出す訳にはいかぬ、私はこの厳しさに耐えられるのか・・・。
心臓外科医としての来し方を振り返り、私は自身の旗をうち立てられたとは思わない。しかしそれは私の能力がなかったからであり、努力が足りなかったからだとは思わない。そうして一例一例を大切に兎にも角にも続けてくることができた。途中何度か、手術がうまくいかなかった後に悩んでやめたくなったり、仕事の重圧が続き逃げ出したくなった時もあったが、その都度LeCompte先生の事を思い出し、落ち込む心を自ら励まし「とにかく今は続けよう」と声に出して呟いた。
心臓外科は経験の学習効果が顕著な分野である。今まで約5,000例の開心術を執刀してきたが、振り返れば今もう一度手術をさせてもらえれば助けられると思う命は多い。だからこそ、心臓外科を選ぶに臨んでは腹をくくらねばならない。尊い命を預かり、その診療行為の積み重ねが能力の向上に必須であるなら、苦しい思いも苦い経験も全て我が身に引き受けてなおかつ失われた命の冥福を祈りつつ、歩み続けねばならない。弔鐘は故人に対してのみならず我が身を戒めるためにも打ち鳴らしつづけねばならない。我々は続けなければならないのである。
私の手紙が若き心臓外科医のキャリアデザインにどのように役立つのか甚だ心もとない。履歴書を賑々しく装飾するためには恐らく何の足しにもならないだろう。しかし、報奨の数と量を計算するより前に、我々にはなすべき事がある。なすべき事を成就するには乗り越えなければならない障碍がある。そして障碍を乗り越えられるか否かは、能力の多寡よりも続ける努力の有無にかかっているのである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上である。
私が“心臓が凍てつくような感動”を覚えた理由がお解かりいただけたことと思う。
この理由とも関連することであるが、この文を読んだ後の坂田先生との一連の会話の中で先生が言われた言葉、『私は、この文は、遺言のつもりで書きました。これまでこんな文書いたことなかったし、これから先も書かないと思います。一度だけ書き残しておこうと思って書いたものです。』を聞いて、私はやっぱりそうだったのか!と思った。山村雄一先生のお話(2006年4月6日記の思うこと『第83話』)を聴いた時にも、何かを若者に伝えようという“遺言的”気迫を感じたし、今回の坂田先生の文にも、まさにその“遺言的”気迫を感じ、感動したのであった。 私がこれほどまでに感動したことは、私も若者の心と感性をまだ保っているということでもあろうか。
