1
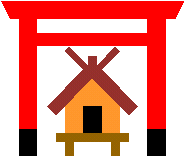 七福神とは
七福神とは |
七福神は、一般には恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、布袋尊、寿老人、福禄寿の七神をいい、室町時代に民間信仰として始まったと伝えられている。
|
|
|
|
2
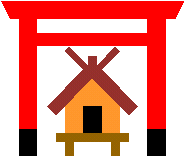 恵比寿
恵比寿 |
【商売繁盛、除災招福の神】
伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命の第三子蛭子尊(ひるこのみこと)と言われるが、大陸から来た異邦人とする説もある。本来、豊漁の神であったが、後に商業の神としても信仰を集めるようになった。
|
|
|
|
3
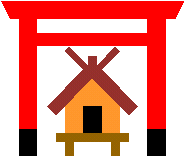 大黒天
大黒天 |
【五穀豊穣、子孫愛育の神】
インドの戦闘神シヴァの化身と言われる。中国を経て日本に伝来した後、大国主命(おおくにのぬしのみこと)と習合し、大地を掌握する農業の神として民間信仰の対象とされた。福徳開運、財産授与のご利益もあり、七福神の中では恵比寿と並びなじみ深い。
|
|
|
|
4
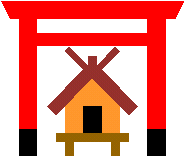 毘沙門天
毘沙門天 |
【開運厄除、大願成就の神】
帝釈天の四天王の一仏で、別名多聞天というインドの神様。北方世界の守護に当たり、邪鬼(気)をも払う盛んな威勢により疾病・災難を除き、富貴を授け、大願成就を果たすとして信仰される。美と福徳の神、吉祥天を妃に持つことから、福をもたらすともされる。
|
|
|
|
5
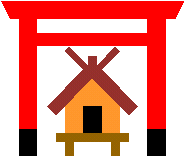 弁財天
弁財天 |
【恋愛成就、学問成就】
七福神中唯一の女神弁財天は、元はインドの水神で、後に学問・芸術の守護神となった。この由来ゆえに、水辺に多く祀られている。日本へ伝来後、当初は弁才天と称せられていたが、後世に吉祥天と混同し、福徳・財宝賦与の神として弁財天と呼ばれるようになった。
|
|
|
|
6
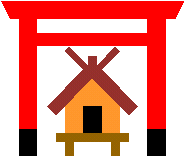 布袋尊
布袋尊 |
【夫婦円満、財宝賦与】
中国、後梁の時代の禅僧で、七福神の中では唯一実在の人物。常に笑みを浮かべ、人を見れば物を乞う、浮浪者風の人物であったらしい。袋の中の財宝で貧者救済を行うとともに、福々しい容姿・容貌から福徳円満の神として信仰が厚い。
|
|
|
|
7
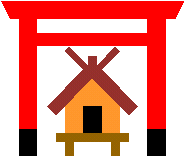 寿老人
寿老人 |
【長寿延命、富貴招福】
中国時代の仙人である寿星の化身とされるが、福禄寿と同じ南極星の化身と言われる。玄鹿を引き連れ、桃を手に持つことから長寿の象徴とされる。長頭、白髭、巻物を括ったあかざの杖等、福禄寿と混同しやすい。七福神では、吉祥天と入れ替える場合がある。
|
|
|
|
8
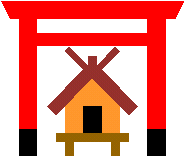 福禄寿
福禄寿 |
【招徳人望、俸禄増加】
福禄寿の名前の由来は、福(幸福)、禄(俸禄)、寿(長寿)であり、この三徳を授けるものとされる。中国北栄時代の道教の長寿神とも、南極星の化身とも言われる。白鶴従え、団扇を持つことがある。同じ南極星の化身とされる、寿老人と異名同神との説もある。
|
|
|
|

![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。