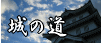 |
| トップ>メニュー>関東地方>小山御殿 |
| おやまごでん |
| 小山御殿 |
| 別称: |
| 所在地:栃木県小山市中央町1丁目 |
 |
| 形状 |
ー |
平城 |
史跡指定 |
ー |
国特別 |
| ー |
平山城 |
ー |
国 |
| ー |
山城 |
ー |
都道府県 |
| ○ |
陣屋・館 |
ー |
市町村 |
| 遺構 |
ー |
建築物 |
天守閣 |
ー |
現存 |
| ー |
石垣 |
ー |
木造復原 |
| ー |
土塁 |
ー |
鉄筋復原 |
| ー |
水堀 |
ー |
復興 |
| ○ |
空堀 |
ー |
模擬 |
|
| 整備して欲しい御殿跡(撮影年月 H17・7) |
|
| 現存建築物 |
国宝 |
なし |
| 国重文 |
なし |
| 都道府県指定 |
なし |
| 市町村指定 |
なし |
| その他 |
なし |
|
| アクセス |
鉄道 |
JR東北本線小山駅下車徒歩8分 |
| 車 |
国道4号線からすぐ |
| ミニ情報 |
市役所の敷地にあたります |
| 地図情報 |
 |
|
| 城略史 |
小山御殿は徳川将軍家が日光社参の際に立ち寄る休憩所、宿泊所として設けられた。御殿の作りは厳重で、周囲に堀を巡らし、土塁は二重、番所は16ヵ所というものであったらしい。
日光社参は四代将軍家綱の時の寛文3年(1633)以降、財政難を原因として八代吉宗の享保13年(1728)まで途絶えたが、その間に小山御殿は大風等により建物が壊れてしまい、天和2年(1682)、古河藩によって解体された。「小山評定」の吉例により築かれたらしいが、今ではその雰囲気さえ伝わるものはない。 |
|
| 主な見どころ |
 |
 |
| ↑御殿復元図:想像の域を超えていないと思われます。これほどの歴史的重要性のある地でありながら、なぜもっと調査をしないのでしょうか。 |
↑現地案内板:この案内板と偶然出会ったおかげで周囲を散策し遺構を探すことにしたのです。というか、案内板くらいしか手がかりが無い。 |
 |
 |
| ↑御殿広場:御殿広場は何かの跡地であるようです。しつこいですが、折角の空き地ですので調査してください。 |
↑空堀:御殿広場の西側にある堀と思われる遺構。しかし実際のところわかりません。もちろん橋は関係ありません(と思う)。 |
| 探訪年月 |
①H17・7 |
| 併設・周辺資料館 |
|
| 参考見学所要時間 |
約0時間30分 |
| お薦め度 |
私見 |
小山御殿と言っても何も残っていない。江戸時代のものなので場所は特定できるというだけである。現地には案内板もあるので興味のある方は行くと良いでしょう。それだけのために行くこともないでしょうが。 |
| ー |
城郭ファン以外も必見 |
| ー |
見逃せない対象です |
| ー |
城好きは行きましょう |
| ー |
予備知識がある方は・・ |
| ○ |
マニア向け |
|
|
|
| 初版20061200 |
| 戻る |




