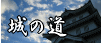 |
| トップ>メニュー>関東地方>源経基館 |
| みなもとのつねもとやかた |
| 源経基館 |
| 別称: |
| 所在地:埼玉県鴻巣市大間字城山 |
 |
| 形状 |
ー |
平城 |
史跡指定 |
ー |
国特別 |
| ー |
平山城 |
ー |
国 |
| ー |
山城 |
○ |
都道府県 |
| ○ |
陣屋・館 |
ー |
市町村 |
| 遺構 |
ー |
建築物 |
天守閣 |
ー |
現存 |
| ー |
石垣 |
ー |
復原 |
| ○ |
土塁 |
ー |
外観復原 |
| ー |
水堀 |
ー |
復興 |
| ○ |
空堀 |
ー |
模擬 |
|
| (撮影年月 H19・2) |
|
| 現存建築物 |
国宝 |
なし |
| 国重文 |
なし |
| 都道府県指定 |
なし |
| 市町村指定 |
なし |
| その他 |
なし |
| 復元建築物 |
なし |
|
| アクセス |
公共 |
JR高崎線鴻巣駅下車後徒歩15分 |
| 車 |
国道17号線から吉見方向、鴻巣高校を目標に行くとよい |
| ミニ情報 |
駐車場はありません |
| 地図情報 |
 |
|
| 城略史 |
埼玉県の史跡に指定はされていますが、未だに源経基館跡との確証はなく、あくまでも頭に「伝」という文字がつきます。実際、館跡としてほかの場所にも伝承があります。
源経基は、清和天皇の孫で貞純親王の第六子で「六孫王」と呼ばれました。武蔵介として武蔵国に下向し、天慶2年(939)武蔵武芝らとの争いに巻き込まれ、平将門が介入したため京に戻り、朝廷に謀反を訴えました。翌年将門追討軍の副将軍として板東に赴き、まや藤原純友の乱でも活躍し、数カ国の国守を歴任したあとは鎮守府将軍となりました。応和元年(961)に源朝臣の姓をを賜り、その年には没したため、実際に源経基と名乗った期間は短いことになります。しかしながら清和源氏の祖として称されています。
(参照「埼玉の城址30選(埼玉新聞社)」) |
|
| 主な見どころ |
 |
 |
| ↑空堀跡①:四方を、というわけではありませんが方形を想像するに難くない見事な空堀が現存しています。 |
↑空堀跡②:長年の風雨で掘底が埋まってしまったのでしょう。それを割り引くと、かなり堀幅も広いものであったことが考えられます。やはり、中世武士による改変が為されているのは明らかです。 |
 |
 |
| ↑館内:見事に木々で埋め尽くされてしまっています。何とかならないものでしょうか・・・。 |
↑石碑:土塁跡のような、やや高い場所に建つ石碑。「六孫王」という文字が見ます。いいんでしょうか?確証無いのに・・・。 |
| 探訪年月 |
①H19・2 |
| 併設・周辺資料館 |
|
| 参考見学所要時間 |
約0時間15分 |
| お薦め度 |
私見 |
見事に方形である遺構から、中世武士の館という印象はぬぐえません。鴻巣市の発掘調査でも、源経基館跡である証拠を発見することは出来なかったそうです。ですが、あまりにも見事な方形の空堀はいずれにせよ誰かしらの館であったことは間違いなく、それなりの地位と権力を掌握していた武士であったとが想像できます。どちらにせよ、伝承・想像の域を脱することは出来ず、現場で純粋に遺構を楽しむか、想像力をフル活動するほかはないようです。 |
| ー |
城郭ファン以外も必見 |
| ー |
見逃せない対象です |
| ー |
城好きは行きましょう |
| ○ |
予備知識がある方は・・ |
| ー |
マニア向け |
|
|
|
| 初版20070808 |
| 戻る |




