

2003.04.10
北信越・北陸漫遊(北陸本線・小浜線)
4月10日。鉄道に乗車する事実上の最終日となった。
今日は昨日までの2日間がうそのようないい天気である。
ホテルから再び30分の道のり、敦賀駅に到着した。
 |
 |
敦賀駅 (左)駅舎 (右)広い構内が鉄道の要衝である事を物語る
まず敦賀駅から湖西線で山科駅まで行くのであるがここにあったのである。ループ線が。
敦賀駅を7時20分に発車した列車は下り線を右手に見て左側に回り高度を上げ始める。
そしてぐるりと右にループを描き始めた。
続いて下り線をオーバーパスしてトンネルに入っていったのである。
これはトンネル内でもループしているのがはっきり分かる。ループの半径がかなり小さいのではないか。
トンネルを出るとすでにループは終了していた。
近江塩津駅で北陸本線と分岐して湖西線に入った。
駅を出て左手に琵琶湖が見えたがすぐにトンネルに入った。
このあたりから通学の高校生が多くなってきた。
近江今津駅で乗り換えとなるがかなり混んできた。
本来なら改札を出たいところだがこれだけ混んでいると移動する気が起きなかった。
近江今津駅を発車すると左手には琵琶湖が眺められる区間が多くなってきた。
 |
 |
琵琶湖(志賀−蓬莱間)
堅田駅あたりでは高校生はばったりいなくなった。
しかし今度は通勤客がだんだん増えてきた。
京都に近づくにつれ車内は混み通路までいっぱいになってきたのである。
綾小路さんはだんだん心配になってきた。なにしろキャスターに載せたバッグを抱えている。
はたして山科駅で降りられるのか?しかも乗換え時間は3分しかない。
列車の前から降りようかそれとも後ろからにしようかと迷っていた。
しかし車内を観察していると意外とドアが近いことに気付いた。
これなら大丈夫だろうと思い始めた頃に列車は山科駅に到着した。
ここでは下車する乗客もかなりいて思ったよりスムーズに下車出来た。
これで湖西線は一応完乗した。
複線であるためか列車待ちはなかった。また列車内の混雑もあって途中の駅を探索出来なかったのは残念であった。
まあしかたないが魅力的な駅舎はなさそうだったのであきらめはついていた。
無事に東海道線に乗換えたが先ほどの混雑で今までの旅行気分もぶっとんでしまった。
ここから米原までの約50分も混雑列車だった。
そして米原駅に到着した。山科駅の探索を見送ったのもすべてはここで駅弁を購入するためであった。
ここ米原駅は駅弁の種類が豊富で迷ってしまう。井筒屋、ええ仕事してまんな!
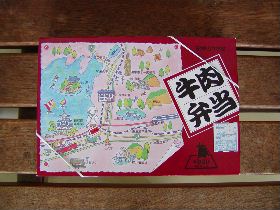 |
 |
 |
(左、中)米原駅弁 牛肉弁当 ¥930 (右)米原駅
米原駅では10時23分発の列車に乗車した。しかしこの列車は3駅先の長浜駅行きであった。
ところがその長浜駅に目的があったのである。
旧長浜駅舎。長浜駅から徒歩5分のこの建物は現存する最古に建設された駅舎との話しである。
普通の駅舎のイメージとは違っていて隣の文化会館と間違えそうになったほどであった。
しかし明治の初期はこういう風だったのかもしれない。
 |
 |
(左)長浜駅 (右)旧長浜駅舎
明治15年3月10日に長浜−柳ヶ瀬(廃止)間、洞道口(廃止)−金ヶ崎(後に敦賀港、廃止)間の仮開業で北陸本線の歴史が始まった。
この旧長浜駅舎はどうやらその時に建設されたものらしい。
明治17年4月16日に柳ヶ瀬−洞道口間が開業して長浜−金ヶ崎間が正式に開業。
長浜−米原間は関ヶ原経由で迂回する形で連絡されていたが現区間は明治22年7月10日に開業した。
これで米原−敦賀間が全通となったのである。
その後にルート変更もあって現在の形となったがここから直江津方面まで連絡していく事になる。
時間がないので急いで長浜駅に戻り11時03分発の列車に備えるが接続列車が車両故障の影響で遅れ14分程出発が遅れた。
こんなことならもっとゆっくり出来たのに。
列車は20分程度で近江塩津駅に到着した。
この時点で足掛け4日。北陸本線の完乗である。
えっまだ?なになに敦賀−新疋田間は下り線も乗車が必要だというの?
例のループ区間の反対方向だな。なるほど下り線はループしないで直進で山下りとなるのか。
じゃ、しゃあない。乗るか。と言う訳で敦賀まで行くことにした。(どのみち行くのであるが)
新疋田駅を過ぎて敦賀までの途中にループにさしかかる上り線の貨物列車に遭遇した。
 |
 |
敦賀−新疋田間路線 貨物列車は右手から左手に移動中、この後すぐにトンネルに入りループする。
その後しばらくして敦賀駅に到着したが綾小路さんはそのまま乗車して福井方面に向かったのである。
列車は敦賀駅を発車してすぐに北陸トンネルに入った。
全長13870m、在来線では青函トンネルを除くと最長のトンネルである。
昨日も通過したが夜の9時過ぎだから気が付かなかった。
トンネルを出るとすぐに南今庄駅に到着した。
 |
 |
南今庄駅
ここで先程の敦賀駅で購入していた駅弁を食べた。
これが今回の漫遊で最後の駅弁となった。
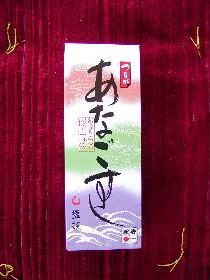 |
 |
敦賀駅弁 あなごすし ¥950
綾小路さんは南今庄駅から折り返して敦賀駅に戻った。
このあとは今回の漫遊最後の小浜線に乗車してフェリーの発着場所の東舞鶴駅まで行く予定である。
まず13時11分発の列車に乗車して粟野駅と西敦賀駅を探索した。
 |
 |
(左)粟野駅 (右)西敦賀駅
 |
|
上中駅
続いて上中駅に行くまでに目星を付けていた十村駅まで戻った。
先ほどの粟野駅と同じく大正6年9月の建築。建物財産標で分った。
駅前には懐かしい”よろずや”があった。
郵便局も兼ねているみたいである。
以前は数多くあったけどいつの間にか少なくなった。
 |
 |
(左)十村駅 (右)駅前のよろずや
小浜線は敦賀側から敷設され大正6年12月15日に敦賀−十村間が開業した。
その後、小浜、若狭高浜までと順次開業。
大正11年12月20日に若狭高浜−新舞鶴(現東舞鶴)間が開業し、全通した。
綾小路さんは上り列車で小浜駅に到着した。
ここで19分間停車するのである。その時間を利用して駅を探索した。
改札を出て駅舎を見ると前面には派手な飾り付けがしてありがっかりした。
若狭路博をアピールするためであろうが似合っていない。
あー、つまらんとまたホームに戻り辺りを眺めていて驚いた。
あれは給水塔ではないか?ホームの東舞鶴よりの端に巨大な給水塔があった。
しかもこんな間近に目にできるとは。
綾小路さんは廃線駅では見た事があったが現役の駅では初めて見た。
(後で敦賀駅構内の写真でそれらしきものは写っていたが)
給水塔があるなら転車台は?駅構内を見回すがない。
給水塔の向こう側にそれらしきものがあったがカメラのズームで拡大しても何か分からなかった。
しかしこれがそうだったのだ。やっぱり無いなと決め付け駅員にも聞かなかったのも悪かった。
列車が発車してまじかに迫った時にやっと分かった。転車台の跡だったのだ。
転車台自体は撤去され跡には奇麗な穴がぽっかり開いていた。
コンクリートで型取りされている。
ああ、カメラも間に合わない。綾小路さんがっくし。
 |
 |
小浜駅 (左)派手に飾られた駅舎 (右)の給水塔の向こう側には転車台の穴も写っていた。
そして小浜駅を16時53分に発車した列車は若狭本郷駅へ到着した。
ここの駅舎は”国際花と緑の博覧会”で義経号の駅舎として使用されたものを移築したそうだ。
そんな事は綾小路さんは知らないから駅の裏に義経号があったので驚いた。
これは義経号のレプリカでその博覧会で使用されていたものらしい。
 |
 |
若狭本郷駅
若狭本郷駅では18時11分発の列車に乗車して東舞鶴駅に到着した。
これで小浜線は完乗となった。
綾小路さんは舞鶴線も乗車したくて18時50分発の列車に乗車した。
どうせフェリーは深夜に出発なのである。
まだまだこの漫遊を続けたかったのかもしれない。
 |
|
綾部駅
そして綾小路さんは今回の漫遊最後の駅に向かった。もちれん東舞鶴駅である。
ここは現在高架駅となっているが以前は戦時中に建てられた駅舎があったらしい。
簡素だが軍港舞鶴の玄関口にふさわしい堂々たるものだったという。
できればそのころに来たかった。
駅から舞鶴のフェリー乗り場まではまた徒歩である。30分ぐらいでフェリーターミナルに到着した。
 |
 |
(左)東舞鶴駅 (右)舞鶴港前島ターミナル
23時30分、綾小路さんは舞鶴港から小樽港に向け、今度は28時間の船旅についたのであった。
次に綾小路さんはいつ、どこを漫遊するのか請うご期待!
| 若狭高浜 |  |
若狭本郷 | 十村 |  |
粟野 |  |
西敦賀 | 至 直江津 | ||
 |
 |
 |
 |
 |
||||||
| 東舞鶴 | 小浜 |  |
上中 | 近江塩津 |  |
敦賀 |  |
南今庄 | ||
 |
 |
 |
||||||||
| 綾部 |  |
京都 | 近江今津 | 長浜 | ||||||
 |
 |
 |
 |
|||||||
| 至 幡生 | 山科 |  |
米原 |  |
至 東京 |
 トップ |
 鉄道 |