

2004.09.26
のと鉄道漫遊(其の四) 路線図を表示
綾小路さんはタクシーが嫌いである。
せっかくの名駅舎も駅前にタクシーがたむろし、興ざめとなったことが何度あったことか。
駅は日常の生活に密着した場所なので、タクシーや乗客があってこそ生きた写真が撮れる・・・。
なんて考えもあるかもしれない。
しかし、名駅舎は邪魔者なしで撮りたいものである。 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
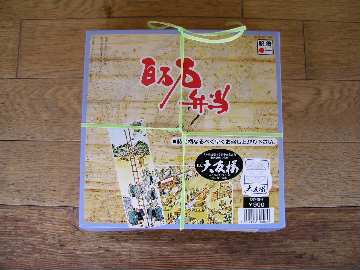 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 トップ |
 鉄道 |