

2003.04.04
北信越・北陸漫遊(磐越西線・只見線)
うーむ、眠い。朝の3時過ぎに目が覚めた。さあいよいよ北信越・北陸の漫遊だ。
ゆうかり号は予定通り5時30分に新潟港に到着した。
歩いて5分、バス停に到着。バスは市内を15分程走り新潟駅へと到着した。
 |
 |
新潟駅
新潟駅から6時30分発の信越本線で新津駅まで行き、6時58分発の磐越西線に乗り換えた。
新津駅では駅弁を購入し朝食とした。
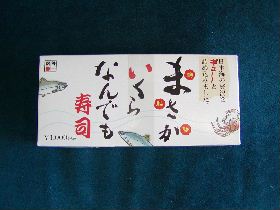 |
 |
新津駅弁 まさかいくらなんでも寿司 ¥1000 ま(鱒)さ(鮭)か(蟹)といくらの寿司
あわただしく駅弁を食べ、20分後に五泉駅に到着した。
ここは平成11年10月3日まで蒲原鉄道が4キロ先の村松まで接続していた駅である。
綾小路さんが持っている平成11年5月発行の道路地図にも載っていた。
しかしさかのぼれば昭和60年3月31日までは信越本線加茂駅まで運行していたようである。
JR駅構内にはホームを撤去しただだっ広い空地や路線跡が確認出来た。
 |
 |
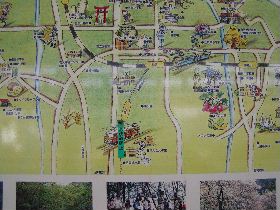 |
五泉駅 (左)駅舎 (中)蒲原鉄道跡 右にカーブして村松方面に向かう。 (右)駅ホームの案内版、まだ蒲原鉄道が載っていた。
 |
|
馬下駅
仕切りなおし、8時50分五泉駅発の会津若松行きの列車に乗車した。
磐越西線は先程の馬下駅を過ぎると阿賀野川沿いに敷設されていて徐々に高度を上げていくみたいである。
阿賀野川の景色を楽しみながら40分後に津川駅にて下車した。
かつて津川は阿賀野川の水運の中継基地として栄えた。
しかし鉄道の開通とともに阿賀野川水運は衰退したそうである。
市街地が橋を渡った対岸にあるのは水運と鉄道の歴史との関係から来ているのかもしれない。
 |
|
津川駅
 |
 |
 |
津川駅駅名標 (左)磐越西線SL運行駅の駅名標 (中)きつねの嫁入りの駅名標 (右)通常の駅名標
長い途中下車の後、10時26分発の列車に乗車した。
しかし北海道とは全然違う景色だ。津川も結構雪深いはずだがほとんど残っていない。
阿賀野川も雪解け水で増水している様でもない。やっぱ気温が違うのか?
まあよく考えればもう4月である。
車窓にちらほら蔵が見えてきたと思ったらほどなく喜多方駅に到着した。
綾小路さんはここで下車した。そうラーメンを食べるためにである。
駅にはラーメンマップが置いてありラーメン店が一目で分かる。
その幾多のラーメン店から綾小路さんが選んだのは大安食堂。
(本当は坂内食堂やまこと食堂とかに行きたかったが遠かった。)
店に入ってびっくり。客が一人もいない。たらー、冷汗が出てきた。
綾小路さんはずしたか?しかし今さら店を出ることも出来ずしかたなくチャーシュー麺を注文した。
待つことしばし、チャーシュー麺はやって来た。
綾小路さんおそるおそる口に運ぶ。
あれっうまいじゃない。ズズズズズー、スープまで完食した。
喜多方ラーメンおそるべし!
ちなみに喜多方駅からは昭和59年3月31日まで日中線が熱塩まで通じていたがそのホームがまだ残っていた。
末期には1日3往復、通勤、通学の朝夕しか走らないため日中に走らない日中線と揶揄されたそうだ。
 |
 |
 |
(左)喜多方駅 (中)日中線ホーム、駐車場の柵あたりに熱塩までの線路が敷かれていた。 (右)旧熱塩駅 H14-11-21撮影
さて大満足の綾小路さんは12時35分発の列車で会津若松駅にやってきた。
ぱんぱかぱーん、ぱんぱんぱん、ぱんぱかぱーん。今週のハイライト。
古いな!
まあそう言っても過言ではない。なんと只見線に乗車するのである。
会津若松駅から小出駅まで135.2キロ。
ついにこの日がやってきた。
きしゃきしゃぽっぽっぽっぽっ、しゅっぽっしゅっぽっしゅっぽっぽっ。綾小路さん、はしゃぐ。
13時08分、ついに綾小路さんを乗せた只見線の列車は出発した。
しかし期待とは裏腹に会津若松駅を出てしばらくは町中を走りやがて田園風景が広がった。
おかしい!こんなはずでは。もっと秘境を走るのではないのか?
疑問を感じながらも列車は進行した。
このあたりは会津本郷駅、会津高田駅、新鶴駅など線路の撤去された対抗ホームを持つ駅が多い。
会津高田駅なんかまだ枕木も残っていた。そうだよな、会津若松−小出間の直通列車は1日3往復、交換施設は不要だ。
会津坂下駅を過ぎて登り坂にかかってきた。それもディーゼルエンジンがうなりをあげているのでかなりの急勾配だ。
何かここまでは奥羽本線の福島−赤岩間に似ている。
福島市内から田園地帯を少し走り庭坂を過ぎてから板谷峠に挑んで行く。
この後も似ていればよいのだが・・・
塔寺駅を過ぎトンネルを立て続けに2つ通過した。いいぞ!
しかしそこにはまたしても田園風景が待っていた。だがさすがにだんだんとムードが出てきた。
郷戸駅を過ぎたあたりから只見川が右へ左へと並行して走るようになり絶景が見えるようになった。
 |
 |
(左)只見川(会津桧原−会津西方間) (右)只見川(会津西方−会津宮下間)
列車は会津宮下駅を過ぎた。
この辺りは対岸の国道252号線が凄い。
少しは切土しているとは思うが絶壁の中をくり貫き道路を通しているように見える。
スノーシェッドを兼ねたロックシェッドの連続である。
 |
 |
 |
只見川 全て会津宮下−早戸間
そして列車は会津川口駅に到着した。ここで対抗列車待ちで12分間の停車となった。
線路は只見川の川面より少しだけ高い所に敷設されていた。
川が氾濫でもしたらホームは水浸しになるのではないかと思った。
また、ここで綾小路さんは初めてタブレットの交換を目にした。
 |
 |
 |
会津川口駅 (左)駅舎 (中)ホームは川沿い (右)タブレット交換
会津川口駅の前、会津水沼駅あたりからであろうか。
いつの間にか雪解けしてない地域に入っていた。
このあたりからが只見線沿線の豪雪地帯となるのか?
やがて列車は只見駅に到着した。
何だろう、駅舎が木板で覆われている。豪雪から駅舎を守るためなのか?
 |
 |
 |
只見駅 (左)木版で覆われた駅舎 (中)改札口を出たところに海抜372mの標識が (右)時刻表、さすがに運行本数が少ない
只見線は会津側が大正15年10月15日、会津線として会津若松−会津坂下間が開業した。
その後会津柳津、会津宮下、会津川口までと順次延長された。
そして昭和38年8月20日、会津川口−只見間が開業した。
一方小出側からは小出−大白川間が昭和17年11月1日に開業した。
永らく陸の孤島状態であった只見−大白川間が昭和46年8月29日に開業し、会津若松−小出間が全通した。
 |
|
田子倉駅
続いて列車交換のため6分間大白川駅に停車した。
駅の脇を流れるのは只見川ではなく末沢川か。
魚野川に合流してすぐに信濃川に合流する。越後山脈の西側の越後平野を延々流れて日本海に注ぎ込む。
一方、六十里越の向こうの福島側からは只見川が越後山脈の東側を流れ会津盆地で阿賀川に合流する。
阿賀川は越後平野に出てくるがこの時は阿賀野川と名前が変わっている。
そしてこれも日本海に注ぎ込むのである。河口は信濃川河口と10キロも離れていない。
 |
 |
大白川駅
列車は最後に魚野川を渡って小出駅に到着した。
とうとう綾小路さんは只見線の完乗を果たしたのであった。
この達成感を何にたとえたら良いのか?絶世の美女を口説き落とした時の感じか?
綾小路さんの漫遊はまだまだ続く。次は北堀之内駅に姿を現した。
 |
 |
(左)小出駅 (右)北堀之内駅
これで本日の予定は終了。
綾小路さんは越後湯沢の健康ランドに向かったのである。
綾小路さんの漫遊は北信越・北陸漫遊(上越線・吾妻線)に続く!
| 新潟 | 新発田 | 至 秋田 | ||||||||
| 柏崎 | 宮内 | 新津 | 津川 | 野沢 | ||||||
| 高崎 | 北堀之内 | 五泉 | 馬下 | 山都 | 喜多方 | |||||
| 越後湯沢 | 小出 | 只見 | 会津川口 | 会津坂下 | 会津若松 | |||||
| 大白川 | 田子倉 | 会津宮下 | 会津柳津 | 至 郡山 |
 トップ |
 鉄道 |