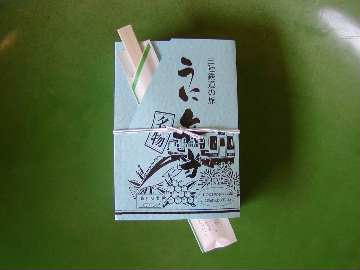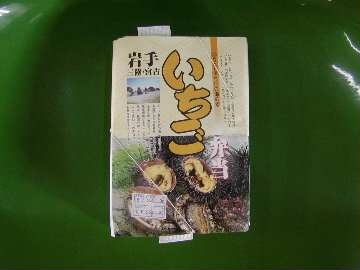2003.05.28
北東北漫遊(八戸線・三陸鉄道北リアス線・岩泉線)
|
どうやらこの八戸健康ランドは天然温泉のようだった。
それで大部屋、リクライニングシートでの仮眠コースで
2100円、いいんでない。
レストランでの食事もなかなか安くてグー。
しかし難点は駅から遠い事である。
ここは約40分かかった。徒歩で来る人のために作られていないからしかたがない。
そしてようやく八戸駅に到着した。
新幹線駅と複合した大橋上駅である。
隣のりっぱなホテルの位置にも昔は駅施設が建っていたのだろう。
|
 |
本日まず最初に乗車するのは八戸線である。
しかし途中下車する時間がとれそうにない。
せめて途中駅のひとつでもカメラに収めておきたかったのでやむなく列車を一本早めた。
それで5時30分出発、早やー。いったい何時に起きたんだ。
|
当然単線だろうと思っていたら隣には線路が並行して走っている。
そうか、ひょっとして鮫駅までは八戸への通勤圏で複線かもしれない。
と思っていたらその線路は左方向に分岐していった。そしてまた分岐していく。
あれはなんだったんだろうと地図を見ると、どうやらそれは八戸港に行く貨物線の様である。
あっもう一本、これは高架なのに線路が撤去され砂利だけが残っていた。
そして20分後に鮫駅に到着した。
|
 |
|
鮫駅を発車すると左手にすぐ大平洋が見えてきた。
八戸線は海岸線を走っているのに意外と海が見えなかった記憶があった。
しかし思ったより見えるなと車窓風景を楽しんでいると、種市駅で交換列車待ちのため20分間の停車となった。
|
 |
車窓からは尚も太平洋が見えた。遠目で暴風林の切れ目や家屋越しにではある。
そしてふっと海岸沿いに出たのである。
それまで海面から5〜10mぐらいのところを走っていた列車は有家駅を過ぎて高度を上げだした。
次ぎの陸中中野駅付近ではかなり下側に海岸が見えた。
そこから尚も高度を上げトンネルに突入。内陸部に入っていったのである。
そしてしばらくして久慈駅に到着した。
久慈駅 (左)JR駅舎 (右)三陸鉄道駅舎
八戸線は1894(明治27)年1月4日に尻内(現八戸)−八戸(現本八戸)間が開業した。
本八戸から先は時間がかかり、1924(大正13)年11月10日に八戸−種市間が開業。
翌1925(大正14)年11月1日には種市−陸中八木間が開業した。
最後、1930(昭和5)年3月27日に陸中八木−久慈間が開業して全通した。
時間は8時を過ぎたばかり、しかし朝が早かったのですでに空腹の極みである。
三陸海岸沿線といえば”うに”である。
目的としていた駅弁を首尾よく購入でき、列車待ちの間にいただいた。
久慈駅弁(三陸鉄道) うに弁当 ¥1260 清雅荘
久慈駅からは9時10分発の三陸鉄道北リアス線に乗車した。
この路線は”トク得北東北パス”では乗車できないがしかたない。
また八戸まで引返すのもバカバカしいし。
久慈駅から最初の停車駅は陸中宇部駅である。(左)
その次が陸中野田駅であり、ここは道の駅に併設されているそうである。
ホームの右奥にはいかにも道の駅といった建物が写っている。(右)
三陸鉄道北リアス線はトンネルを数多く通過するようだ。
陸中野田駅からすでに3本通過していた。
太平洋が見えなかったのは八戸線ではなくこちらの路線だったか。
ここで野田玉川駅に到着となった。(左)
そこからは石門トンネル、銭神トンネル?、第一安家トンネルと3本あった。
そして大型橋梁の先の第二安家トンネルを通過した。
次の駅が堀内駅である。(右)
堀内、前浜、沢向の3本のトンネルのあとにまた大型の橋梁が控えていた。
さらに大沢トンネルのあとには第一白井トンネルを通過して白井海岸駅へ到着した。(左)
次の普代駅(右)までには第二、第三白井と第一、第二、第三力持の5本ものトンネルがあった。
こうトンネルが連続するのでは番号を付けないと間に合わない。
そのあと列車は普代トンネルに入った、これは長いトンネルである。
明戸トンネルとさらに一本トンネルを通過して田野畑駅に到着した。
列車は久慈駅を出発するときも空いてはいたが乗客は徐々に下車していった。
ここでとうとう乗客は綾小路さんひとりになって北海道のローカル線みたいになった。
このころになるとワンマンカーの運転手も列車の前方で写真を撮っている綾小路さんに興味を持ったのか話しかけてくるようになっていた。
聞くと地震の影響で団体客のキャンセルが相次いだという。
この三陸鉄道も今乗車している北リアス線は運行しているが盛−釜石間の南リアス線は今日いっぱいは運休との事だった。
平井賀トンネル、次に第二島越、第一島越トンネルと通過していく。
この間にトンネル番号の順番が変わった、それまで久慈側が若い番号だったがここから宮古側が若くなる。
三陸鉄道が久慈側と宮古側の双方から敷設が進められたからであろう。
そして列車は次の島越駅に到着し、ここで綾小路さんは下車した。
ここから3人乗車したようでかろうじて乗客0は避けられたようである。
その島越駅の駅名標には”カルボナード”島越と書いてあった。
宮沢賢治の童謡にちなんで冠名が付けられたとの話である。
三陸鉄道は他の駅もなにかしら冠名が付いているようであった。
島越駅からは徒歩でひと駅戻り田野畑駅に到着した。
ちなみにここは”カンパネルラ”、これも賢治の童謡からきている。
(左)島越駅 (右)田野畑駅
田野畑駅から再度三陸鉄道に乗車した。
島越駅に続き浜岩トンネル、次に切牛トンネルを通過した。
その次の小本トンネルは長い。
そして小本駅では列車交換で2、3分停車した。
写真を後から見ると左手に駅舎がありそうだ。
三陸鉄道では一部レトロ調気動車を運行していてその写真を撮っていて気付かなかった。
そこから小本川を渡りトンネルを1本通過して摂待駅に到着した。(左)
その次に真崎トンネル、地図を見ると三陸鉄道北リアス線で一番長いのがこのトンネルのようだ。
さらに第三、第二、第一田老トンネルを通過して田老駅に到着となった。(右)
まだまだトンネルは多い。
佐羽根駅(左)までには逢の山、第二庄転、第一庄転、堀野、第二佐羽根とトンネル5本の通過を要した。
そして第一佐羽根トンネルに続き一の渡トンネルを通過して一の渡駅に到着したのである。(右)
予定ではこの駅で下車だったが小さい駅なのですぐ探索は終わるだろう。
しかし乗車してきた列車は交換列車待ちをするようだった。
このとき、宮古行き列車でも久慈方面への列車でもどちらでも乗車可能であった。
しかし時間は2分間である。しばしの葛藤。しかし止めた。
あまりあくせくするのも嫌になってここで下車する事にした。
列車が行って静かになった駅周辺を探索、やはりすぐに終了した。
ここから2.9キロプラスαでひと駅戻り佐羽根駅を探索しようかとも思ったがまた汗をかきそうなので断念。
先ほどの列車内からの写真で事足りているだろう。
そして1時間30分待ちのはずであるが20分ぐらい後に列車の音が聞こえてきたのである。
貨物列車が第三セクターにあるのかと思ったが客車だった。
しかしそれは団体列車で確認したが乗車出来なかった。
その後1時間後にも今度は逆方向の列車がやってきたのである。
なんだ臨時列車は結構走っている。
|
ようやく到着した列車に乗車して宮古駅に向け出発。
猿峠、第二山口、第一山口、長根と4本のトンネルを通過して右側に山田線の路線が見えてきた。
宮古駅はもうすぐそこになる。
|
 |
宮古駅 (左)三陸鉄道駅舎 (右)JR駅舎
三陸鉄道北リアス線は国鉄時代の敷設に始まる。
まず1972(昭和47)年2月27日に宮古線、宮古−田老間が開業した。
一方、久慈側からも敷設され1975(昭和50)年7月20日に久慈線、久慈−普代間が開業した。
工事は尚も進められたがその後に国鉄赤字ローカル線の第一次廃線候補となる。
しかし早々に第三セクター”三陸鉄道”に移管する事が決定した。
1984(昭和59)年4月1日に宮古線の宮古−田老間、久慈線の久慈−普代間が三陸鉄道に移管される。
同時に田老−普代間を開業させ、三陸鉄道北リアス線の宮古−久慈間として全線開業した。
すでに2時近く、空腹の綾小路さんは駅弁を購入する事にした。
しかしキオスクには”魚元弁当売り切れ”の文字が。
やっぱり、しかしこれを予想してここは予約を入れておいたのである。
抜け目ない?綾小路さんが購入したのは”いちご弁当”。
”いちご”とは”いちご煮”の事でウニとアワビを使った三陸地方の郷土料理である。
汁の中のウニが野イチゴのように見えたことからこの名が付いたとか。
昔はウニもアワビも安かったのか。
これを待合室で食べる事にしてまず撮影、しかし実にうまそうである。
そこでキオスクに戻りビールを購入。時ならぬ宴会タイムとなった。
宮古駅弁 いちご弁当 ¥1150 魚元
さあこれからお楽しみのローカル線、岩泉線の乗車である。
宮古駅が14時55分発で岩泉線起点の茂市駅でしばらく停車、その後岩泉駅に至る直通列車がある。
これに乗車するが釜石方面からの列車が遅れており10分以上の遅れが生じた。
これも地震の影響か?
遅れるのはいいが茂市駅で20分間の停車時間を利用した探索時間が減るのは問題だった。
列車は宮古駅から茂市駅には20分かかる。
やはり列車運行中での時間挽回とはいかずに、残り時間は5分少々だった。
茂市駅 (左)駅舎 (右)跨線橋からの眺め、直進が岩泉方面、左カーブが盛岡方面
茂市駅から先、列車はいよいよ岩泉線に乗り入れた。
いいねえ、予想通りである。日本の農村風景がここにあった。
そののどかな風景の中を岩手刈屋駅、次いで中里駅に停車した。
(左)岩手刈屋駅 (右)中里駅
このままのどかな景色が終点まで続く、と思っていたら岩手和井内駅あたりから山中に分け入った。
次の押角駅は板張りのホームのみの駅だった。
列車が発車して尚も周辺を観察していると石造りのホームが見えた。
そうだった、ここは昔スイッチバックの駅だったのだ。
茂市方面からの列車は石造りホームに停車後にいったんバック、その後前進して岩泉方面を目指していたらしい。
帰りに写真を撮ったが暗くてシャッタースピードが遅くぶれていた、残念。
押角駅 (左)ホーム (右)スイッチバックホームへの引込線
|
隣を走る国道にもはやセンターラインはない。
舗装こそされているが細い道である。気が付けばはるか100mぐらい下を走っていた。
その後国道との高低さは徐々になくなり、国道はまた広い道路となった。
そしてすぐに岩手大川駅に到着した。
|
 |
次の浅内駅には大きな駅舎があり下車したい衝動に駆られた。
しかし1日に3往復の岩泉線である、途中下車をすれば終点の岩泉駅までは行けない。
さらに岩泉駅からの帰りにはなんと給水塔を発見した。
これは今までに見た事がないタイプだったので半信半疑だった。
そこで車掌に聞いたところやはり給水塔であるという。
押角駅のスイッチバックと合わせまた探索に来たくなった。
浅内駅 (左)駅舎 (右)給水塔
その後列車は二升石駅に停車していよいよ終点の岩泉駅に到着した。
さあ折返しの列車が発車するまで急げ!
となると思ったがあわてなくてもよかった。
普通はこの手の盲腸線は5分か長くても10分程度で折返すがここは50分間もあった。
他の2便は8分と5分で折返す。どうやら高校の下校時刻に合わせているようだ。
駅舎はコンクリート造りで大きなものである。
”乗って守ろうみんなの岩泉線”の看板がかかっていた。
岩泉線も他のローカル線と同様に廃線の危機が迫っているという。
町には日本三大鍾乳洞のひとつ龍泉洞もあるがそれを見学する時間はなかった。
しかしそんな時間があったら先に押角駅や浅内駅の探索を先にするだろう。
岩泉駅 (左)駅舎 (右)岩泉線スローガン
岩泉線は1942(昭和17)年6月25日、小本線として茂市−岩手和井内間が開業した。
1944(昭和19)年7月20日には岩手和井内−押角間が開業。
1947(昭和22)年11月25日に押角−宇津野(その後廃止)間が開業した。
ここまでは順調に延伸してきたがここからの敷設には時間がかかった。
1957(昭和32)年5月16日に宇津野−浅内間が開業した。
そこからさらに時は過ぎ、1972(昭和47)年2月6日に浅内−岩泉間が開業し全通した。
もともとは現三陸鉄道小本駅までの敷設計画であったがこの時点でこの先の計画は中止となっていた。
そして小本線から岩泉線に路線名称が変更されたのである。
その後は茂市駅まで引返して盛岡方面への山田線に乗り換えた。
すでに暗闇は迫っていたがあとしばらくは車窓風景が楽しめそうである。
さっそく地図を見て座席のどちら側に座るか決める事にする。
どれ、えっ、ない。綾小路さん、またやってしまった。
すぐに車掌に連絡して調べてもらう。
結局は盛岡駅に到着したときに改札で聞く事になったがどうやら岩泉線の列車内に忘れたらしかった。
しかしそのまま宮古駅まで行ってしまい宮古駅受取か、着払い宅急便で自宅に送るしかないと言う。
結局今後の予定とかを考え宮古駅に取りに行く事にした。
盛岡では夕食、駅近くに焼肉の有名店があり久々に贅沢した。
その後は隣駅の厨川駅まで行き健康ランドに宿泊であった。
”盛岡でビジネスホテルに宿泊して普通の夕食”とのてんびんにかけた結果の選択であった。
綾小路さんの漫遊は北東北漫遊(花輪線・秋田内陸縦貫鉄道)に続く!
| 陸中八木 |
 |
久慈 |
 |
陸中宇部 |
 |
陸中野田 |
 |
野田玉川 |
 |
堀内 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 種市 |
 |
鮫 |
|
二升石 |
 |
岩泉 |
|
普代 |
 |
白井海岸 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
本八戸 |
|
浅内 |
 |
岩手大川 |
|
田野畑 |
 |
島越 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
| 青森 |
 |
八戸 |
|
岩手和井内 |
 |
押角 |
|
摂待 |
 |
小本 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
厨川 |
|
中里 |
 |
岩手刈屋 |
|
田老 |
 |
佐羽根 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
| 大曲 |
 |
盛岡 |
 |
区界 |
 |
茂市 |
 |
宮古 |
 |
一の渡 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
東京 |
|
|
|
|
|
釜石 |