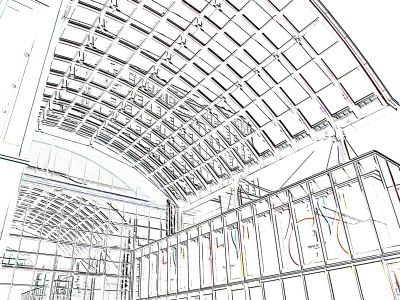
伝助の夕立
1967年の夏、山並助一郎が遭遇した夕立は彼にとって特別な夕立であった。
*
中学2年生だった彼は、父・伝助と二人で自転車に乗って隣の街までサイクリングをした。
彼の自転車は、伝助に買ってもらったばかりの青色のサイクリング車で3段変速ギアが付いていた。伝助はと言うと、がっしりしたフレームで見るからに重そうな自転車に乗っていた。先頭を走る伝助の自転車の後ろに彼はぴったり付いて走った。
橋の長さが東京都内で1番というF橋を走る。2階建てのビルより高いF橋は、何処までも続いているように彼には思えた。日陰のない橋の上、それでも走っていると、暑さは幾分和らいだ。
「こりゃ、一雨来るぞ」
伝助がそう言った矢先、雨がポツリポツリと額に当たった。差していた陽が隠れ、空は暗雲に覆われた。彼らは側道から橋の下に慌てて降りた。橋の下に入ると、たちまち、すごい勢いの雨が降り始めた。
降りしきる雨。橋の下で彼らは雨宿りをした。遠くで稲光がし、暫くしてからゴロゴロと雷の音が鳴った。
「光と音の間が長ければ、雷様は遠いとこにいるからすぐ傍に落ちる心配はないが、低いとこにいたほうが安全だぞ」
伝助が独り言を言うように空を見上げて言った。伝助の物知りを感心しながら、彼は飽きることなく路肩を流れる雨水と時々光る空を見上げていた。30分くらい経っただろうか。
「晴れてきたぞ」
今まで黙っていた伝助がぽつりと言った。なるほど遥か遠くの空が少しずつ明るくなってきた。どんどん黒い雲は流れ、日がかすかに差して来た。
「さあ、行くぞ」
雨はいつの間にか小降りになっていた。伝助の掛け声で自転車にまたがる。ペダルをこぐと、頬に冷えた風が当たった。暑い夏の日に感じた清涼感だった。
*
2010年、秋、助一郎は、あの日から、随分、遠くまで来てしまった、と思う。夜、鈴虫がなく季節、彼は涼しい風を受けながら、あのじりじりと汗のにじんだ身体と暑い空気を思い出す。そして、今はいない父のことを一人になると思い出す。父のどこか嬉しそうな言葉。
「もうすぐ一雨来るぞ」
あれは、何か父の儀式のようなものだったのかもしれない。
|