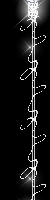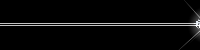どんな道を歩いたって
どんな死に様を選んだって
それは自分がした選択
誰かが用意した訳でも
誰に選ばされた訳でもない
それは――。
自分が取らなくてはいけない責任
Postlude
「お前が好きだ」
もし、そう言えたら何か変わっていただろうか。
もし、そう言えたら何か起こっていただろうか。
そんな『もし』は意味のない事だと分っている。
分っていてそれでも心の中で繰り返される。
もしあの時そう言えたら。
俺は今でもお前の傍に居られたのだろうか―――。
冬の寒空の中、寒々しい程の純白が舞い上がる。
風になびく彼のマントは恐ろしい程に白くて、それがまるでここが現実で無いかのような錯覚を覚える。
危なげなくフェンスの上に立ち地上の星を見下ろす孤高の怪盗。
その姿を新一はじっと見詰めていた。
声をかける事を躊躇う様な、凛とした空気の中佇む怪盗。
その姿は世界の全てを拒絶している様に見えた。
「いつまでそうしていらっしゃるおつもりですか?」
どれくらい時が経ったのか。
感覚すら麻痺し始めた頃、そう声をかけられる。
「気付いてたのかよ」
「気付いていたのも、気付いていらっしゃった癖に」
屋上に設置された貯水ポンプの裏から姿を現わせば、クスッと笑う声が響いた。
見えずとも新一は知っている。
その笑い声に反して、彼の瞳が決して笑ってなどいない事を。
「全く、さっさと声をかければいいものを…」
呆れた様な響きを持った言葉に、新一は苦笑する。
尤もだ。
逆ならともかく、探偵が怪盗を逃がすかもしれない状況でこんな風に見詰めていたなんて。
余りにもお笑い草だ。
「そうだな」
だから敢えてどうという言い訳も、嘘も吐かなかった。
見詰めていたいと思ったのは紛れもない事実だ。
新一の言葉をどう取ったのかは知らないが、怪盗はふわりとフェンスから降りると新一へと向き直った。
「一体今日はどうされたんですか? いつもはいらっしゃらない貴方が、寒い中こんな所まで」
身体だって、まだそんなに良くはないのでしょう?
続けられた言葉に、新一はただ怪盗の藍色の瞳を見詰めた。
澄んだ藍。
そして、冷めた藍。
「気が向いたんだ」
「じゃあ今日はラッキーな日ですね」
そう言って怪盗は笑う。
決して瞳は笑っていない、作られた笑みを構成する。
「探偵が来て『ラッキー』だなんて言う怪盗はお前ぐらいだよ」
普通なら嫌うのに。
普通なら避けるのに。
目の前の怪盗は敢えて毎回毎回新一宛てに予告状を送る。
警察宛ての物とは違う、もっと難解で、もっと新一の心を躍らせる暗号を。
けれどそれは、予告状であって、予告状ではない。
犯行後に立ち寄る何処かを示した物。
要は、犯行後の密会へのお誘いだ。
「そうですか? 名探偵に来て頂けるなら喜ぶ犯人も少なくないと思いますよ?」
小さく笑う怪盗を睨みつけて、新一は溜息を吐く。
「そりゃ、迷惑な話だな」
新一は嫌な顔を隠しもせずにそんな風に言う。
確かに過去に新一目当てで犯行を犯した犯人が居るのは事実だ。
曰く、『工藤新一に捕まえて貰いたかった』だそうだが、新一にとっては激しく迷惑な話だ。
「気持ちは私も分らなくないですがね」
ただ、もう少しスマートなお誘いを心がけてはいますが。
言うが早いか、新一の前にひらひらと一枚のカードが降って来た。
真っ白く少し光沢のあるソレは屋上のライトの灯りを受け、キラキラと光る様に新一の手の中へと落ちてきた。
「何だよ、コレ」
「プレゼントですよ。折角お越し下さったのに、お土産の一つもないのでは申し訳ないでしょう?」
探偵を呼び出すだけでも随分と常識ハズレなのに、この怪盗は『お土産』なんて物まで下さるらしい。
随分と奇特な怪盗である。
怪盗なんてものをやっているだけで、充分奇特だが。
「俺が素直に貰って帰るとでも?」
「貴方の大好きな暗号ですが、それでもお持ち頂けませんか?」
「…………」
そう言われては、新一とてそれに興味が湧かない訳がない。
まじまじとその純白のカードを見詰めて溜息を吐くと、それをコートのポケットへとしまった。
「用事はこれだけか?」
「ええ。これだけですよ」
わざわざ作られたあの難解な暗号は、作るのにも相当な時間がかかった筈。
それをこんな事の為だけに作る労力があるのなら、もう少し他の事にその労力を回せばいいものを…、と新一は思う。
幾ら怪盗キッドとて、そうポンポンとあんな暗号が作れる訳もないだろう。
時々思う。
暗号は解読するよりも、作る方がよっぽど難しいのではないかと。
「これだけならあんな暗号で態々こんな所に呼び出さなくても、うちのポストにでも入れとけば良かっただろうが」
呆れた様にそう言った新一を、怪盗は意外な事に真っ直ぐ見詰めてきた。
その瞳に、新一は戸惑う。
「……キッド?」
躊躇いがちに怪盗の名前を呼んでも、返事が返ってくることはない。
冷めた藍が戸惑う蒼を見詰める。
沈黙に耐えきれずに、もう一度口を開いたのは新一の方だった。
「一体、何なんだよ…」
視線を逸らせば良かったのか。
それとも、相手になどしなければ良かったのか。
どちらの選択も取る事が出来ずに、ただ躊躇いがちに怪盗を見詰め返す探偵の蒼に、今日初めて怪盗が瞳を和らげた。
「何でもありませんよ。ただ、名探偵の綺麗な瞳を見詰めていたかっただけです」
「……そういうのは、喜ぶ奴に言ってやれ」
素直ではないと笑う怪盗に、少し気恥ずかしくなって、漸く新一は怪盗から視線を逸らした。
言いはしないが、一つ確かな事がある。
新一とて、怪盗の藍を、澄んだ綺麗な藍を見詰めていたいと思っていた。
「相変わらずつれないお方ですね」
「つれてどうする」
「私は嬉しいですけどね」
ふわっと笑った顔が余りにも眩しくて。
新一は一瞬目を奪われた。
いつものポーカーフェイスとは違う。
怪盗の素の顔とでも言おうか。
余りにも印象の違うそれに、新一は言葉を失う。
それをどう取ったのかは分らないが、怪盗はコツコツと、一歩また一歩、新一に近付き、そして直ぐ目の前で足を止めた。
そして手袋をはめた手で、そっと新一の頬に触れる。
手袋にしては滑らか過ぎる感触に、新一はそっと目を閉じる。
視界が塞がれた事により、感覚が研ぎ澄まされよりリアルに怪盗の存在を感じる。
「私は、名探偵の事が好きですから」
夢幻の様な世界の中で、そっと唇に落とされた温もりだけがこれが現実なのだと教えてくれた。
フェンス越しに夜の街を見下ろす。
さっき怪盗が見ていたのと同じ景色ではあるのだろうが、フェンスの上に立っていた怪盗が見て居たのは何にも邪魔されない『真実』の姿。
フェンスに邪魔された『偽り』を見ている自分とは違う。
フェンスを掴んでいる左手はそのままに、新一は右手の指先でそっと唇に触れた。
寒さでもう冷えてしまったそこに先程の温もりは存在しない。
それが寂しいなんて自分でも何だか笑えてくる。
相手は―――『怪盗』
自分は―――『探偵』
その二人がどうこうなるなんて、悲劇か喜劇でしかない。
余りにも……非現実的だ。
尤も、『探偵』も『怪盗』も、余りにも非現実的過ぎるけれど。
ふわっとふいた風の冷たさに新一は眉を顰める。
別に寒いのが好きな訳ではない。
だからこんな所に未だ留まっている自分を、自分自身理解できない。
あまりにも感傷的な気分に浸っている自分も。
寒さにかじかんできた手をポケットにつっこめば、指先に触れる微かな感触。
そういえば…と思い出し、それをそっと掴み出す。
彼を思わせる純白の白いカード。
それを、何の気なしに月に翳す。
一体どういう仕組みなのかさっぱり分らないが、浮き上がった文字に新一は言葉を失った。
それは暗号でも何でもなかった。
それは余りにも単純な7文字の羅列だった。
けれど―――。
たった7文字の言葉に、これ程心が動いたことなどない。
たった7文字の言葉を、これ程見返したこともない。
唇が寒さ以外の何かで震える。
震えて零れ落ちそうになるカードを、慌ててしっかりと掴む。
どうして、と思った。
どうしてこんな事を、と。
彼が探し物をしている事など新一に分っていた。
ビッグジュエルばかりを狙い。
何故か犯行後は素直にそれを返却する。
きっと何かを探しているのだと推察するには余りにも単純だった。
今日盗まれた宝石も、さっき返却されたと聞いてからここに来た。
だから分らない。
どうして探し物の途中である怪盗がこんな事を自分に渡すのかなんて。
そのカードをそっとポケットに再びしまうと、新一はただ茫然と黒い闇に浮かぶ月を見詰め続けた。
終焉は余りにも単純だった。
余りにもあっけなく謎は解けた。
それは、新一が予想していたよりも余りにも呆気ない謎だった。
あの日から―――怪盗キッドが現れなくなった。
いや、厳密には違う。
怪盗キッドが――『日本』に現れる事がなくなっただけの事。
今でも彼はまだ海外で活動を続けている。
きっと日本にあったビッグジュエルは皆、彼の求める物ではなかったのだろう。
だから彼は今でも探し続けている。
新一の知らない、『何か』を見付ける為に。
「ビッグジュエルでも買ってみるかな…」
リビングのソファーに身体を埋め、彼の白程は白くない天井を見詰め、一人呟く。
そして、そんな事を呟いた自分に笑えてきた。
彼に逢いたいのだと思う。
彼を好きなのだとも思う。
けれど、これで良かったのかもしれない。
自分達はあくまでも対極。
交わる事のない関係。
「見つからないといいな……」
怪盗には悪いけれど、まだ見つからないと良いと思う。
彼の探し物が。
そうすれば―――あるいはこの先、また逢う事があるかもしれない。
「God bless you」
届かない別れの言葉を口にして口元に僅かに笑みを上らせると、新一は静かに瞳を閉じた。