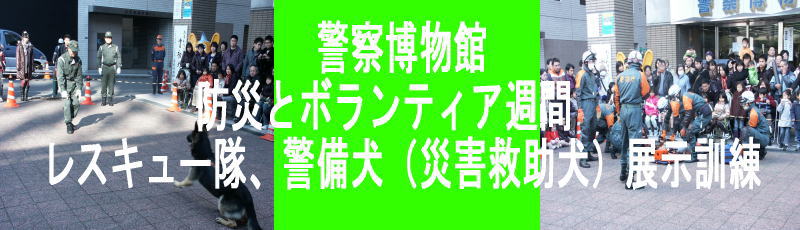
警察博物館 防災とボランティア週間 レスキュー隊、警備犬(災害救助犬)展示訓練
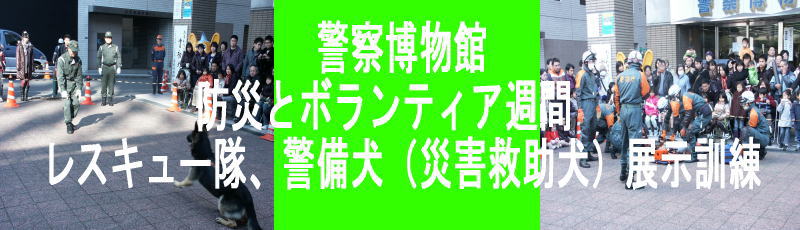
 |
| 警察博物館(東京都中央区京橋3丁目5番1 )では平成22年1月15日から1月21日の「防災とボランティア週間」に併せて「震災パネル展」を実施しました。 また阪神淡路大震災が発生からちょうど15年を迎える平成22年1月17日には警視庁特科車輌隊のレスキュー隊と警視庁警備二課に所属する警備犬の合同訓練の模様が展示公開されました。 「救助=消防」というイメージが強いなかで、この展示訓練は災害救助における警察の存在を如何なく周知する絶好の機会となったことは間違いないでしょう。 |
 |
 |
 |
| 警備犬と担当者 警備犬は警備二課装備第三係に所属し爆発物の探索から犯人制圧、災害時の負傷者の捜索などの複数の業務を1頭でこなします。 |
訓練に参加した警備犬 | 投げたダンベルをひろってくるときの様子 |
 |
 |
 |
| ダンベルを拾って戻ってきたときの様子 警備犬担当とは強い信頼が築かれており、犬が持つ能力を最大限に活かして捜索などにあたります。 |
警備犬担当のユニフォーム 犬の横顔をモチーフにしたワッペンと帽子を着用しています。 |
警備犬レスター号 2004年10月23日に発生した新潟中越地震では崖崩れで数日間埋没していた乗用車から救出された2歳の幼児の生存を最初に確認した。当時の模様はこちら |
 |
 |
 |
| 警視庁特科車両隊のレスキュー隊による救助資機材の展示。 | 機動救助Ⅰ型車 都費購入のレスキュー車。緑色をベースにしたデザインは警視庁と一部の警察本部だけに見られるものです。 |
ロープ結索の体験コーナーの様子 |
 |
 |
 |
| 訓練展示に参加した警備犬オビ号(2歳) | 司会を務めた警視庁特科車両隊の隊員 | 警備犬による倒壊した家屋内の人命検索 警備犬の鋭い嗅覚は救助現場では生存者の発見に威力を発揮する。 |
 |
 |
 |
| 現場に到着した特科車輌隊第4中隊のレスキュー小隊 警視庁機動隊には他の警察本部にはない救助の任が課せられている。但し常設の部隊ではなく機動隊の業務の1つとされている。 |
ボーカメを利用した内部の検索 |
内部に進入する救助隊員 隊員は「POLICE」と書かれた感染防止衣を着用しています。 |
 |
 |
 |
| 倒壊した家屋内で応急処置を行う隊員 隊員はJPTEC(Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care:外傷病院前救護ガイドライン)の研修を修了しており高度で迅速な救命措置が行われます |
負傷者を救出するためにバックボードを入れる隊員 体を動かすことのできない負傷者を搬出するために用いるバックボードは消防の場合、オレンジか黄色をしているが警察の場合は青いのが特徴。 |
負傷者をバックボードに固定 |
 |
 |
 |
| バックボードを用いて倒壊家屋内から救出 |
バックボードを用いての搬送 |
負傷者の観察をおこなう隊員 |
| 当日のイベントの様子(私が撮影した動画です) |
 |
通称:「技術の特車」 もともとは装甲車や放水車で機動隊を援護する目的で発足した隊です。 現在では第一から第九までの他の機動隊と同じ任務をこなしています。 1972年のあさま山荘事件では中隊長 高見繁光警視正を連合赤軍の銃撃により失うという悲劇に見舞われています。 |