病気やけがや災害から自分自身を守り、けが人や急病人(以下「傷病者」という)を正しく救助し、医師または救急隊などに引き継ぐまでの救命手当及び応急手当を赤十字救急法といいます。
救急法を学ぶには各都道府県の日本赤十字社の支部が行う講習を受講する必要があります。講習は赤十字救急法基礎講習と赤十字救急法救急員養成講習があります。
|
赤十字救急法
|
救命手当 |
市民が行う一次救命処置
(赤十字救急法基礎講習)) |
心肺蘇生
(胸骨圧迫、気道確保、人工呼吸) |
| AEDを用いた除細動 |
| 気道異物の除去 |
| 応急手当 |
一次救命処置 以外の処置
(赤十字救急法救急員養成講習) |
急病の手当 |
| きずの手当(止血、包帯) |
| 骨折の手当(固定) |
| 搬送 |
赤十字救急法基礎講習を受講した後に赤十字救急法救急員養成講習を受講し、効果が確認できると赤十字救急法救急員として認定されます。
赤十字救急法基礎講習の模様はこちらをご覧ください
赤十字救急法救急員
「赤十字救急法救急員」とは、赤十字の使命を理解し、事故の防止に努めるとともに、傷病者に対して赤十字救急法を実践する知識と技術を有していることを日本赤十字社が認定した人に与える資格です。特別な任務や責務はありませんが、災害時や事故発生時、日常生活においてボランティアの精神で事故防止と傷病者の救助に努め、赤十字の協力者になることが期待されます。
 |
赤十字救急法救急員養成講習を終えると写真のような認定証が交付されます。 |
講習にかかる費用は?
「いくらかかるの?」というのは気になるところですね。
受講料は無料(講習にかかる経費は皆様からお寄せいただいた寄付金等で賄われております。)ですが、教材費と保険代として以下の費用が必要になります。
基礎講習
1500円(教本・教材費・保険代)
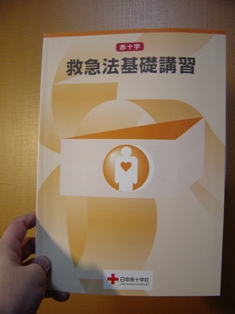 |
| 基礎講習の教本です |
養成講習
1500円(教本、ファーストエイドバック[三角巾2枚、ガーゼ]、保険代)
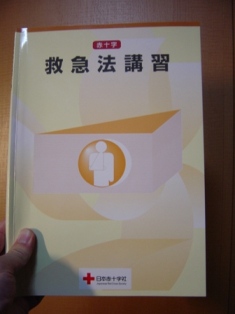 |
 |
| 養成講習の教本です |
ファーストエイドバックです
中に三角巾2枚とガーゼが入っています。 |
講習はどこでやっているの?どれくらい時間がかかるの?
基礎講習
昼食を含む10:00~16:00の6時間です。
東京都の場合、日本赤十字社東京都支部(東京都新宿区大久保1-2-15)のほか都内の赤十字施設で行われています。
詳しくはこちらをご覧ください。
養成講習
昼食を含む9:30~17:30の8時間の講習を2日間連続で行います。
基本的に土日の連続した2日間です。
東京都の場合、日本赤十字社東京都支部(東京都新宿区大久保1-2-15)のほか都内の赤十字施設で行われています。
詳しくはこちらをご覧ください。
ここでは養成講習の内容を紹介します。基礎講習の内容はこちらをご覧ください。
1日目
午前:学科
赤十字救急法救急員とは
急病の手当
けがの手当
きずの手当
午後:実技
搬送法・三角巾を用いた止血・固定・被覆など
2日目
午前:実技の復習
午後:実技の効果確認・学科試験
意外に思われる方もいると思いますが、学科試験があります。初めて講習を受ける人がほとんどなので基本的には「一夜漬け」で対応するしかありません。これはどの受講生も同じ条件です。変な引掛け問題はありませんので教本の内容を1日目の夜に復習しておくとよいでしょう。
ポイントは次の内容です。
赤十字救急法救急員とは
赤十字の使命を理解し、事故の防止に努めるとともに、けが人や急病人に対して赤十字救急法を実践する知識と技術を有していることを日本赤十字社が認定した人に与える資格
|
赤十字救急法救急員に求められる能力
(1)正しい観察と判断を行える能力
①周囲の観察と二次事故防止のための判断
②傷病者の観察と傷病にあわせた手当の判断
(2)リーダーシップ |
心臓発作の手当について
119番通報する
原則として飲食物は与えない
全身を保温し観察を継続する |
熱中症
(症状)
「熱痙攣」「熱疲労」「熱射病」の3種類
(対処法)
風通しが良い日陰か冷房の効いたところに運び、衣類を緩めて楽にする。
顔面が蒼白で脈が弱い時は足を高くする。
意識があり、吐き気、嘔吐がなければ水分補給をさせる。 |
骨折
(症状)
腫れ、変形、皮膚の変色、その部分に触った場合の激痛
(対処法)
全身及び患部を安静にする。
患部を固定する。
患部を高くする。
保温する。 |
熱傷
(対処法)
冷たい水、水道水で痛みが取れるまで冷やす。
水疱は潰さず、消毒した布か洗濯した布で覆い、その上から冷やす。
手足の熱傷は患部を高くする。 |
保護ガーゼの効果
圧迫による止血
血液や分泌物の吸収
感染防止
苦痛の軽減 |
包帯の目的
きずに当てた保護ガーゼの支持固定
副子の固定
手や腕を吊る
強く巻くことによる止血 |
搬送の準備
傷病者の手当ては完了したか
傷病者をどんな体位で運ぶか
保温は適切か |
消防署などで行われている普通救命講習や上級救命講習と比較すると非常に内容が濃いことを受講前に覚悟しておくことが重要です。
実技は2人1組で行うことが多く、積極的に取り組んでください。
受講希望者が年々増加しています。早めに申し込みを行うことをお勧めします。
(このページの内容は2014年1月11日・12日に日本赤十字社東京都支部で行われた救急法救急員養成講習の模様をもとに作成しています)
戻る
|

