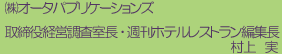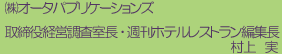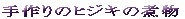
世代によって食べ物についての拘りは随分と異なるというのが私の率直な感想である。私自身を例にこの詳細を語ってみたい。昭和26年6月17日、東京生まれである。父は大正元年、母は大正7年生まれである。兄弟は4人で、順に上から昭和18年(長男)、21年(次男)、23年(長女)、そして私となる。こういう家族構成であることを予備知識に、私がどういう時代に育ったのか、何を食していたのかの記憶を蘇らせてみたい。
物心つくのが4,5歳であろうか。この頃の記憶が私のDNAとなっている。朝の食卓がおぼろげに頭の片隅に残っている。父は一段高い畳敷きで床の間を背にして何膳もの賑やかな食卓を前に無言で食を摂っていた。母や兄弟は畳部屋から一段下がった上がりに座布団を敷いて、これまた無言での味気ない朝の食卓であった。惣菜らしきものは野菜の炒め物ぐらいで、私が小学校を卒業するぐらいまでは一汁二菜といった、いま回想すると極めて質素な内容だったように記憶している。卵焼きなどは遠足や特別の行事がなければ口にすることが出来ないものであった。
ただし、母の手作りであったヒジキの煮物だけは毎食食卓に上っていたのと、必ず牛乳が用意されて居たことが妙に思いだされる。牛乳はなかなか好きになれずに、上の兄に頼んでいつも代わりに飲んでもらっていた。いまでも牛乳だけは苦手で、何が原因なのかは分からないが、多分想像するにこの時分の何かが影響しているのだろう。
この我が家の食卓のパターンは殆ど変ることなく、私が高校に入学する頃までは続いていたように思う。そして、ある日に“事件”はおこった。これはテレビが遠因であった。何かの番組でアメリカンスタイルの朝食のシーンを映画で見たのが、強烈な印象になって私の頭を占拠してしまった。トースターから飛び出したトーストにバターを塗っているシーンは、まさに驚愕であり、様々な感動の心がすべて集約された瞬間でもあった。
「トーストを食べたい。あのトーストを食べたい・・・・」。これはほとんど呪文のようでもあった。そして、意を決して母に告げた。「明日から朝はトーストが食べたい!」。母は瞬間困った表情を見せて、「無理なのは分かりますね。お父様はスタイルを変える人ではないでしょう」と窘められた。
この事件の数日後に私は家を出ることになった。理由は何だったのか。父とのちょっとしたコミニュケーションに齟齬が生まれたことが原因であったのであろう。封建的な家に育ったことだけは間違いのない事実である。いま、自らが二人の子供の親となり、一言で言えば家風という表現を使うならば、やはり自分が生まれ育った頃の慣習を引き継いでいることにある種の不思議を感じざるを得ない。 |

 |
 |
|
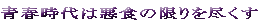
家を出てからの私の食生活は乱れに乱れた。その生活がそうであったように。ろくに朝も食べることもなくなり、腹が減ったら身の回りに置かれているパンやら、当時流行りつつあったインスタントラーメンなどを悪食していた。高校の終わり頃、学生運動の大きな流れの中に身を任せるようになった。アルバイトで糊口をしのぐという毎日である。ひょんなことから渋谷の駅前にあったスナックが常宿になる。見よう見真似でシェーカーを振ったり、カレーやピラフなどのスナックを作るようになっていた。
70年安保も過激派の流れと挫折感を感じつつあるノンポリの延長線上にあった我々のようなだらしない学生のグループに大別されるようになる。浅間山荘事件をきっかけに、私は学生運動から突如身を引くことになる。このことの詳細は省くが、この突然の日和には実はその当時の食生活が大きく影響したのではないかと思う。
もともと、父は食事や食に関する事柄について一家言をもつ人間だった。私がいまでも日本茶が苦手なのも、実は父の影響がある。お茶一杯飲むのにも理屈がある人だった。夕食など、テレビを見たさに簡単に済まそうと茶碗にお茶をぶっ掛けてお茶漬けにして食べたとき、父は私の食膳卓を思い切り蹴っ飛ばして、「バカ野郎!ふざけた真似をするな。お茶漬けなんぞは10年早い。子供はお茶漬けなんか食うな!」と激高したことがある。それが何故かという理由は未だに分からないことである。
いまの職についてから既に30年近い歳月が流れた。ホテルやレストランという世界のジャーナリストであるから、ときとして高級な料亭やフランス料理店なども頻繁に足を運ぶ。
世界中のホテルやレストランにも随分と出掛けた。そこでの世界は、まさに天才が料理を作り、華麗なるメートル・ドテール(給仕長)の神業とも思えるような手捌きで、至福という世界を味わせてくれる。何年か前に、名古屋の某有名料亭に招かれた。かの北大路魯山人の名器が日常使いされるという老舗にして名料亭である。
この招きは、いささか照れるがある人妻の誘いであった。かれこれ20年来の付き合いであるが、肌を合わせるといった仲ではなく、同い年ということからの大人の付き合いである。彼女は通人である。俳諧の世界に遊び、銘菓を慈しみ、そして悠久の世界にロマンを感じる人である。彼女の子供の結婚話の協力をした、その御礼でその席に呼ばれた。「その縁談は壊れた」と嘆く彼女の背中には、えもいわれぬ色気があった。そう感じたのである。
その夜に饗された料理は、どれもが手の入った料理職人の技を感じさせるものであり、一品毎に魯山人の器の目利きを楽しむと言う実に優雅なものであった。
女将が兆度頃合に挨拶に顔を出された。「我が侭を言って申し訳ないが、茶付けが食べたい。出来ますか」と問うた。「もちろん、お客様のご要望には何でも応えます。ご遠慮なさらずに」という女将の言葉に、腹の底から感動した。魯山人の茶碗でお茶漬けという贅沢、これは昔日の父との思い出の趣旨返しかも知れない。
|
 |
 |
|
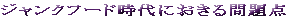
人間の体には、先天的な食に関する対応や嗜好があるという説と、あくまで食は後天的な要素が基本となるという解釈が混同しているが、その真偽はともかく、後天的な要素は味覚を論じる場合に完全に否定は出来ないだろう。
私は、俗に言う甘口であり甘党である。日本酒なども辛口よりは甘口に近い系統のものを好む。羊羹などを食しながらウィスキーを嗜むという蛮行もある。通人にとっては問題外の仕業である。しかし、この手の趣味嗜好は個人の勝手であるから、余人は関係なきものと別段気にすることもない。40歳を超えて、体のふしぶしに支障を来してはいるが、かと言って気にするわけでもない。問題は、むしろ若い年齢層の方々にある。小さい頃からポテトチップスやらポッキーなどをむさぼり食ってきたこの世代は、明らかなジャンクフード世代である。年の頃なら今30代以下の方々が特に危険な兆候を示している。
訳も分からずに怒ってみたり、逆に無気力な表情になってみたりと明らかな情緒不安定である。この原因も、 また食生活にあると分析する専門家がいる。確かに体は大きくなっても心とのバランスを欠いた、見るからに気の抜けた風情の若者が多くなっている。
「渇!」と言いたいところだが、これは精神的なものだけでなく、明らかに食の偏重が齎した物であると専門家は警鐘する。問題は、この無気力なる若者をいかにして救うかと言うことである。
そこで「食育」という考え方をNPOなりNGOで考え、啓蒙して行こうというのが今回のこのコラムの趣旨である。 結論から言えば、昭和30年代の食生活を体現することである。この機を逃すと、日本人のDNAとして継承されてきた食物繊維を中心にした食生活は完全に破綻してしまう。肉がどうのこうのと、言っているのではなく、すべての、毎日の食生活から完全に変えなければいけないというミッションである。
ヒジキの煮物がどれほど体と精神の熟成に役立つかは既に管理栄養士の言を待つまでもなく証明されている。お母さんが作るヒジキの煮物・・・。どうですか、皆さん、この運動に参加しませんか! |
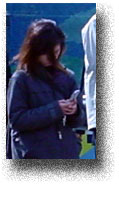
食育
pagetop |
 |
HOME |