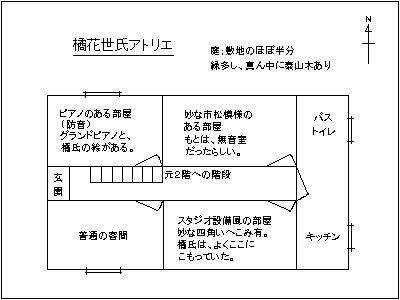この作品はフィクションであり、現実および架空の個人、
団体、事件、事象ともにいっさい関係ありません。
この話には島田荘司氏の創作人物である御手洗潔が登場し、
そういう意味ではシニカルなパスティーシュ(贋作)と言えますが、
むしろ作者が敬愛する作家達へのオマージュであることを
最初に明記しておきます。
『子音欠落症』
0.
ムシュウ・シャルマンこと橘花世画伯は、三人の息子をこの世に残した。
一番上の榊原総司氏は長年病院を営み、二番目の高見沢公樹氏は彫刻家で、最近は主に舞台建築をやっている。一番下の柳田亮一青年は、精密機械のメーカーに勤め始めたばかりだ。
その三人の息子達の所に、このところ謎の品物が送られてきていた。
榊原氏の病院の待合室には色とりどりの風船。高見沢氏のアトリエには大量のモルタル。柳田青年の家にはアンティークなランプ。
それだけのことなら、三人は間違い郵便の類だとして気にも止めなかったかもしれない。
だが、一緒に送られてきたテープの中には、亡くなった彼らの父親の声が、恐ろしく歪んだ音で吹き込まれていた。
「私を殺したのは、あああああ……」
彼らは首をひねった。
いったい誰が? 何のためにこんな嫌がらせを?
送り主の名は《橘カオル》となっていた。それは、三人が三人とも、まるで聞き覚えのない名だった。
しかしそれらは、奇怪な密室殺人を解く、全ての鍵だったのである。……
1.
御手洗潔という男を、女嫌いだと思っておられる読者の方はさぞ多いだろうが、正確なところをいうとそれは誤解である。
あんな書き方をしておいて今更なんだ、とお叱りをうけるかも知れないが、先入観なしで私の本を再度読んでいただければ、その事実はすぐにおわかりいただけると思う。確かに彼は、女性を揶揄からかいの対象にすることが多いが、人を人でないようにあしらうことは、相手が男性であってもさして変わりはない。彼はみだりに恋愛感情を表出しないだけのことであって、不幸な境遇にある御婦人を慰めたり、才能ある女性を誉めたりすることはやぶさかでない。
今回は、そのことを例証するささやかな事件をお話ししようと思う。御手洗をうならせた女性の話を、である。
実を言うとこの話、いささか発表がためらわれる。私が以前発表したある事件と似通った点が多い等、いくつかの問題があるからだ。ただ、今まで御手洗の扱ってきた事件とはだいぶ毛色が違うし、彼が珍しい側面をみせた事件でもあるし、事件の方で御手洗を選んだ、また、探偵御手洗潔でなければ扱えなかった事件であるということで、皆さんにご紹介する意義があると思い、今回の運びとなった。そのへんを楽しんでいただければ、書き手も幸いである。
その、涼しい風の吹く七月の朝まだき、御手洗は散歩をねだる犬よろしく、私を強引に叩き起こした。
「こんないい朝に、いつまでも寝ぼけているのはもったいないぞ。さあ、出かけよう石岡君」
なんの気まぐれかしらないが、唐突な朝歩きの計画である。下手をすると、寝巻きのままで引きずりだされそうだ。無駄だとは思いつつも、せめて朝食なり、と訴えた。すると、普段完全に空腹中枢の麻痺しているこの男が、珍しくも素直にうなずく。
「うん、そうだな、こんな日に、君を餓死させるのも気の毒だ。ピクニックに行く訳じゃなし、たっぷり食事をとっておくのも悪くない。……ただ、あまり時間をかけると、せっかくの早朝の風情が失われる。朝飯をとるなら、早いこと片付けようじゃないか。もちろん五分とかからないだろうね」
そう言われてはひきさがれない。急いで私は、簡単なイングリシュ・ブレックファーストを準備した。
すると御手洗は、実に旺盛な食欲をみせてそれに取り組む。すこぶるつきの上機嫌である。その浮かれ加減は、新しい謎に夢中になっている時の様子によく似ているが、実際そういう時は、わずかな食事の時間さえ惜しむ男だ。この余裕のある表情は、仕事からややずれた興味の対象を見つけた証左であろう、と見当をつけられる。この一週間ほど、馬車道の事務所には、さしたる事件も持ち込まれていない。その退屈に飽いて、この男、なにか新種の遊びを開発したに違いない。
「で、今日はどこへ行くんだ、御手洗」
「朝のそぞろ歩きに行き先を求めるとは、君も無粋だな。あてなどないよ。それより黙って、早く食べたまえ」
いつもの居丈高な物言いだが、嫌味な感じはしない。せっかくの御機嫌を損ねてもと思い、返事をせずにただ首をすくめた。
すぐに着替えて外へ出ると、御手洗はまっすぐ桜木町の駅に向かって歩きだした。どこが行くあてのないそぞろ歩きだ。夏の朝特有の甘ったるいオゾン臭に洗われながら、私は彼のあとを足早に歩いた。
駅につくと、御手洗はためらわず終点までの切符を買い、東横線の鈍い銀色の車両へ乗り込んだ。
「なんだ、渋谷へ行くんだったのかい」
御手洗はかすかに笑った。
「さっきもいったろう、石岡君。目的の亡者になると、大切なことを見おとすよ。なあに、別に意味のある小旅行じゃないんだ。籠ってばかりいると、頭も心も曇ってくる。そういう意味での気晴らしさ。今日はのんびり、人間観察会と洒落ようじゃないか」
私たちは並んで座席に腰掛け、横浜の港を見おろした。
確かに、東横線の高架の見晴らしはひどく良い。古いものをうまく残しながらどんどん変質してゆくこの街の顔を充分に見ることができ、人の生活の情緒というものを窺い知ることができる。なにげなく急行列車にのってしまったが、今日は土曜だし朝も早い。例の殺人的ラッシュに巻き込まれる心配もないだろう。たまのひととき、郊外列車にゆられてしばし、というのも悪くない話だ。私はほっと息をつくと、座席に深く腰掛けなおした。
だが、始発駅にもかかわらず、発車間近になると、ちらほらと座れない乗客がでてくる。
私たちの斜め前に、分厚いペーパーバックを読みふける妙齢の女性が立っていた。よく干した藁のように淡く輝く金色の髪。顔の輪郭が薄闇に溶けてしまいそうなほどに蒼白い肌。西洋人にしては地味な顔に、かすかに色の入った丸い眼鏡をかけている。シンプルな焦茶のワンピース姿で静かにたたずんでいる様子には、なんともいえない気品があり、紳士を気取るわけではないが、この席を立って、どうぞとすすめたくなった。全体のはかなげな様子、特に華奢で細い肩のあたりが、男性の保護本能をひそかにくすぐるのである。
御手洗は、そんな私の心の動きに気付いたらしい。ニヤリと笑ってこちらをこづく。
「石岡君、僕に遠慮することはこれっぽっちもないんだよ。いいたいことがあるのなら、声をかけたまえよ」
「なにをいうんだ、御手洗」
私はハッとし、次にムッときた。私は別にやましいことを考えていたわけではない。それに、知り合いでもなんでもない女性に、いったいなにをどう喋れというのだ。
いや、御手洗が本気でないのはわかっている。ただ、私の乏しい英語力と、度胸のなさを、単純にからかっているのだ。だが、うすのろよばわりされるのは本意でない。私がム、と口をつぐむと、御手洗はなおも畳みかけるように、
「大丈夫だよ、石岡君。君の英語力は犬も保証している。今日の相手は人間だよ。伝えたいことがあれば通じない筈はない」
「おい、そこまで嫌味をいうことはないじゃないか」
「嫌味なんかであるもんか。だいたい君には、語学のセンスがある筈だよ。そういうセンスのない人間には、長い文章は書けないものだ。何冊も本を出しているような日本語のエキスパートが、英語は全くできません、というのはおかしい」
自分ができると思う人間は平気でこういうことをいうから嫌だ。私もつい大人げない気持ちになって嫌味を返した。
「しかし、結局日本語と英語は違うよ。それに君と違ってね、僕の脳味噌の左側は論理的にできてないんで、外国語には不向きなんだ」
「やれやれ石岡君、君はまだ六十年代の迷信にとりつかれているのかい。確かに、民族的な論理と言語には密接な関係がある。だが、文化的な差はともかく、大脳の働きに優劣はないんだ。日本語と英語の差は、子音と母音の処理の仕方の差でしかないんだよ。西欧人は、左の論理脳で子音中心の言語を音節単位で処理し、母音その他の社会音を右の音楽脳で処理している。そして日本人といえば、この左の脳で、母音も子音も社会音も、すべて言葉の類として処理する。……ただそれだけのことなんだ。子音中心の言語が優れているとは、いわくいいがたい。結局、母音のないところに音節は成立しないんだから、そういう意味では西欧人の脳の中にも矛盾があるというものだ。むしろ日本語は、十数個の子音と五つの母音で整理されている単純な言語でありながら、高度なニュアンスを伝える優れた言葉なんだ。このことは、世界に誇っていいことなんだぜ。言語というものは、単純であればあるほど進化した形なんだからね。アクセントや発音の平板化が、これから言語の変化にどういう影響を与えていくかはまだわからないが、日本語は微妙なイントネーションを必要とする繊細な言語だから、日本人の耳はますます鋭くなっていかなければならないんだ。だが、実際に起きているのは反対の現象だろう、従って……」
またぞろ例の悪い癖、ところかまわぬ説教癖だ。頭が痛くなってきた。私の理解不可能な範疇にまで話はすすんで、もうろくな相づちも打てないというのに、御手洗は延々としゃべり続ける。声高な蘊蓄は、朝から疲れ果てている通勤者のやすらかな眠りを奪っており、さらに私の心をも悩ませた。しかし、いさめようにも簡単におさめられる相手でなし、しかも変わらぬ上機嫌なだけに、私にはどうすることもできなかった。曖昧な笑顔でうなずきながらも、私の視線と思考は、車中をあてどなくさまよい続けた。
だいぶ乗客が増えてきた。すぐそばに男子高校生の一群がいて、たわいない会話を弾ませている。御手洗の声と彼らのにぎやかな声がごっちゃになって、私の頭痛は悪化した。
だが、ふと、学生達のしゃべり声が低くなった。見ると、一か所人垣が切れている。よく目をこらすと、そこにはぴたりと目を閉じた女性が一人、すっくと背筋を伸ばして、しっかりとそこに立っているのだった。
彼女はきちっと白い杖をつき、自らの第三の足にしていた。青年達の声が途切れたのは、この女性の盲目に気付き、自分達の位置を変えたためだったのだ。
私は感動した。
青年達の礼儀もそうだが、その女性の表情が実に穏やかで美しいことが、私の心をうった。縫いとりのある白いノースリーブのブラウスに、細い紺のパンツというあっさりとした清潔ないでたち、その自然な存在感も、ひどく好ましかった。人との距離がとれないこういう閉鎖空間では、普通の人間はあんなふうに平穏で静かな表情はできないものだ。この人は、視力というものがないかわりに、別の豊かな世界を手に入れているのだな、と感じ、人に平等に与えられる能力や、何かを失うかわりに研ぎ澄まされる感受性といったものに、思いを馳せた。
ふと、御手洗の声が低くなった。
「石岡君、確かに女性の扱いは君の分担だが、下手な同情はほどほどにしておくといい」
「どういう意味だい」
つい声が大きくなった。私は何をした訳でもないし、みだりな同情もしていない。その反対で、不幸にも負けず、しっかりと生きている女性に感動していたのだ。
だが御手洗は、私の怒りをさらりと受け流し、
「言わぬが花さ。……さあ、もうすぐ終点だよ、石岡君。いよいよ、君の望んだ目的地だ」
謎めかして言葉を切る。
電車はようやく渋谷駅につき、私たちは重い腰をあげると、人波に流されながら、長いホームを歩き始めた。
なんとなくほっとした次の瞬間、御手洗はとんでもない行動に出た。
先程の白い杖の女性の前に飛び出すと、その杖の先を足先でガンと蹴りとばしたのだ。
「何をするんだ、御手洗」
私が叫ぶ間もなく、彼は次の行動に出た。彼女の手を掴むと、思いきりねじあげてしまったのだ。
「これは僕の仕事だ。それより君、急いでさっきの金髪の女性を呼び止めてくれ」
杖を失った女性は、御手洗の手を逃れようと激しくもがいている。その様子は、やはり唐突に暴行を受けた若い女性のものではない。私は訳がわからなかったが、とにかく言われたとおり、焦茶のワンピースの女性を追った。
すぐにその姿は見つかったが、どう呼びとめたものかわからない。英語で叫べば待ってくれるだろうか?
えい、ままよ、とにかく声を出そう。
「プリーズ、ウェイト!」
彼女はぴたりと立ち止まった。くるりと振り向くと、小首を傾げ、なんの御用でしょうという表情をつくった。
「ええと、あのう」
言葉に詰まって困っていると、御手洗がとんできた。
何事か早口で呟いてから、ぱっと手を開く。そこには銀の指輪が光っていた。
彼女の口から、柔らかな声音が漏れた。
《まあ、一体どうして、あなたがそれをお持ちですの?》
それは英語だったが、私の頭にはぱっと字幕が閃いた。
《間違いなく私の物です。どこで落としたのかしら?》
とりたててゆっくりでもないのにその英語は非常にわかりやすく、一瞬日本語かと思うほど滑らかに私の耳に滑り込んできた。だが、そんなことに驚いている場合ではない。私は二人の会話に割り込んだ。
「おい、僕にも説明してくれ、御手洗」
「簡単なことだよ。さっきの女性はスリだったのさ」
「あの、目の見えない人がか?」
「ああ。あれは白杖の赤井っていって、さる筋では有名なスリなんだぜ。噂は前から聞いていたんだが、今日やっとお目にかかることができてね」
「そのために、今日はでてきたっていうのかい?」
「そうだよ。昨日、さる所から情報が流れてきて、ここらへんを赤井が流してるっていうんで、そのお手並みを拝見、と思ってね。僕の目の前でやってくれるかどうか心配だったが、見事なもんだったよ。腕は確かに悪くなかった。最近はやりの集団強盗のような連中に比べれば、ずっとマシとは言えるだろう。ただ、業の秀抜さがあるのに目の見えないふりをするのが、姑息というか気に入らないんで、現行犯で捕まえてやろうと思ってね」
「御手洗、間違いなく、あの人はスリなのか? 君も初めて見たんだろう? 本当にあの人は、目の見えない人じゃないのかい」
「そうだよ。一見してわかった」
「何故」
「あの女性、白い杖に自分の体重をかけて立っていたろう。本当に目が見えない人間は、お年寄りのように杖を身体の支えに使うことはない。あれは自分の感覚器、触覚として使うものなんだから、常に軽く、ものや地面に触れていなければいけないものなんだ。……違うかい?」
「ああ」
私が絶望にうめくと、金髪の女性はつつましやかに尋ねた。
《あの、もしかして、私はこれを落としたのではなくて……日本の親切な探偵さんが、私のために取り戻して下さったということなんでしょうか》
御手洗は、その倍のスピードの英語で、ぱっと返事をした。彼女はまあ、と頬に手をあて、
《本当にありがとうございます。なんとお礼を申し上げたら良いのか……》
彼女は、ガーデニア・シムス、と名乗った。アメリカの言語学者で、二年前に来日し、K大で英語の講師をしているという。差し出された名刺には、表には日本語、裏には《Gardenia Simms/Linguist》と印刷されていて、桜木町の住所と、勤め先のK大の住所が添えられていた。
私達は、駅舎で少し待たされる羽目になった。本来、こういうケースで官憲に赤井某嬢の犯行を認めてもらうのはかなり難しいのだが、やってきた警官の方で御手洗の名を信用してくれ、すんなり連行していってくれた。以前の犯行状況などから顔を知られている等の理由もあったが、どうやら私立探偵御手洗潔の名前が、いざという時の権威を持つようになっていた様子だ。ただ単に、うるさ方の民間人としての悪評が官憲に届いていて、向こうが面倒を避けただけかもしれないが。
だが、あろうことか、なんとミス・シムスまでもが御手洗の名を知っていた。しかも、私の書いた本によってである。そろそろ売れない画業なんぞは廃業して、本腰を入れて作家になるべきか、とチラと思った。
御手洗はミス・シムスに私の名を伝えたらしい。彼女は私を見上げ、目を丸くして尋ねた。
《まあ、あなたが作家の石岡先生でしたの。御本は拝見させていただいております。本当に御手洗さんと御一緒にお仕事をなさってらっしゃるんですのね》
海外でよく知られるほど私は有名な作家ではない。驚いて、日本語のまま質問する。
「あなたは、日本語の本をお読みになるんですか?」
《ええ。探偵小説を読むことは、洋の東西を問わず言葉の勉強にとても適しています》
私は赤面し、
「いえ、私の本は、とてもそういう役には」
ミス・シムスは甘く柔らかい笑い声をたてた。感情の波が生きもののようにその顔に立ち上がり、透き通ったような白い面をより麗しいものにした。
《御謙遜を。あなたのお書きになっているのは、とても素晴らしいものですわ。探偵小説のなんたるかをご存じですのね。あなたの書かれる本は、コナン・ドイルの騎士道精神、エラリィ・クイーンのケレン、セイシ・ヨコミゾの怪奇性、セイチョウ・マツモトの社会風刺を兼ね備えた、優れたものです。本当に興味深いので、探偵小説で一番大切な、もう一つの要素があれば、と惜しまれますけど》
面と向かってこんな賛辞を受けたのはほとんど初めてのことだった。その表情の豊かさ美しさに、相手の言葉が英語であることも忘れてひきこまれ、重ねて日本語で尋ねた。
「探偵小説で一番大切な要素とは、いったいなんですか?」
《それは、チェスタトンのスピリットです》
「チェスタートン?」
聞き返すと、ミス・シムスは悪戯っぽい笑みをこぼし、
《ええ。……お会いできてよかった。またの機会が楽しみです》
くるりと踵を返すと、彼女は鮮やかに去っていった。
私はしばらくポカンとしていたが、はっと我にかえると、先にいってしまった御手洗のあとを追った。
「御手洗」
追いついて声をかける。
「なんだい」
「チェスタートンの精神ってなんだろう?」
「チェスタトン? なんの話だ」
私は、さっきのミス・シムスの言葉を繰り返した。
「なるほどね、一理ある。傾聴に値する意見だな。現時点では最高の賛辞だろうね。つけくわえるとすれば、君にはカーのおどろおどろしさや、アイリッシュばりのロマンスなんかもお似合いだよ。いや、君はアイリッシュとは違うかな、あそこまで女性や運命に対して、辛辣になれないからね。……それにしても、チェスタトンのスピリットとはね。たいした女性だ」
「たいした女性?」
「ああ。彼女はまさしく、チェスタトンの世界の住人だ」
「ちょっと待ってくれ、それはいったいどういう意味なんだい? チェスタートンってのは、地味で風変りな探偵のでてくる小説を書いた男だろう? それがどうして彼女と関係あるんだい?」
御手洗は真顔になった。
「何をとぼけてるんだ、石岡君。チェスタトンといえば狂人の論理さ。あの幻想文学の巨匠のお家芸は、それが罪だろうとなんだろうと、ガンとして自分の論理の筋を通し抜く人間を描く事だろう?」
待て。
それでは、今日私が心ひかれた女性二人は、実はスリと狂人だったというのか?
「じゃあ君は、ミス・シムスが狂ってるっていうのか」
顔を思わず曇らせると、彼はアハアと笑った。
「なあに、この世は狂人の巣窟さ。オレンジ色の帽子を被っているのは、女性ばかりじゃないがね」
「じゃあ、やっぱり」
これでは御手洗でなくても女性不信に陥る。ガクリと肩を落とすと、御手洗は手を振って、
「そんなにがっかりするなよ、石岡君。狂っているというほどのものじゃない。ただ彼女の信念が、実に堅固で面白いというだけのことでね」
「信念? 彼女の信念ってなんだい?」
「ああ、それは君自身が尋ねるといい。再会の日を待ってね。すぐにきけるさ」
それよりあと、御手洗は口を閉ざしてしまい、彼女の秘密を私に語ろうとはしなかった。そう、彼は次に起こる出来事を、その時すっかり予測しきっていたのだった。
2.
御手洗の予言どおり、ミス・シムスとの再会には、たいした時間も手間もかからなかった。
向こうから、馬者道の事務所に電話を入れてきたのである。
《あの、シムスと申しますが、石岡さんでいらっしゃいますか?》
耳にそっと滑り込んできたのは、直に人の心に染み入るような涼しい声。
私の胸は高鳴った。
《お忙しいことと思いますが、今日はお願いがありますの》
「私にできることでしたら、なんでも」
《あの、野毛山の白骨事件をご存じでしょうか》
「ああ。近所ですし、新聞でも読みました」
先日、野毛山のとある空き地で白骨死体が発見された。ずいぶん古いものらしく、いったい誰の死体か取り沙汰された。
《私、その事件の関係者になってしまっているんです。それで、是非お力を貸していただけたらと思いまして》
「関係者というと」
《詳しくは、電話などではとても……よろしければ今晩、その、問題の野毛山の家にきていただきたいのですが、御無理でしたら……》
私はすぐに会うことを約束し、電話を切った。
後ろをふりむき、大きな声を出す。
「起きてるんだろう? ……そんな訳で御手洗、今晩野毛山までつきあって欲しいんだ」
「僕は、たぶんいかない方がいいと思う……一人で行ってくればいい。誘われたのは君じゃないか」
御手洗はソファから身を起こした。ゆるやかな午睡を中断されて、けだるげである。しかし固い拒絶ではないから、私はさらに重ねて頼んだ。
「君にとっては特別興味深い事件ではないかもしれないが、御手洗、ミス・シムスは君の力が借りたいんだよ」
「わかってる。だからこそ……いや、とにかくあんまりいきたくないんだよ、僕の方は」
乱れた髪をかきあげて、御手洗は薄い口唇を歪めた。
「おい、それは一体どういう意味だ?」
この男、変わり者ではあっても、ひねくれ者ではない。事件に興味がないなら、最初から鼻にもひっかけない。それがこの煮えきらない妙な物言いをするというのはどういう訳だ。まさかあの後、彼女が個人的な接触をしつこく御手洗に試みてきて、それに困り果ててなんとか彼女を避けようとしているのじゃあるまいな……?
などとつまらぬ邪推をしていると、御手洗は一つ大きく伸びをして、
「うーん、しかたない。いいよ、いくよ、つきあうよ」
ミス・シムスが指定したのは、ただでさえ緑と坂の多い野毛山の辺りでも、かなり小高い、平たく開けた場所にある家だった。だいだい三百坪くらいはあろうかという敷地に、コルビジェ風といえばきこえがいい、つまりコンクリート打ち放しの四角い建物がぽつんと建っている。古い家とは思えないモダンさがあるというか、文化住宅らしい合理的な形に押し込められているというような素っ気ない建物である。
仄暗い夕闇の中、よく近づいて見てみると、その壁は幾度か塗り直されている様子だった。あちこち部分的に白かったり、暗い色をしていたりで、その無計画なパッチワークはフランケンシュタインのモンスターを想起させた。
《石岡さん、よくいらしてくださいました。お待ちしておりました》
ドアを開けてくれたのは、ミス・シムスだった。
「お招きにあずかりまして」
私達の挨拶に、彼女の後ろから男の声が返ってきた。
《おや、誰がきたんだい》
そこに、もう一人の外国人がぬうっと立っていた。
年の頃は私達とさしてかわらないだろう。世慣れた四十代半ばと見た。濃い金髪に緑の眼。背がひょろりと高く、肩先がごつごつしている長身の男。
《あら、お話してあったでしょう? 作家の石岡先生と、探偵の御手洗さんよ》
《ああ。なるほど》
男は値踏みするようにジロジロと私達を眺めていたが、急に破顔し、大きな手を差し出してきた。力強い握手をしながら、
「失礼しました。私は彼女のアメリカでの弁護士で、ジュリアン・アレクサンダー・バーといいます。先日は、彼女がずいぶんお世話になったそうで」
濶達な日本語が、自信ありげな口元から流れ出す。
「いや、あの時は当然のことをしたまでですよ」
御手洗は薄く微笑んで、じろりと相手をにらみ返す。ミスター弁護士はほとんど気にしない風で、
「日本は探偵小説が盛んな国ときいていましたが、本当なんですねえ。本物の探偵に、探偵小説家とは。私も、そういうものは大好きです」
「そうですか。いい御趣味ですね」
私は卑屈な気持ちになって、つい嫌味っぽく答えてしまった。日本の探偵小説など底が知れているくせに、という軽蔑を感じたのだ。
欧米人は普通、探偵小説は大人の寓話、お手軽な暇つぶしと割り切っている。だが、質の低いものは決して認めない。どんな三流作品であっても、それなりに出来のいい娯楽でなければ許されない。だから、作家にもそれだけのプライドがあって、日本に国産のミステリがあるなどというと、驚く輩さえいるそうだ。それは高慢な発言であるのみならず、人種差別ではなかろうか。
だいたい、このバーって奴は何者だ。日本語は驚くほど滑らかだし、探偵小説好きだと公言する弁護士なんぞ、うさん臭いにも程がある。
彼は私の不機嫌に気付いていないのか、ニコニコしたまま返事をした。
「ええ。仕事柄、みじめな現実の事件には飽き飽きでね。確かに一見、探偵小説は不謹慎な娯楽です。生者が死者をつつきまわし、あげくまわりを踊り狂う。でも、それは一つの儀式であって、死にはそういう類の厳粛さもありうると思うのです。他のジャンルでは描きえないものがありますね。優れた探偵小説には良心が存在する。一人の死者をだしたら、最後まで丁寧に弔わなければならない責任がある。そういう約束事はとても美しいです。これからも、是非いいお仕事をなさって下さい」
その日本語は普通のインテリ以上でうますぎ、社交辞令にしては言葉が多すぎた。これは正真正銘、良心的なミステリマニアであるのに違いない。私は恐れいって、曖昧にうなずきながら案内された部屋へ入った。
四人が腰を落ち着けると、奇妙な沈黙が部屋を領した。御手洗は今回、まるであてにならない。おしゃべりな男の価値は話題のない時に気のきいた話題を切り出すことだろうに、と思いつつ、私は自分でミス・シムスに質問を投げかけた。
「で、いったい、どうしてあなたがそんな殺伐とした事件に巻き込まれたんです」
《石岡さん、実は私は、例の死体の発見者なんです》
「えっ、どうしてそんなことに」
ミス・シムスはうつむき、白い頬に翳をおとした。
《話すと長くなるのですが……この庭で発見された死体のことはどのくらいご存じでしょうか》
仏頂面で椅子へ深く沈み込んでいた御手洗が、ぶっきら棒に返事をする。
「遺体の正体は、橘花世っていう女名前の絵描きだ。前世紀の遺物みたいな甘ったるい絵を描いていた男で、ムシュウ・シャルマンとあだ名されていた。運命の女とか、そういう類の幻想的絵画を描き散らし、資産にまかせて世界を渡り歩いた放浪画家で、しばらくのあいだ行方知れずになっていた」
ミス・シムスははっと顔をあげ、
《ええ、そうです。よく御存知でいらっしゃるわ。……この土地とこの建物は、昔、その橘さんという方のものでした。橘さんはいろいろな国をまわっていらしたのですが、十数年前、アメリカの南部の田舎町で、偶然知り合った孤児を絵のモデルにしました。このモデルが気に入った橘さんは、それから実子同然にその子の面倒を見ました》
「ああ。それが、あなただったんですね」
《はい。橘さんは本当にいろいろと親切にして下さって、一度、日本のこの家にも私を連れてきてくださったのです。まだ私が、十になるかならずやの頃でした》
ミス・シムスは長い睫毛を伏せがちにして、
《異国の情緒にはなかなかなじめないものもありましたが、私はいつしか日本が好きになりました。橘さんは、私がアメリカに戻る前に、日本の思い出になるようなプレゼントをなにかあげようといってくださいました。それで私は、この家の庭にある大きな木を一本いただけないかとお願いしました。日本ではタイザンボクとかいう、マグノリアの木です》
私はそっと御手洗に耳打ちした。
「マグノリアってのは何だったかな?」
「ああ、モクレン属の木の総称だな。泰山木は、北アメリカ原産のモクレン科の常緑高木だ。洋玉蘭ともいって、モクレン特有の肉厚な花をつける。初夏になると、赤ん坊のしゃれこうべぐらいの大きな白い花が、濃い緑の艶やかな楕円の葉の波間に、ぼんやりと浮かぶように咲きだすんだ。二十メートルくらいになるから、よく街路樹にされたりしてるが、実は怪談がふさわしい木だぜ。通俗作家の香山滋にも、この花をタイトルにした陰惨な小説がある。この木の濃密かつ刺激的な香りが、ある女性の魔性の殺意を暗示してだな……」
「よせよ御手洗、それ以上気味の悪い説明をするなよ」
彼女は私達の無駄口が終わるのを待って、後を続けた。
《橘さんは、おまえは面白いものが好きだね、こんなものでいいのかい、とおっしゃりながら、その木を私に下さる約束をしてくださいました。その後、私はアメリカに戻りました。親のいない暮しを心配して、その時橘さんは、私に後見人がわりの弁護士をつけようとおっしゃって……》
ちらりとミスター弁護士を見やって、
《このアレックをつけて下さいました。私はそれから、私なりに平穏に暮らして参りました。しかし、私は知らなかったのですが、私の帰国直後、橘さんは行方不明になってしまわれたのです。十五年前の夏の夜、この家で大きな火事が起こり、それきり橘さんはぷつりと姿を消してしまったのだそうです。ただ、火事場跡に死体は見つからず、そのままに……。近所づきあいもまともにせず、突然ふらりと出かけることの多かった橘さんは、運よく不在だったのかもしれない、ということになって、その失踪は深く取り沙汰されませんでした。事情を何も知らなかった私は、二年前に日本にきて驚き、橘さんの弁護士さんを尋ねました。柏木さんとおっしゃって、日本語と英語の遺書をもっていらっしゃいました。橘さんには正式な配偶者がなく、もう姿を消してからずいぶんたつので、生死も不明だというお話でした。ただ、万が一の時のための遺書の中で、私にマグノリアを残していて下さったというお話なので、せめてお花だけでもと思い、先日ここに譲り受けにあがったのですが……》
「御手洗、赤の他人にも、遺言で何か残すことができるんだったかな?」
その私の耳打ちには、日本語の達者な弁護士氏が返事をした。
「できますよ。日本の法律ではそれをイゾウというそうで、きちんとした遺言状ができていれば有効なのだそうです。アメリカでは、遺言がきちんとしていれば、実の子が何人いようが赤の他人に私有財産のすべてを譲ることができますが」
「イゾウ?」
どんな字を書くんだったか?
「遺贈だよ。遺書の遺に、贈与の贈。……アメリカ人に日本語を教わらないように。だいたい、仮にも君は推理小説作家だろう」
御手洗が半眼で呟く。どうも今回のこの男は変だ。気乗りなさげな割にこの場にそれとなくつきあおうとしている。いったいどういう興味があって、ここに座り続けているのか。
ふと気づくと、ミス・シムスが先を続けるのをためらっていた。
「すみません、いちいちお話を中断して。どうぞ先を続けて下さい」
《あの、そういうことではないんです。これから先は、どんな風にお話したらいいのか、迷っていたんです。橘のおじさまは、あの……アレック》
灰色の目が助けを求めて、明るい緑の目を振り仰ぐ。大男はうなずいて、
「彼女には話しにくいこともあるでしょうから、続きは私が話しましょう。……つまり橘氏は、芸術家の常で、美しい花を見るとその場で手折らずにはいられない人だったんですよ」
つまり橘氏は、生涯正式な結婚をしなかったが、その奔放な生涯の中で認知した子供が、日本に三人いた。
そして、ミス・シムスの依頼で公開された遺書には、遺産を残す相手としてその子等の名前が当然のように連なっていた。
彼らはすぐに父親の失踪宣告を申し出、遺産を受け取ることにした。資産が手にはいる云々はともかく、姿を消して生死不明の父親のその後に、この息子達はあまり関心がなかったらしい。まあ当たり前の話だろう、常に所在不明、いいかげん無責任な父親に深く心をかけていても仕方がない。心労ばかりが積み重り、いいことは一つもないからだ。そんな親は、幻か死人と割り切って暮らした方がよほどいい。
橘氏が遺言に残したのはほぼ不動産ばかりで、この野毛山の土地、および、この焼け残った直方体の建物だけだった。そして、その遺言は、その三人に、この土地を三等分に分割して与えるように指示されていたのである。
三人は、土地をとりあえず分割した。
息子達の中で一番年長の男は、ここに建築物をたてたかった。次の男は、ここを売り払って、まとまった金に変えたがった。三番目の男は、ここに住みたがった。
しかし、どれにも障害があった。年長の男がほしがった場所のど真中には、ミス・シムスのマグノリアが咲いており、二番目と三番目の男がほしがった場所には、焼け残った建物が頑丈に建っていた。この建物は、橘カオルという女性に贈られることになっていて、二人はその女性の所在を求めたが、現在のところまったくもって不明だった。
遺言に残されなかった資産も曖昧で、その行方が知れない。
お互いゆきづまってしまったので、ガーデニア・シムスは、一つの突破口を開いた。つまり彼女は、近い将来アメリカに戻るつもりでいるので、マグノリアだけ譲り受け、故郷へ移植したいと申しでたのである。
異国の地が、日本で育った泰山木にとってよいものとは思えない。だが、元々米国から来た品種でもあるし、常緑樹で生命力も強い木だ。ムザムザと切り倒されたり、燃やされたりするよりはずっといいだろうという考えだった。
特に珍しい樹木という訳でもない、そこまで執着しなくても、と思われるかもしれないが、なかなかの大木であるし、懐かしき思い出の木、というのであれば仕方ない、と三人は納得し、移植のための工事が始まった。
だが、木の根元が掘り返された途端、そこでとんでもないものが発見された。遺産騒動は自動的にストップをかけられた。
と、いうのは――。
仰々しい身振りで語り続けていたミスター弁護士がそこで言葉を切ると、御手洗が面倒くさげに後を引き継いだ。
「つまり、その木の根元からあらわれた白骨死体が、鑑定の結果、幻の天才画家、橘花世氏と判明してしまった訳だ」
今まで黙っていたミス・シムスが、そこでようやく口を開いた。
《ええ。とてもショックでした。でも、それだけではないんです。……あの》
その時、玄関のチャイムが鳴った。
「どうやらこれで、やっと今夜の登場人物が皆そろうようですね」
ミスター・バーが立ち上がり、部屋を出て行った。
私は広い客間をあたらめて見回し、ミス・シムスに尋ねた。
「この家は昔、焼けたというお話でしたが、その後修理をしたんですか?」
南向きの窓は、よく磨かれている。人が住んでいてもおかしくないくらい片付いている。ミス・シムスは、かすかに首を傾げ、
《そうですね。以前とさして変わっていませんから、修理はなされたようです。この家にはもともと二階があって、そこの広い一部屋が、橘さんのアトリエになっていました。今はすっかりありませんから、その一部屋がまるごと焼け落ちてしまったのでしょうね。一階の防火対策がしっかりしていたのか、二階から火がでたのかわかりませんが》
ドアが勢いよく開いた。ミスター・バーが入ってきた。
「さあて、三人の秀麗な相続者の登場だ」
大男の後ろから入ってきたのは、確かにどれもやや日本人離れした雰囲気の漂う、痩身の美男子だった。それぞれ歳は違うが、面影が似通っている。
一番年かさの、たぶん五十代の初めだろうと思われる男が、私達に視線をちら、走らせ、最初に口を開いた。
「……こちらの方達は?」
あ、とミス・シムスが声をあげた。確かに説明が難しい。
だが、次の瞬間、御手洗はすっと立ち上がり、実に愛想のいい笑顔を浮かべると右手をさしだした。
「探偵屋で、御手洗といいます。シムスさんに頼まれて、橘カオルさんの行方を調査しているものです。頼りにはならないかもしれませんが、あなたに御迷惑はおかけしません。どうぞお見知りおきを」
ひどく、腰が低い。
私は驚いた。御手洗が口からでまかせをいうのは珍しくないが、今まで他人にむけてこんなに芝居がかった卑屈な様子をしてみせたことが、少しでもあったろうか。
だが、年長の男はミス・シムスと慇懃な御手洗を見比べると、豊かな頬にゆったりした笑みを浮かべ、納得のいったようにうなずいた。
「それはどうも御丁寧に。私は一応医者の端くれで、榊原総司といいます。いや、私の方でも、そのカオルさんとやらを捜してもらってはいるんですがね。この建物が処分できれば、土地の分割もすっきりといって、後味もいいので」
まっすぐに手を差しだして、しっかりと御手洗の手を握る。物慣れた見事な握手である。
突然、隣の撫で肩の男がしゃがれ声で呟いた。
「いや、できれば持ち主なんぞ見つけないで欲しいよ。この建物、なかなか興味深いんでね」
これはやや年が下がって、私達より少し年上、四十代の半ばを過ぎているかどうかといった感じの男だ。削げたような頬、意志的な強い目つきがその容貌を際だたせている。年の割には身体つきが少年のようにアンバランスで、芸術家風な妖しい魅力を醸し出している。
「高見沢君はこの土地はいらない、といったじゃないか。どういうつもりなんだ」
高見沢と呼ばれた男は、細い肩をすくめ、
「ああ。確かに土地はいらない。ただ、それに見合った分の金がもらえるならもらう、というだけの話でね。今更ケチなことは言いたくないんだ」
と彼が嘘ぶいたところで、一番若い、まだ青年とでもいうべき男が、のんきらしい口調で辛辣な台詞を吐いた。
「いまさら互いの強欲さを隠す必要もないでしょう。今日だって、この家が使いものになるかどうかを皆で見にきたんじゃないですか。カオルって人が現れないことをあてこんで」
「柳田君、それは言い過ぎだ」
榊原氏がとがめるような声をあげると、柳田青年はニヤッと笑った。ゆるく巻いた髪が青白く濡れたような頬にかかって、ぞっとするような凄味のある美青年だ。
「そうかな、別にリンショクは罪じゃないのにな。……さあ、もう一度みんなで見てまわりましょうよ。たいした資産価値のある家とも思えないけど。だから、僕があずかりましょうっていってるのに」
「だが、この家は橘の仕事場だったんだ。ただ普通に住むにはそうとう不便だぞ」
高見沢氏がひきとると、柳田青年は先に立ってドアを開けた。
「僕はそれでもいいんだよ。……じゃあ、回りましょう。さあ、皆さん御一緒に」
「そうしましょう」
そう言ってミスター弁護士は男達を追い出すと、私達に目配せした。どうしますか、ということらしい。御手洗を振り返ると、ああ、とうなずいて、
「一緒に話をきくことにしよう。欲望に正直な普通の人達ばかりで、実に面白いからね」
私より先にドアノブを握った。
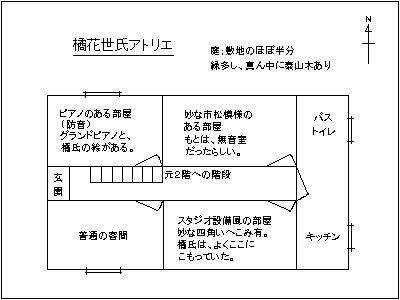
この家には、四つの部屋があった。玄関を入ると、田の字形に並んだ部屋の、向かって右の手前が、今いた客間、その奥は、何にもない部屋だった。まん中に、大きな四角いくぼみのあるばかり、窓もない部屋だった。
「ああ、ここは昔、スタジオみたいな部屋だったんだよ。床が、今でいうフローリングでさ。橘さんが一番気に入ってた部屋だったよ。よく籠ってたみたいだった」
皆が検分しているところで、またぞろ柳田青年が、独り言にしては大きな声でいった。高見沢氏が眉を寄せた。
「なんでそんなことがわかる」
「だって昔、よく遊びに来たからね。僕、橘さん好きだったし。あの人、面白い人でさ、ねだれば何だってしてくれたよ。かくれんぼだって、ままごとだって。夏は水遊び、冬は焚火、懐かしい遊びにはことかかない人だった」
「そうかい」
高見沢氏は苦虫を噛み潰した表情になり、そっぽをむいた。
榊原氏が、苦笑しながらとりなす。
「橘花世という男は、確かにこう、不思議な魅力のある男だったよ。堅物のうちの母親が惚れこんだぐらいだから、相当にね」
「へえ、榊原さんは、やっぱり橘さんにかわいがってもらったクチかい?」
白痴めくだらしない笑みを浮かべて、柳田青年は尋ねる。 榊原氏は小さく咳払いをすると、首をふった。
「いや。そういうことはない。私はそんな風に無邪気に遊んでもらったことはなかったよ。うちの母親に出会った頃には、もう画の勉強を始めていて、二、三の画商に才能を認められてはいたものの、絵かきというよりはむしろ詩人といったほうがいいような人でね……」
遠い目をして声を低める。
「本当に極端な夢想家で、仕事をするよりは寝ころんで夢をみている時間の方が多いというような人だった。ひどい移り気で、何かに夢中になるかと思うとすぐ飽きて、次の日になると見向きもしない。繊細にして熱烈、執拗にして冷酷、頭は切れるが、正しい興味の方向を持たない……要するに、生まれながらにして、あらゆる悪魔的なものを身につけた、天性のシラノ・ド・ベルジュラックとでもいうべきひとだった」
どうやら榊原氏はかなりの文学青年だったらしい。柳田青年は無邪気に喜んで、
「わあ、華麗な賛辞だ。昔の小説の主人公並だね」
すると、高見沢氏がますますヒネて、
「なんだ、結局とんでもない悪党じゃないか。誉めるとこなんかありゃしない。嫌な奴だよ。しょっちゅう甘ったるい鼻にかかったしゃべり方をしやがって、言葉尻もハッキリしないし、ガラクタばかりに興味を持って、子供じみた奴だったじゃないか。何を考えて生きてるんだかわからない、妙ちきりんな奴だったよ」
柳田青年はおや、と首を傾げ、
「そうかなあ。僕はいかにも繊細な芸術家って感じがして好きだったよ。確かに子供っぽい人だったかもしれないけど。僕はあの人に諸行無常とか、もののあわれとか教わったんだよ。秋の風情とか、お祭りの面白さとか、はかなさとか」
「もののあわれだって? あんな男がか、いい加減にしろ」
そのままいくと喧嘩になりそうななので、榊原氏が割って入る。
「おいおい君たち、喧嘩するためにきたんじゃないだろう。さあ、次の部屋にいこう」
とりなしが無事すむと、皆揃って、向かって左手奥の部屋に移動した。ここも窓がなく、壁に一面、妙なブロック跡がついている。
「この部屋には、いれてもらったことなかったな。なんだったんだろう」
柳田青年が首をひねると、高見沢氏が鼻で笑った。
「ここは、旧式の無音室だったんだ」
「きたこと、あるの?」
「来たことがなくても、このブロック跡をみればわかる。これでも舞台建築で飯を喰ってるんだからな。音響の知識は初歩だ。いいか、こういう風に木の板を組むと、音が全部すいこまれて、何にも聞こえなくなるのさ。だいたい、二十年くらい前は、こういう部屋が最新だったろう」
「なるほど、橘さんという人は、音楽関係に広く興味のある方だったんですね」
私はついうっかり口を挟んでしまい、皆をぎょっと振り向かせてしまった。
気まずい沈黙が流れる。
その中で、榊原氏が、ああ、と鷹揚にうなずいて、
「そういえば、そういう嗜好もあったようだな。あの人はピアノが好きで、趣味でよく弾いていたらしいが、ここにも置いてあるんだろうか」
ミス・シムスが返事をした。
《ありますわ。残っています。音がでるかどうかわかりませんが。古いものですし、調律もされていないでしょうから》
「へえ、残ってるの」
柳田青年が先に立って、ふらふらと部屋を出て行く。皆も続く。
最後の部屋には、確かに立派なグランドピアノがおかれていた。高見沢氏がすっと寄っていって、サーッと鍵盤を撫でる。
「ふん、オーソドックスにスタインウェイか。多少音は狂ってるが、手入れをすれば充分に弾けるな」
高見沢氏は椅子に座り、いくつかの和音をパアンと響かせた。その後、ちょっと肩をそびやかすと、聞き覚えのあるメロディを器用に弾き始めた。その幾つかは古い唱歌だった。
「ああ。橘さんの好きだった……」
榊原氏が呟く。
ふと気づくと、低い歌声が唱和している。ミス・シムスが、英語で歌っているのだった。ほうけたように見とれていると、御手洗がすかさず耳打ちしてきた。
「『庭の千草』は、元はアイルランドの歌なんだよ」
《この夏の最後の薔薇です、どうぞ手触れずそのままに/美しい仲間の花は、皆散り消えてしまいました/近しいものも幼いものも、皆ここにはないのです/容色を誇ろうにも、嘆息をつこうにも、もはや誰もいないのです》
聞き惚れていると、御手洗に再びつつかれた。
「見てみろよ、石岡君。どうやらあれが橘氏らしい」
見ると、奥の壁に大きな絵が掛かっていた。流麗かつ写実的なタッチの細密な肖像画が、壁にきっちりはめこまれている。その中にいるのは、いささか時代がかった壮年の男だ――すらりとした長身を椅子の中にゆったりとのばし、暗い眼ざしで静かに暖炉の火を見つめている。無雑作なようでいて、実はどこにも隙のない身仕舞いの紳士の、悠々とまどろんだ姿である。
蒼白い額の下に霞んだような黒い眼があって、熱情と沈欝をあらわしている。頬は丁寧に剃られて、子供のようになめらかだ。すっきりとすがしい気品のある鼻と、かたちのいい口唇。顔にはどこか疲れたような色があるが、それは、この秀抜な面に一層の深味をあたえ、たとえようのないメランコリックな美しさをつくりあげていた。
「これは……門閥貴族の末裔かなんかかい、なんだか凄いな」
私がため息をつくと、御手洗は真面目にうなずいて、
「そのとおり。名門の血筋らしい。ただ、名だけでなく実もあったらしいな。社会的な信用や資産の運営能力はともかく、絵の才能は確かにある。実物は初めて見たが、なかなか大したものだ。この部屋が焼け残ったのは実に幸いだな」
声音に常ならぬ深い感嘆が含まれている。私は何故かムッときて、
「でも、こういう古典的でリアルな絵は一般受けもしにくいし、専門家にも軽んじられるよ。少なくとも僕は、橘花世なんて絵かきはきいたことがないね」
「そうか。橘氏の活躍時期は、まだ歴史になっていない、中途半端な古さなんだな。ま、君は実利的なイラストしか描かない男だし、路線が違う画家じゃ知らなくても無理はないねえ。だが、この種の品の良さを持つ世代は死に絶えて久しいし、また、古き良き時代を懐かしむ手合いは良くも悪くもいつまでも絶えないからね、もし橘氏の未公開の絵画が発見発掘された場合、どのくらいの値打ちがつけられるものかわからないな。一体、どのくらい残っている物なんだろう」
腹がたつ程ベタ誉めする。確かに橘という男、テクニックは確かだし、才能のある絵かきだったかもしれないが、この絵一枚では、判断は難しい。だいたい、自分の肖像をここまで美的に描くのは、ナルシズムの極みである。しかもこれが本当の美貌なら、なおさら嫌味な話ではないか。
「ふう」
一通り弾いて満足したらしく、高見沢氏は椅子を立った。
だが、その瞬間、にぶい爆発音が響いた。
「なんだ」
「あっ、あれは」
「畜生、ここでもか」
一同、色めきたつ。
なにか物が激しく打ちつけられる音がした。そして、地の底を這うような声が切れ切れに続いた。
《ああ。橘のおじさまの声》
ミス・シムスはすうっと青ざめて、弁護士氏にすがりついた。
「ああ……助けてくれ……誰だ、俺を閉じ込めたのは……そうか、アイツか……開けてくれ、カオル、助けてくれ、開けられないか、熱い……ああそうだ、やったのは、アアイアアオ、ウイイなんだ……だが、それは……いいか、それは……」
曖昧な言葉が途切れると、鈍い爆発音がたて続けに響いた。
「橘カオルか!」
榊原氏が叫んで、頭を抱えた。
「畜生、どこだ。どこに仕掛けがあるんだ」
高見沢氏は、ピアノの中に顔を突っ込み、中をかき回しかねない勢いで何かをさがし始めた。柳田青年はしばらくぼうっとつったっていたが、やがて感心したような声をあげた。
「うへえ。橘カオルだあ……」
「どういうことなんです」
弁護士氏が、ミス・シムスをかばいながら尋ねる。
「嫌がらせだよ。俺たちに対する。あんたたちのところにはこなかったのか」
高見沢氏が怒鳴る。
「畜生、見つからない。ピアノの裏蓋に反響してたんだな。スピーカーの類も見つからないなんて。そうか、絵の裏か?」
さっと壁際に寄ると、絵の縁を叩く。
とたん、絵が扉のように壁から離れ、その裏にぽっかり空洞があいた。そこには、極小のスピーカーがガムテープでがっちりとはりつけられている。
「なんだ、タイミングのよかった割には、凝った細工じゃない。時限式だ。俺達の動きを関知して動く、くらいのことをしてるかと思ったが」
高見沢氏がみんなにそれをみせびらかすと、ミス・シムスは息を飲んだ。悲鳴めく声が洩れる。
《ああ、厭! 誰が、いつの間にこんなことを》
ミス・シムスは両頬を押さえ、細い身体を震わせて気絶しかねない様子だ。ミスター弁護士はその肩に手を置き、
「ガーディニア、ここは空き家だし、入ろうと思えばどこからでも入れるんだ。落ち着きなさい。大したことじゃない」
御手洗が、肩をすくめて呟く。
「やっぱり僕らの出番なんか全然なさそうだぜ、石岡君」
《いいえ、石岡さん!》
ミス・シムスが、ミスター弁護士の手を逃れて、私の前にやってきた。
《あの、お願いです。私たちを助けて下さい。お願いです。ああいう類の嫌がらせが、ずっと続いているんです。ですから……》
御手洗は、それを冷たく遮った。
「シムスさん、私達の仕事は、ガードマンじゃないんです。そういうお役にはたちませんよ」
「御手洗」
慌ててとりなそうとすると、ミスター弁護士が寄ってきた。
「ガーディニア、とりあえず、皆さんで話をしよう。客間に戻ろう」
全員が客間に揃って戻る。
みんな目をギョロリとさせて、互いの顔を見合わせていたが、最初はやはり最年長の榊原氏が切り出した。
「実は私は、あんな嫌がらせを受けなくとも、もともとこの話には乗り気じゃなかったんだ。確かに労せず財産が増えるというのは嬉しいことではあるが、今のところ特に暮しに困っているという訳ではないし……こういうことは特に、やっかみを受けたり嫌味を言われたりするものでね、客商売にはマイナスになるんだ。税金の問題もあるし、子供へもいらぬとばっちりがいくし、余計な人間がつきまとってきたりもする。ましてや橘さんのように、行方不明で動産不動産のある人の相続人、となると、苦労をしょう事になるだろうと覚悟はしていた。だが、それにしても、こんな意味のない嫌がらせを受けるなんて……」
実は皆、同じ様な嫌がらせを揃って受けていたのだった。話し合いをすることで、それがはっきりとした。三人の息子たち、そしてミス・シムスは、先刻の声の入ったテープを、それぞれに送りつけられていた。……そして、その送り主の名は、《橘カオル》。
「橘カオルって奴はいったい何者なんだろう」
高見沢氏が口唇を噛む。
「だいたい何が目的なんだ。俺んとこには、大量のモルタルと一緒にこのテープを送ってきたんだ」
「モルタル?」
弁護士氏が聞きとがめると、高見沢氏は眉をあげ、
「ああ。壁の隙き間をうめるセメントみたいなものだよ」
「私のところには、風船が山程だ。水素の入った大きな風船が、大量に病院に送りつけられてきた」
榊原氏が額をおさえてうめくと、柳田青年がのんびりと続ける。
「あ、そういうのも良かったな。僕のとこはランプだ。ガンドウっていうのかな、覆いがかけてあって、振っても火の消えないランプが、幾つか来たよ。あれ、見覚えがあるんだけど、たぶん橘さんが使ってた奴と同じものじゃないかな」
「いったい何のつもりなんでしょうか」
弁護士氏が首をひねると、ミス・シムスも首を振る。
《わからないわ。私の所にも、その名前で、ツルハシと鍬が送られて来ました》
だが、御手洗はまだ黙っている。
私は自分が知りたいことを尋ねることにした。
「送り主が一緒だったんですよね。それは、橘カオルという人の所在の手がかりにはならなかったんですか?」
高見沢氏が即答した。
「もちろん調べたさ。でもわからなかった」
「電話一本で、なんでもできる時代だからね。送り主が幽霊だって、わかりゃしないよ」
柳田青年は嬉しそうにいった。
「そういやこの家、昔オバケが住んでたんだぜ。橘さん、そんなこといってたもん。この建物の前にあった建物で死人が出て、そのたたりだっていってた」
「馬鹿なことを」
榊原氏がたしなめる。嫌な予感のした私は、別の方面に話をもっていきたくなって、次の質問をした。
「あの、あのテープの声は、本当に橘さんという人の声なんでしょうか?」
高見沢氏が子細らしくうなずく。
「ああ。あのだらしないしゃべり方には憶えがある。機械をとおってるからわかりにくいが、たぶん本物だろう。ただ、この際問題なのは、誰がそんなテープを持ってるかってことだと思うがね」
ミスター弁護士がそれを受ける。
「で、その橘カオルという人は、本当にこの世に実在するのですか? その証拠が、あるのですか」
榊原氏が答える。
「ああ。いたことはいたらしい。遺言に指定された施設に、橘カオルという女の子が十年前にいたことは、確認されているんだよ。ただ、それ以降のことは……つまり、現在の橘カオルは行方不明だから、幽霊になっていようが、誰かが名をかたっていようが、まるでわからないんだ。だが、それにしても、その目的はいったい、何なのか」
皆、そこで考え込む。
御手洗は、相変わらず眉間に皺を寄せたまま黙りこくっている。
夜も更け、それ以上新しい情報も得られないので、三人の息子達は、また再来するということにして帰った。
ミス・シムスとミスター・バーも、それぞれ自分の家に帰るという。
「じゃあ、おいとましよう、石岡君」
さっさと行きかける御手洗に、ミス・シムスの細い声がかかった。
《あの、御手洗さん。ぶしつけとは思いますが、先程のお願いを……》
御手洗は、ひどく冷たい声で返事をした。
「それは、橘カオルさんの行方を、僕がさがせというようなお話ですか?」
《御無理でしょうか?》
「別に無理ではありません。ですが、あなたはそれで随分と嫌な思いをなさるかもしれませんよ。それでも、本当によろしいんですか?」
その慇懃さは無礼と言っていいほどのものだった。私はまた口を挟まざるをえなかった。
「おい、そんな言い方はないよ御手洗……いや、あの、シムスさん、何らかの思い出があるのはわかりますが、譲り受けた物を放棄することはできないんですか? たぶん、それがすべての原因なんじゃないかと思うんですが」
ミス・シムスは、灰色の瞳をじっと私に向けた。その目はわずかながら潤んでいた。
《石岡さん。それは、わかっています。でも、できないんです。どうぞご覧になって下さい。私のマグノリアを》
ミス・シムスは先に立って、庭を歩きだした。緑の豊かな、広々とした庭を。
《橘のおじさまは、あの、文字どおり、詩人でしたの。……夏のお祭りの夜でした。熱があって、外へ出られない私に、小さな四角い紙の箱を渡して、「ほうら、おまえの手の中にお祭りが踊っているよ」と。遠い夜の祭り囃しが、薄い紙箱に共鳴して、私の手の中で震えていました》
立ち止まると、くるりと振り向く。
《日本のもの、好きなもの、沢山ありました。ただ私は、お祭りは好きではありませんでした。すぐ死んでしまう金魚、空に飛んでいってしまう風船、消えてしまう花火、どれもはかない命の象徴のようで、好きになれませんでした。だから私は、いつまでもかわらない常盤木を愛しました。それで、橘のおじさまは、私にこの夏の木を下さったんです。どんな闇にも染まらない、どんな日差しにも耐えて、香り高い白い大きな花を咲かせるマグノリアを》
そこには、白いロープに囲まれた大木が立っていた。
遠い街灯のひかりを浴びて、思いきり生い茂っている、濃い緑の葉。何百年を経てきたのか、一抱えもある灰色の幹。
見ると、宵闇に浮かぶその花はさらしたような白さだ。本当に風雨にさらされたしゃれこうべを思わせる程に白い。その太い根の先は、鋭敏な触手となって、橘というやさしげな男の肌を吸い、その腐肉にすべりこみ、その躰のありとあらゆる場所にまとわりついて、長い年月、ゆるゆると滋養をひきあげていたのである。当世の幻想作家さながらの妄想を思い浮かべ、私の背筋は凍りついた。
《御手洗先生。私はこの木が、どうしても欲しいのです》
灰色の目が、強い熱情を物語っていた。
後ろで御手洗が、深いため息をついた。
「わかりました。ここまで来たんだ。なるべくあなたのご希望に添うようにしましょう」
「御手洗」
《ああ。ありがとうございます。よろしくお願いします》
ミス・シムスは泣きださんばかりの顔になって、何度も頭を下げ、そしてミスター弁護士に伴われて帰っていった。
私たちも連れだって帰途についた。
御手洗は相変わらず表情が硬い。私は不安になって、
「なんだか気のすすまないところにひっぱりだして、申し訳なかった」
思い切って下手にでると、また、実に彼らしくないか弱い微笑をしてみせる。
「いや。いいんだよ。僕も思うところがあるからね。……石岡君こそ、いいのかい?」
「何が?」
「君がいつになく熱心だから、心配なんだ」
「え? どういう意味だい」
御手洗はいい淀んだ。
「だから……なんていったらいいか……例えば君、あの気障なペリィ・メイスン君をどう思う? いや、つまり下司な言葉で言えば、ライバルとして……」
驚いて、私はまじまじと御手洗の顔を見つめた。本当に下司な意味でいっているのでもないらしい。
確かに、私は、ミス・シムスの美質に強くひかれている。しかしそれは、御手洗に心配してもらうような事ではない。
「厭だなあ、淑女を助けるのが紳士の仕事だよ。そんなことをやっかんでも、しかたないじゃないか」
御手洗は、ガクンと肩を落とした。
「そうか。そういうつもりでいるのか。……ならいい。彼女の期待に素直に答えてやることにしよう」
そういって頬を撫で、顔色を整える。
今回の御手洗は本当におかしかった。
私はまだその理由を掴めずにいて、彼のいたわりにただ感謝していた。
3.
「畜生、全く、つくづく因果な商売だなあ」
御手洗はその午後、突然そんなことを呟いた。
はぐっていた書類を投げ出すと、どんとソファにもたれかかり、背もたれの上に組んだ腕に細い顎を埋めた。ダダをこねる子供よろしく、ひどく不機嫌な顔をしている。
「いったいどうしたんだ、御手洗」
「探偵屋ってのはやっぱり卑しい職業だよ。人死にを食い物にしてるのに、それを積極的に防ぐでもない。苦しむ人間の叫びをただ面白がって弄んで、ろくな後始末もできはしないんだ。こういう仕事をしてていったい何になるっていうんだ」
「おい御手洗、大丈夫か、疲れてるのか? まさか、悪い病気にかかったんじゃないだろうな」
とてつもなく弱気の発言に、私は驚き慌てた。こんな愚痴を聞くのは初めてだ。害になるほど溢れかえっていた普段の自信は一体どこに消えたんだ? 不惑を越えて、かえって惑うようになったか?
確かに近頃、実にいろいろな種類の事件がこの馬車道の事務所に持ち込まれている。それぞれ猟奇だったり陰惨だったり、気の滅入るようなものが少なくなかった。だが、この様子のおかしさは、この間の事件、つまりミス・シムスと関わってからの事なのである。あの事件がいったい、この男にどんな災厄をもたらしたというのだろう。
御手洗は私の思惑をしってかしらずか、浮かぬ顔のままで返事をする。
「いや、平気だ。疲れてもいない。ただねえ……ねえ、石岡君、犯罪っていうものがいったいなんなのか、君、わかるかい?」
「急にそんな曖昧なことを言われても……どういう犯罪のことだい?」
「僕が興味を持てる類の事件は、いくつかある。だが、その中にもうまく扱いかねる事件がある。純粋芸術としての犯罪、自己表現としての犯罪だ」
そこでソファからむくりと身を起こし、
「美しい犯罪というのは、孤独で我が侭な王者の叫びだ。『我を認めよ』『我を止めよ』『我を抹殺してみよ』。……それは、誰にも救うことができない犯罪なんだ。低俗な利益を求めない、純粋な意図をもった犯罪者に対してはみな無力だ。もちろん今まで、そういう事件を扱ってこなかった訳じゃない。だが、僕の柄じゃないんだ。こういうものを扱えるのは確かに、チェスタトンの小説にでてくる探偵屋くらいだろうからね」
立ち上がって、部屋の中を歩き出す。
「だが、本当に扱えなくていいんだろうか? 事件そのものはひどく簡単だっていうのに。手がかりがありすぎてウンザリするとはいえ、受けてたった勝負を投げ出すのはポリシーに反する。いくら自分の嗜好と違うといったって……。ふむ、とにかく出かけよう、石岡君」
急に出仕度を始める。私も慌てて立ち上がる。
「おい、いったいどこへいくんだい」
「例の、ミス・シムスの日本の弁護士のとこだ。柏木って名前だったな」
「え、その人がどこに住んでるのか知ってるのかい」
御手洗はきっと眉根を寄せ、
「君もたいがい失敬だなあ。今、言ったろう? 一度頼まれた仕事だ、他の仕事と並行しながらちゃんと進めてるよ。橘カオルは誰だとか、不審な人間の背後関係を調べるとか、基本的なところは押さえてあるさ。なにしろ、押さえざるをえないんだからね」
一瞬パッと怒ったが、すぐふてくされたような顔になり、低い声でぶつぶつと呟き始める。
「でも、さすがにいやんなるな。自分が動かないのに、向こうからいろいろと手がかりが押し寄せてくる事件なんてのは。まあ、探偵冥利につきるというべきで光栄な事なのかもしれないが。だが、汚水のたっぷり入ったビニール袋を針であちこちつついてまわる真似は、そろそろ御免こうむりたいね。……まあいい、とにかく行ってみることだ」
善は急げの勢いで飛び出した彼を追って、さっそく京浜東北線に乗る。
うまく隅のボックス席をせしめると、御手洗はそれを待ちかねたように、先刻眺めていた書類をすいとこちらへ押しやった。
「君の言うとおり、この事件に関しては僕は手を抜いているかもしれない。さすがにアメリカまで行く気はしなかったし。……ああ、余計な心配はいらないよ。信頼のおける筋に頼んでつくってもらった報告書だ」
きれいにタイプされたその書類はすべて英語で、私は一瞬とまどったが、表紙に大きく『ミス・シムスに関する身上書』と書いてあるのを見てとると、意を決して中身をめくった。
――S・ガーデニア・シムス。オクラホマ州タルサの近くの小さな町で生まれる。母親は日系人、彼女を出産後死亡。父親は不明。幼年期の資料無し。二重国籍者だったが、十八の年にアメリカ国籍を選ぶ。E大学を優秀な成績で卒業後、言語学(音韻論)で博士号をとり、二年前来日、K大学講師となる。――
「御手洗、これはいったい?」
何を読み取れというつもりかわからず、曖昧な質問を返すと、御手洗はあいかわらずの浮かぬ顔で、
「別に。どうということはない。ただ、こういう少ない事実にも、メロドラマというのは透けて見えるってことさ」
「え? どういうメロドラマだい?」
「ちょっとでも自分で考えてみろよ。そのプロフィールだけでも、いろいろ想像できるだろう? タルサの側の小さい町ってだけでね。だいたいアメリカ南部の田舎町なんて、昔はどこも似たようなもんだ。ひたすら乾いただだっぴろい荒野にぽつりぽつりとあばら家があって、埃にまみれた住民が目ばかりギョロギョロ光らせて暮らしてるんだぜ。人間性のすさむ土地柄だよ。大人も子供も、日本の昔の田舎よりよっぽど閉鎖的で、醜くせせこましい人間関係に縛られてる。おかげで、若者はグレるか都会におん出ていくかしかないから、まともな働き手もいないような有様だ。それに、華やかな娯楽に欠けるから、互いのゴシップを徹底的に暴き出してそれを楽しむようになる。……現在でもたいして状況は変わってやしないさ。自由平等の国アメリカ、のキャッチフレーズはどこへやら、あいかわらずの人種差別の世界だ。政府のお仕着せの混合政策なんて付け焼き刃にすぎない。そういう街で、日系人が私生児を産むという状況が、どれだけ白い目で見られたか分からないかい? その子供がどんな酷い目にあったかってことに、少しでも想像が及ばないかねえ?」
「それじゃ、彼女の少女時代は……」
「少なくとも、生い立ちは幸せなものじゃなかったろう。僕らの想像が当たってないことを祈りたいくらいにね」
御手洗は再び言葉少なになり、物思いに沈んだ。
今日の尋ね人はたやすく見つかった。その弁護士事務所は、都心から少し離れた、わかりやすい一角にあった。浅草の駅から近く、墨田川を背にした赤レンガの雑居ビルの四階に、その人はいた。
柏木弁護士なる人は、今すぐ引退すべきではないかと思われるほど高齢の男性だった。年の割には非常に元気で、しゃべり方もまともだが、実際ほぼ隠居状態といってもいいのだろう、アポイントメントもないのに、すぐにあってくれたのが、そのいい証拠だ。
御手洗は人当たりのよい笑みを浮かべ、柏木氏と握手をしながら、
「どうも。シムスさんから仕事の依頼を受けている御手洗というものです。……その後ろの作品、橘画伯のものですね」
途端、柏木氏は相好を崩した。
文字どおり、顔がそのまま崩れてしまいそうなほどの笑みをうかべて、好々爺は椅子の後ろにかけられた絵を見上げた。
「ああ、そうです。《まぼろしのひと》という作品で、橘の後半の作風とその特徴を、よくあらわしているものです」
額縁の暗闇の中に、白と金色の炎が大きく燃えている。
その、ゴッホのような凄さまじいほむらの中に、一人の女性が浮かびあがっている。揺らめく火の手に輪郭が霞んでいるが、豊かな黒髪が裸身にそって流れ落ち、女性の静かな重量を示している。引き締められた口唇は、シンとした芯の強さを示しているが、足元は実に頼りなさげ、うつろな瞳は、彼女の深い心の闇を思わせる。
その構図は西欧の世紀末の画家が好んで描いたようなものであったが、印象派風の淡い繊細なテクニックと、野獣派風の大胆でくっきりとしたタッチが巧みに融合されており、独自の世界を築いていた。モデルの圧倒的な存在感と、画家の対象へのおそるべき気迫と情熱が、見るものに一種の沈黙を強いる。
御手洗はそれをつくづく眺め、感にたえないといった様子で話を切り出す。
「本当に全く素晴らしいタブローだ。……柏木さんは、旧制中学の頃、橘画伯の同期だったそうですね。余程親しかったんですか」
「ええ、まあ友人といえる立場にありました」
「ああ、素晴らしい事だ。橘氏の人となりについてお話をうかがえるかと思うと、僕は昨日の夜はよく眠れなかったほどです」
柏木氏は満足そうにうなずいて、私達に椅子をすすめた。
「いや、橘は、作品はともかく、私生活は特に誉められるところはなかった男ですよ。奇癖や奇行のある絵描きといわれたこともあったが、たいしたことはしていなかった。生き物や植物やらを部屋に持ち込んで人を驚かすとか、子どもっぽい悪戯は好きでしたがね。夜歩きが好きで、あまり昼日中は外へでない男ではありましたがね」
御手洗はそれこそ身を乗り出すようにして、相づちを打つ。
「なるほど、夜の夢こそまこと、というタイプの芸術家だった訳ですね」
柏木氏は面白そうにガラガラと喉を鳴らし、
「あはあ、橘の夜歩きはそんな風情のあるものじゃあないです。結局女遊びなんだから。……まあ、よくある類のドンファンなんだが、実際、女の敵の中で橘以上に恐ろしい相手はいないでしょうね。恋の幻想の一番甘い部分をくすぐるのがウマくて、どんな女でもうち勝つことができない。騙されていると知りつつ、皆そのまま滅ぼされていってしまうんだから」
「だが、滅ぼされるといっても、関係のあった女性がみな死んでしまった訳でもないんでしょう?」
御手洗の目がキラリと光る。
柏木氏はおもむろに書類の束を持ちだすと、それを繰りつつ、声の調子を落として続けた。
「つみとられた花は、結局すぐにしおれてしまうものですよ。昨今のたくましい娘さん達はどうだかしらないが、昔のお嬢さん方は、世をはかなんで死ぬ、という美学を持ちあわせておりましてね。そこまではいかなくとも、ひどく気落ちして、そのまま人生を転落していった方もかなりいたようでしたよ。……あれはとにかく落ち着いて暮らせない男でね、三人残っている息子達にしろ、橘を親とは思っていないでしょう。ただ、一番年長の榊原総司という男の母親は、七十を越えてるんだが健在で、息子と一緒に現役で医者をやっていますね」
「優秀な女医さん、という訳ですね」
「ええ。専門は耳鼻咽喉科で、榊原医院という名でやっています。総司は手狭な医院をどうにかしたくて、今回の相続に乗り気になっているんだな」
「高見沢や柳田は、どういう様子なんですか」
柏木氏は眼鏡をひからせ、書類に素早く指を走らせながら、
「高見沢公樹は、母親が死んでいる。ごく最近のことですが、急に倒れてそのまんま、という形で亡くなっている。名のある女性建築家だったそうですが、御存知ですかな? ウーマン・リブというか女性運動の闘士だったとかで、流行りの言葉でいえば、過労死という奴ですな。高見沢は仕事もうまくいっていますし、ほぼ遺産相続に興味はないようで、むしろ関係者を少し困らせたいだけのようです。柳田亮一の母親もこの世の人ではありません。ああ、これは嫌な死に方をしている。この女性は、日本でも有数の腕のいいオルゴール職人だったそうで、仕事でスイスに招かれた時に飛行機が落ちて亡くなっていますよ。そう、これは二年前の話だ。亮一は相続に熱心ですが、母親の保険金がおりているので、金に困っている様子はありませんな。だからといって、別にぶらぶらしてる訳でもない。勤め先の精密機械のメーカーで真面目にやっているようです」
きわめて要領のよい答え方で、かつての敏腕弁護士ぶりが目に見えるようだった。御手洗はその勢いにつられるように、重ねてたずねる。
「ではもう一つ、もう一人の遺産相続者、橘カオルという女性のことをおききしたいのですが」
柏木氏は眼鏡の縁を押し上げると、書類から顔をあげた。
「ああ。カオルのことですか。……私もそちらは詳しくは知らないんですよ。あったこともないのでね。話だけはききましたが、どうやら近くの孤児院にいた女の子らしい。橘は意外に子供好きで、その手の施設によく出かけていたんです。ただ、財産を残すほど執着したのは初めてでしたがね。名前までつけてやったそうですから。それならいっそ養女にすればいいのに、といったんですが、それでは目的と違う、といって譲りませんでね」
「目的?」
「ああ、説明が必要ですな。……私が橘の遺言の相談にのったのは、火事騒ぎ、つまり失踪する少し前のことでした。財産の始末は若いうちにできるだけしておいたほうがいいだろうな、といってね。自分は放浪流浪の生活しか送れない性質で、いつどこで何が起こるかわからないから、それぞれ自分に関係のある人間に、家族の絆などと不確かなものでなくて、きちんと何かを残しておきたい、といったんですよ」
御手洗は眉間に深い皺を寄せ、
「それはつまり、橘画伯が自分の死を予感していたというような意味でしょうか」
「いや、それはわかりません。もともと蒲柳の質というか、この世のはかなさを常に憂いているような男でしたからね。それに、自分の父親の死んだ年齢を越えたこともあったのでしょう」
「父親?」
「ええ。橘の父親は火事でなくなっていましてね。四十年も前の話ですが……戦争でも焼け残り、接収もまぬがれた屋敷なのに、何もかも全部燃えてしまって。まだ若かったあいつは、一時期途方に暮れきっていましたね」
御手洗は険しい顔のままうなずき、
「若い頃に父親をなくして……それはさぞ苦労なさったんでしょうね」
「いや、そういう意味ではないんですよ、二十歳はこえていましたし、絵かきの才能も萌えだしていましたから、金銭的な苦労などもさしてなかったんでしょうがね。父親を慕う心も薄い男でしたしね……」
「おや、では家庭的に不幸せなひとだったんですか?」
「いや、そういう訳でもなかったのですが……ただ、橘子爵という人は女癖のよくない人でね。花世という嫡子があるというのに、いろいろと女をつくってね。家にいれても、すぐに飽きて放り出してしまう、つまり始末のよくない人で、火事の時の花世の母親は、確か三人目の母でした。ミヤさん、とかいったな。西の田舎の方の育ちでしたが、気性のまっすぐな、しっかりした女性でしたねえ。子爵と一緒に火事に巻き込まれて死んでしまって、実に気の毒なことでした。家族愛に憧れていた花世は、自分と年の近い美耶さんにも肉親に向けるような愛情を寄せていて、その落胆ぶりは端で見ている方も胸が痛むほどでした」
柏木氏はその時を思いだしたらしく、恐ろしく悲痛な表情になった。御手洗も深いため息でそれに応え、
「ああ、そこまで感情の深い方だったんですね。……ですがそれなら、なぜ結婚せず、自分の家庭をきちんと築こうとしなかったんでしょうかね?」
「さあ……ただ、冷たい家庭に育ったものは、往々にして暖かい家庭をつくるのが難しいようですよ。橘は基本的に身勝手な男でしたしねえ。だいたいあいつが子供達に何か残すのなら、絵を残すべきだったんだ。いくら資産価値の不定なものとはいえ、ご覧になればおわかりでしょうが、一財産になるだけのものを橘は描いていたんです。それをいたずらに散逸させてしまって……行方不明の作品も多いんですよ」
「それは、全くもったいないことだ。僕も実に残念に思いますよ」
御手洗はその後も、橘花世という絵かきをこれでもかと誉めちぎり、丁寧に老弁護士に礼を述べると、事務所を辞した。
御手洗はまたぞろ無言になり、さっさと先を歩いていく。いつもの沈思黙考だ。ただ、通常の憑かれたような熱狂でなく、ただより深い淵に沈んでいくような様子なのが気にかかる。
「御手洗、今日の収穫は……どうだったんだい」
後ろからおそるおそる声をかけると、ぱっと急に振り向いた。私の鼻先にトンと指先をつきつけると、すさまじい勢いで、
「いいかい石岡君。この事件は、本当に、ひどく簡単なものなんだ。一つ一つポイントを整理してみれば、どんな乏しい想像力の持ち主でも真相がわかる。真実を見抜きたいという気持ちがある人間なら、誰でもわかるものなだよ」
それに押されて私は戸惑い、
「え、あ……その、ポイントっていうのはなんだい」
「だから、この事件の謎の部分のことさ。それを取り上げて見ていけば、輪郭がはっきりしてくるじゃないか」
御手洗は指を折りながら幼い子供に教え諭すような口調で、
「一つ。この事件は、十五年後の今になって、何故いきなり明らかになったのか。一つ。どうして誰も、橘カオルという人間を見も知らないのか。一つ。橘カオルという女性の目的はいったいなんなのか。一つ。どうしてあの嫌がらせのテープの意味はなにか。あんな目的も不明な中途半端なものと、ツルハシだの風船だのランプだの、というとりとめのない品物を併せて送ってくる脅迫の意味は、全体なんなのか。一つ。どうしてガーデニア・シムスという女性は、あんなにマグノリアに執着するのか」
全部手指を握りこんでしまうと、その拳をパンと左手にうちつけ、
「僕には見えるようだよ、橘花世という男の生涯が。才はあり心根も優しいが、幼くて、舌たらずで、沢山の人間を傷つけながらも、愛され、慕われて……だが、結局は孤独であった男の姿が。全く気の毒な話だ。なぜ、そうまでして恋愛に夢を見なければならない? 相手を実物大で見られない? 全く、人が、家庭や家族というものにそうまで過大な幻想を抱かなければ、偏見で他人を押し潰さなければ、この手の事件はきっとほとんど起こらないんだろうに!」
「御手洗」
その興奮の暗さに、私は口を挟もうにも挟めなかった。
「世の不幸というのはこうやって脈々と受け継がれていくんだ。一昔前のような事件が、時代遅れの幽霊話のようにはびこっている。畜生、なんて下らない話なんだ!」
そう言い捨てると、御手洗は再びくるりと身を反転させてさっさと歩きだした。
「御手洗、おい、御手洗」
その夜、御手洗は口をきかなかった。
4.
そんな訳で、九月に入った頃の御手洗は原因不明の憂愁に閉ざされて、活動をだいぶ停滞させていた。
ただ、他にもいくつかの事件を抱えているために事務所に蟄居している訳にもいかなかった。必然的な外歩きはいくらか彼の気持ちをまぎらわしたらしく、数日後の夕暮れには、愚痴をこぼしながらもだいぶ穏やかな顔になっていた。
「石岡君、こう気味の悪い事件が多いのは、やはり世紀末ゆえなのかもしれないね。一見、世相は明るく清潔で、みな優雅にすごしているように見えるが、それは全くうわっつらだけの話だ。例えば労働条件は一世紀前よりも悪化している。時間の密度は無意味に高まり、快適な環境はすべて汚染され、癒えない疲れは増え続ける。派手なショウライトのまぶしさに、影のあるべき場所にその影が見えず、人工の闇を求めて苦しむ人間が現れる。それとは知らず、つもり積もらせた心の闇を抱えた人間が、さらに不気味な得体のしれない事件をうみだしてゆく。薄ら笑って暗躍する連中のみならず、はじきだされた弱いものが、さらに弱いものを圧迫して……これは、どう考えても悪循環だよ」
そういいながらデスクの角を曲がった時、卓上の電話が鳴りだした。
「はい」
御手洗はとっさに受話器をとる。相手の声を聞いた途端、キリ、と真顔になった。
「今晩、そちらへうかがえばいい訳ですね。わかりました。ですが、重ねてお尋ねしますが、本当に構わないんですね、この僕がその場で事件の真相を話してしまっても……? ええ、わかりました。それでは」
受話器を置くと、スイと上着を取り上げる。
「石岡君。でかけるよ」
「どこへ?」
「聞こえただろう? ミス・シムスのところだ。これから来いってさ」
私もすぐに上着をとり、御手洗の後に続いた。
この数日で残暑は急激になりをひそめ、黄昏時の町にはぐっと冷たい風が吹いている。私は歩きながら奇妙な寒気をおぼえ、それをまぎらわすように先行者に話しかけた。
「御手洗、一つききたかったんだが……君は今回の事件にひどく気乗り薄だったのに、どうして引き受けたんだい」
御手洗は振り向きもせず、呟くような声で返事をした。
「いったろう? これは本来の僕の事件じゃないんだ。むしろ、僕が台なしにした事件とさえいえる。でも、仕方なかったんだ。ここまでやったんだし、とにかく僕がいくしかないんだ。ああ、本当に嫌な類の不幸だよ」
不幸?
御手洗がこの件に関してここまで逡巡するのは何故なんだ?この事件はいったい、なんだというんだ?
整理すれば、確かに要素の少ない事件だ。放浪画家の十五年前の失踪。そして、今夏の死体の発見。うまくいかない遺産相続と、謎の女性による奇妙な嫌がらせ。
思い返して浮かぶイメージは、華やかな生涯を送った絵描きの末路のはかなさ、残された者達の不可思議な未練、そして、白い花を執拗に求める美貌の学者。
そう、ミス・シムスは、うつろうものより永遠不変を好む。頼りにならない人間の情よりも、常緑樹の生き生きとした生命に対して、深すぎるほどの愛着を持っている。それはつまり……?
次の瞬間、私は思わず口走っていた。
「御手洗、犯人はミス・シムスじゃないよ。彼女はその頃まだ子供だったんじゃないか。絶対に荒事は無理だよ」
御手洗は急に足をとめ、ゆっくりと振り返った。
「……そうかい? 君は、本当に、そう思うのかい? 彼女に、そういう類の事は、全く不可能だと? あのラ・ベル・ダン・サン・メルシ――無情の女がかい?」
その目にはなんの表情も浮かんでいなかった。柏木弁護士の事務所で見た絵の女性のような、おそろしく虚ろな瞳で私を見返す。ぞっと背筋が凍りつく。
「御手洗……」
「何にせよ、ここまで来たら決着をつけるのが筋だよ。そうだろう、石岡君」
私は返事が出来なかった。御手洗はつい、と視線をそらすと、歩調を戻してさっさと歩き始めた。
灰色の廃屋は、薄青い夕暮れの空の色にしっとりと沈んで、思わぬ風情で待っていた。
ドアをトントンと叩くと、ミスター弁護士、ことアレキサンダー・バー氏がひょっこり顔を出す。
「ああ、あなた達が先に来て下さったんですね」
「ミス・シムスはどこです」
御手洗は詰問口調で応じる。
「部屋にいますよ」
弁護士氏は先にたって、ピアノのある部屋の扉を開けた。
重たい鍵の音に、たどたどしい歌声。
それは、ミス・シムスのものだった。
「ウゥミノォヒノ、シズゥムヲミィレバァ、タァギリオツイキョウノナァミィダ……オモォイヤル、ヤエノシィォジィオ、イィズレノヒニィカ、クニィニカエラァアン」
唱歌『椰子の実』だった。
細い指は所々もつれるが、それがかえってこの曲の物哀しい情緒を醸し出している。曖昧な発音は、幼い子供が悲しみにくれながらも懸命に歌っているようで、さらに胸に迫る。
ピアノが鳴りやむと、ミスター弁護士は彼女に静かに声をかけた。
「ガーディニア、探偵さん達が来たよ」
彼女は立ち上がり、一礼した。
《ありがとうございます。来て下さったんですね》
御手洗は重々しくうなずき、
「お招きにあずかりまして。……で、例の三人は?」
《もうすぐ、来ます》
ミス・シムスも、思い詰めたような顔で応える。
「本当に、いいんですね」
《おまかせします》
その時ドアが開いて、榊原氏が入って来た。後ろに高見沢氏と柳田君がいる。
「失礼、橘カオルの居場所がわかったっていうのは、本当ですか」
御手洗が、片手をあげて返事をした。
「ええ。私が発見しました。詳しいお話をしたいと思います。居間へ戻りましょう」
先日のように居間に入り、全員が腰を下ろすと、御手洗は一人立ち上がり、ミス・シムスの座った椅子の脇へ行くと、冷たい声で一言、
「ミス・ガーディニア・シムス、あなたは、いざとなったら、殺人も辞さない予定でしたね」
彼女は細い首を伸ばし、御手洗を見上げて恐ろしい台詞を呟いた。
《ええ。……もう、一人や二人殺しても、と思っていました。あなたのおかげで出来ませんでしたが》
御手洗はパンパンと手を叩き、顔をあげて皆を見渡す。
「そう、この人が全ての事件の犯人なんだ。この人が橘カオルであり、橘花世氏を殺し、その象徴となる事物を皆さんに送りつけて、脅迫まがいのことをしたのです。すべてを自分のものにするために」
途端に異議の声があがった。
「なんだって?」
「どうして?」
「おかしいじゃないか。橘カオルはアメリカ人だったっていうのか?」
三人の息子達の抗議を片手で制し、御手洗は続けた。
「生まれたのはアメリカですし、彼女の現在の国籍もアメリカのものです。ですから彼女はアメリカ人である事には間違いありませんが、その両親は日本人です。そして、彼女の男親が、橘花世氏だったのです」
私も思わず口を挟んだ。
「ちょっと待て、御手洗。彼女が橘氏の実子なら、その権利を主張すれば、他の子供達を脅かさなくても遺産が受け取れるじゃないか」
「本来ならね。まあ、黙って話をききたまえ」
ヒラリと手を翻すと、御手洗はキッと背筋を伸ばした。
「皆さんも、彼女の生い立ちと花世氏の関係について話をきいていたと思います。だが、その話は最初から不自然でした。可憐な大正浪漫の中で育ち、ゴシックな欧風趣味の持ち主である橘画伯が、アメリカのひなびた田舎町で孤児を拾い、日本へ連れてくるなどという話は、全く彼のイメージにそぐわない。普通、彼女を彼の実子と考えるのが自然でしょう。それを何故隠したか? ここに、花世氏の一種独特なロマンティシズムがあるのです」
「おお、ロゥマンティシズム」
ミスター・バーがおうむがえしに呟く。御手洗はちらりと一瞥したが、頬をさらに引き締めて言葉を継いだ。
「花世氏は父親の不品行を見て育った青年でした。彼がそれをどう感じていたか、僕には詳細はわかりません。ただ、子供好きであった彼が、生涯正式な妻をむかえず、家庭も持たなかったという事実は、何か彼の中に満たされない気持ちがあったと見ていいのではないでしょうか。父の悪癖をうけついだ彼ですが、妻になるひとを悲しませたくない、という気持ちがあったのではないでしょうか」
突然、高見沢氏が立ち上がった。
「それは違う。あいつにはどこかに惚れた女がいたんだ。でも、それがうまくいかなくて、いつまでもふらふらしてたんだ。確かさ。いつも、その女の話をしてたんだから」
御手洗は薄く微笑んだ。
「ああ、あなたはそれを御存知でしたか。でしょうね、その事を知っている人は少なくない筈だ。なんといっても、運命の女、幻の恋人がテーマの画家であったですから。……そうです、橘花世氏はある一人の女性の姿を追い続けていました。その人の名は、橘美耶。うら若い、彼の義理の母親でした」
ああ、柏木氏の事務所にあった絵の、あのきんいろに輝く女性のモデルは。
「母……だって?」
高見沢氏が腰くだけになると、御手洗は慰めるような穏やかな口調で、
「ええ。四十年前、父の橘子爵が火事でなくなった時、美耶さんは一緒に死んだことになっていますが、遺体は発見されていないのです。つまり彼女は助かったのです。それがなぜ無籍の人間になったか。それはたぶん、父子爵が死ぬ前に、花世氏と美耶さんの間に一つの過ちがあったからだと思われます。美耶さんはそれを恥じ、花世氏の前から姿を消した。だが、花世氏は美耶さんを追った。そして、美耶さんは逃げた。それこそ世界中を逃げまわった。そして花世氏は、彼女を追って追って追い続けた。美しい継母への傾心だけで、彼は素晴らしい作品を描き続けた。……彼が彼女をようやく捕まえたのは、アメリカの南部の町での事でした。十数年も自分を追いかけてきた男を、彼女はそこでついに受け入れた。そしてそこで、美耶さんは花世氏の子供を産んだ。だが、彼女は、その産まれた子供を見、絶望のあまり死んでしまった。その子は、金髪で白い肌をし、色の薄い目をした、異国の少女だったからです」
皆、一斉にミス・シムスを見た。彼女は、じっと御手洗だけを見つめている。
「美耶さんという人は世界中をとびまわった人だ。当然、生活の才覚は優れてあったでしょうが、女一人の旅で、身を慎むのは大層難しい話だったでしょう。ある種の商売をしなければならなかった時期があったかもしれません。無論、花世氏を信じ、受け入れた後はそんなことはなかったでしょうが。……だが、産まれたのは両親に似ても似つかぬ容貌の子。口さがない土地柄の中、美耶さんは信じられないほどのいかがわしい憶測と誹謗を受け、徹底的に追いつめられた」
御手洗は、自分の胸が本当に痛むかのように押さえた。
「美耶さんは真実、その時の花世氏に対して誠実だったと思います。そう、生まれた女の子は、単に色素を持たぬ子、つまりアルビノだったのです。もともと、日本人離れをした橘氏の顔立ちや背格好が、金色の髪と薄い色の目でひきたち、すっかり白人らしくなってしまったのでしょう。ただそれだけの事であった筈です。……だが、花世氏は噂話に踊らされ、美耶さんを疑ってしまった。最後の最後に疑われてしまった事が、彼女のプライドをすっかり破壊した。そして彼女は、そのまま自らの命を絶ったのです。こんな詰まらない事で最愛の美耶さんを失ってしまった花世氏は、傷心のまま少女を連れて、日本に帰りました。彼は子供の髪を黒く染め、色のついた眼鏡をかけさせ、橘カオルという名をつけました。そこで、彼は娘をしっかり育てれば良かったのです。しかし、戸籍を失った女性から産まれた娘です。その生い立ちの不幸を、できれば他人にあかしたくない。自分は長年の放浪癖が抜けないし、一人で育てる自信もない。そこで、彼女を自分が拾った孤児ということにし、信頼できる施設にあずけ、自分は元の生活に戻ったのです。……ただ、可愛い娘ですから、夜になると仕事場に連れてきて一緒に遊んだりしていたのでしょう。橘氏の奇行や奇癖の噂は、こんな所から発生したものと思われます」
柳田青年が、あっと叫んでミス・シムスを指さした。
「この子が、あの、オバケだったんだ」
ミス・シムスははっとして、柳田青年を見返す。
「僕、まだ小学生の頃、あなたにあったこと、あるでしょう。そうだよ。あるよね。僕、夜に寂しくなってさ、突然、橘さん家に遊びに行った事があったんだ。その時、ちらっと人影を見たんだ。……そうか、あれはあなただったのか。あの人さ、他にももう一人子供がいるよ、って僕が言ったら、それは幽霊だっていったんだよ。そうか、あれはまさしくオバケだったんだ」
御手洗は青年の興奮した口調を静かに遮った。
「花世氏はカオルを愛したし、カオルも花世氏を深く愛していました。だが、二人きりの楽しい夜遊びの最中、カオルは、誤って彼を殺してしまったのです。彼女は施設に逃げ戻り、橘氏のかつて世話した青年、アレキサンダー・バー氏を頼って、十八の年アメリカに渡り、優れた研究者になりました。だが、日本の事が、やはり忘れられない。そして、事件から十五年がたち、殺人の時効が来たので、自分の犯罪の露呈がこわくなくなった。それで、愛しい彼の残したものを、すべて自分の手にするために、他の子供達を脅迫してまわったのです。ただ、皆さんは、遺産に対してがっつく様子を見せなかったので、彼女はあなた達を殺すことまでしなかった」
難しい顔をしていた榊原氏が、そこで割って入った。
「ちょっと待って下さい。彼女はまだ二十代でしょう。その頃は十才かそこらだ。犯罪に責任の持てない年齢じゃないですか。時効におびえるなんて、話がおかしい。それに、そんな小さな女の子が、どうやって大の男を殺せるんです」
「もちろん、それは事故に近い出来事でした。橘氏の興味の方向が、その事件を引き起こしたのです。彼は、語学や音楽というものに淡い興味をひかれていました。橘氏の女性遍歴を眺めてもわかる。三人の息子達の母親の職業をご覧なさい。耳鼻咽喉科の医者、音響建築家、オルゴール職人。モルタルを塗り込めて完全に防音した密室で、スタジオ遊びをする有様です。だが、その遊び場に入り込んだカオルは、無邪気ないたずらをしました。床に枯葉を敷き詰め、部屋に沢山大きな風船を入れ、ランプを配しました。それは橘氏の愛した秋の情緒の先取りでした。花世氏は部屋に入り、このほほえましいいたずらを見つけましたが、中に敷き詰められた枯葉に火がついているのに、しばらく気付きませんでした。気付いた時にはすでに遅く、彼は火に囲まれていた。熱でドアは開かなくなり、水素をいれた風船は次々爆発し、橘氏は絶命したのです」
「ああ!」
突然、柳田青年が頭を抱えてうめいた。
「じゃあ、犯人は僕だったのか!」
「なんだって?」
皆が驚いて見つめる中、青年は叫び続けた。
「それをやったのは、カオルじゃない。僕なんだ。それは僕が、いたずらでやって、そのまま家に帰ったんだ。まさかそれが、火事の原因になったなんて……」
はっと顔をあげて、ミス・シムスを見つめる。
「じゃあ、あの脅迫は橘さんを殺した仇をつきとめるためだったのかい?」
彼女はかたく口唇を噛んでいた。灰色の瞳を大きく見開いて、なにかを堪えるような顔をしていたが、ようやくその口唇を開いた。
《あの夜、私は二階にひそんでいて、橘さんが迎えにあがってくるのを待っていたの。それなのに、突然、物音がして。驚いて降りていって、スタジオの部屋の戸を懸命に叩いたわ。橘さんは大火傷をしながら、自力で部屋を脱出してきたの。火は上まで燃え広がったわ。橘さんは私を連れて、そのまま庭へ出て行ったの。そして言ったの。「カオル、これは事故だから、誰も恨んではいけない」と。そして、新しい植樹の為に庭に開けられていた穴に、自分から降りて、そこで死んだの。私は泣きながら土をかぶせたわ。……いいえ。橘さんには天罰が下ったの。自業自得なの。だって、橘さんはその昔、事故にみせかけて、お父さんを焼き殺したんですもの。だから私、事件を暴くのを十五年待ったの》
「なぜその火事を偶発事故でなく、犯人のいる事件と断定したんですか?」
私の喉はカラカラだった。なんにせよ、その判断は十才前後の子供の考えとは思われない。
《私と橘さんは、その時、話をしたから》
ああ。
「あのテープの橘氏の話相手は、あなたなんですね」
《そう。火事のあった部屋には、橘さんがしゃべった声が、熱に耐えてテープに奇跡的に残されていたの。彼は、ふと思い付いた曲や言葉をよくテープに吹き込んでいたから、私との会話も、偶然残っていたのね》
そうか。
ああいう話を最後にしていたなら、確かに事故でなく、事件だと思うだろう。
《だから、誰かがこの仕掛けをつくったのは間違いない。でも、あれだけでは、この事件は単なるいたずらから起こったのか、それとも誰かがいたずらでやったようにみせかけたのか、断定できなかった。そのうえ、肝心の犯人の名前がよくききとれなかった。どんなにきいても『ああいああ、おおいい』にしか聞こえない。だから私はじっくり待ったの。罪を知るべき人が、自分から罪を認めるのを》
三人の息子達は悄然としてそれをきいていた。ミス・シムスはすらりと立ち上がった。
《私の気は、これで済みました。私はあのマグノリアをもらって、国に帰ります。他の場所の処分は御随意になさってください。……行きましょう、アレック。ありがとうございました、御手洗さん、石岡さん》
二人は先に居間を出ていった。私は慌てて彼女を追った。
「待って下さい、シムスさん。私にはまだわからない。なぜあなたは、偽名まで使ってここまでまわりくどいことを」
「それはね、石岡君。彼女が《子音欠落症》だからさ」
後ろで御手洗が返事をした。
「彼女は、どうしても犯人の名前をききとりたかった。父を殺したのが誰か、知りたかった。だが、どうしてもわからない。普通の人間なら、そこであきらめてしまっただろう。しかし、彼女は子音欠落症だった」
「子音欠落症ってなんなんだい?」
御手洗は私の横に並んだ。
「子音がききとれず、発音できない症状だ。彼女は自分だけが聞き取れないのかもしれないと思って、三人の息子達に自分達で判断させようとして、あのテープを送ったのさ。犯人が自分で動き出す事を期待したのかもしれないが」
成程。そんな事情があれば、まわりくどい方法をとる人間もいるかもしれない。
「だが御手洗、そんな病気はきいたことがないよ」
御手洗はうなずいて、
「ああ、病気というのとは違うんだ。いいかい、普通の人間は十二才までに習得した母国語の子音をききとって話すことができる。だが、日本人の十人に一人はこの子音欠落症で、その人達は、母国語の中に生活しながら、文脈や母音だけで言葉の内容を判断して暮らしている。そういう人達がいるんだよ。ほら、日常生活で、聞き間違いの多い人間がいるだろう? その大部分は子音欠落症なんだよ。たぶん、花世氏もそうだったんだろう。それで、言葉よりも音楽に興味を持っていたんじゃないかな。遺伝的な要素もあるが、これは民族的な差のある症状でね、日本語を話す日本人のほとんどは英語に対する子音欠落症なんだよ。それが、英語に対する恐怖心をあおる一因になっている。石岡君は、ミス・シムスのいっていることがよく判ったろう? 彼女は日本で育ってしまったために、日本語の発音ばかりでなく、正確な米語の発音ができないんだよ。だいぶそれらしくはしているがね」
ミス・シムスは振り返り、はにかんだような笑みを浮かべた。
《それでも私は、これ程度の発音で充分人を欺いてまいりました。でも、御手洗さんは、一度きいただけでおわかりになったようですね。語学には堪能だとお聞きしていましたが、本当だったようですね》
御手洗は首を振り、
「子音欠落症という概念に十才かそこらで気付き、なんとかしようとしたあなたの方が素晴らしい。ただ一つの言葉を聞き取るために、日本で語学の勉強を重ね、それが駄目だとわかると、渡米までして勉強を重ね、立派な言語学者になったんですから。それはまさに、チェスタトン的な立派な執念だ」
《お誉めいただいて、ありがとうございます》
御手洗はその笑顔にこたえかけて、ふとまた眉を寄せた。
「いいですか、あなたは才能のある女性だが、それを間違って使わないようにして下さい。帰国しても、犯罪者としての才能は伏せて生活して欲しいものです」
《ええ、もう悪戯はやめます。本当にお世話になりました》
ミス・シムスは頭を下げた。子供っぽく舌を出した笑顔を見せると、ミスター弁護士の腕にすがって去った。
私は、ふと首をかしげた。
「……御手洗、最後に変な釘をさしたのは何故だい? もう事件は片付いたんだし、彼女が犯罪をする必要なんてないだろう? 今回の事件での脅迫だって、脅迫にならない程度のレベルに押さえていたじゃないか。彼女がいったい何をしたっていうんだい?」
御手洗はまじまじと私の顔を見つめ、
「なんだ、君は、彼女のお膳立ての能力の物凄さを全然わかってなかったのかい? 僕らが彼女に会ったのは偶然じゃないんだよ。最初の捕り物は茶番だったのさ。今回の事件で、彼女はどうしても探偵が必要だったろう? 白羽の矢をたてた僕らをひっかけるために、あらかじめ、足を洗いたいスリと話をしてあったんだよ。綿密な打ち合せをしておいて、さる筋に情報を流し、わざと僕らの前で仕事をしてみせたんだ。だから、彼女はおそるべき女性だといったんだ。僕は最初からすっかり道化だったのさ。見事にしてやられたんだよ。僕のように名があって、その上でしゃばりな自信家は、さぞ扱いやすかったことだろう。あそこまで鮮やかにひっかけられたからには、後にはひけないしね」
そういって肩をすくめた。私は思わず朗らかな気持ちになり、大笑いした。
「あっはは、なんだ、それがこのところの君の不機嫌の原因だったのか。なるほどね。あはははは……」
主のない灰色の建物は、その後取り壊されることになった。
その際、防火の行き届いた居間の壁の中から、橘氏の絵が幾葉も発見された。その絵は、当然のようにミス・シムスに送られた。あの建物は元々、橘カオルに贈られたものだったからである。
--THE END--
贋作者注:子音欠落症という言葉、および症状は、経験から類推された贋作者の造語である。ただし、類似の現象は言語学の本を幾冊かひもとけばいくらでも見られ、例証されている事でもあるので、全く根拠のないものではない。シムスという無名の学者が、きっと類似の論文を書いているだろうし、御手洗はもしかしたらそれを読んでいたかもしれない、というのは、物語の興をさますだろうか?
「The Last Rose of Summer」by Thomas Moore
'Tis the last rose of summer
Left blooming alone;
All her lovely companions
Are faded and gone;
No flowers of her kindred,
No rosebud is nigh,
To reflect back her blushes,
Or give sigh for sigh.
庭の千草も、むしのねも、かれてさびしくなりにけり
ああ、しらぎく、鳴呼白菊、
ひとりおくれて 咲きにけり
露にたわむや菊の花、しもにおごるや、きくの花
あああわれあわれ、ああ白菊、
人のみさおもかくてこそ
(1992.9脱稿・同人誌『御手洗潔の災難』のための書き下ろし/初出・恋人と時限爆弾『frenzy』1995.9)
《推理小説系創作のページ》へ戻る
copyright 1999
Narihara Akira
http://www5f.biglobe.ne.jp/~Narisama/
|