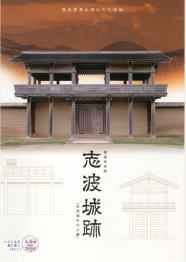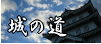 |
| トップ>メニュー>北海道・東北地方>志波城 |
| しわじょう |
| 志波城 |
| 別称: |
| 所在地:岩手県盛岡市吉原 |
 |
| 形状 |
○ |
平城 |
史跡指定 |
ー |
国特別 |
| ー |
平山城 |
○ |
国 |
| ー |
山城 |
ー |
都道府県 |
| ー |
陣屋・館 |
ー |
市町村 |
| 遺構 |
ー |
建築物 |
天守閣 |
ー |
現存 |
| ー |
石垣 |
ー |
復原 |
| ー |
土塁 |
ー |
外観復原 |
| ー |
水堀 |
ー |
復興 |
| ー |
空堀 |
ー |
模擬 |
|
| (撮影年月 H18・8) |
|
| 現存建築物 |
国宝 |
なし |
| 国重文 |
なし |
| 都道府県指定 |
なし |
| 市町村指定 |
なし |
| その他 |
なし |
| 復元建築物 |
外郭南門、築地塀、櫓、政庁南門、目隠塀など |
|
| アクセス |
公共 |
JR東北本線盛岡駅からバス(岩手県交通)飯岡十文字バス停下車 |
| 車 |
東北自動車道盛岡ICから約15分 |
| ミニ情報 |
|
| 地図情報 |
 |
|
| 城略史 |
志波城は、古代東北地方の城柵で、蝦夷を統治するために築かれたものです。蝦夷統治の歴史は、724年多賀城の造営により現在の宮城県北部までが律令体勢に組み込まれることから始まります。797年には坂上田村麻呂が征夷大将軍となり、802年に胆沢城(現在の水沢市)を造営、翌803年に志波城を造営し北上盆地北部まで律令支配下になります。しかし38年戦争が終わる811年には、水害を理由に移転が決り廃城となります。わずか10年という極めて短い存続期間でありました。
志波城跡は、かつて前九年の役の古戦場跡だとか陣場跡だとかと伝えられていましたが、調査の結果城柵とされ、昭和51年からの発掘調査では長く所在が不明であった「志波城」であることが確認されました。
(参照「志波城跡(志波城跡愛護協会)」) |
|
| 主な見どころ |
 |
 |
| ↑現地案内板:志波城の北側は雫石川に面していました。水害により北側は欠落してしまいましたが、水運に活用していたともいわれています。 |
↑外郭南門①:二層の巨大な門。発掘調査により、その基礎の部分は判明したでしょうが、上部はまったくの想像でしょう。このような雰囲気であったのでしょうけど。 |
 |
 |
| ↑外郭南門② |
↑築地塀と櫓:塀は基底部の幅が2,4㍍・高さは4,5㍍と考えられています。さらに櫓が60㍍おきにあったようです。ものすごく厳重な造りで、当時この柵を落とすことなど、天変地異以外不可能であったのではないでしょうか。 |
 |
 |
| ↑南大路:外郭南門をくぐると、政庁に向かってまっすぐ道が延びています。かなたに見える門は政庁南門です。 |
↑政庁南門①:南大路のつきあたりに構える政庁南門。外郭に比べると随分小規模です。左右の築地塀は基底幅が1,8㍍です。 |
 |
 |
| ↑政庁南門②:四角い政庁には、四方に4カ所門がありましたが、南門にはなかを見通すことを防ぐ目隠塀がありました。 |
↑政庁西門:むこうに見えるのは政庁東門です。 |
 |
 |
| ↑政庁:正殿と脇殿がコの字型に配され、他にも多くの建築物があったとみられています。 |
↑政庁正殿跡:この正殿も推定復元されると、古代城柵のイメージがかなり広がり、見学がより一層楽しいものになることでしょう。 |
| 入場券・パンフ等 |
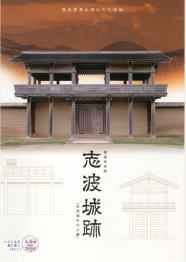 |
 |
| パンフ(表):公園の案内所で販売されているもので、値段は忘れてしまいましたが、高価なものではありません。 |
パンフ(裏) |
|
| 探訪年月 |
①H18・8 |
| 併設・周辺資料館 |
志波城古代公園
入園時間:自由
案内所は9時から17時まで(3月15日~12月20日)
休館:なし
℡019-658-1710 |
| 参考見学所要時間 |
約1時間00分 |
| お薦め度 |
私見 |
古代城柵は、東北地方に何カ所かあります。まだ他の城柵跡を探訪したことがないので、他と比べようがないのですが、しかし遺構の保存範囲は広く、復元建築物もダイナミックで見応えがあります。やはり東北地方の良いところで、復元がちまちまとしていないので、古代の浪漫にたっぷり浸ることができる素晴らしい城跡です。 |
| ○ |
城郭ファン以外も必見 |
| ー |
見逃せない対象です |
| ー |
城好きは行きましょう |
| ー |
予備知識がある方は・・ |
| ー |
マニア向け |
|
|
|
| 初版20070401 |
| 戻る |