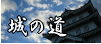 |
| トップ>メニュー>近畿地方>姫路城>姫路城2 |
| ひめじじょう |
| 姫路城 |
| 別称:白鷺城、姫山城 |
| 所在地:兵庫県姫路市本町 |
 |
| 形状 |
ー |
平城 |
史跡指定 |
○ |
国特別 |
| ○ |
平山城 |
ー |
国 |
| ー |
山城 |
ー |
都道府県 |
| ー |
陣屋・館 |
ー |
市町村 |
| 遺構 |
○ |
建築物 |
天守閣 |
○ |
現存 |
| ○ |
石垣 |
ー |
復原 |
| ○ |
土塁 |
ー |
外観復原 |
| ○ |
水堀 |
ー |
復興 |
| ー |
空堀 |
ー |
模擬 |
|
| (撮影年月 H16・9) |
|
| 現存建築物 |
国宝 |
大天守、東小天守、西小天守、乾小天守、イ・ロ・ハ・ニ・の渡櫓 |
| 国重文 |
化粧櫓、ニの櫓、折廻り櫓、備前門、水の一門、水の二門、菱の門、い・ろ・は・にの門、ぬの門など74棟 |
| 都道府県指定 |
なし |
| 市町村指定 |
なし |
| その他 |
なし |
|
| アクセス |
鉄道 |
JR山陽本線姫路駅下車後徒歩15分 |
| 車 |
山陽道姫路東ICから約5㎞ |
| ミニ情報 |
|
| 地図情報 |
 |
|
| 城略史 |
南北朝時代、赤松貞範が縄張を施したのが姫路城の始まりとされている。その後、黒田氏により戦国時代末期築城され、羽柴秀吉の中国経営のために拠点として使用された。播磨平定の後、秀吉は長浜から拠点を姫路に移し、本能寺の変、山崎の戦いの後には弟の秀長が入城した。
現在目にすることのできる姫路城を築いたのは、関ヶ原合戦後に入封した池田輝政である。また池田氏の後に入封した本多氏により西の丸が築かれ、千姫で有名な化粧櫓もこの頃に築かれた。
明治維新後は、戦災も奇跡的にくぐり抜け、国宝として現存し、平成5年には世界文化遺産にも指定されるなど、日本を代表する城郭である。 |
|
| 主な見どころ |
|
| 城下 |
|
 |
 |
| ↑中の門跡:中曲輪正面五門のうち中央にある門跡。枡形を構成し櫓門形式であった。 |
↑桐二ノ門跡(大手門):大手口にあるので通称は大手門だが正確には桐の門で二ノ門は桜門という名称。ここから内側が三の丸。 |
 |
 |
| ↑桐の門跡(大手門)と三の丸内堀 |
↑喜齋門跡:大手に対する搦手にあたる門跡。巨石がさりげなく使われている。 |
|
| 菱の門 |
|
 |
 |
| ↑二の丸入口にある門で、現在はここから有料。飾り金具などの装飾が施されていて、姫路城の中でも一、二を争う華美な門。 |
|
| 西の丸 |
| 池田氏のあとに入封した本多忠政が、今に残る西の丸を整えた。なかでも化粧櫓は、千姫が結婚生活を送った場として有名。 |
|
 |
| ↑西の丸全景 |
 |
 |
| ↑「ワ」の櫓:ここから入って見学する。姫路城は櫓の現存が多数有り、当たり前のように感じてしまうが、素晴らしい遺構です。 |
↑「レ」の渡櫓:「ワ」の櫓から「ヲ」の櫓まで結ぶ。 |
 |
 |
| ↑「ヲ」の櫓 |
↑「ヨ」の渡櫓:右側には女たちが住んだ部屋が続く。敷居の様子からして、畳が敷かれていたようである。 |
 |
 |
| ↑化粧櫓:南北に破風を設ける二重二階の櫓。二階が主室であったらしい。 |
↑化粧櫓内部(1階):このような光景は、本来2階で見られたものであろう。 |
|
| 門 |
| 姫路城には、多くの門が現存しほとんどが国の重文に指定されている。あまりにも多いため、つい見逃してしまうこともあるので細心の注意が必要です。 |
|
| 第1路 |
 |
 |
| ↑「は」の門①:二の丸から乾曲輪へと至る門。 |
↑「は」の門②:内側から。小さな門だと思って侮ってはいけません。厳重な守りです。 |
 |
 |
| ↑「に」の門①:櫓の下を通過する構造となっている有名な門です。 |
↑「に」の門②:はっきりいって、ここまで厳重だと想定の事態にまで攻撃されることはないと思います。 |
 |
 |
| ↑「ほ」の門:天守は目の前。しかし鉄製の埋門が行く手を阻みます。 |
↑水の二門:いよいよ天守曲輪に入ります。 |
|
| 第2路 |
 |
 |
| ↑「る」の門①:この門は二の丸経由で上山里曲輪に抜ける正規のコースではない門。埋門形式の穴門で有事の際は、まさしく埋められるのであろう。 |
↑「る」の門②:内側から撮影したもの。 |
 |
 |
| ↑「ぬ」の門:上山里曲輪へと抜ける城内最大級の門。鉄板張りの門の上に、二重の櫓が立つ。 |
↑「り」の門:上山里曲輪を出て帯曲輪へと至る門 |
 |
 |
| ↑「と」の門①:搦手門である。上部の板張りなど、姫路城では一種異様な雰囲気をかもしだしている。 |
↑「と」の門② |
| 姫路城2へ |
| 戻る |

























