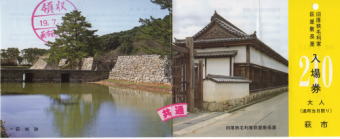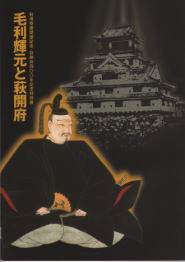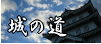 |
| トップ>メニュー>中国・四国地方>萩城 |
| はぎじょう |
| 萩城 |
| 別称:指月城 |
| 所在地:山口県萩市堀内 |
 |
| 形状 |
○ |
平城 |
史跡指定 |
ー |
国特別 |
| ー |
平山城 |
○ |
国 |
| ○ |
山城 |
ー |
都道府県 |
| ー |
陣屋・館 |
ー |
市町村 |
| 遺構 |
ー |
建築物 |
天守閣 |
ー |
現存 |
| ○ |
石垣 |
ー |
復原 |
| ー |
土塁 |
ー |
外観復原 |
| ○ |
水堀 |
ー |
復興 |
| ー |
空堀 |
ー |
模擬 |
|
| (撮影年月 H19・7) |
|
| 現存建築物 |
国宝 |
なし |
| 国重文 |
なし |
| 都道府県指定 |
なし |
| 市町村指定 |
なし |
| その他 |
なし |
| 復元建築物 |
北の総門、土塀 |
|
| アクセス |
公共 |
山陰本線萩駅から萩循環まぁーるバス西回り「萩城跡・指月公園前」下車すぐ
山陰本線玉江駅下車徒歩20分
|
| 車 |
国道191号線で萩市内に入り案内板に従う |
| ミニ情報 |
気候が良ければ貸自転車で。駐車場は城跡前に有料Pと、すぐ隣に萩史料館の無料P |
| 地図情報 |
 |
|
| 城略史 |
萩城は、松本川と橋本川のデルタ地帯に築かれています。山麓と指月山に位置しており、関ヶ原合戦後に防長36万石に減封され広島から移りました。当初、毛利輝元は防府か山口に府城を置きたいと考えていたそうですが、徳川幕府の意向で山陰側の萩となりました。慶長9年(1604)に着工された城は、4年がかりで完成し、指月山の山城と、山麓の平城部分を総称したものです。平時は、平城部分で藩政を執っていました。幕末十四代敬親が山口に居城を移したので、建物の用材を山口へ充てたりして漸次寂れていきました。西南隅には天守が上げられていましたが、明治6年に破却され、今は石垣が残るのみです。指月山は詰城で、石垣が残りますが、木々が生い茂りかつての物見は望めません。
(参照「国別城郭・陣屋・要害台場事典(東京堂出版)」) |
|
| 主な見どころ |
| ーーー城 下ーーー |
 |
 |
| ↑萩城下遠望:吉田松陰誕生地からは、城下が一望出来ます。写真中央の直角三角形の山が、詰丸のある指月山で国の天然記念物にもなっています。 |
↑松下村塾:松陰誕生地からすぐの場所にある松下村塾。随分と城下から離れた場所にあります。城下を眼下に見下ろす場所にあり、塾生達はどのような感情で見ていたのでしょうか? |
| ーーー三の丸ーーー |
 |
 |
| ↑三の丸・北の総門と外堀(復元):三の丸へ出入りする3カ所の総門のうち、北の総門と呼ばれる一番北側の門。ほかに中之総門、平安古之総門がありました。 |
↑北の総門:日の入りから日の出までは閉ざされ、手形を持つ者しか通れなかったそうです。なお、北の総門は、萩城唯一の復元建築物です。 |
 |
 |
| ↑厚狭毛利家萩屋敷長屋:現存する建築物で、国の重文。三の丸に位置し、二の丸南門の目の前という絶好のロケーションです。 |
↑萩城模型:厚狭毛利家萩屋敷長屋内に展示してある萩城の模型。萩博物館にも同様の模型があります。こちらの模型は、ややデフォルメされています。矢印が同長屋です。 |
| ーーー二の丸ーーー |
 |
 |
| ↑二の丸南門:二の丸へ出入りする門は2カ所。南門は、内枡形門で大手門にあたりました。今も厳重な石垣を見ることができます。二の丸を囲む中堀は残念ながら埋め立てられてしまっています。 |
↑二の丸東門:こちらが二の丸へ至るもう1カ所の門。時打櫓という櫓に守られた厳重な、やはり内枡形門。ちなみに二の丸内は、萩焼資料館や土産物屋が建ち、ここまでは無料です。 |
 |
 |
| ↑華櫓付近の石垣:二の丸は本丸と指月山を囲むように北へ広がっています。そして海に面して石垣が続き、間隔をおいて櫓があがっていました。 |
↑紙櫓付近の石垣:南北に広がる長い二の丸は、紙櫓で一度仕切られて、また北へ延びていきます。復元された土塀の向こう側が海です。 |
 |
 |
| ↑二の丸土塀(復元):復元された土塀の先で角張る石垣は、手前が紙櫓、奥が華櫓の台です。 |
↑潮入門:直接海に向けられた門跡。今は海水浴場として、砂浜がやや広がっているが、すぐ海であることには変わりない。開口部からして相当規模の大きい門であったことが想像されますが、どんな役割を担っていたのでしょう。 |
 |
 |
| ↑満願寺跡:二の丸北側には、かつて満願寺という寺院がありました。おそらく、その遺構としての塀であると思われますが、案内板もなく詳細はわかりませんでした。 |
↑満願寺櫓付近の石垣:目の前がすぐ海である素晴らしい光景。海岸にそそり立つといった感じ。 |
 |
 |
| ↑三摩地院櫓跡と埋門跡:二の丸最果ての櫓跡と石垣。この写真から、まさに海に接しているのがわかると思います。その雰囲気は、戦闘的であるというより、むしろ郷愁を感じます。 |
↑埋門跡:なんともいえない雰囲気です。萩城へ行ったら、是非見てほしい景色です。 |
| ーーー本 丸ーーー |
 |
 |
| ↑本丸内堀と本丸:左に見えるのは天守台。内堀はコの字型に本丸を囲み、本丸へ至るには、現在は全て石橋ですが、かつては本丸側のみ木橋でした。 |
↑本丸石垣雁木:左の写真でいえば、天守台から右側の一段下がった部分の裏側には全て雁木が設けられています。全国でも最大規模だということです。 |
 |
 |
| ↑本丸:現在は志都岐山神社となっています。萩城は有料となっているので、この神社に参拝するにはお金がかかるということになります。神社としては珍しいケースです。 |
↑天守台①:かつては5重5階望楼型で、1階が天守台より半間ずつ出っぱった天守閣がそびえていた。 |
 |
 |
| ↑天守台②:反りの美しい天守台。天守閣模型はJR東萩駅ロータリーにあります。目立つのですぐにわかると思います。 |
↑天守礎石:天守台が立派なら、礎石も立派です。天守台だけ築き、天守閣をはじめから上げる予定のないものには礎石が無かったりしますが、萩城の礎石は大きく立派なものです。 |
| ーーー詰 丸ーーー |
 |
 |
| ↑詰丸登山口と石垣:登山口を登るとすぐ、竹藪の中に石垣を見ることができます。これは本丸を囲み、また指月山を守る石垣の一部であるかと思われます。 |
↑詰丸案内図:詰丸は標高143メートルの指月山の山頂にあり、本丸と二の丸に分かれています。 |
 |
 |
| ↑要害門①:麓から20分位でしょうか。蚊の大群に襲われ、坂道は急で整備状況は決して良いとはいえません。人並みの体力があるとは思いますが、ここは結構きつい!! |
↑要害門②:コの字型になっている要害門。最後の砦として、あらん限りの防御を施しているといった印象です。 |
 |
 |
| ↑詰丸(二の丸):切り割り石。残念ながら使われなかった石が放置されているのでしょうか。各地で残念石とか云われます。 |
↑詰丸(本丸):本丸部は、二の丸よりも一段高くなっています。藩主や幕府巡見使の休憩所があったそうです。 |
 |
 |
| ↑詰丸貯水槽:詰丸には井戸がなかったので、貯水槽を設けたそうです。巨石の周囲が掘られて貯水槽になっていますが、なんとも不思議な感じです。 |
↑眺望:夏ということもあり眺望は期待できません。麓にも展望台ではありませんみたいなことが記載された看板があります。確かに、苦労して登ってこれでは苦情になるでしょう。 |
| 入場券・パンフ等 |
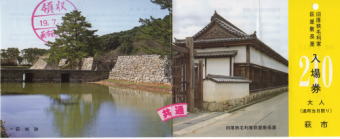 |
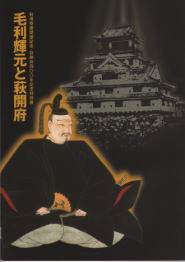 |
| 入場券:萩城跡と厚狭毛利家萩屋敷長屋と共通券になっています。 |
毛利輝元と萩開府(萩博物館):萩博物館開館記念の特別展で発行されたガイドブック。萩博物館で恒常的に販売しています。 |
|
| 探訪年月 |
①H19・7 |
| 併設・周辺資料館 |
開園時間:8時00分から18時30分(季節変動あり)
料金:210円
休館:なし
℡0838ー25ー1826 |
| 参考見学所要時間 |
約1時間30分(指月山含む) |
| お薦め度 |
私見 |
萩城には、現存建築物が一切ありませんが、街中が江戸時代そのままのようです。天守台から本丸にかけての石垣は芸術的な景観を作り出していて見飽きることがありません。また、指月山の詰丸も必見ですが(夏は汗だくになりますが)、海に面した石垣の連なりは一見の価値があります。自然の地形に沿って続きますが、最後は埋門形式で終わる石垣と周囲の景色に、必ずや来て良かったと思うはずです。 |
| ○ |
城郭ファン以外も必見 |
| ー |
見逃せない対象です |
| ー |
城好きは行きましょう |
| ー |
予備知識がある方は・・ |
| ー |
マニア向け |
|
| 公式サイト |
|
| 参考サイト |
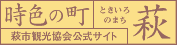 |
|
| 初版20070807 |
| 戻る |