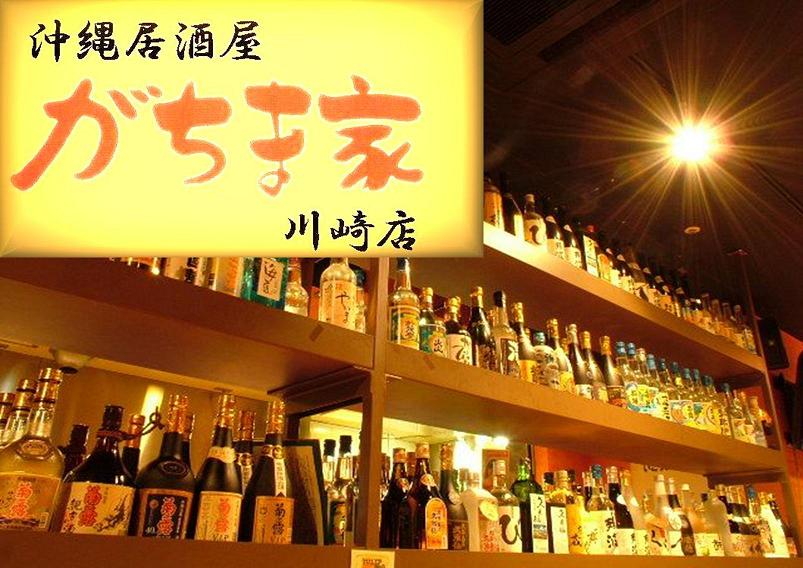
 ムヌガッタイ
ムヌガッタイ
※ムヌガッタイ(沖縄の方言で「ゆんたく」に似た意味です。与論島の方言ですよー)
このページでは、がちま家での近況、沖縄・奄美についてちょっとづつ紹介していきたいと思います。
 塩せんべい(2009.1.14 up)
塩せんべい(2009.1.14 up)
 サトウキビ
サトウキビ
 徳之島について その1
徳之島について その1
 6月11日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子
6月11日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子
 5月14日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子
5月14日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子
 塩せんべい
塩せんべい
 さとうきび
さとうきび
 鹿児島県大島郡徳之島 1
鹿児島県大島郡徳之島 1
 6月11日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子
6月11日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子
 5月14日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子
5月14日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子
このページでは、がちま家での近況、沖縄・奄美についてちょっとづつ紹介していきたいと思います。
 塩せんべい(2009.1.14 up)
塩せんべい(2009.1.14 up) サトウキビ
サトウキビ 徳之島について その1
徳之島について その1 6月11日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子
6月11日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子 5月14日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子
5月14日(水曜日)新里学さんによる島唄ライブの様子

|
塩せんべいの食べ方
沖縄好きな方、行ったことある方、地元の方はもちろんご存じ「塩せんべい」
塩っ気とあのサクサク感がたまりません。戦後生まれの素敵な味です。
食べ方として、そのままサクサク、マーガリンつけたり、チョコつけたり。
多少堅めなので、口の中を若干切ったりした方もいらっしゃるでしょう。
はまると止められない、すごい魅力の塩せんべい。
あまりにも好きで、他に食べ方を模索致しましたところ、発見致しました。
もう発見している方もいらっしゃるでしょうが。。。
鍋!!
鍋にせんべい!
まぁっ。青森県八戸の郷土料理とされる「せんべい汁」に近いですが。
美味しそうだとおもいませんか??
塩味が鍋にとけだし、汁をたっぷり吸い込んだせんべいと、スープ。
ちなみに、キムチ鍋・豆乳鍋にはあまり合わないかも!!
ちなみに、当店のレジ前にもご用意致しました!!
是非、ご賞味ください!!
沖縄好きな方、行ったことある方、地元の方はもちろんご存じ「塩せんべい」
塩っ気とあのサクサク感がたまりません。戦後生まれの素敵な味です。
食べ方として、そのままサクサク、マーガリンつけたり、チョコつけたり。
多少堅めなので、口の中を若干切ったりした方もいらっしゃるでしょう。
はまると止められない、すごい魅力の塩せんべい。
あまりにも好きで、他に食べ方を模索致しましたところ、発見致しました。
もう発見している方もいらっしゃるでしょうが。。。
鍋!!
鍋にせんべい!
まぁっ。青森県八戸の郷土料理とされる「せんべい汁」に近いですが。
美味しそうだとおもいませんか??
塩味が鍋にとけだし、汁をたっぷり吸い込んだせんべいと、スープ。
ちなみに、キムチ鍋・豆乳鍋にはあまり合わないかも!!
ちなみに、当店のレジ前にもご用意致しました!!
是非、ご賞味ください!!
|
△ページ先頭へ戻る |

|
こんにちは。今回のムヌガッタイ。さとうきび。
さとうきびといえば、やっぱり砂糖の原料として利用されるのが一番多いですよね。
「ザラメ」とよばれる大きめの粒の砂糖や、ご存じ「黒糖」、
和菓子の高級砂糖として利用される「和三盆」
が、、、
やっぱり、サトウキビにそのままかぶりつくのが一番おいしいです。
根っこのそばあたりを折って、歯で皮をむいて、かじります。
繊維が歯の隙間の挟まるのでご用心
学校帰りとか、部活での校外走の途中とか、かじるととても元気がでました。
※他人の畑のさとうきびは許可をもらいましょう。
サトウキビの収穫時期はだいたい12月〜4月頃なんですが、
家族総出でやり、男性はキビを斧で倒して並べ、女性は葉などを取り除き束をつくり、
それを男性がまた運ぶという流れでやってました。
ハチと遭遇したり、キジがいたり、無くした野球ボールがでてきたり。
そして現在、川崎でもサトウキビそだつか、実験計画中です。
さとうきびといえば、やっぱり砂糖の原料として利用されるのが一番多いですよね。
「ザラメ」とよばれる大きめの粒の砂糖や、ご存じ「黒糖」、
和菓子の高級砂糖として利用される「和三盆」
が、、、
やっぱり、サトウキビにそのままかぶりつくのが一番おいしいです。
根っこのそばあたりを折って、歯で皮をむいて、かじります。
繊維が歯の隙間の挟まるのでご用心
学校帰りとか、部活での校外走の途中とか、かじるととても元気がでました。
※他人の畑のさとうきびは許可をもらいましょう。
サトウキビの収穫時期はだいたい12月〜4月頃なんですが、
家族総出でやり、男性はキビを斧で倒して並べ、女性は葉などを取り除き束をつくり、
それを男性がまた運ぶという流れでやってました。
ハチと遭遇したり、キジがいたり、無くした野球ボールがでてきたり。
そして現在、川崎でもサトウキビそだつか、実験計画中です。
|
△ページ先頭へ戻る |

|
今回のムヌガッタイ。徳之島の紹介をしたいと思います。
鹿児島県大島郡徳之島。
県は鹿児島なんですが、文化、音楽共に沖縄県と共通点が多い島。
琉球文化が根付き、「琉球弧」と名付けられた、現在の沖縄文化が礎となった島です。
方言も沖縄と共通するものがあり(トゥジ(妻)、ドゥシ(友達)等)、
音楽に関しては、琉球音階(ド・ミ・ファ・ソ・シ・ド)で構成され、
アジア、古来の日本、現在の琉球音階とよばれる音階で多用されるもので島唄が歌われます。
徳之島出身といえば、
長寿のシンボルとなった「泉重千代(享年120)」。
医療の先駆者「徳田虎夫」。
牛が大きいです。「闘牛」。
というのも社長は徳之島出身、店長は沖縄県浦添市出身、私は徳之島と沖縄の間の与論島出身。
当店は、沖縄・奄美の料理を直送するという意味で、
共通する言葉「がちま家(がちまや→くいしんぼう等の意味)」。
そして、奄美諸島のみの「黒糖焼酎」、沖縄でしか商標許可されていない「泡盛」
を皆様に楽しんでいただけるよう、多数ご用意しております。
是非お試しください。
鹿児島県大島郡徳之島。
県は鹿児島なんですが、文化、音楽共に沖縄県と共通点が多い島。
琉球文化が根付き、「琉球弧」と名付けられた、現在の沖縄文化が礎となった島です。
方言も沖縄と共通するものがあり(トゥジ(妻)、ドゥシ(友達)等)、
音楽に関しては、琉球音階(ド・ミ・ファ・ソ・シ・ド)で構成され、
アジア、古来の日本、現在の琉球音階とよばれる音階で多用されるもので島唄が歌われます。
徳之島出身といえば、
長寿のシンボルとなった「泉重千代(享年120)」。
医療の先駆者「徳田虎夫」。
牛が大きいです。「闘牛」。
というのも社長は徳之島出身、店長は沖縄県浦添市出身、私は徳之島と沖縄の間の与論島出身。
当店は、沖縄・奄美の料理を直送するという意味で、
共通する言葉「がちま家(がちまや→くいしんぼう等の意味)」。
そして、奄美諸島のみの「黒糖焼酎」、沖縄でしか商標許可されていない「泡盛」
を皆様に楽しんでいただけるよう、多数ご用意しております。
是非お試しください。
|
△ページ先頭へ戻る |

|
 お客様、満席です♪ |

エイサーをしてる方もいらっしゃいました |
 店長もカチャーシー
|

スタッフの新里さん命名「ステファニー」と
|
以前遊びに来てくれたお客様が、再度遊びに来てくれました。ありがとうございます。
毎回、違った雰囲気のライブで、とても楽しいライブです。
次回は7月9日(水)を予定しております。次が楽しみですねー
ちなみに今回も、新里さんが一番酔って楽しそうだった〜
毎回、違った雰囲気のライブで、とても楽しいライブです。
次回は7月9日(水)を予定しております。次が楽しみですねー
ちなみに今回も、新里さんが一番酔って楽しそうだった〜
|
△ページ先頭へ戻る |

|
 さぁっ!始まりました! |

皆さん、聞き入ってますね♪ |
 だんだん盛り上がって参りました〜
|

やっぱり最後はカチャーシー!
|
今回、誕生日の方が3名もいらっしゃって、島唄バースデイパーティとなりました。
新里学さんのライブは、お客様と一体になるとてもとても楽しいライブです。
次回は6月11日(水)を予定しております。是非遊びにいらしてくださいね。
新里学さんのライブは、お客様と一体になるとてもとても楽しいライブです。
次回は6月11日(水)を予定しております。是非遊びにいらしてくださいね。
|
△ページ先頭へ戻る |
Copyright (C) gachimaya All Rights Reserved |