網膜静脈閉塞症(RVO)への鍼施術 2025年3月26日Web公開版
2025年3月9日(日) 第40回 「眼科と東洋医学」研究会 台東区区民会館
・解説内容については、当日参加いただいた先生方にスライドを交えて報告した内容を、広く一般の方に分かり易くお伝えするために
大幅に補足しています。当日は限られた時間のためにお伝えできなかった部分も含めて、完成版として見ていただけたら幸いです。
・千秋針灸院では皆様のご協力により多数の検査画像等を保有していますが、許可を得て研究会や学会報告、院内での説明時に限定しています。
・個人情報がネット上で拡散した場合、今後検査結果を患者さんが入手し辛くなるケースも考えられるため、安易な公開は慎むよう努めています。
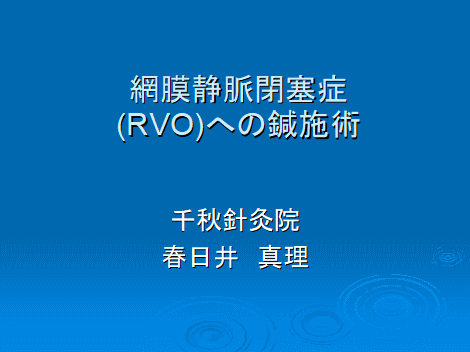
・今回は網膜静脈閉塞症(RVO)への鍼治療を、視力変化と症例報告を通してご紹介しました。
・今回は第40回の節目で、竹田先生から山本先生への会長の引継ぎや、初の会場とZOOMでのハイブリット開催でもあり、斬新な大会となりました。
・網膜静脈閉塞症(RVO)は、視力低下や視界内の歪み(変視)を伴う疾患で、眼科では抗VEGF硝子体内注射(アイリーア等)が用いられています。
・抗VEGF硝子体内注射(アイリーア等)は、RVOによる視力や変視の改善に効果的ですが、数ヶ月で効果が切れる度に再発する場合も多いです。
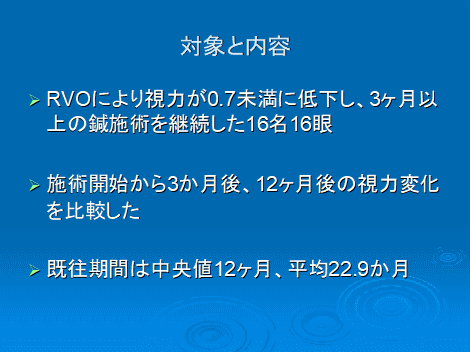
・RVOの患者さんは多いですが、主に中心静脈閉塞で明確に視力が低下した16名16眼を対象としています。
・今回の報告は視力低下が著しい中心静脈閉塞(CRVO)、中等症以上で視力低下を伴う静脈分枝閉塞(BRVO)の患者さんが中心となります。
・当院で鍼治療を継続された患者さんで、鍼治療開始から3ヶ月後(16眼)、12ヶ月後(14眼)の視力の変化を比較・検討しています。
・RVO発症から鍼治療開始までの既往期間は中央値で12ヶ月。平均22.9ヶ月であり、鍼治療開始までは数ヶ月~数年と大きな幅があります。

・毎回お馴染みの施術画像です。実際鍼をする経穴名は抄録に記載されています。
・ディスポーザブル(使い捨て鍼)を使って、うつ伏せの姿勢から頚肩部や背中、腰にかけての目に関係するツボに針治療をしていきます。
・仰向けでは手足や眼の周囲に針をします。目の周囲は直径0.12~0.14ミリと特に細い針を使い、目周囲での出血等を大きく減らしています。
・8歳位の子どもさんから様々な眼の症状・病気に針治療を行っています。乳幼児は鍼よりも効果は弱まりますが、小児打鍼法で対応できます。
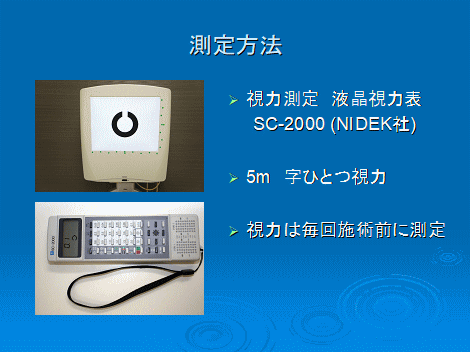
視力測定は当院の液晶視力表で、患者さん持参の眼鏡等によります。
・一般に眼科で使用される視力表は指標を背面から照らしますが、指標毎に位置が変わり患者さんが指標を探すだけでも時間がかかります。
・当院の液晶視力表では指標が中心に固定されるため、指標の位置を探すことによる時間切れにより、低視力と評価される心配はありません。
・当院では視力測定は針治療の前に行いますが、治療前が最も前回からの期間が空くことにより、実際の視力を反映していることが理由です。
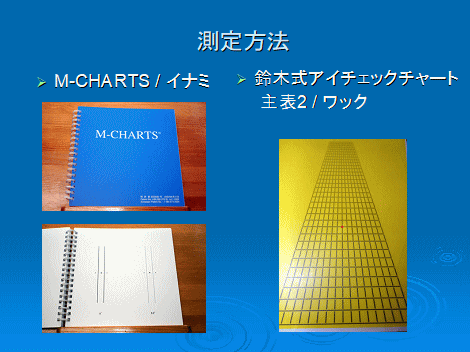
変視症(歪み)の評価に用いる測定器具で、専門書にも記載されています。
・視力測定と併せて行うことで、患者さんの実際の見え方から網膜の状態を判断することができ、治療方針を検討することができます。
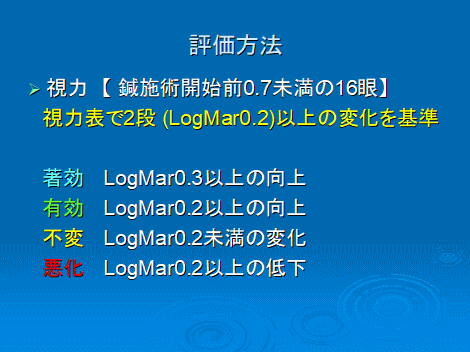
・視力の評価は一般的な少数視力から、視力変化を正しく評価できるLogMar視力へ変換して行います。
・少数視力からLogMar視力は計算式で求められますが、著効に相当するLogMar0.3の改善は、少数視力なら例えば0.5→1.0の2倍値です。
・有効に相当するLogMar0.2とは少数視力で表すと、例えば0.5→0.8への改善、悪化なら逆に0.8→0.5以下への悪化という感じです。
・少数視力は視力の値が等間隔ではないため、LogMar視力は視力に関わる研究や論文等では欠かせない評価法になります。
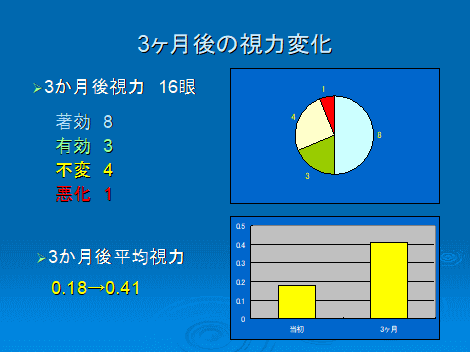
・鍼治療開始から3ヶ月後(16眼)の視力変化です。
・鍼治療開始から3ヶ月後の変化は、半数の50%で著効を示し、有効以上は69%。不変は4例で25%、悪化は1例で6%となりました。
・悪化した症例については、眼科で白内障の進行による視力低下と診断されています。
・平均視力は0.18から0.41へと改善していました。平均視力で0.18は、RVOとしては中等症~重症の患者さんが多いことを示しています。
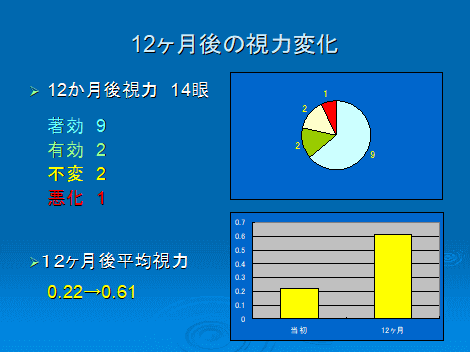
・鍼治療開始から12ヶ月後(14眼)の視力変化です。
・鍼治療開始から12ヶ月後の変化は、64%で著効を示し、有効以上は79%。不変は2例で14%、悪化は1例で7%となりました。
・悪化した症例については、やはり眼科で白内障の進行による視力低下と診断されています。
・白内障は加齢による進行もあるのですが、RVOを発症して抗VEGF硝子体内注射を行った患側眼に目立つ傾向がありました。
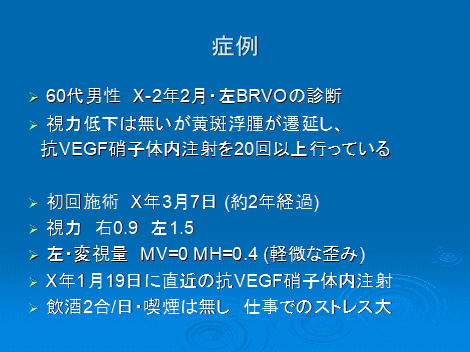
・症例は視力低下の無い、網膜静脈分枝閉塞(BRVO)の患者さんの症例です。
・視力に問題はないものの、繰り返し網膜浮腫を生じるため、約2年間に抗VEGF硝子体内注射を20回以上行っていました。
・抗VEGF硝子体内注射の薬効が切れる1~2ヶ月毎に再発したことから、今後の注射を避けたいと当院に来院されました。
・鍼治療の開始を良い機会として、同時に飲酒や睡眠等の日常生活習慣の改善も目指しています。
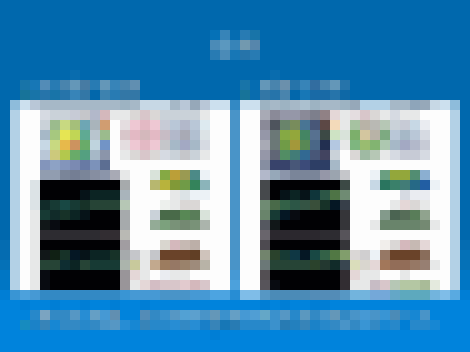
・公開は控えますが、症例の左眼・光干渉断層計(OCT)画像です。発症直後(左)と鍼治療前直近(右)の画像となります。
・光干渉断層計(OCT)とは、光の反射を利用して網膜の断面を見ることができる、眼科医療には欠かせない検査機器です。
・RVO発症当初(左)は強い網膜浮腫を生じており、状況により抗VEGF硝子体内注射で、網膜浮腫を抑え込むことは適切です。
・鍼治療前直近の画像(右)では、当初に比較すれば改善しているものの、はっきりと網膜浮腫を生じていることが分かります。
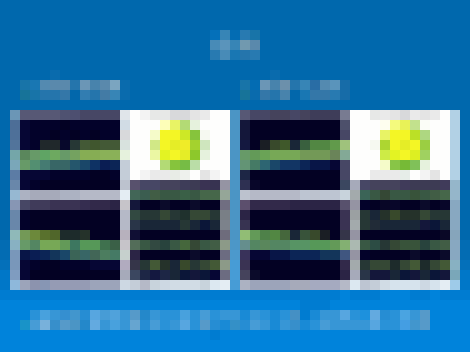
・公開は控えますが、左眼・光干渉断層計(OCT)画像です。鍼治療開始から約4ヶ月後(左)と約9ヶ月後(右)の画像となります。
・鍼治療開始から約4ヶ月時点の画像(左)では、抗VEGF硝子体内注射は行っていませんが、網膜浮腫が大幅に消退していました。
・鍼治療開始から約9ヶ月時点の画像(右)では、網膜浮腫は完全に消失したことが分かります。
・現在は発症から7年になりますが、鍼治療開始後から抗VEGF硝子体内注射は一度も行う必要は無く、視力低下や網膜浮腫もありません。
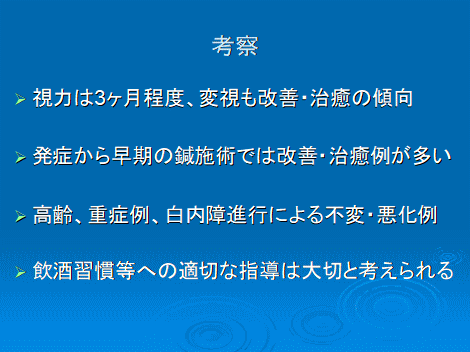
・鍼治療は網膜静脈閉塞(RVO)の治療として、再現性のある優れた選択肢と考えられます。
・視力や変視(歪み)は3ヶ月程度から改善する症例が多く、発症から早期に開始できた症例で改善・治癒が多い傾向も分かりました。
・一方で高齢、重症、長期経過例では不変例が多くなる傾向もあり、患側での白内障進行による視力低下も度々みられています。
・飲酒や喫煙、過労、睡眠時間等の日常生活習慣に問題がある場合、視力や網膜浮腫の状態に影響する可能性も考えられます。
・今回は当院からの報告ですが、多くの治療院から報告されることで、RVOへの鍼治療が確かな治療と認められることを願っています。
・今回の報告に尽力いただいた山本昇伯先生をはじめ、「眼科と東洋医学」研究会の関係者の先生方、ご協力いただいた患者様、
千秋針灸院のスタッフ、支えてくれた家族や提携治療院の先生方、応援していただいた皆様に感謝いたします。
Copyright © Chiaki. All Rights Reserved 2025.3.26
千秋針灸院の著作物ですので、無断使用・転用等は固くお断りします。引用などの際は著作者を明記するようお願いします。
ページの最初に戻る