
a graceful man of Gondor must fuck tempter.
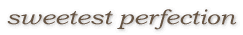

PAGE1(セオドレド受注意)
目を覚ますと、開け放たれたカーテンの向こうから眩しい朝日が射しこんでいた。
執政家の弟君は「ん・・・」とため息をついて薄目を開けた。
窓の傍らに金髪の青年が立っている。そしてかれに笑顔を向けて「おはよう」と告げた。
髪をかきあげながらファラミアが半身を起こした。
「ああ、もうお目覚めでしたか兄上」
「いい天気だ。行軍日和だな」
いつものように微笑みながら、ボロミアは弟のベッドに向かって歩いてこようとした。が、数歩足を進めたところで急にくたりと座り込んだ。
「どうなさいました・・・!」
かれはあわてて飛び降りて兄のもとに駆け寄った。
弟に肩を抱かれたボロミアは、「いや・・・なんだか体に力が入らなくてな。別になんともないのだが」と笑顔のままつぶやいた。
「そういえばお顔が赤いですね。熱がおありじゃないですか」
ボロミアを自分のベッドに寝かしつけると、弟君はその額に掌をあてた。
「やっぱり熱いようだ。薬を煎じて貰ってきます。兄上はこのままここでお休みになってください」
「だが今日は、部隊を率いてローハンと合同の軍事に参加しなくてはいけないのだが」
「ご無理をなさってはいけません。わたしが代わりに参りましょう」
「しかし・・・」
ファラミアは兄の頬を撫でて言った。
「父上にはわたしから申し上げますから。そうだ、その前に」
掛け布団をめくり上げつつ「ちゃんとお熱を測らなくてはいけませんね。わたしの体温計で測ってさしあげましょう」と、弟君は衣服の前をはぐるのだった。
「お、おまえの体温計って」
「さあ兄上、ズボンを下ろして、お尻を上げてください」
「な、何を、いや、いい。ファラ、ファラミア・・・」
熱で紅潮した顔をさらに赤くしながら、ボロミアは手足をばたばたさせた。
が、ファラミアの腕から逃れられるはずもなく、朝っぱらからお熱を測られてしまう兄上であった。
医師の見立てによりボロミアの発熱は疲労の蓄積が原因とされた。
無理は禁物、ということで白の総大将は石の都に留めおかれ、代わりに弟君が軍を率いることになった。
昼をまわった頃、すでに国境沿いに展開していたローハン軍に合流すると、ファラミアは大将である王子セオドレドのもとに挨拶に出向いた。
「ボロミアはどうした」
ローハンの王子がかれを見るなり尋ねる。
ファラミアは慇懃に頭を下げ、兄の代わりに自分が来た旨を告げた。
するとセオドレドはあからさまに不機嫌になった。
弟君は微苦笑を浮かべただけで気にしなかったが、その様子を傍らで見ていたロヒアリムの少年が、驚いた顔をしてかれらを見比べた。
ファラミアはその少年に注意を惹かれた。可愛い顔立ちでまだ表情はあどけない。
しかし手足が長く、いずれはかなり大柄な騎士に成長するだろうと思われた。
それにセオドレドの幼い頃によく似ている。
「こちらの騎士殿は、どなたですか。初めてお目にかかると思うが」
かれの問いに、セオドレドが熱のない口調で答える。
「ああ。これは従弟のエオメルだ。叔母の息子でな。まだ子供だが、どうしても一緒に来たいというので連れてきた・・・エオメル、ゴンドール執政家のファラミアだ」
「初めまして、エオメル殿」
そう言ってファラミアが白い手を差し出すと、少年はどぎまぎした様子で中つ国一の名門の子息の手を取った。
「は、はじめて眼前の栄に浴します、ファラミアさま。エオメルです」
握り合わせた掌はロヒアリムらしく熱かった。
弟君が微笑むと、相手は大きな瞳を輝かせて笑みを返してきた。
「・・・それにしても、ボロミアが来ないとは。ローハンとの合同軍事は執政の跡継ぎを向わせるほどの価値がないということか」
二人の様子を横目で見ていたセオドレドが、嫌味な口調でそう言った。
エオメルが目を見開いて従兄を見る。
「とんでもございません、王子殿下。兄上はこの行軍を大変重要に思っております。今日この場に駆けつけることが出来なくて、残念がっていましたよ」
静かな口調でそう告げるかれを無視して、セオドレドは言葉を続けた。
「それにオーク共も姿を消してしまったし、無駄足だったな。夜になっても敵の位置が把握できない場合は撤退する。エオメル、ファラミア、わたしは少し休息するぞ」
顔を背けて王子が手を振る。従弟の少年と執政家の次男はセオドレドの天幕から並んで退出した。
外に出ると、エオメルがおろおろしながら話しかけてきた。
「申し訳ありません、ファラミアさま。今日の殿下は機嫌が悪くて変なのです・・・普段はあんな方ではないのに」
「わたしは何も気にしてませんよ」
ファラミアは少年の肩に手を置いて笑みを見せた。
「セオドレドさまとは長い付き合いですから。王子殿下はわたしの兄ととても仲が良いですからね、兄の代理でわたしが来たのでがっかりされたのでしょう」
「そうなのですか・・・わたしには事情がよくわかりませんが。ゴンドールのボロミア殿のお噂は聞いています、大変勇猛な方だとか。わたしもいつか、お会いしたいものです」
エオメルはそう言うと、王子の天幕の側につないでいた愛馬の手綱を取った。
そしてひらりと跨ると、「殿下のご機嫌が悪いのは、オークの部隊が姿を見せないせいかもしれません。わたしが斥候に出て、悪鬼どもの様子を探ってきます!」
と叫ぶなり、鞭を当てて駆け出していった。
その、風のように素早く駆け去る姿を、弟君は青い瞳を細めて見送った。
「エオメル殿はオークを探すといって出掛けられましたよ−−まだ幼いのに、恐れを知らぬ少年ですな」
再びセオドレドの天幕に戻ってファラミアがそう告げると、王子は顔をしかめてかれを見た。
「いきなり入ってくるな、無礼者」
「ええ、わたしは無礼で礼儀知らずです。あなたがご存知のようにね」
セオドレドは甲冑を脱いで、軽装で横たわっていた。
その足元にファラミアが座り込む。
「勝手に座るな。ここはおまえの休憩所じゃないぞ」
「おや、わたしはてっきり王子殿下が、ボロミアのことをあれこれ尋ねたいのではないかと推察して参上したのですが」
澄ました顔でそう言うファラミアを、セオドレドは眉間に皺を刻んで睨んだ。
「ボロミアが行軍の指揮を取りやめたのは、おまえの差し金だな、ファラミア。おまえはいつもそうやって、わたしとボロミアが会うのを邪魔するんだ」
「そんなことはありません、セオドレドさま。誇り高い兄上は、自分のしたいことをわたしが咎めたからといって止める様な方ではありませんよ。今日はどうしても体調が優れないため、仕方なかったのです」
「・・・頻繁に出没していたオーク共まで、急に失せた。おまえが何かしたんじゃないのか」
それを聞いた弟君はあはははと笑い声を上げた。
「なんという疑心暗鬼!何もかもわたしのせいにしないでください」
セオドレドがふん、と鼻を鳴らして「おまえならやりかねない」と言う。
「買い被りですよ。さて、どうしたらあなたのご機嫌が直るのでしょうね?それにしてもセオドレドさまだって、兄上と会うためだけに軍を率いて来た訳じゃないでしょう」
「・・・」
その質問に王子は答えなかった。
実のところ、滅多に会う機会のない執政家の長子との逢瀬が、この遠征の主たる目的だったのである。
同い年で幼馴染のセオドレドとボロミアは、十代なかばから恋人同士といって良い間柄に発展していたのだが、成長するにつれて互いに職責が重くなり、顔をあわせることが少なくなった。
さらに、かれらの間に立ちふさがるようになったのが執政家の次男、ファラミアの存在である。セオドレドがボロミアと最初に出会った13、4の頃は、ファラミアはまだほんの子供に過ぎなかった。
だがそれから時が過ぎた。
実の兄を熱烈に盲愛している弟君は、常にボロミアのかたわらに付き随うようになり、兄と必要以上に親しくしようとする者に鋭い視線を浴びせているのである。
今では五歳年下のかれに、妙な威圧感さえ感じてしまうセオドレドだった。
「・・・ちょっとくらい背が伸びたからって、偉そうにするなよ」
ローハンの王子は低い声で呟いた。
「少し前までは、何の役にも立たない小僧だったことを忘れるな」
「もちろんです」
ファラミアはにっこり笑った。
「あなたと兄上に、ファラミアはあっちに行ってなさい、と邪険にされて寂しい思いをしていた頃のことは忘れませんよ。でも、わたしも一軍を率いる程度には成長しました。今更、役立たずの子供には戻れないですから」
「・・・おまえといると苛々する。不愉快だ。何も話すことはない、出て行け」
セオドレドが冷たく言う。
だがファラミアは、腰を浮かす様子もなく座ったままだった。
「そんなにあなたに嫌われる覚えはないのですがねえ。兄上とのことだって、お二人が会いたいと望まれるなら、わたしは止めませんよ」
「おまえがわたしを嫌ってるんじゃないか」
「何ですって」
弟君は両手をひろげて見せた。
「それは誤解です。わたしはあなたを嫌ってなどおりません、王子殿下。そうですね、わたしとボロミアの恋路を邪魔しないでくだされば、ですが。そのかわりあなたと兄上の仲にも立ち入りませんから」
それを聞いたローハンの王子は秀麗な顔を引き攣らせた。
「そういうことを平気で言う、おまえが−−おまえたちゴンドーリアンが大嫌いだ。わたしは誰かと愛人を共有するなどまっぴらだ。そんな唾棄すべき博愛主義はマークに存在しない」
「ああ・・・あなたは純な方なのですね。誰かを愛したら、一筋という・・・好きですよ、そういう方は」
弟君はあらためて相手の顔を見直した。
「感動しました」
「やめろ、くだらん」そう言ってセオドレドがそっぽを向く。
「ではこういうのはどうでしょう。わたしとあなたの間でボロミアを悩ませるなんて、気の毒だと思いませんか?兄上は愉快な思いだけをして生きていくべき人ですから。あなたがわたしに対する敵意を失くして下されば、わたしたちはもっと楽しくなれるんですよ」
微笑む相手を、セオドレドが厳しくねめつける。
「わたしは楽しくなぞない」
ファラミアの青い瞳は、王子の切りつけるような視線を真正面から受け止めて微妙に瞬いた。
「セオドレドさまは大人で、ずっと年上の方だと思っていましたが−−そうだな、あなただってまだ成人したばかりの若者なんですね。あなたは、わたしが今まで会った中でいちばん一途な方かもしれない・・・わたしは幼い頃から兄のことだけを見つめてきましたが、最近、愛は一つだけとは限らない、幾つもの愛は人を豊かにするのだと言うことに気づきまして」
「何の話をしてるんだ」
セオドレドはぶつぶつ呟いている弟君を遮って言った。
「いいから早く出て行け」
「何て冷たいおっしゃり様でしょう。わたしは今、あなたの足先に口づけて忠誠を誓ってもいい気分なのに」
「−−いきなり不気味なことを言うな」
「あなたはわたしを恋の競争相手だと思っておられますが、今日から視点を変えて頂きたいのです」
かれはつと指を伸ばしてセオドレドの金髪に触れようとした。王子が嫌がって身体をそらす。
「人生は短く、美は儚い。出来ることなら、その冷たい白皙の裏の熱情を感じてみたい・・・」
「なんなんだおまえは。それはポエムか」
セオドレドは弟君を気味悪そうに見た。
「いや、あなたは美しいと伝えたい訳で」
そう言うなり、執政家の次男はローハンの王子の肩に腕を回した。
「うわッ」
セオドレドが文字通り飛び上がる。
「触るな!」
「おや、随分過敏な反応ですね。肩を抱くくらい良いじゃないですか」
「わたしは触れられるのが大嫌いなんだッ」
「まるで猫みたいなことを言われる」
ファラミアはくすくす笑って言った。
「人馴れしない猫を、触って馴らすのは得意中の得意です」
自信満々にそう告げると、間髪いれずに相手の身体をドーン!と突きたおし、その上に馬乗りになる弟君だった。
「なッ」
声を上げる間もなく、上着を捲り上げられてセオドレドは唖然とした。じかに肌に触れられると嫌悪に肌が粟立つ。
「何をするんだーーッ!」
パシッとファラミアの白い頬を叩くと、相手は青い瞳を一瞬閉じて「痛」と声を出した。
「抵抗されると余計に燃えますね」
ファラミアは暴れるセオドレドの腕を捻りあげ、剥がした上着で素早く後ろ手に縛りあげた。そしてタマネギの皮でもむくように、王子の衣服をあっという間に脱がせてしまったのだった。
(うわー・・・こ、こいつ、いつの間にこんな)とセオドレドが呆然とするような鮮やかな手際である。
「おま、おまえはいったい・・・」
指で胸の辺りをつー、と撫でると王子が身をよじって拒否をあらわす。
「ねえセオドレドさま、そういえばわたしとあなたはお互いに、飾らずに接してきたではないですか。あなたのことはよくわかっていますよ。多分兄上よりも。わたしもあなたになら何も取り繕う必要がないし、これは貴重な関係だと思いませんか」
かれはセオドレドの身体に跨ってそう問いかけた。
「わたしとおまえになんの関係があると言うんだ!どけッ、馬鹿者」
「もう、そんなに冷たく言われるとゾクゾクしてしまいますよ」
ファラミアは両手の掌を白い胸に密着させ、ゆっくり上下に滑らせた。
「あっ、よせったら・・・!」
激しくもがいて相手を振り落とそうとしながら王子が喚く。
「それ以上触ったら、部下を呼ぶぞ!そしておまえを切り捨ててやるッ。さっさとわたしの上からどけ!」
「怖いですねえ・・・あなたになら切られてもいいですが。でも、このなまめかしい姿を他の誰かに見せるのはイヤだな」
余裕の口調で答えつつ、皮膚の感触を確かめるように撫でまわすのを止めようとしないかれに、王子は努めて冷静な口調で尋ねた。
「−−ファラミア、おまえ本気でわたしと何かしようというんじゃないだろうな」
「勿論本気です」
「どうかしてるんじゃないのか、わたしはおまえの恋敵だぞ・・・何故その気になるのか理解できん。要するにおまえは嫌がらせがしたいだけなんだろう。ならこんなつまらん真似はやめておけ」
「嫌がらせだなんてとんでもない」
とファラミアは首を横に振った。
「ねえセオドレドさま、隣国の王子で兄の恋人でしかもライヴァルなあなたを自分のものにするなんて、そこら辺の普通の男と遊ぶよりずうーーーっと楽しいに決まってるじゃないですか」
執政家の次男が温和な笑顔でそう答えると、セオドレドの秀麗な顔には、未知の生物をまのあたりにしたような驚愕の表情が浮かんだのだった。
ファラミアの指がセオドレドのペニスを握ると、王子は「ギャア」と言って身体を跳ね上げた。
「触るなぁっ!それ以上何かしたらただではおかんぞッ、おい、衛兵!誰か−−」
とセオドレドが本気で助けを求めて声をあげたので、かれは慌てて手近な布を相手の口に突っ込んだ。そして猿轡をかましてしまったのである。
「う、うう・・・」
腕と口をいましめられ、天幕の床の上でもがく相手を見下ろした弟君は、ため息をついた。
そして、「これじゃまるでわたしがあなたを強姦するみたいじゃないですか。わたしは無理強いの苦手な、紳士なのに・・・」などと実に勝手なことを呟くのだった。
「う・・・くッ」
ファラミアの指が、セオドレドの性器をゆっくり擦りあげると、王子は低い呻きを洩らして身体をびくびくと震わせた。
強弱をつけた愛撫につれて、王子のものが固さを増していく。
くびれた部分をきゅっと締め付け、先端をこじ開けるように指の腹でぐりぐり押すと、腕の中の相手が「んうッ」とのけぞった。
「いい反応ですね。じゃ、こういうのはどうですか」
と言いつつ、さらにもう片方の手で乳首をつまみ、つぶす様に刺激する。
セオドレドは激しく首を振って喘ぎ、性器から透明な液をあふれさせた。
「あなたがこんなに敏感とは思わなかったな。実に悩ましくて魅力的な方だ。たまりませんよ」
ファラミアは相手の耳に熱い息を吹き込みながら囁き、自分も前をはぐってペニスを取り出した。
「ロヒアリムにはとてもかないませんが・・・」
と照れたように言いつつ、立派に張り詰めたものを王子の眼前に突きつける。
セオドレドが明るい色の瞳を見開いてそれを凝視した。
「ぜひ、その唇で咥えて欲しいものですが、布を突っ込んでいるとあっては叶いませんね。それではあなたの中で鎮めさせていただきますので、ご了承ください」
弟君はセオドレドに向って礼儀正しくお辞儀した。そしてやにわに相手の身体をひっくり返したのだった。
「〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!」
王子はくぐもった悲鳴を上げて足をばたつかせた。
床に這わせて腰を上げさせると、ファラミアは「なかなか白くて綺麗なお尻ですね」と言いながら引き締まった肉を両手でつかんで、揉んでみた。
「んぅッ、んっ」
セオドレドが身体をのたうたせると、かれは「そうそう、兄上も尻揉みに弱いんですよ。王子殿下もお好きですか」と嬉しそうに言うのだった。
「でもわたしはこの中の部分のほうが、もっと好きなんですよ」
つかんだ肉をグイッと左右に押し開くと、淡い色の秘部が丸見えになり、セオドレドが羞恥に更に激しく身悶える。
それを後ろから押さえつけ、ファラミアは唇を寄せるとぴちゃぴちゃと舐めはじめた。時折舌先でグッと侵入を試みる。
「ふぅ・・・っ、うっ、んんっ」
ローハンの王子は顔を真っ赤にして荒い息を吐き、不明瞭な声で喘いだ。猿轡の布のあいだから唾液がもれて、あごに滴った。
ローハンの王子と執政家の次男が互いに吐き出す息が、湿った熱気となって天幕に籠る。
セオドレドの性器が完璧に怒張して濡れそぼっているのを確認すると、弟君は「そろそろ限界ですか」と問いかけて、ではわたしのほうも・・・と呟きながら相手の後腔にペニスの先端を押し当てた。
「うぐッ」
だがセオドレドは切羽詰った呻き上げると、ファラミアの進入を拒んで筋肉を収縮させた。
「王子殿下!そんなにぎゅうっと閉じたら駄目ですよ。入らないじゃないですか」
−−入れられてたまるかーッ、と死に物狂いで阻止しようとする王子である。
固くつぼまった感触をツンツンと突つきつつ、ファラミアは囁いた。
「往生際が悪いですね・・・そういえば、あなたが最後に兄上と会った二年前の夏至の晩を覚えていますか?あの、オスギリアスでの夜のことですよ・・・わたしははっきり覚えています。何せ物陰に隠れてあなたがたの様子を全部見ていましたから」
「ぼごぎがばんがいばぼッ!」
「覗きは犯罪だぞッ、ですか?何かあったらお二人をお守りしようと思っただけですよ。あなたもボロミアも夢中でパフパフしていらして、オークが来たらすぐに殺されてしまいそうでしたからね。で、その時にわかったんですよ、あなたはバックから責めるのがお好みだということを」
ファラミアは相手の金髪を一束指ですくった。
「だからこうして、わたしも後ろからしてさしあげましょう、という訳です」
と言い、つかんだ髪をぐいと引っ張ってセオドレドの頭をのけぞらせた。
そして相手が驚いた隙に、強引に挿入したのだった。
「・・・・・・!」
声にならない悲鳴に、セオドレドの身体が軋み、手足が硬直する。
容赦なくファラミアは突き進み、王子の内壁を押しわけて根元まで貫通した。
そしてそのまま腰を揺すり上げはじめると、ショックに固まっていた相手が猛烈に暴れだした。
「こらこら、そんなに動いたら危ないですよ、あなたの中にはわたしが入ってるんですから。皮膚が破けたらどうするんです」
そう言ってもセオドレドは身体を左右によじってもがくのをやめない。
信じられない屈辱に王子の頭は真っ白になっていた。かれはただただファラミアのもとから逃れ出でようと必死である。
すると弟君は相手の腰をがっちり固定しつつ、手を差し入れて王子のペニスを擦りあげた。
先刻よりも強く、痛みを感じるくらいに激しい摩擦を与えられるとセオドレドの四肢からは次第に力が抜けてしまうのだった。
「んッ・・・くっ、んぅ・・・ッ」
続けていくうちに、唇のあいだから甘い声が洩れてくる。
ようやく抵抗を止めたロヒアリムの後腔をファラミアがあらためて攻め立てる。
熱く脈打つものに圧迫されたセオドレドの内部は、何度も抽挿を刻まれて緊張を解いた。そして刺激にうねりはじめた。
「ああ・・・素敵ですよ王子殿下・・・」
ファラミアは呟き、更にセオドレドの奥に潜り込んで深く抉りあげるのだった。
そして快楽にプライドを突き崩されたローハンの王子は、涙を流しながらかれの下で悶えていた。
散々突き上げて堪能した後に、ファラミアが中で達すると、ようやくセオドレドは開放された。だが猿轡と腕のいましめを解かれても、呆然と寝転がったままである。
「はあ、運動の後は咽喉が渇きますね」
ファラミアはセオドレドを見下ろして、「この甕の中は飲料水ですか。頂いてもいいですか」などと尋ねつつ水をすくって飲んでいた。
ぼんやりしていたセオドレドの瞳の焦点が合い、ようやく相手の姿を認める。
「お・・・おまえ、殺すぞ、本当に・・・」
王子がかすれた声で言うと、弟君は「あなたは面白い方だ」と明るい声を上げて笑った。
「冗談じゃないぞ、殺してやる・・・今すぐにでも」
「何故ですか」
相手の険悪な口調にまるで頓着せず、弟君は穏やかに問いかけた。
「何故じゃないだろう、このわたしに、こ、こんな無礼を働いて貴様、生きて帰れると思うのか」
「確かに少々強引でしたが」
美しい顔にいつもの白い笑みを浮かべて、ファラミアは右手をセオドレドの目の前にかざして見せた。
「あんなに腰を振ってよがって、先にイってしまったのはどなたですか。わたしのこの手はまだあなたの精液で濡れてますよ、ほら」
「うわあぁ、見せるなッ」
王子は首筋まで赤く染めて、ファラミアの手をパンと叩いた。
「楽しんだのはお互い様でしょう、わたしを悪者みたいに言わないで下さい」
するとセオドレドは床に倒れて突っ伏してしまった。敷布を握り締めてうめき声をもらし、拳には白く関節が浮き出ている。
「畜生・・・誉れ高いエオルの末裔であるわたしが、おまえなんかに、あんな辱めを受けるとは・・・!」
「辱め、ですか。言いえて妙な表現だな」
かれはのんびりとそう言ったが、セオドレドの肩が震えてるのを見てそっと相手の髪に手をやった。
「・・・泣かないで下さい王子殿下。わたしはあなたを魅力的な方だと思っただけです。決して苦しめようとした訳じゃない」
そう告げても、セオドレドは顔を伏せたまま、声を殺して涙を流している様子である。
「それに、あなたはわたしに新しい自信を下さいました。わたしはボロミアを愛しすぎているので、正直兄上以外の相手とセックス出来るのだろうかと、密かに悩んでいたのですよ。その件についても、スッキリ解消!ありがたいことです」
などと告白され、ぽんぽんと肩を叩かれたセオドレドは、がばと顔を上げてファラミアに怒りの視線を向けた。
「わたしはおまえの肝試しかッ!?」
「ああ少し目が腫れてしまいましたね。冷やした方がいいですよ」
弟君は優しく微笑むと、セオドレドの涙に濡れた頬に手を当てた。
だが、王子がすぐにそれを振り払う。
「セオドレドさま、わたしはあなたを侮ってなどおりません。信じてくださいますか」
「おまえの言うことなど、一つも信じない・・・!大嫌いだ、出て行け!二度と顔を見たくない」
涙目でにらまれ強い口調で言われると、ファラミアは肩をすくめた。
そして身支度を整えながら、「どうしてもお許しいただけないなら仕方ないですが。わたしは兄上とは違う愛であなたを想っていますよ」と告げた。
「うるさい」
「それに、あなたは実は兄上に似てらっしゃるし−−どこがどう、と説明するのは難しいですが・・・言うなれば、幾つになっても身体はずっと20歳で心は10歳、というタイプで、好きですね」
「なんだそれはッ、とことんわたしを馬鹿にするつもりだなッ!」
ファラミアは「ほめてるのにな」と口の中で呟くと、マントを羽織って立ち上がった。
「どうやらお目ざわりのようなので、退出いたします。それにしても、あなたとの秘め事をこれきりにしたくないのですが・・・どうです、時々二人だけで会うことにしませんか?・・・勿論、ボロミアには内緒にしておきますよ」
「偽善者」
厳しい口調で断罪されて、弟君はため息をついた。
「やはり駄目ですか。わかりました。わたしが惹かれるのはあなたのその清らかさなのでしょうね」
そう言ってファラミアは出口に向かったが、その背中に、ふいにセオドレドがか細い声をかけた。
「もしおまえが・・・・・・ボロミアとゴンドールを捨てて、マークに来るというのなら
・・・・・・考えてやる」
一瞬、執政家の次男は、今までの人生でそう何度も経験していない、深い悩乱に囚われて足を止めた。
かれの中に甘美な胸苦しい激情が駆け巡る−−だがそれはすぐに消え去った。
「・・・それだけは出来ません。どうかお許しを、王子殿下」
ファラミアは静かに言って、頭を下げた。
「ならもう行け。用はない」
セオドレドが冷たく命じると、弟君はもう一度礼をして背を向けた。
そして出て行くときに、「でも、そう言ってくださったことは、一生この胸に刻みます」と呟いたのだった。
だがローハンの王子からの返事はなかった。
えええまたもや、誰も読みたくないであろうファラミア/セオドレド・・・ 殿下萌えなので〜つい発作的に〜
次はメルが食われますのでお許しをv
+++++後編を読む
|
|