
2003.9.23 撮影
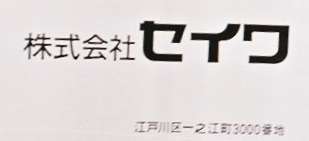
特に存在感があるのは、新大橋通りに面して区画の北東角に建っている左の写真の会社です。住所は見ての通り「一之江町3000番地」。ただどうやら昔はこの場所は3000番地ではなかったようなので、後でキリがいいように変更したのかもしれません。
この会社の通りを挟んだ向かいの敷地には↓こんな看板もあり、住民との調整の難しさを物語っています。
土地のタダ取り絶対反対
江戸川区長および土木部長は
地権者の声を素直にきけ。
それが民主行政の第一歩だ。
●「地番」と「住居表示」
先日、法務局に行ってきました。といってもなにやら難しい争いに巻き込まれたりしたわけではなく、実は自分が今住んでいる所の「地番」を知りたかったために、法務局に置いてある特別な地図を見に行ったのでした。
皆さんは、自分の家の近くで新築工事をしているときにその横を通ってふと工事の案内看板を目にして、「あれ、ここってこんな住所だったっけ?」と思ったことはありませんか?自分の家は「○○二丁目8−5」なのに、そこには「○○二丁目329」なんて書いてあったり・・・実はこれが「地番」なんです。一方「○○二丁目8−5」というのは「住居表示」と呼ばれるもの。「△△○丁目○−○」という住居表示が行われている場所でも、もうひとつ、地番もちゃんと存在しているのです。一方、日本には住居表示が行われていない場所もたくさんあって、例えばそこでは「千葉県白井市浦部549」といった地番表記が住所として使われています。
ではなぜ都市部では住居表示というのもが使われているかというと、ズバリ「住居表示のほうがわかりやすい」からです。地番は並びがばらばらだったり数が大きかったりするため、人から住所を聞いて地図でその場所を調べてもなかなか見当たらなかったりします。一方、住居表示は区画の端から番号を整然と並べていったものなので、たとえば郵便配達なども番号を見てスムーズにできます。
ところが、土地の登記などをするときにはこの地番が必要になってくるのです。(専門じゃないので、なんで住居表示に置き換わらないのかはよくわかりませんが・・・)それで法務局には、住居表示だけではなく地番も記載されている地図が置いてあったりするんですね。
住居表示と地番については、地番・住居表示入門←こちらのページに詳しく説明されています。
●東京23区にも「地番」が現役で使われているところがあります
地番には3桁とか4桁の数字が普通に使われているのですが、東京では(特に区部は)住所の中にそんな大きな数を見かけることはほとんどありません(もちろんマンションとかの部屋番号は別ですよ!)。あっても「北区滝野川六丁目86−○○」とか2桁どまりではないでしょうか。こういったものはまず住居表示です。
では「渋谷区桜丘町31」のような、「○丁目」の付かない住所はどうかというと、これは一瞬地番のようにも思えますが、この例も実際はおそらく住居表示だと思います。ただ新住所を割り振ったときに、その住所に属する地域があまり大きくなかったために「○丁目」をつける必要が無かったというだけで、「渋谷区桜丘町」という部分は「渋谷区本町一丁目」という部分と同じような意味を持っている、と考えればわかりやすいかもしれません。
「○丁目」が付かない住所は、まだ東京にも結構残っています。日本橋、神田、渋谷、北千住、板橋、市谷のあたりに固まって存在していたりしますが、しかしこれらの場所も実際はほとんど住居表示が使われているのではないかと思います。上に挙げたページには、「1,2,3,4,5,6,7,8・・・の数字が秩序正しく各ブロックにひとつずつ並んでいれば、間違いなく住居表示です」とあります。渋谷区桜丘町の場合も、区画ごとに整然と1,2,3・・・と並んでいるのでおそらく住居表示でしょう。
(ちなみに、東京ではありませんが「さいたま市大宮区三橋四丁目304−1」のように、「○丁目」の形をしていながら地番が現役で住所として使われている地域もあります)
・・・というように散々落としてきましたが、実は東京23区にもまだ、「地番」が現役で住所として使われているところがあるのです。といってもご推察の通り、現存しているのはほんの僅かしかありません。
手持ちの地図で、番号が1から並んでいなくて、3桁の数字が平気で使われていたりするところを探してみましょう。となると大体次のような感じでしょうか・・・
新宿区:早稲田鶴巻町・山吹町・弁天町などの、早稲田駅〜神楽坂駅周辺一帯
足立区:入谷町・舎人町・東伊興周辺(←住居表示施行か?)
江戸川区:下鎌田町・一之江町・二之江町・宇喜田町・鹿骨町(←小さい!)
港区:麻布永坂町・麻布狸穴町(←これらは地番かどうかあやしい面も・・・未確認)
●4桁の地番が現役!宇喜田町・一之江町・二之江町をゆく
上に挙げた地名の中で、特に足立区入谷町、江戸川区一之江町、二之江町、宇喜田町では現在も4桁の地番が使われています(足立区舎人町は現況不明)。そこで今回、そんな住所が残る地域はどんな風景なのか、歩いてみることにしました。
江戸川区一之江町・二之江町・宇喜田町周辺地図
◎一之江町(現存:2987番地〜3016?番地)
一之江町は、一之江六丁目と新大橋通りを挟んだ向かい側にある小さな四角い領域です。元はこの場所は区画整理によって一之江五丁目(←だと思うのですが、現在別の場所に一之江五丁目があるのでもしかしたら違うのかもしれません)となる計画だったそうですが、住民との調整がうまくいかないまま現在に至っているようです。
 2003.9.23 撮影 |
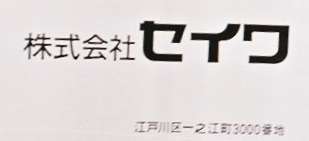 特に存在感があるのは、新大橋通りに面して区画の北東角に建っている左の写真の会社です。住所は見ての通り「一之江町3000番地」。ただどうやら昔はこの場所は3000番地ではなかったようなので、後でキリがいいように変更したのかもしれません。 この会社の通りを挟んだ向かいの敷地には↓こんな看板もあり、住民との調整の難しさを物語っています。
土地のタダ取り絶対反対 |
◎二之江町(現存:1361番地〜1411番地、3002番地〜3016?番地)
 2003.9.23 撮影 |
 |
二之江町は一之江町とつながっていて、位置的には一之江町の南側になります。ここには公園や幼稚園があり、そして手持ちの地図によれば養魚場もあるそうです(実際に確認はしませんでした)。というのも江戸川区は昨今まで金魚の一大産地で、その名残でこの周辺にも養魚場が何軒か残っているのです。
町内では、このような電柱広告の住所の表示を見ることができました。 |
◎宇喜田町(現存:3桁以下、及び1004番地〜1521番地)
 2003.9.23 撮影 |
都営新宿線船堀駅から南に下っていって橋を渡ると宇喜田町に入ります。東京に残る4桁地番地域の中でも、宇喜田町は最大の規模を誇り堂々と構えています。
町内を歩いていると、普段街中で見かけるような細長い(青とか緑とか茶色とかの)官製の町名標識ではなく、白い板に住所が書かれた左のような標識をよく見かけます。これは推測ですが、住居表示に反対したということで町名標識を作ってもらえないのか、あるいは区は「どうせ将来住居表示が施行されるから」と考えて町名標識を作る気がないのかもしれません。(一之江町や二之江町にも官製の町名標識はありませんでした。) |
 2003.9.23 撮影 |

では宇喜田町には何があるかというと、宇喜田町は見ての通り広いので、一通りのものはあります。交番、ガソリンスタンド、中学校、クリーニング店など(やや寂れかけですが)。 |
 2003.9.23 撮影 |
また宇喜田町は新川という川に面しているのですが、川沿いの道は遊歩道になっていて、その遊歩道には家と家の間の狭い道をすり抜けていくと入ることができます。そしてこの新川の真下にはなんと駐車場もあるなど、散策してみてなかなか興味深い地域です。
|