|
今回はCMOS Inverterの特性について触れていきたいと思います。無責任の様な感じですが、よりによって式とかは扱いません。ここの領域ではこういう風に電流が流れるんだよ。とかそんな感じで説明していきます。式はおそらくここで説明するよりも書籍などを読んで勉強するほうがいいと思われます。サイトの中に赤ペン引っ張ったり書き込みできませんしね。
さて、それではまず回路図から見ていきましょう。
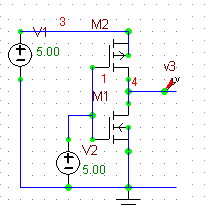
MOSは上がPMOS下がNMOSです。後は電圧源です。この様なPMOSとNMOSが合わさった回路をCMOS回路と呼びます。なのでCMOS InverterはCMOS基本回路とも呼ばれることがあるようです。しかし、CMOSインバーターは物凄く大切な回路です。CMOSディジタルでもCMOSアナログでもどちらでも使われ、用途も広いので、しっかし理解しておいた方がいいです。
次は電圧電流特性を見てみましょう。下の回路図ではPMOSのチャネル幅を3.5u、5.5u、7.5uと変えて電圧を測っています。NMOSのチャネル幅は2uのまま固定です。
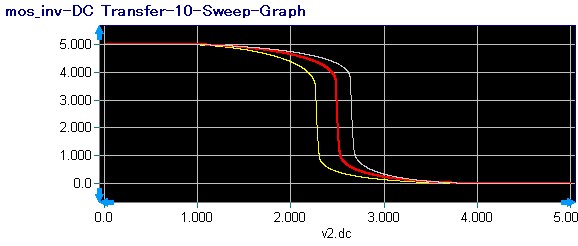
こんな感じになりました。実はこれがすごく大切な図です。というか特性です。図の赤い線の時、つまり急激に電圧が低下する線が2.5Vの時、この状態のCMOSインバータを理想的なCMOSインバータと呼びます。図で言うと赤い線グラフの時です。またこの電圧が急激に落ちる電圧値をゲートしきい値と呼びます。またこのゲート閾値はP及びNMOSの閾値と流れる電流に依存しています。何故PMOSのチャネル幅がNMOSより高くなければいけないかと言うと、電流がキャリア移動度に依存し、その値がPとNで異なるから、また閾値電圧が異なるからです。大体ですが、PMOSのキャリア移動度がNMOSの3分の1位なのでPMOSのアスペクト比(W/Lの事)を3倍くらいにすると結構いい感じの電圧特性が得られます。←適当
今度はCMOSインバータをディジタル回路っぽく扱ってみましょう。下のグラフはV2にパルス波を入力した時の特性です。
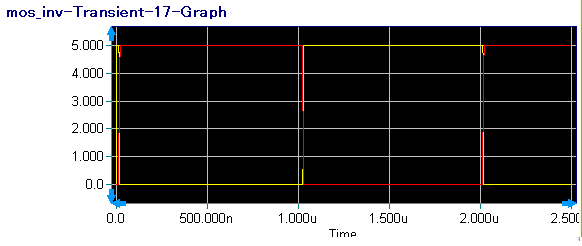
赤い線がV2のパルス波で、黄色の線が出力電圧です。これを見るとわかるように…、そうCMOSインバータはディジタル回路で言うNOT回路です。つまり1が入力されれば0が0が入力されれば1が出力されます。因みにインバータと言葉は2つの意味があり、ディジタル回路ではNOT回路を指し、電源の回路では直流を交流に変換する装置のことを指します。
下のグラフは上のグラフの電圧が下がる所を拡大したものです。理想的なCMOSインバータで設計しているので2.5Vの所でちょうどスイッチングされています。
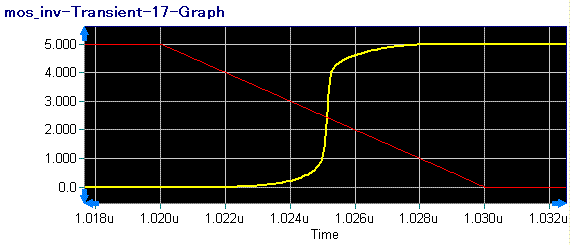
この様な特性を利用して、CMOSインバータはコンパレータ(電圧を比較したりする)として利用することもできます。
|