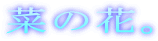ヒロは料理がうまい。
ついでに掃除もうまい。
ピアノもうまいし、歌もうまい。
なのに口はうまくなくて、
なんというか、愛しいなぁ、なんて感じる。
あたしよりはるかに忙しい毎日を送っているだろうに、
いつもあたしの話を聞いてくれて、
笑ったり、慰めたり、時には怒ったりしてくれる。
彼は自分の為ではなく、あたしの為でもなく、
単純に、「あたし」という存在を愛してくれている。
こんなふうにあたしを想ってくれる人はなかなかいないだろうな、と、
おのろけではなく、ゼリーに針を刺すように、すぃ、とそう分かる。
ユウは料理は一切しなかった。
あたしが作らないと、
コンビニで何か買ってくるか、ハンバーガーにかぶりつくか、
お腹をすかせたまま本でも読んでいるか、
一事が万事そんな感じだった。
掃除も下手だったし、洗濯も満足にできないし、
ピアノどころかカラオケでさえひどい音痴だった。
ヒロは優しい。
女々しい優しさではなくて、自律した男の頼もしさを感じられる優しさだ。
他人を気遣えるだけでなく、自分の事も大事にできる。
その場のノリで悪ふざけをしたり、誰かを中傷したりは決してしない。
自暴自棄になって自分を痛めつけるようなことも絶対しない。
ユウは不器用だった。
不安定で、気分屋で、浮き沈みが激しくて、
他人も自分も傷つけて、最後にはふて寝してしまう。
あきれた。
小学生じゃないか、それじゃ。
ヒロは美術館が好きだ。
映画や演劇も好きで、よく2人で観に行く。
繊細な心の機微を読み取るのが実に鋭い人で、
それは多分、ヒロ自身の感受性がきわだって豊かだからだと思う。
ユウの観たがる映画ときたら、
どっしゃーん、ばりりり、がしゃがしゃ、ぼぅん、の派手なアクションばかりだった。
ヒューマンドラマとか人間模様を描いた作品は、
どうもよく意味が分かりにくくて苦手だ、と、
本気で苦手そうな渋い顔をしてそう言っていた。
菜の花。
あたしは菜の花が好きで、
見るのも勿論のこと、菜の花のおひたしも大好きだ。
さっとゆでた菜の花に、白胡麻たっぷりの甘い味噌ダレをちょいとかけると、
それだけでボウル1杯は食べられるほど美味しい。
ある時、ユウに菜の花のおひたしを昼ごはんの一皿に作ってあげたら、
ユウはじぃっとその美味しそうな菜の花のおひたしをまっすぐに見つめ、
その後ポツリと言った。
「おれ、これ、いらない。」
あたしは内心ムッとした。
せっかく作ってあげたのに。
だいたいあんたは野菜の好き嫌いが多すぎるんだ、
男ならがつがつ食え!
ユウはそれでも、菜の花に手を出さなかった。
あたしはわざとらしくタメイキをついて、
ユウの分の菜の花まで全部綺麗にペロリと食べた。
「…菜の花はさ、食べちゃいけないと思うんだ。」
あたしが不機嫌になったのに気がついたのか、
申し訳なさそうにユウがそうつぶやいた。
「は?」
怒気を含んだ声で返すあたし。
何の言い訳だ、それは。
「…可哀相じゃないか。」
それだけ、消え入りそうに小さな声でやっとこさ絞りだすと、
ユウはそれきり沈黙した。
ふとユウの顔を見ると、今にも泣き出しそうだった。
ヒロは菜の花のおひたしが好きだ。
あたしより美味しい胡麻ダレを作れるので、
自分で作ってあたしにも食べさせてくれる。
今夜も、メインのブリの照り焼きの隣りに、品のいい小皿に盛られて用意されている。
何回も食べさせて貰ったから、味は良く知っている。
おいしいんだ。すごく、おいしいんだ。
知ってるさ。とっくに。
ヒロはおいしい、おいしい、と、何度も口にする。
でもね、ユウは食べられなかったんだ。
魚も豚も牛も鴨ももしゃもしゃほおばってたくせに、
菜の花だけは食べられなかった。
じっと見つめて、可哀相だ、って、あたしに言ったんだよ。
ほうれん草と小松菜の区別もつかないくせに、
菜の花だけは、きちんと愛していた。
そしてそんなユウを、あたしは全身全霊でもって愛していたんだ。
BACK