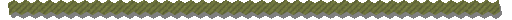法泉寺縁起由来
創建年代 明治22(1889)年12月9日
本尊形式 十界互具大曼陀羅ご本尊。
一塔両尊四士(中央に多宝塔,
向かって左に釈尊像,右に多宝如来)
寺宝 身延山久遠寺31世日脱上人御本尊
勧請諸尊 日蓮大聖人説法座像
天拝鬼子母尊神像 (村雲日栄尼公殿下御祈願)
大黒福寿尊天像
山内諸尊
太平稲荷大明神(正一位伏見稲荷)
観世音菩薩像(水子供養)
慧光照幸福観音像(交通安全・世界平和)
大聖不動明王尊(伊達藩八代の重村公の武運長久
を御祈願す)
開 基 中興開基は池上・本門寺第六十五世文明院日薩上人
法泉寺は,千葉県夷隅郡より寺号移転したのであるが,
そもそもは池上本門寺第八世大運阿闍利・常住院日調
《文亀1・3・20(1501年)》 が千葉県行川の妙泉寺を
上総120ヶ寺の触れ頭と定め,幕府のご朱印寺となり,
自らは妙泉寺の隠居寺 としての 法泉寺に住したのが
始まりとなる
開 山 中興開山は観如院日持上人
慶応3年齢13歳の時,
新潟県三島郡出雲崎の円徳寺にて剃髪得度す。
能登の妙成寺,金沢立像寺充洽園で勉学修行す。
師匠の観如院上人は、妙成寺の貫首に晋む。
長じて二十歳の頃,中里村196番戸に寄留し,撃鼓唱題。
東・西磐井郡・ 宮城県北に広がる教線を張られたのです。
第二世 本光院日榮上人( 城戸口妙春)
第三世 本牙院日貫上人( 佐藤瑞啓)
第四世 観解院日昭上人 (吉家本義)
第五世 観誠院日勇上人(千葉本勇)
第六世 観義院日宣上人 (吉家妙弘)
第七世 観明院日顕 現住 (吉家本浄)
◎村雲祈願所・天拝鬼子母尊神の由来
明治26年10月26日より京都・門跡村雲御所瑞竜寺の
瑞法光院宮日榮法尼が、北海道巡錫の砌り,開山早川本榮上人
の懇請におこたえなされ法泉寺において七日の間、国家安穏そして
明治天皇の武運長久の祈願を鬼子母神様にこめられ,加えて善男
善女に説法を為されたとの事です。
その由来により,「天拝鬼子母尊神」「村雲祈願所」と称する。
御逗留なされた建物は,「村雲御殿」と称され,新本堂建設の時,
解体されました。
二部屋続きで本堂からの回廊付き建物で,その当時としては珍しい
色付きのガラスの窓があり,尼公殿下は,そこから北上川を往来する
帆掛け舟をご覧になられ大層お慶びになられたとのことです。
御親教七日間は警官が寝ずの番をして,県知事をはじめ大勢の人の
参詣があったと,今は亡き古老が話しておりました。
◎日清戦争戦没者供養石塔
池上・本門寺貫主名代として,昭榮院住職が大導師として法要が
厳修された。
◎昭徳院殿胡風日薫大居士の由来
俗名 柵瀬軍之佐
昭和7年8月28日寂 享年64歳
居士は,当地の出身であるが,山梨,鎌倉で生活する中で日蓮大聖人
の御教えを信仰し 法華経・お題目に帰依するようになった。
古老の伝によれば,居士は,近所の日蓮宗寺院から朝夕聞こえてくる
鐘の音,木柾の音を聞きながら「自分の亡き後,遺骨は故郷の日蓮宗の
寺に納めるように・・・」と申されていたとの事。
現在,お位牌のみが当山に安置されている。