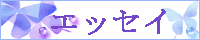
海市(『未来図』15周年記念コンクール エッセイの部に投稿)
鹿児島には海の見えないところはない、とは地形上無理だろうが、海を感じないところはない。
それだけで、この地に好印象を持った。休みの度に主人の運転で目的地よりもむしろ到着までの
道のりを楽しんでいる。おそらくはどこにでもあるような風景であり、実際のところ、うたた寝を
貪っていることも多いのだが。太平洋も東シナ海も錦江湾も、そこに生まれ育った人々には、そうあるべき
姿であり、あるいは自然や人為の造作によってかつての面影を失った場所であろう。しかし私は自らの
意志の外のきっかけでここを訪れ未定ながらも期限が来ればこの地を去るものである。
原風景というものを自覚したことはない。生まれて数週間を過ごした佐渡の真向いの小さな港町の印象も、
長じてからの帰省の記憶に違いない。最後に残った祖母が母の許に来てからは地名を聞けば懐かしい程度で、
いつかまた、という思い入れを失った。原風景があいまいなので、どんな中継点も、今まで見たどことも似ていない。
とりわけ海の表情。錦江湾にその雄姿を漂わす桜島は、一日に数回色を変えるというが、それは空の色と海の色の
微妙な配合による。また、吹上浜の白砂は人影を吸い込んでしまうほどの眩しさだが、魂を肉体に留めておけるのは
千変万化の波の音のお蔭だ。絶えず移りゆくものの中に身を置くことで、自分という枠組を超越し得ぬ生身の自分に
再会する。取り残される自分自身以外はすべて去りゆく者に他ならない。
海岸線を行く時、島々が近付いては遠ざかっていくように見えるが、移動しているのは車に乗った私である。
同様に、時間や季節が巡るのではなくて私がその局面に向かったり離れたりしているのを、そう錯覚しているだけなのかもしれない。
ましてや、その感応を言葉に掠め取ることの困難さは、あながち技術の拙さのみとは言えまい。それでも何かの形で
脳裏に焼き付けておきたいと願うのは、喪失感を埋めるためでも自らの存在を誇示するためでもなく、流れていくことを
肯定することで流れに受け入れられたいという切ない想いなのだ。
昼下がりの阿久根の道から穏やかな日差しを浴びて風の無い静かな海が一面に乱反射するのを眺めるのが好きだ。幾つもの島を
越えてはるかな水平線からせりあがるように都市の影が浮かび上がって来る。こちらに向かって進んでくる巨大な船は、しかし近付いては来ない。
一年中停泊している蜃気楼などあるのだろうか。地図では読み取りにくい陸地が実在しているのだろうか。夕暮れにはそのまま消えてしまい
街の明かりも見えないのだから、どこか対岸があるとも思えない。同行者に確かめてみればはっきりするのだろうが、実在していると
判ったとしたらなんだかつまらないし、かといって私の幻覚だと言われるのも恐い気がして、いつもそのままにしてしまう。
ぼんやりと遠く視界をさまよいながら、あれは私の来たところだろうか帰るところだろうかと考え始めれば潮の加減か波が立ち始め、思考は
そこで途切れてしまう。ままよ、古歌の如く、一期は夢よと割り切って、それでは向かって来ながら止まって近付いてこないあの巨船は
いったい何の暗喩なのだろうか。
Internet Explorer5.0以上でご覧ください。