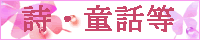
百エーカーの森へ(南日本新聞お茶の間エッセイ「とっておきの時間」投稿 1998年)
息子が生まれて、意識するしないに関わらず数多くのキャラクターに囲まれて
生活するようになった。かれこれ四歳になろうとする時期、出来るだけ無作為に
与えてきたキャラクターの中から、息子自身が判断して幾つかに絞り込み始めた。
息子の友達を見ていると、ほとんどが活劇モノのヒーローを好み、ときにはそれに
なりきって、互いに罪のない攻撃を仕掛けあっている。が、むすこはが大好きなのは
「くまのプーさん」である。
私自身は、プーさんは哲学・心理学系の本で紹介されているのを読んだのが最初で、
それ以前は(流行に懐疑的であるせいもあって)ただの黄色い間抜けなクマ、くらいの
認識しかなかった。しかし、実際に子どもを持ち、彼が主人公クリストファー・ロビン
の年齢に近付きつつある今、プーさんに囲まれて遊んだり、プーさんのビデオを見たり
本を読んだりするのが、一番のとっておきの時間だ。
失敗を重ねていくうちに何となく大成功してしまうプーさん。「何もしない」のが得意な
彼にしても、まったくの自然体でいられるわけではなく、眉を寄せて考え込んでみたり、
懸命の努力をしたり、それなりに前向きに行動している。いきあたりばったりの計画も、
全て許してしまいそうなかわいい笑顔も、毎度の大騒動も、どこか息子に似ている。
現実の息子との葛藤の中では、息子の成長を手離しで喜んであげられる余裕のない、ちょうど
ラビットさんみたいな母に、プーさんは、無責任に子どもに戻って息子と一緒に
涙が出るほど笑える時間を提供してくれるのだ。
いつか大人になって、百エーカーの森から出て行くクリストファー。いつか大人になって、
私の手から離れていく息子。親として、著者A・ミルンのようにきっぱりと、プーさんに
子どもの世界を預けて旅立つ息子を客観視出来るだろうか。そう思うと、プーさんは
現在の息子であり、未来の自分でもある。百歳になっても、別の人生を歩みながら、息子の
人生の中に存在し続けることが出来るだろうか。いつか住んでいた所として、いつでも
戻れる所として。
「プーさんが、どうして好きなの?」
「プーさんだからだよ。」
「そうだよね。」
どこか、禅問答めいているが、息子の答はいつもそうだ。そうやってプーさん自体を楽しんで
いる息子と一緒にいると、忘れていた何ともいえない懐かしい気持ちが甦ってくる。自分が
物語全体となって、自分自身を見ているような錯覚すら憶える。そのとき、大人になってしまった
自分への感傷を超えて、息子と対峙する可能性をつかみかけた気がして、何度も何度も繰り返しをせがむ
息子と、もう一度テープを巻き戻すような気持ちで付き合うことが出来る。
息子が、プーさんが好き、と言うとき、それはとても単純なことなのだろう。特に他の事と比較するでもなく、
優劣をつけるでもなく、純粋に「好き」なのだと思う。息子くらいの頃にプーさんに出会っていたら
私は今と違う私になっていただろうか。多分、それほど違いはしないだろう。そして、いつか息子が自力で
プーさんと再会しても、初めて出会ったような印象を受けるかもしれない。どこか懐かしい物語だと感じることはあっても。
息子がどのように子育てに参加していくのか今は想像もつかないが、自分の子どもに対するのに、A・ミルンのように
社会的評価から離れた本質的な部分を子どもに見せてあげられるような父親になってくれたら素敵だなと思う。
息子のプーさんと私のプーさんは同じでありながらまったく違うものなのだが、それでも一体感をもてるのが架空の物語の力だ。
その力の恩恵に浴して、とりあえず、家事とか育児とかその他諸々の日常から出て、百エーカーの森に行く。そこで、
「何もしないこと」をするのが、私のとっておきの時間である。いつかそこを出て行くことがあっても、森は森であり続け、
プーさんはプーさんであり続ける。私が私、息子が息子であり続けるために。
Internet Explorer5.0以上でご覧ください。