





















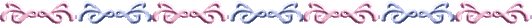








パパといっしょに度々おとずれた砧のはずれにある花屋に着いた頃には、冬の淡い太陽が、すでに光の明度を落とし始めていた。それなのに、軒先に並べられた花達だけは、旧くからの顧客の到着を辛抱強く待ちかねていたかのように、花弁の先まで北風に身を震わせながら、その色彩を真昼のように保っていた。
店の片隅にしつらえられた棚に並んでいる椿や梅や南天の木に、今は季節じゃないから、と仲間はずれにされたような一鉢の小さなサツキの苗木が目にとまる。かつて私が、つつじ科の植物を、なんでも、かんでも、十把一絡に「つつじ」と呼ぶと、パパにすかさず、「ノー、これはサツキ」と澄んだ母音が耳にここちよい、イタリア語訛りの日本語で訂正された。彼の発音する「サツキ」という音は、とても透明で、しかも、優しさに溢れていたのを思い出す。サツキに限らず、花の名前を、まるで恋人の名前を呼ぶときのように、いつも特別な愛情を込めて発音する人だった。サツキ、スミレ、スズラン、ブーゲンビリア、ユリ、バラ…、思いつくままに、花の名前を、ひとつひとつ慈しんで、声にしてみる。
ふと、一週間前のパパの死から、凍てつくように硬直し続けていた私の心に、蜜を流したように、甘やかな追憶の灯りがともり、その人の口癖だった言葉が浮かび上がる。
「パパはいつも待っているから。リリのことを待っているから」
娘の訪問を心待ちにする父親にしては、やや情熱のこもり過ぎるパパの言葉を、私はあの頃、ほんのかすかな面映ゆさと、かつて経験したことのない安らぎとを胸の中で入り混じらせながら、はぐらかすように聞き流していた。
日本では見慣れない香草野菜と、この国古来の四季の花が、奇妙に調和のとれた音楽を奏でながら、しかし計算が過ぎることもなく、然るべき場所に配置されている教会の庭を最初に見たとき、それを造った人が、頑固で、譲らない人だということは直感できた。頑固なくせに、完璧すぎるものを、どこかで疎む人。未完であり続けることにこだわる人。花と音楽の人。それがディエゴ神父であり、私のもう一人の「パパ」だった。
一九二一年にイタリア中部の町リエティで生まれたディエゴ神父は、幼少期に母を亡くし、十歳になるかならないかの年頃には、姉に伴われてローマにあるフランシスコ修道会付設の小神学校の門を叩いている。その時から、家族のもとを離れた神学校最年少のおちびさんは、同じ屋根の下で暮らす修道士や神学生達を「おとうさんやきょうだい」に、聖母マリアを記憶のはるか彼方から微笑みをおくり続ける「おかあさん」に重ね合わせながら、司祭への道を歩んでいくことになる。
あれほど明るい人なのに、その背後に一貫して流れるある種の寂しさが、知らず知らずに人を惹きつけてしまうような、光と影の濃い性質は、いったい育った環境のせいだけだったのだろうか。
一九四五年にローマで司祭に叙階したのち、神様の思し召しのままに、宣教師として来日したのは、一九五八年のことだった。以来、富山県の高岡教会で主任司祭を勤めた四年間を除けば、四十年にもおよぶ日本での布教活動のほとんどを三軒茶屋教会でおくり、一九九九年十二月のある朝、渋谷にほど近い病院の一室で、静かに眠るように天国へと旅立った。
ディエゴ神父の葬儀ミサが、神父自身が演出しているのかと見まごうほど、彼の七十八年の人生を色濃く反映させたものであったことは、聖堂を埋め尽くした参列者の全員が共通して感じ取っていたと思う。蝋燭のあかりにぼぉっと浮かび上がる祭壇に飾られた無数の花、棺にそっと寄り添うような情熱の赤いバラ、無造作に捧げられた清涼なミントキャンディー。そして、参列者の意識を、今頃はもう天上へ到着したであろう彼へと、一瞬にして掬い上げるような、精魂のこもった聖歌。その中には、日本ではあまり馴染みのない、イタリアの聖歌が数多く含まれていた。ディエゴ神父が、教会であげた功績の中で、最も大きなものの一つが、聖歌隊の指導だった。人間が創造したものの中で、最もうつくしいものは音楽、そう彼は信じていたような気がする。
喪主をつとめた前川神父が、参列者に挨拶の言葉をおくる。
「生前のディエゴ神父が、その気難しい性格から、時として、皆さんが傷つくようなことを言ったり、失礼な振る舞いをしたりしたことを、本人にかわって、お詫びいたします」
その瞬間、笑いがどっと参列者の間で起こった。みんなが互いに目配せをしあって、やんちゃ坊主のまま行ってしまったね、あの人は…、心の中でそう呟き、それぞれの思いを巡らせながら、彼を赦し、彼を愛しんだ。
「どうして!失礼な振る舞いをした人って誰のこと?」
棺の向こうで、両手の平を宙に向け、小首をかしげながら、抗議するディエゴ神父の姿が、一瞬目をかすめた。
「パパの髪は何色だったの?」
「カスターニャ(栗色)」
昔は栗色だったという髪が銀色に変わり、とうに老年期を迎えていたが、ディエゴ神父の強気は、不変だった。誰がなんと言おうがお構いなしで、すべての事柄に関して、彼の思い描く秩序が優先された。 教会の台所の扉は、常時、開け放たれていなくてはならなかったし、工具は戸棚のここ、万年筆は引き出しのここ、食事の時は音を決して立てずに、猫は花壇に入ってはならず……。
秩序が破られるたびに、すさまじい勢いで扉をばーんと開け、みんなだらしない、と怒鳴っては物を定位置に戻し、隣で蕎麦をすする音が堪えきれずに食卓を離れ、両手を振り上げて猫を追いかけていた。そんな激しい気性の人が、一人で庭の手入れをしているときに見せる、しんという音が聞こえてきそうなほど静かで穏やかな横顔に惹かれて、つい、お庭づくりを手伝いたい、と申し出たのが、運のツキだった。
週に一度か二度、時間は午後三時半からという約束で、ディエゴ神父を手伝って、花に水をやったり、球根を掘り上げたり、雑草をむしったり、落ち葉をはいたり、枯れ枝を集めて燃やしたりするのだが、これら一連の園芸作業が、想像をはるかに超えるハードワークだと いうことに気づいたのは、手伝いを始めたあとだった。
手足は泥だらけになるし、「スカート」は枝に引っ掛けて破けるし、だいいち、作業を終えると、身体中が壊れたように、くたくただった。
ろくに花ひとつ育てたこともないくせに、こんなこと言い出さなければよかった。花壇の地中に深く埋もれた大きな石を、二人で黙々と掘り起こしながら、後悔をした。だからといって、自分から申し出た以上、へこたれた様子をみせるわけにはいかない。意を決して、こちらも、着古したジーパンと赤いアノラックで体制を整えて作業に臨むことにした。ときには、日がとっぷりと暮れてしまうまで、彼と働いているうちに、いったいどれだけの季節が巡っていったのだろう。
その頃の私は、まだ大学に籍をおき、収入といえば、友人のツテで得るわずかばかりの翻訳料で、将来の自分の道が、皆目見えてこないことに苛々しながら、長いトンネルの中を右往左往していた。ディエゴ神父と無心に庭仕事をしたあとで、泥まみれになった手を洗い流すとき、日ごろの自分自身に対する憤りが、石鹸の泡といっしょに払拭されるようで、自分がちょっぴり軽くなることに気がついたのは、手伝いを始めてから、しばらく経ってからだった。
雨が降る日は、とりわけ素敵だった。ディエゴ神父の執務室で音楽を聴く日だったから。オペラのアリアが教会中に鳴り響く。レオンカヴァッロの「道化師」のカニオ役はデル・モナコにかぎる、と彼は主張し、私は、いや、ドミンゴだ、と譲らない。「だって彼(ドミンゴ)は、スペイン人でしょ」と言って肩をすくめる、なんでもイタリアが一番!の彼と、大はしゃぎしながら、「衣裳をつけて」をいっしょに歌う。
音楽にかぎらず、二人の好みは、食べ物から子供時代の得意科目にいたるまで、奇妙に一致していた。まるで、私の分身みたい、そんな言葉が、ふと脳裏をよぎる。
とっくにいい年の大人になっているというのに、少女期に父親を亡くした哀しみを、いつまでも引きずり続け、何かに行き詰まったり、理不尽な目にあったりする度に、ともすると、それが、父を失った哀しみから起因する出来事であるかのように考えがちな私の性質を見抜いたのだろうか。ある日、ディエゴ神父は、私の瞳をのぞきこんで静かに言った。
「今日から、パパって呼んで」
ミサが始まると、カプチーノコーヒーのようなこげ茶色をしたフランシスコ会の修道服を身にまとい、聖歌隊席の上から聖堂中の一挙一動を見守るディエゴ神父の姿があった。それは、聖堂に集まる信者一人一人の態度から、自分よりずっと年の若い主任司祭のミサの進め方にいたるまで、目を光らせる、総監督のような風情だった。
ある日のミサでは、閉祭の歌が終わるやいなや、苦々しげに口を一文字にぎゅっと結んだ神父が、聖歌隊席をすべり降りるように、こちらに向かって歩いてきて、私の前列に腰かけている若い女の人の横でぴたっととまった。何事が起こったのか状況が把握できずに、ただびっくりする、その人の上に、神父の雷が落ちる。「あなたは大きな声で歌いすぎるのを今すぐやめてください!調和がみだれる!」
あ、またか、と、その様子を目にする誰もが、驚かない。事実、ディエゴ神父のことを怒りっぽくて怖いといって、神父に近寄ろうとしない信者も少なくなかった。神父のくせに、抑制のきかない人、と批判する声もあった。
それでも、ミサの後では、常に、扉の開け放たれていたディエゴ神父の執務室は、彼を慕う人々で溢れ、そこに、笑い声の絶えることはなかった。自分との間に塀を敷く者は放っておく、それが実に単純でわかりやすい彼のやり方だった。そのかわり、たとえ大喧嘩をした相手であっても、塀を取り払って彼のもとに戻ってくる人、彼の明るさに引き寄せられて集まる人、彼を必要とする人に対しては、どこまでも、どこまでも、寛容だった。パパの修道服姿が大好きで、私も着てみたい、とせがむと、あっさりオーケーしてくれた。
「ね、どう?これを着ると、聖クララみたい?」
「ぜんぜん、違う!リリの方がかわいい」
それから、私が修道服の裾をつまんで、バレリーナ式のお辞儀をすると、この子は!と言いながら、パパは大笑いした。
あの頃の私達は、いつもお祭りみたいに、他愛ないことを言っては、笑い転げていた。
Marco predica la domenica, e la gente prega con lui.(マルコが、日曜日、説教をして、人々は、彼といっしょにお祈りをする)……私が、イタリアのロック歌手ラフの一曲にこんな歌詞をめざとく見つけて、「マルコ」の箇所を「ディエゴ」に置き換えてうたうと、パパは、呆れかえった表情をして、次の瞬間、ぷぅっと吹きだした。たった一度だけ聴かせたこの曲のメロディを、音感の優れたパパの耳は、いっぺんに覚えてしまったのか、のちになっても、彼がごきげんなときに決まって鼻歌にしていたのが、おかしかった。当の本人は、何の曲だか、すっかり忘れて、うたっていたのだと思うが。
パパが、こまごまとした日用品の買い物に出かける際に、三軒茶屋の商店街へお供をすることもあった。それが西武のようなデパートであっても、しばしば彼は、支払いの段になると強行に値切って、店員さんを困らせるので、私は、そのことが、ちょっと恥ずかしかった。それなのに、目鼻立ちがはっきりしていて、あまり日本風でない私の顔をすかさず見つけた店員さんに「娘さんですか?おとうさんは、こうおっしゃっていますが……」と言われると、「おとうさん」の言葉の魔法が、私を一転してパパに加担させ、「ですから、少しお勉強していただけないかと……」などと、もごもご答えている。
長年、人工透析をうけていたパパは、体調を崩すと、入院をすることが度々あった。
「チャオ、パパ」病室の扉を開けると、部屋の様子が、昨日と一変していることに驚かされる。クロゼットもテレビも冷蔵庫も、すべてが彼の秩序に従って、好ましい位置に置き換えられている。「病人なのに、こんなに重いものを!お引越屋さんじゃあるまいし」と呆れながら感心する私に、「だって、気持ち悪いでしょ」と、その一言で、言ってのける。
「チャオ、パパ」ある日は、病室をおとずれる私を待ちかねていたように、ブルーの少し混じったハシバミ色の瞳が、いたずらっぽく笑っている。それから、声をひそめて「リリ、スイカがある」と言いながら、小さな冷蔵庫を指さしている。開けてみたら、仕切り棚をきれいにはずした狭い庫内いっぱいに、巨大な丸ごとのスイカが一つ、ごろんと横たわっていた。大爆笑だ。「パパ! これ、いったいどうやって切るの? ナイフないでしょ。それとも、パパの頭にぶつけて割ろうか?」キャッキャとはしゃぐ私に、「この悪い子!」と目を細めながら、彼は言った。「リリ、食べて。いつも、いっぱい食べて」
パパが、人生の中でもっとも輝いた一日、それは、司祭になって五十周年を迎えた金祝記念のミサの日だったのかもしれない。その日のパパは、いつも彼が好んで着た簡素な祭服ではなく、白地に豪華な金の刺繍がほどこされた立派な祭服を身にまとい、祭壇席のまんなかで、今日の主役が自分であることをはにかむように頬をばら色に染めながら、緊張のなかに、おごそかで静粛な表情を浮かべていた。モーツァルトの戴冠ミサから選ばれた聖歌が、オルガンの調べにのって、彼が愛した聖歌隊の人々によって、一曲一曲心をこめてうたわれた。聖体拝領が始まり、私が常々パパに、この聖歌が一番好き、と言っていた アヴェ・ヴェールム・コルプスが流れ始めると、清楚な旋律の雨が、心のやわらかいところに浸みいるようで、不覚にも、涙が頬をつたった。聖体のパンを拝領するために並ぶ人達の長い行列に加わり、祭壇に向かって一歩一歩進む。私の順番がやってくる。瞳と瞳が出会う。と、そのとき、それまで神妙な顔をして聖体のパンを授けていたデイエゴ神父が、くしゃくしゃの笑顔をみせたかと思うと、パンを拝領するために差し出した私の手の平を、いきなり、ぎゅっとつねって、それから、そこに、そぉっと大切そうに、パンをのせた。人生最良の日を迎えたパパが、隠しきれずに見せた、五十年という歳月への熱い思いと、心の震えが、手の平から広がるように、私を激しく揺すぶった。
しかし、人生最良の日が、パパにとっては、少しばかり不満を残す日になってしまう。ミサの後の盛大な祝賀パーティに、私の姿がなかったことが、彼のお気に召さなかった。あの日、私は、花束と熊のぬいぐるみのプレゼントを抱えて、パパの執務室をおとずれ、そっけなくお祝いのキスをおくると、お祝いにかけつけた他の大勢の人達に紛れて、うしろめたい気持ちで、早々に教会をあとにした。パパの大切な日だというのに、それをうっかり忘れて、友人と映画にいく約束をしてしまったのだ。あとあとまで、「あの日、リリは逃げた」と言われた。「ずっと、待っていたのに」
三軒茶屋から砧へ向かう藤棚のどこまでも続く道。あれほど何度も何度も行き来した、あの道を、最後にパパの車で走ったのは、いったいいつだったのだろう。青信号が続けば、「神様は私達の味方ね」と、にこにこし、赤信号にでくわせば、「それだけ長く、いっしょにいられるから」と微笑んで、見つめあった。
天使が、ふと、甘ずっぱい夢を私に見させる。夢の中では、パパと私が、いっしょの車に乗って、あの道を、走り続けている。その行き先は、砧でもなければ、教会でもなくて、おそらく、藤の花が咲き乱れる、あの辺りを進みながら、私達の車がゆっくり、ゆっくりフェイドアウトして、真っ白い光の中にとけていく。風景だけは、その輪郭を保ち続け、私達は、静かに、それは静かに、世界中のどこでもない場所をめざして、姿を消していく。至福の笑顔をたずさえ、何にとらわれることも、恐れることもなしに。そう、道化師の「衣裳をつけて」を口ずさんで、大はしゃぎしながら。パパの訃報を知らされたあと、私は、父を亡くすことの哀しみを、生まれて初めて、心に深く刻みつけて、実感した。今だからこそ、愛する人を亡くすことが、光源を失うことに酷似していることに気づく。実の父を亡くした当時、まだ子供だった私は、死という理不尽な別離のもたらす哀しみが、いったい何であるのかが理解できないまま、あたかも、姿かたちのない辛い夢を見つづけているかのように、大人になってしまった。おそらく、子供のときに親を亡くすことの哀しみは、思い出が、より少ない哀しみなのではないか。
だから、これからは、パパがこの世に振り撒いて残していった思い出の光を、一粒でもたくさん拾い集めよう、拾い集めて、心の中にしっかりと繋ぎとめよう、と自分で自分に言い聞かせ、一人で、うん、うん、と頷いていた私の背中で、「ディエゴの娘らしく、強気で生きろよ!」とエールをおくる友人の、からっと明るい声が、妙に、胸に響いた。