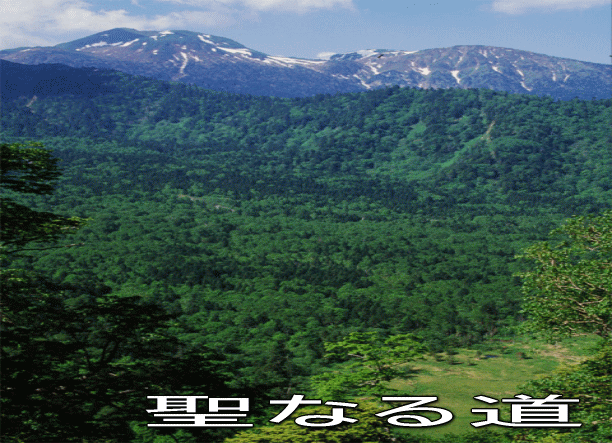| わたしはメシヤに出会った |
 わたしは生まれながらにして異邦人であり、異教徒であった。 わたしは生まれながらにして異邦人であり、異教徒であった。
 しかし、仏教の教理を充分理解し、信じていたわけではなく、先祖伝来の宗教として、伝統的に習慣的に受けつぎ、信じていたに過ぎない。 しかし、仏教の教理を充分理解し、信じていたわけではなく、先祖伝来の宗教として、伝統的に習慣的に受けつぎ、信じていたに過ぎない。
|
 御承知のごとく、仏教には大別して二つの系統があり、一つは自力信仰であり、他は他力信仰である。 御承知のごとく、仏教には大別して二つの系統があり、一つは自力信仰であり、他は他力信仰である。 |
 わが家の信奉した仏教は他力信仰に属し、阿弥陀仏(アミダブツ)の慈悲と功徳(くどく)にひたすらより頼み、ただ一心一念に阿弥陀仏の御名により頼み、「南無阿弥陀仏(ナムアミダブツ)」を称名(しょうみょう)し、救いを求めたのであった。 わが家の信奉した仏教は他力信仰に属し、阿弥陀仏(アミダブツ)の慈悲と功徳(くどく)にひたすらより頼み、ただ一心一念に阿弥陀仏の御名により頼み、「南無阿弥陀仏(ナムアミダブツ)」を称名(しょうみょう)し、救いを求めたのであった。 |
 この六字の名号を一心一念に称名することにより、阿弥陀仏の本願慈悲により、この身このままに成仏(じょうぶつ)し得るとの信仰に立っているのである。 この六字の名号を一心一念に称名することにより、阿弥陀仏の本願慈悲により、この身このままに成仏(じょうぶつ)し得るとの信仰に立っているのである。 |
 これこそは万巻に及ぶ仏教経典を一句に凝縮(ぎょうしゅく)したものであり、深遠(しんえん)な仏教哲学を一語に要約したものと言われているのである。 これこそは万巻に及ぶ仏教経典を一句に凝縮(ぎょうしゅく)したものであり、深遠(しんえん)な仏教哲学を一語に要約したものと言われているのである。 |
 それはまた、ヨエル書3章5節「すべて主(アドナイ)の御名を呼ぶ者は救われる」 それはまた、ヨエル書3章5節「すべて主(アドナイ)の御名を呼ぶ者は救われる」
 にまことに類似しているのである。 にまことに類似しているのである。 |
 わたしがキリスト教と初めて出会ったのは、京都にあるミッション・スクール同志社に入学したことによってである。 わたしがキリスト教と初めて出会ったのは、京都にあるミッション・スクール同志社に入学したことによってである。
 そこにおいて賛美歌と聖書を教えられたのであったが、当時同志社のキリスト教は、近代主義神学に立っており、聖書に対して批判的であり、わたしも自然その感化を受けたのは当然であった。 そこにおいて賛美歌と聖書を教えられたのであったが、当時同志社のキリスト教は、近代主義神学に立っており、聖書に対して批判的であり、わたしも自然その感化を受けたのは当然であった。
 その結果、キリスト教社会主義こそ現代の日本と世界の苦悩を救いえる唯一の道であるとの単純な思想から、社会主義運動に献身するに至ったのであった。 その結果、キリスト教社会主義こそ現代の日本と世界の苦悩を救いえる唯一の道であるとの単純な思想から、社会主義運動に献身するに至ったのであった。 |
 しかし、その世界には闘争があり、暴力があり、流血が断えなかった。 しかし、その世界には闘争があり、暴力があり、流血が断えなかった。
 闘争と暴力は、それがどんなものであっても、必然的に憎悪を生み、それがエスカレートすることによって、いっそう惨事を生まざるを得ない。 闘争と暴力は、それがどんなものであっても、必然的に憎悪を生み、それがエスカレートすることによって、いっそう惨事を生まざるを得ない。
 憎悪は人の心を次第に冷酷なものと変容せしめ、人間関係を極度に悪化させるものである。 憎悪は人の心を次第に冷酷なものと変容せしめ、人間関係を極度に悪化させるものである。 |
 社会主義理論そのものは、社会機構に変革を与え得るとしても、 社会主義理論そのものは、社会機構に変革を与え得るとしても、
 精神的変革においては極めて弱く、何一つ解決し得ないのであり、 精神的変革においては極めて弱く、何一つ解決し得ないのであり、
 真に生きることの意味を与え得ず、 真に生きることの意味を与え得ず、
 したがってそこには真の救済はあり得ないとの結論に到達し、 したがってそこには真の救済はあり得ないとの結論に到達し、
 わたしは久しく手放していた聖書(バイブル)を再び改めて手に取り、 わたしは久しく手放していた聖書(バイブル)を再び改めて手に取り、
 真理の探求に専念することになったのであった。 真理の探求に専念することになったのであった。 |
 幸いにして、当時最も福音主義の指導者として高名であり、 幸いにして、当時最も福音主義の指導者として高名であり、
 日本ホーリネス教会創立者である中田重冶監督の経営する聖書学院に入学を許可され、 日本ホーリネス教会創立者である中田重冶監督の経営する聖書学院に入学を許可され、 中田監督を師と仰ぎ指導を受けることなったのであった。 中田監督を師と仰ぎ指導を受けることなったのであった。 |
 神学校にて学んだ主要テーマは、メシヤご自身であった。 神学校にて学んだ主要テーマは、メシヤご自身であった。
 それは単に神学的に知ることではなく、 それは単に神学的に知ることではなく、
 また、単なるメシヤニズムでもなく、 また、単なるメシヤニズムでもなく、
 生きたメシヤ、永遠に生けるメシヤ、 生きたメシヤ、永遠に生けるメシヤ、
 わたしをアダムの罪(原罪)から解放し、 わたしをアダムの罪(原罪)から解放し、
 永遠のいのちそのものを賦与(ふよ)するところの、 永遠のいのちそのものを賦与(ふよ)するところの、
 生きたメシヤご自身との出会いを求めることであった。 生きたメシヤご自身との出会いを求めることであった。 |
 太陽の光線がプリズムを通ってくるとき、七色の美しい光をもって訪れる。 太陽の光線がプリズムを通ってくるとき、七色の美しい光をもって訪れる。
 聖書が啓示するメシヤも同様であり、 聖書が啓示するメシヤも同様であり、
 栄光に輝くメシヤにのみ心を奪われていると、 栄光に輝くメシヤにのみ心を奪われていると、
 メシヤの他の面を見落としてしまう危険がある。 メシヤの他の面を見落としてしまう危険がある。 |
 昔、ある国に、大変賢明な王子があった。 昔、ある国に、大変賢明な王子があった。
 王子は顔よりも心の美しい花嫁を求めて、旅に出たのであった。 王子は顔よりも心の美しい花嫁を求めて、旅に出たのであった。
 やがてその噂(うわさ)は国中に伝わり、大騒ぎとなったのであった。 やがてその噂(うわさ)は国中に伝わり、大騒ぎとなったのであった。
 国中の娘達は、今に王子が真紅のマントを身にまとい、 国中の娘達は、今に王子が真紅のマントを身にまとい、
 金モールで飾りたてた美服を着、白馬にまたがり、多くの家臣を連れ、 金モールで飾りたてた美服を着、白馬にまたがり、多くの家臣を連れ、
 自分の面前に出現するものと期待し、日々待ち望んでいたのである。 自分の面前に出現するものと期待し、日々待ち望んでいたのである。
 国中の娘達は毎日美しく化粧し、最上の着物を着、宝石をもって全身をかざり、 国中の娘達は毎日美しく化粧し、最上の着物を着、宝石をもって全身をかざり、
 今か今かと心を躍らせつつ待ちこがれていた。 今か今かと心を躍らせつつ待ちこがれていた。 |
 王子は、自分が王子であることがだれにも容易にわからないように変装し、旅に出たのであった。 王子は、自分が王子であることがだれにも容易にわからないように変装し、旅に出たのであった。 |
 ある日の夕方、ひとりの乞食が淋しい山里で道に迷い、寒さと飢えのために道ばたに倒れていた。 ある日の夕方、ひとりの乞食が淋しい山里で道に迷い、寒さと飢えのために道ばたに倒れていた。
 村人は一人またひとりそばを通り過ぎたが、家路を急ぎ、だれひとりとして近寄らず、通り過ぎて行った。 村人は一人またひとりそばを通り過ぎたが、家路を急ぎ、だれひとりとして近寄らず、通り過ぎて行った。
 そのとき、貧しい村の娘が通りかかり、同情のあまり彼を助け、自分の家に案内し、親切にいたわりかいほうした。 そのとき、貧しい村の娘が通りかかり、同情のあまり彼を助け、自分の家に案内し、親切にいたわりかいほうした。
 そのため乞食は次第に快方に向かい、二日間娘の厚い世話になり、丁重に礼を述べて立ち去って行ったのである。 そのため乞食は次第に快方に向かい、二日間娘の厚い世話になり、丁重に礼を述べて立ち去って行ったのである。 |
 それから数日後のある日、真紅のマンとを身にまとい、金モールの美服を着た王子が、白馬にまたがり、多くの家臣を連れ、突然、その村娘の家を訪問したのである。 それから数日後のある日、真紅のマンとを身にまとい、金モールの美服を着た王子が、白馬にまたがり、多くの家臣を連れ、突然、その村娘の家を訪問したのである。
 娘は驚き、王子の前に伏して迎えた。 娘は驚き、王子の前に伏して迎えた。
 すると王子は口を開き、「きょうわたしがここに来たのは、あなたをわたしの花嫁として迎えるためである。 すると王子は口を開き、「きょうわたしがここに来たのは、あなたをわたしの花嫁として迎えるためである。
 わたしはあなたのように心の優しい、愛情豊かな人を求めていたのである」と語るのであった。 わたしはあなたのように心の優しい、愛情豊かな人を求めていたのである」と語るのであった。 |
 この王子が初めて出現した時は、その栄光を隠し、卑しい姿であらわれたのであった。 この王子が初めて出現した時は、その栄光を隠し、卑しい姿であらわれたのであった。
 「彼にはわれわれの見るべき姿がなく、威厳もなく、われわれの慕うべき美しさもない。」(イザヤ書53・2) 「彼にはわれわれの見るべき姿がなく、威厳もなく、われわれの慕うべき美しさもない。」(イザヤ書53・2)
 その姿は、王子のイメージとははなはだしく異なっていたからである。 その姿は、王子のイメージとははなはだしく異なっていたからである。
 しかし、二度目に出現した王子は、実に栄光に輝く姿であり、王子のイメージに全く一致したものであった。 しかし、二度目に出現した王子は、実に栄光に輝く姿であり、王子のイメージに全く一致したものであった。
 わたしが真実のメシヤを求めつつ、イザヤ書9章5〜6節を注意深く読んだとき、 わたしが真実のメシヤを求めつつ、イザヤ書9章5〜6節を注意深く読んだとき、
 そこに驚くべきメシヤの姿を啓示されたのである。 そこに驚くべきメシヤの姿を啓示されたのである。 |
 「ひとりのみどりごがわれわれのために生まれた、 「ひとりのみどりごがわれわれのために生まれた、
 ひとりの男の子がわれわれに与えられた。 ひとりの男の子がわれわれに与えられた。
 まつりごとはその肩にあり、 まつりごとはその肩にあり、
 その名は、『霊妙(れいみょう)なる義士、大能の神、 その名は、『霊妙(れいみょう)なる義士、大能の神、
 とこしえの父、平和の君』ととなえられる。 とこしえの父、平和の君』ととなえられる。
 そのまつりごとと平和とは、増し加わって限りなく、 そのまつりごとと平和とは、増し加わって限りなく、
 ダビデの位に座して、その国を治め、 ダビデの位に座して、その国を治め、
 今より後、とこしえに公平と正義とをもって 今より後、とこしえに公平と正義とをもって
 これを立て、これを保たれる。 これを立て、これを保たれる。
 万軍の主の熱心がこれをなされるのである。」(イザヤ書9・5〜6) 万軍の主の熱心がこれをなされるのである。」(イザヤ書9・5〜6) |
 人類の歴史の中に介入し、時空の間に生まれ出るひとりの男の子、 人類の歴史の中に介入し、時空の間に生まれ出るひとりの男の子、
 その方こそまぎれもなく その方こそまぎれもなく
 全能の神、久遠(くおん)の存在者、平和の君、約束されしダビデの子、 全能の神、久遠(くおん)の存在者、平和の君、約束されしダビデの子、
 イスラエルの王にほかならないのである。 イスラエルの王にほかならないのである。 |
 メシヤの預言者と言われるイザヤは、ここにメシヤの三つの面を啓示しているのである。 メシヤの預言者と言われるイザヤは、ここにメシヤの三つの面を啓示しているのである。
 メシヤの人間性、神性、メシヤ性についてである。 メシヤの人間性、神性、メシヤ性についてである。
 ここにメシヤの完全なイメージが存在する。 ここにメシヤの完全なイメージが存在する。
 大能の神であり久遠の先在者であられる神ご自身が、 大能の神であり久遠の先在者であられる神ご自身が、
 最も弱い姿をとり、ひとりの男の子として人類史の中に誕生し、 最も弱い姿をとり、ひとりの男の子として人類史の中に誕生し、
 すなわち見えないかたが見えるかたちをとり、 すなわち見えないかたが見えるかたちをとり、
 時空を超越したかたが、 時空を超越したかたが、
 時空のもとに神性をを保有しながら人性をとり、 時空のもとに神性をを保有しながら人性をとり、
 神が人間に変化するのではなく 神が人間に変化するのではなく
 真の神でありながら真の人間となられた、と言うのである。 真の神でありながら真の人間となられた、と言うのである。
 その方こそ平和の君であり、約束されしダビデの子、 その方こそ平和の君であり、約束されしダビデの子、
 イスラエルの王なるメシヤなのである。 イスラエルの王なるメシヤなのである。 |
 いかにして神が人性をとるのか。 いかにして神が人性をとるのか。
 「それゆえ、主はみずから一つのしるしをあなたがたに与えられる。 「それゆえ、主はみずから一つのしるしをあなたがたに与えられる。
 見よ、おとめがみごもって男の子を産む。 見よ、おとめがみごもって男の子を産む。
 その名はインマヌエルととなえられる」(イザヤ書7・14)と。 その名はインマヌエルととなえられる」(イザヤ書7・14)と。
 神は前例のない方法によって、 神は前例のない方法によって、
 神の超自然的手段によって、 神の超自然的手段によって、
 乙女が純潔を失うことなくみごもり、 乙女が純潔を失うことなくみごもり、
 それによって神性は人性を実際にとるのであると示している。 それによって神性は人性を実際にとるのであると示している。 |
 また、イザヤ書53章においては、 また、イザヤ書53章においては、
 義の僕(しもべ)が受難を甘受し、 義の僕(しもべ)が受難を甘受し、
 それによって自分自身をとがの供え物とすることによって、 それによって自分自身をとがの供え物とすることによって、
 多くの人を義とすることがしるされている。 多くの人を義とすることがしるされている。 |
 ダニエルは、メシヤの来るときと、 ダニエルは、メシヤの来るときと、
 メシヤが断(た)たれることを預言し(ダニエル書9・25〜26)、 メシヤが断(た)たれることを預言し(ダニエル書9・25〜26)、
 ゼカリヤは「その刺(さ)した者を見る時、 ゼカリヤは「その刺(さ)した者を見る時、
 ひとり子のために嘆くように彼のために嘆き、・・・・・・・悲しむ」(ゼカリヤ書12・10)と預言しているのである。 ひとり子のために嘆くように彼のために嘆き、・・・・・・・悲しむ」(ゼカリヤ書12・10)と預言しているのである。
 以上は、多くの人々が見落としているメシヤの他の面である。 以上は、多くの人々が見落としているメシヤの他の面である。 |
 御承知のごとく、シナイにおいて契約の律法が発布された時、 御承知のごとく、シナイにおいて契約の律法が発布された時、
 モーセは主に燔祭(はんさい)をささげ、その血の半(なか)ばを取って祭壇に注ぎ、 モーセは主に燔祭(はんさい)をささげ、その血の半(なか)ばを取って祭壇に注ぎ、
 その契約の書を民に読み聞かせた後、残りの半分の血を取って民に注ぎかけ、 その契約の書を民に読み聞かせた後、残りの半分の血を取って民に注ぎかけ、
 「見よ、これは主がこれらのすべての言葉に基づいて、 「見よ、これは主がこれらのすべての言葉に基づいて、
 あなたがたと結ばれる契約の血である」(出エジプト記24・6〜8)と宣言したのであった。 あなたがたと結ばれる契約の血である」(出エジプト記24・6〜8)と宣言したのであった。 罪は血を流すこと(犠牲の供え物)なくしては、 罪は血を流すこと(犠牲の供え物)なくしては、
 決してゆるされないとは、律法が強く主張しているところである。 決してゆるされないとは、律法が強く主張しているところである。 |
 主が後の日に、イスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てられる日には、 主が後の日に、イスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てられる日には、
 初めのごとく動物の血によるのではなく、 初めのごとく動物の血によるのではなく、
 義人の血、小羊の血のごときメシヤの尊い血によるあがないによって罪人を義とし永遠の生命に参与せしめるのである。 義人の血、小羊の血のごときメシヤの尊い血によるあがないによって罪人を義とし永遠の生命に参与せしめるのである。
 新契約がシナイ契約にまさるのは、尊いメシヤご自身の宝血によって批准されしゆえである。 新契約がシナイ契約にまさるのは、尊いメシヤご自身の宝血によって批准されしゆえである。 |
 ダニエルが預言したごとく、メシヤは断たれなければならない。 ダニエルが預言したごとく、メシヤは断たれなければならない。
 しかし、メシヤはその神性によって死人の中より復活し、 しかし、メシヤはその神性によって死人の中より復活し、
 死を征服し、 死を征服し、
 ダビデの位に座してそのメシヤ王国をとこしえに公平と正義とをもって支配し、 ダビデの位に座してそのメシヤ王国をとこしえに公平と正義とをもって支配し、
 これを立て、これを保たれるのである。 これを立て、これを保たれるのである。 |
 わたしは、聖書が啓示するところのメシヤに完全に一致適合する方は、 わたしは、聖書が啓示するところのメシヤに完全に一致適合する方は、
 ヨシュア(イエス)以外にないとの結論に到達し、 ヨシュア(イエス)以外にないとの結論に到達し、
 イエスの人性、神性、メシヤ性を全面的に信じ受け入れたのである。 イエスの人性、神性、メシヤ性を全面的に信じ受け入れたのである。 |
 1938年1月9日、夜7時のことである。 1938年1月9日、夜7時のことである。
 聖なる神の臨在がわたしの全存在をおおい包んだのである。 聖なる神の臨在がわたしの全存在をおおい包んだのである。
 しかして忽(こつ)然として聖なる臨在の最中(もなか)より息がわたしに吹きかけられ、 しかして忽(こつ)然として聖なる臨在の最中(もなか)より息がわたしに吹きかけられ、
 息の中より火の玉のごときものがあらわれた。 息の中より火の玉のごときものがあらわれた。
 それはサファイヤのように輝く、発光体の「言」という文字であった。 それはサファイヤのように輝く、発光体の「言」という文字であった。
 それはまさに、エゼキエルの見た神秘的な光り輝く輪であり、 それはまさに、エゼキエルの見た神秘的な光り輝く輪であり、
 生きものの霊が輪の中にあるところのものであった(エゼキエル1・13、20〜21、26〜28)。 生きものの霊が輪の中にあるところのものであった(エゼキエル1・13、20〜21、26〜28)。 |
 その光り輝く輪、発光体の言は動きつつ接近し、 その光り輝く輪、発光体の言は動きつつ接近し、
 わたしの口に触れ、わたしの腹の中に臨み留まったのである。 わたしの口に触れ、わたしの腹の中に臨み留まったのである。
 その瞬間、内在したいのちの言は、 その瞬間、内在したいのちの言は、
 言自体がもつ自己の実体を鮮明に啓示したのである。 言自体がもつ自己の実体を鮮明に啓示したのである。
 「言(ことば)、ロゴス、神、実体、命、言は神なり。」(ヨハネの手紙1・1〜4) 「言(ことば)、ロゴス、神、実体、命、言は神なり。」(ヨハネの手紙1・1〜4) |
 言(ロゴス)は、無限の神秘、その神性の栄光をあざやかに啓示したのである。 言(ロゴス)は、無限の神秘、その神性の栄光をあざやかに啓示したのである。
 わたしはついに神に出会い、神の栄光をまのあたり見たのである。 わたしはついに神に出会い、神の栄光をまのあたり見たのである。
 その瞬間、わたしは「心の中の律法(ト−ラ)」、 その瞬間、わたしは「心の中の律法(ト−ラ)」、
 「人間の中における神の現存」、 「人間の中における神の現存」、
 「永遠の生命の実体」を体験し認識したのであった。 「永遠の生命の実体」を体験し認識したのであった。
 かくして、わたしは神のいのちへの参与によって、 かくして、わたしは神のいのちへの参与によって、
 信仰による革命を自らのうちに体験したのである。 信仰による革命を自らのうちに体験したのである。 |
 しかり、わたしはただイエスのメシヤ性と神性とを信ずる信仰によって、 しかり、わたしはただイエスのメシヤ性と神性とを信ずる信仰によって、
 彼の御名(ハシェーム)、 彼の御名(ハシェーム)、
 すなわち言は神なりとの彼の本質そのものによって永遠のいのちを拝領したのである。 すなわち言は神なりとの彼の本質そのものによって永遠のいのちを拝領したのである。
 彼こそは真の神であり、 彼こそは真の神であり、
 永遠のいのちそのものであられるのである(ヨハネの手紙一5・20) 永遠のいのちそのものであられるのである(ヨハネの手紙一5・20) |