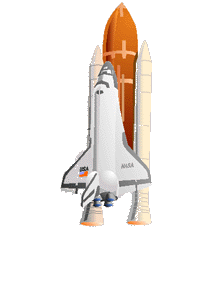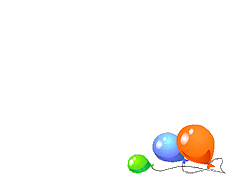「祭りの終りの大事な日に、イエスは立って、叫んで言われた、 「祭りの終りの大事な日に、イエスは立って、叫んで言われた、
 『だれでもかわく者は、わたしのところにきて飲むがよい。 『だれでもかわく者は、わたしのところにきて飲むがよい。
 わたしを信じる者は、 わたしを信じる者は、
 聖書に書いてあるとおり、 聖書に書いてあるとおり、
 その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。』 その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。』
 これは、イエスを信じる人々が受けようとしている これは、イエスを信じる人々が受けようとしている
 御霊をさして言われたのである。」(ヨハネ7・37〜39) 御霊をさして言われたのである。」(ヨハネ7・37〜39)
|
 「人の義とされるのは律法の行いによるのではなく、 「人の義とされるのは律法の行いによるのではなく、
 ただキリスト・イエスを信ずる信仰によることを認めて、 ただキリスト・イエスを信ずる信仰によることを認めて、
 わたしたちもキリスト・イエスを信じたのである。 わたしたちもキリスト・イエスを信じたのである。
 それは、律法の行いによるのではなく、 それは、律法の行いによるのではなく、
 キリストを信じる信仰によって義とされるためである。 キリストを信じる信仰によって義とされるためである。
 なぜなら、律法の行いによっては、 なぜなら、律法の行いによっては、
 だれひとり義とされることがないからである。」(ガラテヤの信徒への手紙2・16) だれひとり義とされることがないからである。」(ガラテヤの信徒への手紙2・16) |
 主イエス・キリストが出現し給うまで、 主イエス・キリストが出現し給うまで、
 人類は神に対して極めて漠然とした概念しか持っていなかったのである。 人類は神に対して極めて漠然とした概念しか持っていなかったのである。
 神は霊であり、永遠の存在者であり、いずこにも偏在し、 神は霊であり、永遠の存在者であり、いずこにも偏在し、
 全知全能、聖にして義なるかた、万物の創造者であり、 全知全能、聖にして義なるかた、万物の創造者であり、
 宇宙の主宰者(しゅさいしゃ)、近づきがたい光に住み、 宇宙の主宰者(しゅさいしゃ)、近づきがたい光に住み、
 人の目にて見ることあたわざるかたと考えられた。 人の目にて見ることあたわざるかたと考えられた。
 したがって神が人間の像(かたち)をとり、 したがって神が人間の像(かたち)をとり、
 ご自身を啓示し給うとは、ユダヤ人の想像し得ない神秘であった。 ご自身を啓示し給うとは、ユダヤ人の想像し得ない神秘であった。 |
 新約聖書は歴史上の人物であるイエスご自身を指し示し、 新約聖書は歴史上の人物であるイエスご自身を指し示し、
 彼の神性とメシヤ性を信ずるように、 彼の神性とメシヤ性を信ずるように、
 そう信じて、彼のみ名(彼の本質そのもの)によって そう信じて、彼のみ名(彼の本質そのもの)によって
 永遠のいのちを得るように(ヨハネ20・31、詳訳参照)招くのである。 永遠のいのちを得るように(ヨハネ20・31、詳訳参照)招くのである。 |
 イエスは、かってご自身の人格に関して、 イエスは、かってご自身の人格に関して、
 「あなたがたはわたしをだれと言うか」と問われた。 「あなたがたはわたしをだれと言うか」と問われた。
 シモン・ペテロは使徒を代表し、 シモン・ペテロは使徒を代表し、
 彼らの抱いているイエスへの信仰を告白し、 彼らの抱いているイエスへの信仰を告白し、
 「あなたこそ、生ける神の子キリストです。」(マタイ16・16)と率直に表明したのである。 「あなたこそ、生ける神の子キリストです。」(マタイ16・16)と率直に表明したのである。 |
 ペテロのイエスへの信仰告白は、 ペテロのイエスへの信仰告白は、
 イエスの神性とメシヤ性をみごとに言い表し、的確なものである。 イエスの神性とメシヤ性をみごとに言い表し、的確なものである。
 するとイエスは彼にむかって言われた、 するとイエスは彼にむかって言われた、
 「あなたはさいわいである。 「あなたはさいわいである。
 あなたにこの事をあらわしたのは、血肉ではなく、天にいますわたしの父である。 あなたにこの事をあらわしたのは、血肉ではなく、天にいますわたしの父である。
 そこで、わたしもあなたに言う。 そこで、わたしもあなたに言う。
 あなたはペテロ(岩)である。 あなたはペテロ(岩)である。
 そして、わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てよう。 そして、わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てよう。
 黄泉(よみ)の力もそれに打ち勝つことはない。 黄泉(よみ)の力もそれに打ち勝つことはない。
 わたしは、あなたに天国のかぎを授けよう。 わたしは、あなたに天国のかぎを授けよう。
 そして、あなたが地上でつなぐことは、天でもつながれ、 そして、あなたが地上でつなぐことは、天でもつながれ、
 あなたが地上で解(と)くことは天でも解かれる」(マタイ16・17〜19)と。 あなたが地上で解(と)くことは天でも解かれる」(マタイ16・17〜19)と。 |
 ペテロのキリストに対するこの信仰告白によってのみ、 ペテロのキリストに対するこの信仰告白によってのみ、
 天国は開かれ永遠のいのちは把握されるのである。 天国は開かれ永遠のいのちは把握されるのである。
 換言すれは、人類は永遠の命を獲得し、天国のメンバ−となるために、 換言すれは、人類は永遠の命を獲得し、天国のメンバ−となるために、
 イエスの神性とメシヤ性を信じ、 イエスの神性とメシヤ性を信じ、
 御名によっていのちを得なければならないのである。 御名によっていのちを得なければならないのである。 |
 イエスの最初の弟子達は、例外なくユダヤ人であった。 イエスの最初の弟子達は、例外なくユダヤ人であった。
 彼らは、生まれるとただちに厳格なユダヤ教の教育・感化の中で育てられ、 彼らは、生まれるとただちに厳格なユダヤ教の教育・感化の中で育てられ、
 ヤハウェなる唯一の神のみを信じてきた人達なのである。 ヤハウェなる唯一の神のみを信じてきた人達なのである。
 したがって、彼らのイエスへの信仰の第一段階は「師(ラビ)」であり、 したがって、彼らのイエスへの信仰の第一段階は「師(ラビ)」であり、
 第二段階は「メシヤ(キリスト)」であり、 第二段階は「メシヤ(キリスト)」であり、
 最終段階において、すなわちイエスの復活の時点において、 最終段階において、すなわちイエスの復活の時点において、
 「わが主よ、わが神よ」(ヨハネ20・28)との信仰に到達したのであり、 「わが主よ、わが神よ」(ヨハネ20・28)との信仰に到達したのであり、
 この弟子達の信仰の成長に関する研究は極めて興味深いものである。 この弟子達の信仰の成長に関する研究は極めて興味深いものである。
 あれほど唯一の神信仰に堅く立っていた彼らが、 あれほど唯一の神信仰に堅く立っていた彼らが、
 イエスへの信仰において、「ラビ」より「メシヤ」へ、 イエスへの信仰において、「ラビ」より「メシヤ」へ、
 メシヤよりさらに「神」に到達したことは驚くべき信仰の革命と言わざるを得ない。 メシヤよりさらに「神」に到達したことは驚くべき信仰の革命と言わざるを得ない。
 イエスをメシヤ、神ご自身として信ずるに至ったことは、まことに革命的変化である。 イエスをメシヤ、神ご自身として信ずるに至ったことは、まことに革命的変化である。
 では、彼らをして「イエス・キリストは主である」 では、彼らをして「イエス・キリストは主である」
 との確信に至らしめた決定的理由は何であったのであろうか。 との確信に至らしめた決定的理由は何であったのであろうか。 |
 それは、イエス・キリストの凱旋的な復活によるのである。 それは、イエス・キリストの凱旋的な復活によるのである。 |
 かの不信の弟子トマスも、イエスの復活、しかり復活のキリストとの出会いにおいて、 かの不信の弟子トマスも、イエスの復活、しかり復活のキリストとの出会いにおいて、
 「わが主よ、わが神よ」と叫び礼拝せずにはいられなかったのである。 「わが主よ、わが神よ」と叫び礼拝せずにはいられなかったのである。
 イエス・キリストに対し「わが主よ、わが神よ」と信仰告白することにおいて、 イエス・キリストに対し「わが主よ、わが神よ」と信仰告白することにおいて、
 キリストへの信仰はまことに頂点に達するのである。 キリストへの信仰はまことに頂点に達するのである。 |
 |
 新約聖書が啓示し強調するところの信仰とは、 新約聖書が啓示し強調するところの信仰とは、
 イエスの神性とメシヤ性に対する信仰である。 イエスの神性とメシヤ性に対する信仰である。 |
 わけてもキリストの神性に対する信仰である。 わけてもキリストの神性に対する信仰である。
 ヨハネによる福音書においては、ことにイエスの神性が強調されているのが特色である。 ヨハネによる福音書においては、ことにイエスの神性が強調されているのが特色である。 |
 「それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、 「それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、
 永遠の命を得るためである。」(ヨハネ3・16) 永遠の命を得るためである。」(ヨハネ3・16)
 「御子を信じる者は永遠の命をもつ。」(ヨハネ3・36) 「御子を信じる者は永遠の命をもつ。」(ヨハネ3・36) |
 「だれでもかわく者は、わたしのところにきて飲むがよい。 「だれでもかわく者は、わたしのところにきて飲むがよい。
 わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、 わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、
 その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。」(ヨハネ7・37〜38) その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。」(ヨハネ7・37〜38) |
 イエスの神性とメシヤ性を信ずるものは、 イエスの神性とメシヤ性を信ずるものは、
 御名により聖霊を受け、ついに神性が流出する存在となるとの意味である。 御名により聖霊を受け、ついに神性が流出する存在となるとの意味である。 |
 「わたしはよみがえりであり、命である。 「わたしはよみがえりであり、命である。
 わたしを信じる者は、たとい死んでも生きる。 わたしを信じる者は、たとい死んでも生きる。
 また、生きていて、わたしを信じる者は、いつまでも死なない。」(ヨハネ11・25〜26) また、生きていて、わたしを信じる者は、いつまでも死なない。」(ヨハネ11・25〜26)
 マルタは、この瞬間まで、イエスの神を信じていたのである。 マルタは、この瞬間まで、イエスの神を信じていたのである。
 それゆえ、イエスはご自身の神性を信ずるようにと迫り給うたのである。 それゆえ、イエスはご自身の神性を信ずるようにと迫り給うたのである。 |
 「これらのことを書いたのは、 「これらのことを書いたのは、
 あなたがたがイエスは神の子(神性)キリスト(メシヤ性)であると信じるためであり、 あなたがたがイエスは神の子(神性)キリスト(メシヤ性)であると信じるためであり、
 また、そう信じて、 また、そう信じて、
 イエスの名(本質)によって命(ゾーエー)を得るためである。」(ヨハネ20・31) イエスの名(本質)によって命(ゾーエー)を得るためである。」(ヨハネ20・31)
 この聖書のみことばは、ヨハネによる福音書の鍵語であり、 この聖書のみことばは、ヨハネによる福音書の鍵語であり、
 永遠の生命を受けるための信仰条件を示しているのである。 永遠の生命を受けるための信仰条件を示しているのである。
 すなわち、イエスの神性とメシヤ性を信ずる信仰である。 すなわち、イエスの神性とメシヤ性を信ずる信仰である。 |
 「人の義とされるのは律法の行いによるのではなく、 「人の義とされるのは律法の行いによるのではなく、
 ただキリスト・イエスを信じる信仰によることを認めて、 ただキリスト・イエスを信じる信仰によることを認めて、
 わたしたちもキリスト・イエスを信じたのである。 わたしたちもキリスト・イエスを信じたのである。
 それは、律法の行いによるのではなく、 それは、律法の行いによるのではなく、
 キリストを信じる信仰によって義とされるためである。 キリストを信じる信仰によって義とされるためである。
 なぜなら、律法の行いによっては、 なぜなら、律法の行いによっては、
 だれひとり義とされることがないからである。」(ガラテヤの信徒への手紙2・16) だれひとり義とされることがないからである。」(ガラテヤの信徒への手紙2・16)
 使徒パウロの信仰は、徹頭徹尾キリスト・イエスを信ずる信仰なのである。 使徒パウロの信仰は、徹頭徹尾キリスト・イエスを信ずる信仰なのである。
 人が義とされるためには、ただキリスト・イエスを信ずる信仰のみで足りるということである。 人が義とされるためには、ただキリスト・イエスを信ずる信仰のみで足りるということである。 |
 人の義とされるのは、ただキリスト・イエスを信じる信仰による。 人の義とされるのは、ただキリスト・イエスを信じる信仰による。
 まさにその通りである。 まさにその通りである。
 義とされし者は、もはや律法の下(もと)に居らず、 義とされし者は、もはや律法の下(もと)に居らず、
 律法より解放されたので、何をしてもよいというがごとき誤ちを犯してはならない。 律法より解放されたので、何をしてもよいというがごとき誤ちを犯してはならない。
 それどころか、義とされし者は、 それどころか、義とされし者は、
 キリストの律法(愛)を全うすべき者なのである(ガラテヤの信徒への手紙6・2)。 キリストの律法(愛)を全うすべき者なのである(ガラテヤの信徒への手紙6・2)。
 なぜなら、義とされることによって、 なぜなら、義とされることによって、
 人間は内面的に一新され、聖化され、神に生きるものとされ、 人間は内面的に一新され、聖化され、神に生きるものとされ、
 神の愛に満たされる者とされるからである。 神の愛に満たされる者とされるからである。 |
 義人にあっては、キリストご自身が知恵となり、 義人にあっては、キリストご自身が知恵となり、
 義となり、聖となり、 義となり、聖となり、
 すべてのすべてとなられるからである(コリントの信徒への手紙一1・30) すべてのすべてとなられるからである(コリントの信徒への手紙一1・30) |
 聖霊が、 聖霊が、
 キリストを通して、 キリストを通して、
 われわれの人格の核心に御名を印される結果、 われわれの人格の核心に御名を印される結果、
 われわれの霊魂のうちにキリストの姿が写され、 われわれの霊魂のうちにキリストの姿が写され、
 キリストの似姿とされるのである。 キリストの似姿とされるのである。
 義とされるということは、ある人々の主張するがごとき、 義とされるということは、ある人々の主張するがごとき、
 レベルの低いことではないのである。 レベルの低いことではないのである。
(人がキリストを信ずるとき、神はキリストを通してその人をごらんになるので、事実は罪人であるが義と認められるのである、との説。) |
 「だれも、新しいぶどう酒を古い皮袋に入れはしない。 「だれも、新しいぶどう酒を古い皮袋に入れはしない。
 もしそんなことをしたら、その皮袋は張り裂け、酒は流れ出るし、皮袋もむだになる。 もしそんなことをしたら、その皮袋は張り裂け、酒は流れ出るし、皮袋もむだになる。
 だから、新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるべきである。」(マタイ9・17) だから、新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるべきである。」(マタイ9・17) |
 自己の力、己(おの)が義に立脚して、 自己の力、己(おの)が義に立脚して、
 律法を実現することによって永遠の生命を獲得しようとするユダヤ教パリサイ主義と、 律法を実現することによって永遠の生命を獲得しようとするユダヤ教パリサイ主義と、
 ただキリスト・イエスを信ずる信仰によって ただキリスト・イエスを信ずる信仰によって
 義とされることを求める福音主義とは、全く相反し両立しないものである。 義とされることを求める福音主義とは、全く相反し両立しないものである。 |
 イエスの神性とメシヤ性を信じ、 イエスの神性とメシヤ性を信じ、
 彼の御名によって永遠の生命を把握し、 彼の御名によって永遠の生命を把握し、
 聖霊によって歩む、 聖霊によって歩む、
 キリストの福音は、全く新しい生命の様式なのである。 キリストの福音は、全く新しい生命の様式なのである。 |
 キリストに在(あ)って、 キリストに在(あ)って、
 神に生きるものにとっては、 神に生きるものにとっては、
 聖霊がその人にあっては新しい生命の原動力なのである。 聖霊がその人にあっては新しい生命の原動力なのである。 |
 「生きているのは、もはや、わたしではない。 「生きているのは、もはや、わたしではない。
 キリストが、わたしのうちに生きておられるのである。」(ガラテヤの信徒への手紙2・20) キリストが、わたしのうちに生きておられるのである。」(ガラテヤの信徒への手紙2・20)
 その人にあっては、このみことばが単なる理想としてではなく、実現されているのである。 その人にあっては、このみことばが単なる理想としてではなく、実現されているのである。
 まことに現実化されているのである。 まことに現実化されているのである。 |

![]()