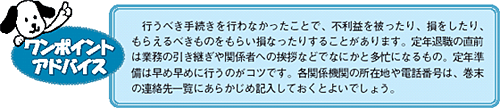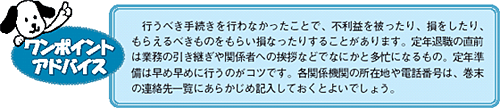●定年を有意義に迎えるために、まず生活資金プランを立てましょう。
定年退職前に、自分は退職金や公的年金がいくらもらえるのか、預貯金や株式などの資産はどの程度あるのかを認識しておくことが必要です。最近、厚生年金を受け始めた男子の平均年金月額は約20万円、消費支出は約30万円と報告されています。大まかなマスタープランだけでも策定して、心の準備をしておきましょう。
●雇用保険、年金、健康保険、税金の手続きはすべて自分で行います。
いざ、定年退職することになると、退職前後にしなければいけない手続きがたくさんあります。これまでは勤務先が代行してくれたので、自分で手続きをする必要はありませんでした。しかし、定年後は「すべて本人が行う」ことが基本となります。まず大切なのは、雇用保険、
年金、健康保険、税金についてきちんと知ることです。ここでは、定年退職前後に必要な諸手続きの種類を紹介しましょう。
●定年退職日までに用意しておくもの
| 用意しておくもの |
確認しておきましょう |
確認 |
年金手帳
(または被保険者証) |
手元にない場合は、会社が保管している場合がありますので、確認しておきましょう |
月 日 |
| 雇用保険被保険者証 |
手元にない場合は、会社が保管している場合がありますので、確認しておきましょう |
月 日 |
写真
(縦3cm×横2.5cm)1枚 |
公共職業安定所で、求職の申し込みを行うときに必要となります |
月 日 |
| 戸籍謄本 |
年金受給権発生後のもので、原則として発行後1カ月以内のものが必要となります |
月 日 |
| 住民票(家族全員の記載があるもの) |
年金受給権発生後のもので、原則として発行後1カ月以内のものが必要となります |
月 日 |
●定年退職前後の手続き
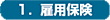
| すること |
提出・受領先 |
提出・受領時期 |
確認 |
| 離職票の受領 |
勤務先 |
退職後10日以内 |
月 日 |
| 求職の申し込み |
住所地を管轄する公共職業安定所 |
離職票受領後すみやかに |
月 日 |
| 60歳以上の定年退職による受給期間延長申請 |
住所地を管轄する公共職業安定所 |
離職日の翌日から2カ月以内に |
月 日 |
| 雇用保険受給資格者証・失業認定申告書の受領 |
住所地を管轄する公共職業安定所 |
求職の申し込みから1〜2週間後 |
月 日 |
| 失業認定申告書の提出 |
住所地を管轄する公共職業安定所 |
指定された認定日・以後4週間ごとに |
月 日 |
| 基本手当の指定口座への入金確認 |
払渡希望金融機関 |
求職の申し込みから1カ月後くらい |
月 日 |
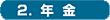
| すること |
提出・受領先 |
提出・受領時期 |
確認 |
| 特別支給の老齢厚生年金裁定請求書の提出 |
勤務先を管轄する社会保険事務所 |
受給権発生後なるべく早く |
月 日 |
| 老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届の提出 |
勤務先を管轄する社会保険事務所 |
雇用保険受給資格者証受領後ただちに |
月 日 |
| 配偶者の国民年金被保険者種別変更届の提出 |
市区町村役場の国民年金窓口 |
退職日の翌日から14日以内に |
月 日 |
| 年金証書・年金裁定通知書の受領 |
社会保険庁 |
裁定請求書提出の2〜3カ月後 |
月 日 |
| 振込通知書の受領・指定口座への入金確認 |
社会保険庁・振込指定金融機関 |
年金裁定通知書受領の1〜2カ月後 |
月 日 |
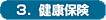
| すること |
提出・受領先 |
提出・受領時期 |
確認 |
| 健康保険被扶養者届の提出 |
扶養者の健康保険組合か勤務先・社会保険事務所 |
退職日の翌日から5日以内に |
月 日 |
| 任意継続被保険者資格取得申請書の提出 |
健康保険組合または住所地の社会保険事務所 |
退職日の翌日から20日以内に |
月 日 |
| 特例退職被保険者資格取得申請書の提出 |
特定健康保険組合 |
年金証書が届いた日の翌日から3カ月以内に |
月 日 |
| 国民健康保険被保険者資格取得届の提出 |
市区町村役場の国民健康保険窓口 |
退職日の翌日から14日以内に |
月 日 |
| 国民健康保険退職被保険者該当届の提出 |
市区町村役場の国民健康保険窓口 |
年金証書が届いた日の翌日から14日以内に |
月 日 |
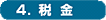
| すること |
提出・受領先 |
提出・受領時期 |
確認 |
| 退職所得の受給に関する申告書の提出 |
会社の担当者 |
退職金を受け取るとき |
月 日 |
| 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出 |
最初は勤務先を管轄する社会保険事務所 |
最初は裁定請求書に記載して提出する |
月 日 |
(注)民間企業を60歳で定年により退職する場合を想定していますが、すべての手続きが必要となるわけではありませんので、あなたに合った手続きを選択してください。